槍玉その47 『天皇の歴史01 神話から歴史へ』大津透 講談社 2011年11月刊
槍玉副題 これでよいのか東大国史学史観 批評文責 棟上寅七
目 次
はじめに・著者略歴・最初の感想・文字に書かれて歴史になる・本のあらすじ
(一)卑弥呼以前の歴史
『三国志』以前・『後漢書』の倭奴国(志賀島の金印)について・稲葉君山の漢倭奴国王印考・極南界とは・寅七と古田武彦氏
(二)『三国志魏志』と我が国の歴史
倭人伝解釈の歴史・狗邪韓国と任那・卑弥呼は国王か・「邪馬台国」問題・大津教授の九州説の説明・卑弥呼は纏向にいたのか・近畿説の狗奴国の位置は・「邪馬台国」行路記事・三角縁神獣鏡・繰り上がる弥生時代・三角縁神獣鏡は卑弥呼の鏡に非ず・佐伯有清氏の見解・銅鐸について・古代の男女政権・卑弥呼の鬼道とは・ヤマタイコクの読み方と纏向遺跡・「壹」と「台」・森浩一氏の「壹と臺」論・大津教授の邪馬台国論の破綻・箸墓と卑弥呼の朝日新聞記事の検討・ところで邪馬壹国とは・倭人伝の「里」の問題・卑弥呼の墓の大きさと冢・三種の神器
(三)金石文と我が国の歴史
七枝刀問題・百済記の貴国と沙至比垝・高句麗好太王碑文・稲荷山鉄剣銘
(四)『宋書』と我が国の歴史
倭の五王・安本美典氏の倭の五王説・古代天皇在位十年説・正解は・倭王武の上奏文の評価・倭王武=雄略=ワカタケル説の破綻・平西将軍問題
(五)『日本書紀』・『古事記』の伝える天皇
大津教授の『記紀』批判・神武東征伝承・マヘツキミ論・景行紀のマヘツキミ・継体天皇の問題・仏教受容の歴史
(六)『隋書』と我が国の歴史
俀国伝とは・大津教授の理解は・阿毎多利思北孤問題・阿輩雞彌と阿輩台と河内直の三題噺・裴世清問題・兄弟政治について・国書問題・冠位十二階問題・遂に絶つとは
(七)『旧唐書』と我が国の歴史
中国との通交記事一覧・高校教科書では・学習指導要綱では・王子と礼を争ったのは誰か・泰山封禅の儀に参加したのは誰か・大津教授が言う第一次遣唐使とは・倭国と日本国・蝦夷国遣使・百済救援の戦いとその意図・敗戦戦後処理・天智(称制)の甲子の宣・天智の防衛策・大化改新と乙巳の変・郡評問題・壬申の乱
(八)天皇号・日本国号成立問題
万葉集解釈について・天皇号成立について・日本国号について・元号開始と中断問題・天皇を神とする思想
(九)おわりに 大津教授が語らないこと
(十)真の天皇の歴史
はじめに
★ 著者略歴
大津透氏の略歴は『天皇の歴史01』のブックカバーに次のように記載されています。
【1960年生まれ。東京大学大学院修士課程修了。山梨大学助教授を経て、現在、東京大学教授。専攻は日本古代史、唐代史。 主な著書に『古代の天皇制』『日本古代史を学ぶ』(岩波書店)、『日本の歴史06巻 道長と宮廷社会』(講談社)など。本シリーズ編集委員。】
Wikipediaによりますと、武蔵中・高卆、1983年東京大学文学部卒(国史学専攻)とありますので、常に東大入学者数トップクラスの名門武蔵高から現役入学し留年することなく、極めてスムースに国史学の泰斗の地位を占められ方のようです。
★最初の感想
この本を読んでまず感じたのは、「通説に凝り固まって、問題があるところは他人の説を紹介する、それを肯定的に行うかどうかで婉曲的に方向づけを行う、たまには独断的に裁断し、手に余ることは無視する」という本だなあ、ということでした。これを批判するとすれば、縄文晩期から八世紀までのわが国の歴史全部を掘り返さなければならない、これは大変だなあ、ということでした。
このホーム頁を開いて7年足らずですが、古田武彦私設応援団の立場から勉強させていただき、槍玉にあがって頂いた方も40人を越します。古田武彦著の書物・論文なども脳内に収まらないくらいになっています。何とかなるだろう、と騎虎の勢いで始めました。ただでさえ、小難しい古代文献解釈などが多い批評文ですが、最後まで目を通して頂ければ幸いです。
読み易さのために、大津教授の著書の引用箇所を赤字で、古田武彦先生の著書からの直接引用箇所を青字で表しました。
さて、大津教授の大先輩の井上光貞氏に『日本の歴史I 神話から歴史へ』中公文庫という著述があります。旧石器時代からの日本の歴史を叙述しています。今回は出版社の企画によって『天皇の歴史』となったものでしょうが、大津教授がこの井上先輩の本を意識されて独自色を出されようと努力されたことと思われます。
天皇の統治組織として、これの氏姓制度・王権の象徴レガリア・即位儀礼などに重点を置かれた叙述になっています。しかし、史料の検討が不十分なまま、次のステップ、王権・レガリア・即位儀礼などに進まれますので大津教授の「天皇の歴史」はおかしくなっているようです。
『魏志』倭人伝では、考古学的整合性はゼロなのに卑弥呼は纏向に居たと断定、『宋書』では、雄略の即位時には倭王武はまだ即位していないのに、武=雄略とする、『隋書』では、多利思北孤には合う天皇がいないので適当にごまかしてみたものの全く説明不能状態、『旧唐書』では、倭国と日本国の区別を無視する、というように、全くお粗末な史料批判の上での大津教授の『天皇の歴史 神話から歴史へ』の叙述です。
これでは天皇が可哀想です。『いつわりの大津史学』とでも言いたい気持ちとなり、主として史料批判の立場から一介の素人古代史好きが現職東大教授の著述に挑んでみることにしました。 ともかく、中学生とはいかぬまでも高校生には理解できる程度に噛み砕いて、なおかつ、大津教授の手の込んだ目くらまし的論議にも反論していくには、こちらも史資料の読み込みが必要で、結果的に1年ちかく時間がかかってしまいました。
「日本の歴史」では、普通「縄文時代」あたりから入って、渡来人が来て稲作が広まり「弥生時代」になって国家が出来始める、というように書いています。しかし、この大津透教授の本には縄文時代の話は全く出てきません。
「天皇」というと大層な位のようですが、まだ石を加工した道具を使って生活していた縄文時代でも、やはりその地域のリーダー「地域の天皇さん」はいたのではないでしょうか? 日本列島各地の巨木文化遺跡の発掘状況や、火焔土器に代表される「縄文時代」の技術レベルを、インターネットでも容易に見ることができます。
この本では、「王権」とか「レガリア」・「三種の神器」などについても詳しく書かれます。その三種の神器の一つ「勾玉」は縄文時代から宝物とされていたものと思われるのですが、それらについては殆んど述べられませんし、弥生時代の宝器「銅鐸」については全く触れません。その上で、大津教授は「歴史は文字で書かれた史料によるべき」とおっしゃいます。
しかし、無文字時代に残された文字以外の資料から、当時のリーダー(天皇の祖先)像を描くことも、歴史家の務めと思うのですが、大津教授はそうは思われないようです。
★文字に書かれて歴史になる?
大津教授は、「文字に書かれて歴史になる」と次のように言われます。
【『古事記』や『日本書紀』のもとになった史料は津田左右吉が明らかにしたように、六世紀前半に「帝紀」と「旧辞」として文字にまとめられたものと考えられ、それ以前には文字による記録はなく、たとえば『日本書紀』が記す三世紀の伝承にしても数百年ののちに文字にされたもので信頼性に乏しい。歴史学はより信頼のおける史料にもとづいて史実を再構築するのが原則である。】 (p38)
このように、”記紀の伝承は六世紀の史官によって文字化され信頼性に乏しい”、と一刀の下に切り捨てます。日本書紀に出てくる「数多くの一書」に曰く、とか「日本旧記」からの引用書自体も同様とされる先輩津田説に全面的に従っているようです。
そして、【一番信頼がおけるのは同じ時代に記録された文章であり、文書や記録は存在しないので、ここでは金石文とよばれる石碑や金属器に刻まれた銘文である。
高句麗が建てた五世紀初頭の好太王碑文や埼玉古墳群の稲荷山古墳鉄剣銘(四七一年)がこの時代の歴史を描く第一次史料である。 とはいえきわめて断片的なものである。
そこで次によるべきは、当時文字による記録を作成していた中国の史料である。(中略) したがって『三国志』魏志東夷伝倭人条に記される「卑弥呼」、『宋書』倭国伝にみえる「武王」など五王によって日本の歴史は始まる。 】(p39)と続けられます。
私は大津教授の「文字があって歴史が始まる」というこの意見を読んで、へ~そうなんだ、文字がなかったアメリカインディアンやアフリカの文字を持てなかった人たちには歴史は語れないのかなあ、などと疑問が浮かびました。
しかし、ざっと読んだところでは、大津教授は「文字に書かれた史料」の判断基準が理性ではなく別の判断基準で取捨選択されているような気もしました。例えば「那須国造碑文」という金石文は全く取り上げられません。このような大津教授の史資料の取り上げ方を中心にして、この『天皇の歴史01 神話から歴史へ』をみていきたいと思います。
大津透教授の本の、わが国の古代史のストーリーはどうやら次のようなものの様です。日本の最高学府の国史学の最高峰の現役教授がお書きになった四〇〇頁に近い大部の著書を、四〇〇字足らずに圧縮してしまって申し訳ありませんが、この論議を読んでいただく読者の便宜のために、まず書き上げてみます。
★『天皇の歴史01 神話から歴史へ』という大津透教授の本のあらすじ
① 三世紀の『魏志』倭人伝と三角縁神獣鏡の分布関係から、卑弥呼は纏向にいたとわかる。九州説は成り立たない。しかし、卑弥呼の前後の即位状況は世襲制ではないから、大王王権が確立されていたとは言えない。
② 四世紀の「好太王碑文」の内容から、『記・紀』の神功伝承は史実の反映と言える。
③ 五世紀の『宋書』の「倭の五王」記事から、倭国がそれまでの中国世界から離れたと言える。国内の二つの「ワカタケル」の金石文から、「治天下」というように独自の天下を作ったと言える。
④ 七世紀の『隋書』などから、煬帝の怒りで国内体制を改めたことがわかる。『日本書紀』はこのあたりの事情(「王子と礼を争う」や「第一次遣隋使派遣」など)を隠している。
⑤ 八世紀の『旧唐書』と『日本書紀』の記事から、白村江の敗戦から日本がうまくその社稷を安んじることができた事情がわかる。
ということの様です。 従いまして、それぞれの「史書」と、併せて大津教授が沢山引用される『万葉集』などの歌の解釈について検討していくことにします。
(一)卑弥呼以前の歴史
★『三国志』以前
大津先生がおっしゃるように、文字に書かれて初めて歴史史実となる、ということを信じるとしたら、じゃあ、卑弥呼が活躍する三世紀の前には、日本の歴史はなかったのか、ということになります。勿論大津先生はその様なへまはなさいません。 卑弥呼が活躍する三世紀の、『三国志』魏志が書かれる前の史書にも、日本の前身の倭国や倭人が出てくることを述べられます。
じゃあ、卑弥呼の前にも日本の歴史はあるじゃないの、といいたくなりますが、待って下さいこの本は「天皇の歴史」なのです、日本の人々の歴史とは違うのですよ、と大津先生からチェックが入ることでしょう。しかし、その基礎史料の判読の信憑性の確認が決定的に重要でしょう。その基礎がしっかりしていなくていい加減な推論の上に立てられた、一見立派に見える論証も砂上の楼閣です。
大津教授が古代史の「基礎史料」とされる、『魏志』倭人伝、『後漢書』、「好太王碑文」、「稲荷山・江田船山鉄剣銘」、『宋書』倭国伝、『隋書』俀国伝(大津教授は「倭国伝」とされます)、『旧唐書』倭国伝・日本国伝などの大津教授の解釈を読ませていただいて検討させていただきます。
ただ注意しなければならないと思いますのは、この本を通読して感じた次のことです。それは、「日本の記録で、外国の記録に合うと思われるものは事実であろう」、というのは当然としても、「外国の記録にあっても日本の記録に無いものは、日本側が都合によってそれを隠したのだ」、という態度に問題があると思われることです。外国の記録にあっても日本の記録に無いものは外国の記録の間違い、という態度に繋がっているのではないか、と思われることです。
「日本の記録で、外国の記録に合うと思われるものは事実であろう」、という大津教授の態度です。外国の記録にあっても日本の記録に無いものは外国の記録の間違い、という態度に繋がっているのではないか、と思われることです。 大津教授は三世紀以前の、卑弥呼以前の「歴史」について次のように『後漢書』の金印の話から入られます。
★後漢書の倭奴国(志賀島の金印)について
この大津教授の後漢書記事の理解について検討してみたいと思います。まず、大津教授の原文の理解が果たして正しいのか、もし誤った理解をしたら、「倭国の成り立ち方」も間違った方向へ進んでしまうでしょうから、そこのところから入りましょう。
大津教授は次のように書きます。
【(倭女王が「親魏倭王」に任じられる以前には、)『後漢書』倭伝、五七年(建武中元二年)に、”倭の奴国、貢ぎを奉りて朝賀す。使人自ら大夫と称す。倭国の極南界なり。光武、賜ふに印綬を以てす。”とあり、ここでは倭の中の一国である奴国王が冊封されたのである。
さらに、安帝一〇七年(永初元)のこととして、”倭国王帥升等、生口百六十人を献じ、請見せんことを願ふ。(中略)“とあり、ここで「倭国王」というまとまりが初めてみえるが、生口一六〇人と多いことと、「帥升等」という複数形の表記から倭の諸国の支配層からの持ち寄りであろう、実質的に初代の倭国王となったのが卑弥呼だったといえるだろう。】p41~42 要約
つまり、中国から「漢委奴国王」という金印を貰ったのは、倭人国の内の「奴国」という小国であり、倭国王というまとまりのある国家ではなかった。漢書に倭国王として出ている帥升という人物も、伊都国王とかそのような小国の王と思われ、倭国全体の王ではなかったのだ、ということでしょう。
これについての疑問を上げてみます。まず何といっても、大津教授の読み下し文です。これでは全く文章の意味が通りません。擬古文調の大津教授の文章を平たく読んで見ましょう。
「倭の奴国が貢物を持ってやってきた。使いの者は自分を大夫と名乗った。(倭の奴国は)倭国の一番南の界〈だ。ということで光武帝は印綬を賜わった。」ということになりましょう。
建武中元の記事の原文は次の通りです。 「建武中元二年倭奴国奉貢朝賀使人自称大夫倭国之極南界也光武賜以印綬」
大津教授の読み方では次の様な疑問が出てきます。
①倭奴国」は「倭の奴国」でよいのか。 ②倭国之極南界也」は「倭国の極南界なり」でよいのか。 ③「光武賜以印綬」は「なにを以って印綬をあたえたのか。
①については古来諸説があるようです。志賀島から出土した「漢委奴国王」印の「委奴国」も同様の問題を含んでいます。今は後漢書の記事の「倭奴国」の読み方について検討します。
中国の天子が夷蕃国に「漢の倭の奴国」というように、三段読みをするような国へ印綬を与えた例があるのか。つまり、倭国の中の奴国という、間接的な支配権がある小国に直接印綬を与えるものだろうか?
これは例えて言うと、旧幕体制時に幕府が陪臣に直接領地の支配権を与えるようなもので、理解するのが難しい。やはり、ここは、漢帝国が自分の庇護下にあることと支配権を認めることを示した印綬渡し、と考える方が合理的解釈と思われます。
つまり、「漢の倭奴国」に印綬は授けられたということでしょう。 そうすると「倭奴国」とは何と読むのでしょうか。一世紀前後の読みについても諸説あるようです。
倭を「ヤマト」と読み、奴を「ノ」と読んで「ヤマトの国」とこじつけた江戸時代の亀井南瞑がいます。一般的に、「倭」は「ヰ」「ワ」の両説、「奴」は「ド(ト)」「ヌ(ノ)」「ナ」の三つの読み方。 この双方を組み合わせて、「イド、イヌ、イノ」などが得られています。
『魏志』にもその国名が出てくるので「伊都国」説が一般受けされるようです。 この倭奴国は、印綬下賜の半世紀後にも「倭国王」という記事が出てきていますから、この倭奴国が倭国の代表であったという理解の方が、「倭国の中の奴国」という理解よりもはるかに合理的と思います。
後の正史『隋書』にも「倭奴国」とあり、その国が乱れて歴年王がなく、卑弥呼が王となって治まった、とあります。「奴国」という小国ということではとても理解できないのです。
大津教授が主張される、この「漢の倭の奴国」という三段読みに対する問題提起は、稲葉君山(本名稲葉岩吉 陸軍大学教授)という方が1911年『漢委奴国王印考』で次の様になされています。
【一、 金印は「奴」のような小国に与えるものではない。 二、 金印を与えるのは宗主国(中心の統率国)に対してであって、その陪従者(被統率者)ではない。 三、 漢が、倭の陪従者である「奴」を認めて大国の王とし、金印を与えたとするのは、すなわち漢制に反している。】(古田武彦『失われた九州王朝』ミネルバコレクション版p23)
「王権」という問題について検討するのがこの大津教授の『天皇の歴史』でしょうから、もっとまじめに後漢書の倭国記事を検討して貰いたい。稲葉君山氏に反論していただきたいと思います。
次に「大夫」という倭奴国の管理組織長名と思われる「大夫」が書かれています。この「倭奴国」が以前より「管理組織・漢字」などの大陸文化が摂取されていたことがうかがえる記事でもあります。『天皇の歴史』と銘打って、天皇の統率組織等について述べられる大津教授が、この後漢書に現われる「大夫」について無視されるのはいかがなものでしょうか?
つぎが、②「極南界」問題です。
この極南界問題には大津教授は触れていません。しかし、印綬を与えられた「倭奴国」のありかを示すかのような記事なのです。大津教授の理解を越えた記事で、「中国史書の誤り」位の理解ではないだろうか、と僭越ながら思ってしまうのです。この問題を理解できなければ、③のなぜ、光武帝が「金印」を与えたのか、が理解できないでしょう。
倭奴国が倭国の極南界ということを文字通りに理解してみた方に豊田有恒氏がいます。SF作家として著名ですが、古代史にも造詣が深い方です。その著書の一冊に『歴史から消された邪馬台国の謎』青春出版二〇〇五年刊があります。
豊田氏の主張は、【漢の時代は、朝鮮半島南部と九州北部が倭人の国であった。それで倭奴国はその極南界である、という記述になった。】と云われるのです。魏の時代になると、日本列島にまで倭人の国となったので、『魏志』倭人伝の記述する三十カ国になった、というのです。
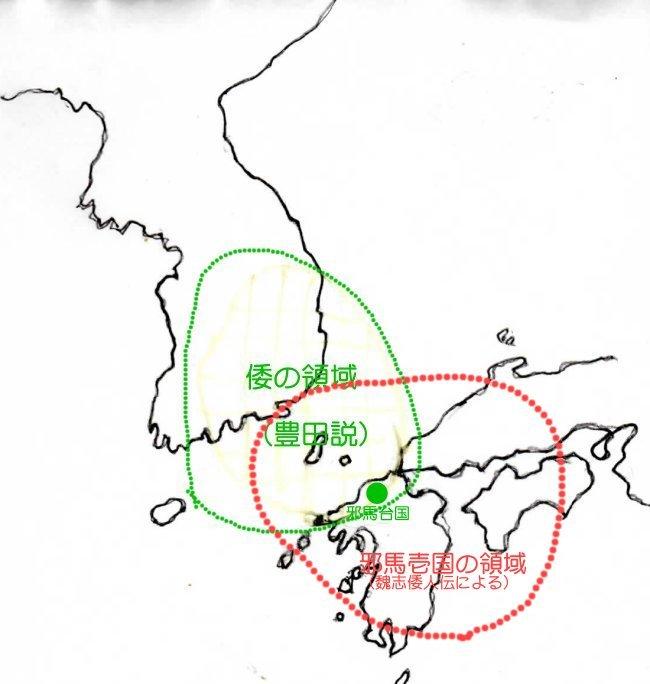
豊田有恒氏の説によると、後漢書が示す倭の領域は、右の図の緑色部分になります。
ただ残念ながら、朝鮮半島が倭人の国であったと云うのは、中国古代(禹の時代)の地理書『山海経』海内北経に、「蓋国在鉅燕南倭北。倭属燕。」という一節があることを根拠にしますが、『漢書』地理誌には紀元前一〇八年に朝鮮半島に漢が楽浪郡はじめ四つの「郡」を置いており、これは随分と無理筋です。
それも「倭奴国は倭の極南界」、つまり南の果て、という地理認識に合わせようと無理をしていることから来ていることに他なりません。大津教授も極南界問題を地理認識に合わせることは至難の業ということで関わりたくないのでしょう。文意が通らない読み下し文を掲げて平然とされています。
では、この問題は解けないのでしょうか?中国文には句読点がありません。そのこともこの記事の解読を難しくしている面があるのでしょう。③の「光武賜以印綬」は「なにを以って印綬をあたえたのか」とも関わって来ます。つまり、②と③の文章は一つの文章なのです。「倭国之極南界也光武賜以印綬」を一つの文章として読み下せば意味はすっきり通るのです。
「倭国の南界を極めるや光武賜うに印綬を以てす」(『失われた九州王朝 ミネルヴァ社コレクション版』p537)、と古田武彦氏は読まれます。 「倭国の南界を極める」という言葉がどのような意味があるのか、恐らく「南界を極めた」何らかの証拠的なものを献上したのでしょう。
古田武彦氏は、魏志倭人伝にある「裸国・黒歯国」のことではないか、と言われます。ともかく、光武帝が印綬を与える程の働きがあった、と認めたからだったのでしょう。
大津教授の読み方では、「倭奴国が朝貢したので印綬を与えた」と言うことになり、朝貢してきた国には金印をお構いなしに誰にでも与えているかのような印象です。それならそうで、中国史書でその様に金印の授与がなされていた、ということを示す必要があるのではないでしょうか?
次に安帝の107年の記事です。
大津教授は前述のように、【160人という大量の生口が贈られたこと、帥升等という複数形であることから、まだ王権の確立した国家としてのまとまりは見られない】、という考えのようです。どうしても近畿王権が成立し日本全土を統一した、ということを以て日本国家の始まりとしたいようです。
『後漢書』にもあります様に、「倭国が乱れた」時代はあったようです。『魏志』倭人伝にも元百余国とありますように、小国があって乱れていない時代があったのは間違いないでしょう。
そのまとまりが倭奴国王、倭国王というまとまりになったのでしょう、たとえ近畿地方は入っていなくても。(『漢書』「地理志」や『後漢書』には倭国以外に東鯷国、や拘奴国などがあることが書かれていますが、大津教授は天皇王権と無関係とされるのか無視されます。)
大津教授が云われるように、極東の百余国もある倭人の国の一つの小国に、このような「金印」与えるというような事例があるのか、何故与えたのか、など当然の疑問に対し、大津東大教授は答える義務があるのではないでしょうか。
ところで、上述のように、大津教授の著作を批評するのに古田武彦氏の著作を引用させてもらっています。この大津透著 『天皇の歴史01 神話から歴史へ』の批評は、これまで引用していることでお分かりのように、古田武彦氏の著作およびその真理探究精神に負うところが極めて多いことをお断りしておきます。
★棟上寅七と古田武彦氏と、について少々説明しておきます。
このホームページを当初から読んで頂いている方々にはお分かりになっていらっしゃるかもしれませんが、改めてこのホームページを開いた経緯について一言しておきたいと思います。
私、寅七は、『「邪馬台国」はなかった』が出版された辛亥の年、一九七一年当時には企業戦士の一員として海外にいまして、日本の情勢、特に、古代史の分野で、辛亥革命・ニクソンショック以上の衝撃を与える、『「邪馬台国」はなかった』がこの年に朝日新聞社から出版されたことを知る由もありませんでした。
一九七二年に帰国し、一九七三年のオイルショックで企業活動が一時混迷の時代に、角川文庫の『「邪馬台国」はなかった』に書店で出会いました。一読して一驚、その論理の組み立て方、緻密さに目の覚める思いがしました。引き続き、角川文庫 から、『失われた九州王朝』・『盗まれた神話』と立て続けに古田武彦氏の本が出版され、勤務の合間にむさぼるように読みふけったものでした。
それまでは、『或る小倉日記伝』以来のファンであった松本清張『古代史疑』や、目が不自由になりながら鋭い感覚で邪馬台国探しをされた宮崎康平『まぼろしの邪馬台国』を読んでは、やはり邪馬台国の確定は無理なのか、と思っていましたが、女王国は博多湾岸に接したところとわかり、積年のツカえが取れた感じで、これで日本の古代史の蒙昧さも晴れた、と思っていました。
それから、瞬く間に三十五年を閲して、紅顔の青年も企業戦士の役を終え、年金生活に入ることになりました。青少年時代乱読した本も読み返す時間は出来ました。古田武彦氏の一連の著作も改めて読み、その後の古代史論争はどうなったのだろう、と興味をもちました。
書店の歴史本コーナーを見てみますと、「君が代論」・「万葉集新解釈」・「多元国家論」などなど、古田武彦著の多彩な本が並んでいます。しかし驚きましたのは、たとえば、『君が代を深く考える』 古田武彦著の中で、“『「邪馬台国」はなかった』、以来、表に立った歴史学会からの批判はなく、邪馬台国の所在は『近畿説九州説両論あり』と頬被りを学会が極めこんでいる、なぜ日本の「古代史学会」は沈黙を続けるのか、”と憤慨されていたことです。
古代史関係の学会というところは、論理で諾否の判断が出来ず、都合の悪い意見は学会内で取り上げない、といういわばムラのルールを押し通すところなのだろうか。 義を見てなさざるは勇なき也、と非才をも省みず、蟷螂の斧を私なりに振るってみようか、ということで、「新しい歴史教科書(古代史)研究会」という古代史本批評の、古田武彦私設応援団会員一名のホームページを立ち上げたのが2006年春、私が70才のときでした。
以後勉強会などで古田武彦氏ご本人にもお近づきできました。古田史学会の会報にもいくつかの論文を投稿したりもしました。氏は、私、ペンネーム棟上寅七、のつたない古代史論議にも丁寧にご意見を頂いたり、二〇一一年夏『鏡王女物語』という処女作小説を原書房から私家版出版した時には、過分な推薦文を書いて頂けました。
というような次第で、この大津透教授の『天皇の歴史01 神話から歴史へ』の批判検討にあたって、古田武彦全著作を参照・引用させて頂いていることをまずもってお断りしておきます。
(二) 『三国志魏志』と我が国の歴史
さて、大津教授が文字に書かれた歴史書として一級の史料とされる、『魏志』「倭人伝」について、大津教授の考えを聞かせて頂きます。
★倭人伝解釈の歴史
大津教授は倭人伝については詳しくない、と謙遜されながらもご自分の解釈を述べられ、倭人伝の解釈の歴史についても述べられます。
流石に現職の東大教授として、白鳥庫吉(東大)の九州説、内藤湖南(京大)の近畿説などという学閥の流れなどには乗ることもせず、ご自分?の解釈を述べられているようなのです。
ここでご自分の?と?を付けましたのは、どうも大津先生のまとめ方は、大学の国史学科の大先輩佐伯有清氏の意見によく似ているようです。しかし、この本では佐伯有清氏に直接言及されてはいません。 佐伯有清氏は大津教授と同じ東大国史学科の卒業です。北大の教授をされ、東大に戻られることなく定年退官後、成城大の教授に迎えられ、沢山の古代史関係の著述をなさいまして2005年に80歳で亡くなられました。
佐伯さんの研究の一つの柱は『魏志』倭人伝について、つまり「邪馬台国」についての研究でした。邪馬台国研究史・邪馬台国論争などがその代表的なものです。享年直前に出版された『邪馬台国論争』にいたって、それまでの「東大の九州説」から「内藤湖南への復帰」を提唱されました。つまり、邪馬台国畿内説が正しい、というご自身の結論を出されたのです。
この同窓の大先輩の「邪馬台国畿内説が正しい」という意見が、大津教授がそれまでの「東大=九州説」からの決別に大きな支えになったであろうことは想像に難くありません。この本で大津さんは、邪馬台国論争には詳しくないと言われながらも、小林行雄氏の説を紹介する形で【卑弥呼は纏向に居たはず】(p44)と言えているのは、佐伯有清さんの意見の上に立ってのことでしょう。
そこで『後漢書』に戻ります。そこに出てくる「倭奴国」についての読み方については前述しました。では『三国志』魏志倭人伝に出てくる「奴国」は何と読むのでしょうか。中国人が倭人から国名を聞いて、表音文字として漢字を選んで書いたものに違いありません。
大津教授は無条件に奴国とルビを振っています。 それで本当に良いのでしょうか。
倭人伝には「奴」の様な表音文字に使われた字が沢山あります。ところが「ナ」には「那」という字が使われています。そして、「ノ」という字が入った国名が全くない、という特異点があります。
このことを数学的に証明出来ないだろうか、と検討を試みました。その結果「奴」がナでなくヌ若しくはノである確率は96%という結果を得ました。 その結果を『古田史学の会 論集古代に真実を求めて 第12集』に、「奴をどう読むか」棟上寅七 を発表しています。 クリックしてみてください。
結果は、100%でなく96%ということで、断定できないのは残念ですが、常識上の判断としては、「奴」は「ナ」でなく「ヌ」若しくは「ノ」であった、と言えると思います。
★「狗邪韓国」と任那について
ちょっと脇道にそれますが、倭人伝に「狗邪韓国」という国が出ています。大津教授はこの「狗邪韓国」について何も書かれていません。しかし、「倭人伝」には倭国の一国というように記載されています。
大津教授は、「三世紀前半の東アジアの地図」を掲載(p40)しています。(下図)
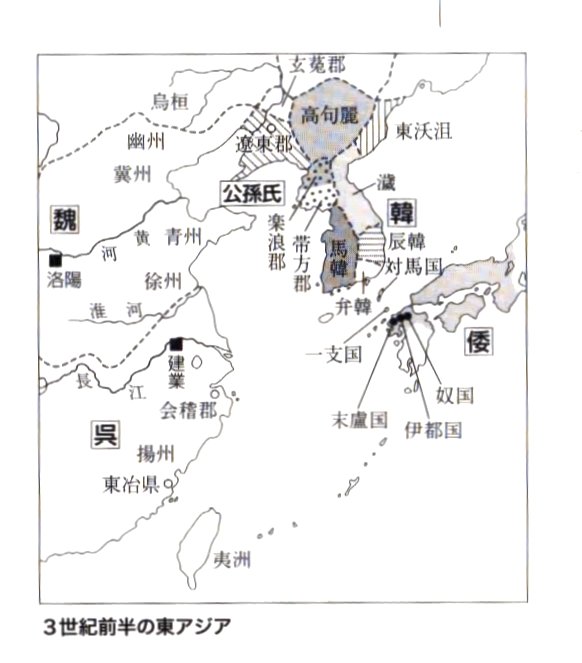
三世紀、「倭人伝」が記述する東アジアの状況を説明する地図に、大津教授は何故か「狗邪韓国」を抹消されています。何故なのでしょうか?
大津教授のいうように、卑弥呼の時代になって倭国が初めてまとまった、畿内にいて、その後のヤマト政権成立に関係がある、というような順序を辿った、のであれば、朝鮮半島の一部が倭国の勢力範囲であったと、と取れる「倭人伝」の記事があるということは、特筆しておいてよいのではないでしょうか。
三韓征伐・任那日本府などの戦前の皇国史観と同一視されることを嫌ったのでしょうか、用心深く「狗邪韓国」に触れていません。 ところが、【日本が一時新羅を圧服した事は事実である】p120と突如述べられ、その「事実」の内容の説明はありません。不思議です。
後に述べます、『宋書』倭の五王の授号記事の内容をみますと、倭王は、新羅など六カ国の軍事についての権利を認められています。その中には「任那」も明記されている問題について、大津教授は、次のように書きます。
【 倭隋への六国諸軍事の授号について、隋は百済について除き加羅を加えて六国として認めた。加羅と任那は同一実態なので意味なく云々】p85とか、p162に四世紀末の朝鮮半島の地図が載せられていますが(下図参照)、 地図の説明では加耶(別名任那)とあり、【 安羅は好太王碑文に「安羅戍兵」とあり倭軍の別働隊であり、安羅と倭の間には深い関係があった。】p163 とも説明されています。

『日本書紀』継体六年の任那四県割譲記事について、【これは加耶地方を百済が実力で支配下においた、ということだろう。】p197 と言われます。 これらの大津教授の任那についての言及の基には、「任那地方は我が国の支配地域であった」という認識があると思われます。しかしながら、「狗邪韓国」については一言も触れられないのは不思議です。
倭国の範囲についての『魏志東夷伝』の記事を認めたくない、ということが基本にあるのでしょうか。それを認めると、卑弥呼が纏向に居た、という説に不利になるからと推測するのは邪推でしょうか。
★卑弥呼は倭国王か
大津教授の説明はこうです。【実質的に初代の倭国王になったのが卑弥呼だったといえるだろう。なお、卑弥呼が都するところが邪馬台国という用例もあるだろうが、やはり諸国が共立したので、邪馬台国を中心とする邪馬台国連合と考えるのが正しいだろう。】(p40)とおっしゃいますが、これは倭人伝の記述とは随分と違った印象です。
例えば伊都国の説明で、「世に王あるも皆女王国に統属する」とか、「女王国以北には特に一大率を置き検察せしむ。諸国之を畏憚す。」とかの記事があります。この記述からは、「小国の連合」というイメージには程遠いと思われるのですが、大津教授はどうしても「邪馬台国連合」という緩やかな組織をイメージしたいようです。
ところで、大津教授の「邪馬台国」についての基本認識を見てみたいと思います。
【邪馬台国はどこにあったのか。いわゆる邪馬台国論争は、江戸時代以来つづいている古代史の長年の課題である。いわゆる九州説をとれば、倭国は九州を中心とする地域にすぎず、その外側に大和政権へつながる強力な畿内勢力があったことになるが、大和説をとれば当時倭国として少なくとも畿内から九州までの列島のかなりの地域の政治的なまとまりが成立し、それが大和政権へと展開することになる。
筆者の能力もあり邪馬台国論争に詳しく立ち入ることはできないが、最近の動向について簡単に紹介しておこう。 邪馬台国の位置は「魏志倭人伝」に記載があり、伊都国へ到ったあと、奴国・不弥国・投馬国につづけて以下のように記す。 南、邪馬台国に至る、女王の都する所なり、水行十日、陸行一月。(中略)七万戸。
この記述によると、北九州の伊都国などからはるか南方、九州の南の海上に邪馬台国が存在することになり、方位または距離のいずれかに誤りがあると考えざるをえない。 九州説については、榎一雄により、伊都国以降の行程は順に読むのではなく伊都国から放射状に読み、「水行ならば十日、陸行ならば一月」という説が唱えられ、九州内に納めることが可能になる。 一方大和説では、南とあるのを東の誤りだとして読みかえる。
「倭人伝」のなかに「その道里を計るに、まさに会稽・東冶の東にあるべし」「倭の地を参問するに、海中洲島の上に絶在す。あるいは絶え、あるいは連なり、周旋五千余里ばかりなり」とあり、会稽は浙江省、東冶は福建省であるから、倭はその東の海上にあり、つまり北九州から南へ琉球・台湾あたりへのびる列島だと考えていたらしい。東へ読みかえることは一定の根拠がある。 】(p42~43)
この大津教授の「倭人伝認識」は、「天皇の歴史」という観点からでしょうけれど、何か先入観があるのではないかと疑われます。「邪馬台国(原文は邪馬壹国)=日本列島の殆んどの地域」と「倭人伝」には書いてありません。朝鮮半島南端の狗邪韓国・対馬・壱岐・松浦・伊都という北部九州の地名が出てきて邪馬壹国に至る、と書いてあるのです。どこにも瀬戸内や大和三山の話もないのです。
★邪馬台国問題
「邪馬台国」と一般に言われていますが、倭人伝の原文は「邪馬壹国」なのです。大津教授はじめ古代史関係者の多くの人が「邪馬台国」と書き表すのは「ヤマト」国と読みたいからなのでしょう。
『魏志』「倭人伝」のどの版を見ても「邪馬壹国」である、と『史学雑誌78-9』 (昭和四四年)に発表されたのが古田武彦氏です。しばらくの間、古代史のシンポジウムなどで、古田武彦氏も発表者として発言の席が与えられていました。
しかし、氏の妥協のない非大和王朝一元論を煙たがる学会・ジャーナリズムによって忌避されるようになり、『東日流外三郡誌』を評価する氏の立場を、野外の考古学の論客である安本美典氏が『季刊邪馬台国』を根城に行った反古田武彦の大キャンペーンなどにより、発言の場が極めて限られてしまっているのは、古代の真実の歴史を解明する立場にとって悲しむべき現状と言えましょう。
大津教授は、「邪馬台国九州説は、倭国は九州を中心とする地域にすぎず、云々」(p42)と否定的な根拠とされている口ぶりです。しかし、その通りではないのですか。卑弥呼の国が倭人国、倭種の国々全体を統括していた、などとは一言も倭人伝には書いてありません。卑弥呼の天敵狗奴国、海を渡って東に倭種の国がある、などと書かれているのです。
本居宣長が言ったように「九州の熊襲の酋長が国王を偽僭した」、と言う方が大津教授の説よりも的を射ているのです。 おまけに、大津教授は九州説を説明するといいながら、古田武彦説については全く言及されません。
古田武彦氏の「九州説」というのは簡単に言いますと次のようにまとめらると思います。【いわゆる「邪馬台国」は博多湾岸にあった。その分派(神武)が東侵して大和王朝をたてた。その本流は筑紫を根城に「倭の五王」の王朝、多利思北孤王朝と続き、白村江の敗戦で滅びた。】と。
★卑弥呼は纏向に居たのか?
わからないのは、大津教授は何故卑弥呼の国を纏向にもって行きたいのか、ということです。
大津教授が主張されるように、【 卑弥呼はまだ「実質的に王権を確立した国王」ではないし、卑弥呼は大和王朝のだれそれという比定することには意味がない】(p56)し、
【 箸墓の被葬者が、神がかりして神意を伝え、三輪山に鎮座する大物主神の妻とされ三輪山祭祀を行う巫女であることは、前述の卑弥呼の性格と不思議に一致していて興味深い。しかしながら、卑弥呼は第七代孝霊天皇の娘(倭トトト日百襲姫)であり、政治を担当した「男弟」が第十代崇神天皇であると論じても、それほど意味があることではないだろう。】(p57)、
ということであれば、なぜ南を東に読み変えることまでして大和に持っていきたいのでしょうか。
倭国は周旋五千里の島山に依る国。気候温暖で野菜を生食する風俗。地域名称は北部九州と思われるところが多く近畿地方を示唆するものは皆無。それでも大津教授は、卑弥呼は纏向にいた、とされる小林行雄氏説に肯定的なのはなぜでしょうか?
【卑弥呼は世襲王権ではない・・・・もう少し時間が必要だろう】(p55) 結論的には【 天皇家がここに成立したとは云えず】(p55)ともおっしゃいます。卑弥呼は天皇家の系譜には繋がらない人物と断定してもおかしくないのに、何となく歯切れが悪く、倭迹迹日百襲媛命 説に引っ張られている感じです。
しかし、纏向遺跡は『記・紀』の伝える天皇の系譜と繋がっている可能性は高いと思うのですが、大津教授はそうはされずに、纏向と卑弥呼との繋がりを一生懸命探そうとされます。
【卑弥呼は天皇系譜に位置づけられるのか。大和王権の発生の地が纏向だとして卑弥呼が大和政権の初代の王であり、のちに天皇制へつながっていくといえるだろうか。天皇の歴史の始まりになるのかというのが本書にとっての課題である。
わかりやすい問いにかえれば、たとえば卑弥呼を、「記紀」の伝える天皇系譜の中に位置づけることが可能なのか、そういう試みに意味があるのか、である。】(p55) と半ばギブアップ状態となっています。
大津教授は、倭人伝が卑弥呼の死後、男王が立ち、国が乱れ、卑弥呼の宗女壹與が立って治まった、と記していることから、【明らかに「記紀」の伝える「天皇」家のような世襲王権は未成立である。王権の次元が違うことに留意すべきである。】(p55)とされます。
王権の次元が違う、とは「万世一系」的な王権を「天皇の王権としてあるべき姿」ととっているようにも思われますが、穿ちすぎの見方でしょうか? ともかく、「邪馬台国=纏向遺跡」と唱えても、もう自分の地位を脅かすものではない、先輩達の説と違っていても叱られるおそれはない、逆らう弟子たちもいないと確信されているのでしょう。
また、【三輪山のふもと纏向の地には、箸墓古墳二八〇㍍が最初の巨大前方後円墳とされるだけでなく、それに先行する纏向型古墳といわれる帆立貝形の古墳が分布する。
さらに纏向遺跡からは巨大な溝や祭祀遺跡が発見され、また関東から吉備・九州にいたる日本列島の広い範囲からの土器が持ち込まれたことがしられ、多くの他地域からの人々が集まり住む都市的な場であることを、寺澤薫氏が詳しく論じている。(王権誕生) また宮殿のような大型建物の跡も発掘され纏向の地に王宮があったとの推定を大きく支持することになった。】(p53-54)ともいわれ
しかし、纏向遺跡の考古学的出土品からみても、倭人伝の描く女王の都とは大きな隔たりがあります。
例えば「倭人伝」に出てくる物には次のよう物があります。①鏡 ②矛 ③刀 ④鉄鏃 ⑤珠・玉 ⑥錦 ⑦金 これらが纏向遺跡から出て来たのでしょうか? 纏向遺跡からは、朱色に塗った鷄形木製品・木盾・木鏃・土器などで、辛うじて倭人伝に載っている「物」に近いのは絹製巾着袋位のものでしょう。
「倭人伝」に出ている「物」について、次のような報告が古田武彦著『ここに古代王朝ありき』に見られます。数値はすこし古いのですが、全体の傾向は変わっていないと思われます。
a)弥生期の漢式鏡の出土は、福岡県149 奈良県0
b)三角縁神獣鏡(舶載)は、福岡県22 近畿四県96(但し、三角縁鏡は弥生期でなく古墳期に属する)
c)銅矛 壱岐・対馬97 福岡県123 近畿六県0
d)鉄鏃 九州51 纏向では0だが、近畿全体だと22
e)鉄製の武器(刀・剣・矛・戈))だと、九州83 近畿2 五尺刀という表現のある大刀は、福岡佐賀だけでも12 関西では和歌山県有田市千田での1例だけ。
f)珠・玉については、日本が真珠の国であり、翡翠は糸魚川流域が産地として有名であり、出土例は全国的である。しかし、ガラス製の勾玉や管玉の出土は北部九州に限られ、その鋳型さえも出土している。
g)絹製巾着が纏向遺跡で出たことを注目されているようだが、福岡県では多くの絹関係出土例が報告されている。
①立岩遺跡刀子柄平絹の巻糸2点
②春日門田遺跡 剣身、柄巻の平絹2点
③吉武高木遺跡
④須玖岡本遺跡 鏡の平絹二点、房糸
⑤長崎三会村遺跡甕棺内の平絹
h)金については、どのような目的で使用されたのか出土品から見て、鏡等の鍍金、刀剣類の象嵌、王冠などの宝飾品と思われる。沖の島の龍頭・指輪、一貴山古墳の金メッキ銅鏡、宮地嶽古墳の 「頭椎大刀」残片など7点 など七世紀とされる古墳の金メッキ製品から、北部九州での金の使用が王族の権威を示す印として金が用いられたと思って間違いない。
余談ですが、一貴山の黄金鏡は現在京都大学博物館所蔵となっています。昭和二十七年に発掘調査が京都大学故小林行雄先生によって為され、研究のために大学に持ち帰られそのままになっています。筆者は二年前、一貴山古墳のある二丈町が町村合併になり糸島市になり、新たな市長選挙が行われたました。その折に、新市長に「黄金鏡里帰り運動」を計画しているのだが、と相談したことがあります。
当方の目的としては、黄金鏡を地元に取戻して、科学的にその「金」の精密な成分分析を行えば、産地にかかわる何らかの手がかりが得られないものだろうか、と内心望んでいました。しかし、市長が部下の方を使って調査されたところでは、【法的に所有権は京都大学にある。現在この黄金鏡は、何も隠匿しているのではなく、各地の博物館などの要請し従って貸し出し展示をしている。市としては取り上げる根拠がない。】とのことで、腰砕けになってしまいました。
閑話休題。この様な弥生期の倭人伝に係わりのある「物」が女王国の在処を示すのは、明らかに北部九州であり、纏向遺跡などの近畿地方ではないことは明らかです。大津教授のように、卑弥呼が纏向にいたとすると、近畿以西がまとまっていてそれがヤマト政権に発展した、ということになり、天皇の歴史をこの辺からはじめようとするのに都合が良い説ではありましょう。
★近畿説だと「狗奴国」の位置に矛盾がでる。
しかし、大津教授のように纏向=女王の都とすると、倭人伝の「狗奴国」との関係で矛盾が出てきて、又「南を東へ」と原文を読み変えなければならなくなるのです。
「狗奴国は女王の国領域の奴国の南」と書かれているのに合わなくなるのです。 大津教授だけではなく、卑弥呼は纏向にいた、と主張する方々も沢山いらっしゃるようです。
白石太一郎さんとおっしゃる国立歴史民族博物館名誉教授もそのお一人です。『古墳とヤマト政権』文春新書という本を一九九八年に出されています。卑弥呼が纏向にいたとすると対立していた狗奴国は何処にあった国だろうか、と誰しも思い浮かぶ疑問でしょう。
白石名誉教授は「尾張にいた」と主張されます。その本のなかで、狗奴国=尾張について述べているところを紹介します。
【邪馬台国のさらに南にあって、卑弥呼と戦った狗奴国との関係が想定される。玄界灘沿岸諸国のはるか南にあるとされる邪馬台国が近畿の大和にほかならないとすると、この南は東と読み替えることが可能となる。近畿のヤマトより東で対等に戦える勢力としては、濃尾平野の勢力を考えるのが自然である。邪馬台国と狗奴国の戦いは、その後の古墳の展開を見る限り前者の勝利に終わったのであろう。】
白石氏の意見について詳しくは、リンクを貼っておきましたので、当HP「槍玉その22古墳とヤマト政権」をクリックし参照下さい。
このように、倭人伝の行路記事を、南を東へ読みかえて、卑弥呼の国を纏向にもって来ると、狗奴国の位置も南を東に読みかえなければならなくなるのです。読みたいように読み替える、という手法がまかり通っているのが古代史学会の現状のようです。
★邪馬壹国への行路記事
しかし、『魏志』倭人伝というれっきとした中国の史書に出ている邪馬壹国への行路記事が、どうしてその様に理解しがたいものなのでしょうか。この書は西晋の時代に出されました。壹与が晋朝に朝貢したことを人々が知っている時代です。この「倭人伝」を読んだ当時の人は理解できた筈です。
陳寿(二九七年歿)が書いた『三国志』(倭人伝を含め)に、後に裴松之(四五一年歿)によって詳しい注書きがなされていますが、行路記事では何も記されていません。少なくとも、裴松之には矛盾なく理解出来たと思って間違いないと思います。
古代の中国文は句読点が無く、特別なことがなければ改行もしません。後漢書の「倭国之極南界也光武賜以印綬」でも、「也」で切るか切らないかで文意が大きく変わります。近年でも中国文には句読点はありません。文章の切れ目にスペースを空けることで、字間があることを示して文章を区切って文意をはっきりさせています。
この倭人伝の外国への行程記事としては、「距離」と「日程」、つまり中国とどれくらい離れていてどれくらいの日数でいけるのか、が不可欠です。
この点に注目して、行路記事に、投馬国の次に書かれている「南至邪馬壹国水行十日陸行一月」は、今なら改行された文章でしょうが、これは行路の締めくくりであって、「帯方郡から邪馬壹国への総日程」と読んだのが古田武彦氏でした。
この画期的な説は『「邪馬台国」はなかった』というタイトルで朝日新聞社から一九七一年に刊行されました。 以後四〇年になりますが、この行路記事を始め、邪馬壹国が九州に存在したという説が、大和王朝一元説の学会の牙城を崩すには至っていないのが現状のようです。
しかし、歴史学界以外では、大和王朝だけがあったのではなく、古代には九州にも、出雲にも、関東にも、東北にもそれぞれ「国としてのまとまりがあった」という、合理的な考えは拡がっているようです。
大津教授は、文献だけでなく鏡という出土品からも邪馬台国は纏向だとされますので、それらと合わせて、もう少し「邪馬台国論争」を見ていきましょう。
★邪馬台国問題と三角縁神獣鏡について
大津教授は、重要なのは小林行雄氏(故人 元京大教授)による三角縁神獣鏡の同笵鏡の分有関係の研究である、として小林氏の研究を紹介されます。
【これは縁部が三角形状に突起し神仙や獣の図様を持つ大型鏡で、「景初三年」などの魏年号を持つところから魏に朝貢して卑弥呼に賜与された鏡と考えられる(のちに仿製三角縁神獣鏡が作られる)。その同笵鏡(一個の鋳型から作られた複数面の鏡)の分有関係を調べると、椿井大塚山古墳など畿内が中心で、九州から関東へ配られたことがわかり、卑弥呼は畿内にいたはずである(太字化は筆者)。
なおこの三角縁神獣鏡は中国大陸では出土していないことから、日本製ではないかとの説がある。しかし鏡研究家によれば、舶載鏡(大陸から搬入した鏡)と仿製鏡(日本で真似て製作した鏡)には技術に差があり、認められないようである。 (中略)
もし仮に日本製だとしても、年号などから卑弥呼が魏から賜わった鏡として配られたことはあきらかだから、中心が畿内にあることは動かないだろう。 小林氏は、古墳に三角縁神獣鏡が埋納されることについて、古墳時代の開始は四世紀初頭であるので、卑弥呼が各地の首長に配布したあと、五〇年以上大切に宝物として保管し、その後古墳に埋納されたと考えた。しかしこれに対して九州説では、邪馬台国あるいはそれを滅ぼした某国が、三角縁神獣鏡など邪馬台国の財宝をもって東遷して畿内に入り、大和政権を樹立し、古墳に鏡を埋めたと考えるのである。 】(p44~45)
大津教授は小林行雄氏の研究を紹介する形で「卑弥呼が畿内にいた」と説明されているととれます。小林行雄さんは1911年生まれで、考古学の大御所として君臨された方です。それにしても古い学説を持ち出されたものです。
いくら小林さんが偉い方でも、その説に非合理な点を数多く含んでいることは、最近の学説も含め以前から数多くの方から指摘されています。しかもそれらの疑問点は合理性に富むものです。大津教授が小林説を正しいとされるのであれば、おかしな「九州説」を説明するのでなく、まともに向き合って貰いたいものです。
大津教授は、卑弥呼に魏朝から下賜された三角縁神獣鏡は、地方の小支配者に分配された、と次のようにも述べます。
【地方豪族に対して剣や鏡が分与され、一方で豪族は服属の証しに彼らが祭る剣や鏡を献上したのだろう。福永伸哉氏によれば現在確認されている三角縁神獣鏡の数は、舶載鏡が約三九〇面、仿製鏡が約一三〇面併せて約五二〇面となる。卑弥呼がもらったのは一〇〇面だから、おそらくその後半世紀にわたって魏や中国東北部から輸入がつづけられたのであろう。
仿製鏡の製作の契機は、小林行雄氏の「大和政権が地方の小支配者にたいして中国鏡を分配していった段階において、中国鏡のストックが底をつく時期が到来した。そこで応急策として、「仿製鏡をもって中国鏡にかえるという方法が立案され」たという理解が妥当だろう。】(p72)
全く東大国史学科教授というわが国最高峰の学者らしからぬお粗末極まる立論と思いませんか。『魏志』倭人伝にくわしく卑弥呼の国との関係が述べられている末盧・伊都・不弥・奴などの北部九州には弥生初期の墳墓から沢山の中国鏡(漢鏡)は出土するのに、なぜ三角縁神獣鏡は出土していないのか、その説明も必要でしょう。
「三角縁神獣鏡は、卑弥呼が魏から下賜されたものである」、ということへの疑問の主なものは次の六個にまとめられるかな、と思います。
①現在までに発掘された三角縁神獣鏡は五五〇面を越えるという。発掘されていない同様の鏡はその数倍乃至十倍はありうる。魏から倭国への特注品としても無理な数ではないか。
②黒塚古墳が顕著な例だが、三角縁神獣鏡は棺外に多数配置され、中国鏡(後漢鏡)が棺内に置かれている。このような状況からみて、三角縁神獣鏡がそれほど崇拝に値する物ではなかったのではないか。
③中国にも朝鮮半島にも三角縁神獣鏡が出土しないこと。つまり国産である可能性が非常に高い。
④当時の倭国では鏡を鋳造出来ないというが、弥生期の代表的な青銅器の一つ銅鐸はどうなのだ。大型銅鐸を鋳造できた当時の技術レベルを軽視しているのではないか。
⑤三角縁神獣鏡が出土する古墳は四世紀の物が多く、三世紀の古墳(つまり卑弥呼の時代)からの出土はみられない。(最近の古墳時代の繰り上げが、この「無理」を修正したいという勢力の願望による圧力でなければよいのですが。)
⑥魏朝は部下に分配せよとは言っていない。皆に見せて魏朝のオボシメシを知らしめよ、と「倭人伝」に書いてある事に反する。 などが上げられます。
これらについて大津教授は、①最近の研究で古墳築造年代が繰り上がった。②中国から卑弥呼への特注品であった。などと反論されていますが、前述のように【 かりに日本製としても年号などから卑弥呼が魏から賜った鏡として配られたことは明らかだから、中心が畿内にあることは動かないだろう。(太字化は筆者) 】(p44-45)と強弁されています。
つまり箸墓古墳は三世紀中葉までさかのぼり、卑弥呼の時代に合うということがその論拠になっているようです。
しかし、三角縁神獣鏡が出土するのは四世紀以降の古墳からのみで、卑弥呼の時代である三世紀の墳墓からは一面も出土しておらず、年代が合わないのです。箸墓の築造年代が三世紀に繰り上がっても、その箸墓から一面も鏡の出土はありません。
第一に前述のように、古墳期前期の黒塚古墳に副葬された鏡は、棺内被葬者頭部に画文帯神獣鏡(漢鏡)が置かれ、三角縁神獣鏡は棺の外に三十二面も配置されています。この例からも明らかに三角縁神獣鏡は「卑弥呼からの下賜品」らしくない扱われ様なのですが、大津さんは「 考古学は素人であるが」(p44)として逃げることだけなのです。
最後には「 卑弥呼が魏から賜った鏡として配られたことは明らかだから・・・」(前出)と断定するなど、東大教授らしからぬ蛮勇をふるわれるのは驚きです。
このような大津透教授が率いる東京大学国史学科の将来はどうなることかと心配です。
★「繰り上がる弥生時代」
わずかに頼みの綱とされているのが、三角縁神獣鏡への疑問⑤と関係があるのですが、「繰り上がる弥生年代」という最近の測定技術の進歩による仮説です。「繰り上がる弥生時代」とはどういうことなのか、このことについて大津教授は次のように述べます。(p45-46)
【弥生時代は紀元前四~三世紀にはじまり、紀元後二~三世紀ころまで、というのが大体の通説であった】、と言うような事を述べ、【 ところが近年、弥生時代の年代がもっと古くなり、(弥生時代)後期は紀元後一世紀から二世紀まであるいは二五〇年くらいまでと五〇~一〇〇年繰り上がって考えられるようになった。】と書かれます。
その理由として「年輪年代法」と「放射性炭素法」の研究の進展に伴うものである、と説明されています。【 しかし、放射性炭素法に従うと弥生時代は五〇〇年も従来より遡るということになり考古学会ではあまり従う人はあまり多くなく、専門外の筆者には判断できない。ただ年輪年代法とあわせれば、弥生時代の年代は少し古くなることは確かなようである。】と結ばれています。
春成秀爾氏(国立民俗歴史博物館教授)の『考古学はどう検証したか』によりますと、弥生時代の始まりは紀元前九百~一千年で、北部九州と近畿地方ではその始期が百~百五十年ほど差がある(北部九州が早い)と報告しています。 大津教授は、【年代年輪法、放射性炭素法によって弥生時代が五〇〇年ほど繰り上げられ、古墳時代も若干繰り上げられるだろう】、と言います。
しかし、「古墳時代の繰り上がり」については、一般的な個々の古墳が土器分類年代測定などとの関係で変更されたのか、箸墓の築造年代変更に伴っていわば機械的に引き上げることにされるのか、もう少し詳細な説明が要ることでしょう。
例えば、従来の古墳年代設定で四世紀とされていた箸墓古墳のみならず、今まで四世紀初めごろの築造とされていた北部九州の前方後円墳・那珂八幡古墳や前方後方墳・焼の峠古墳もその築造年代が繰り上がるとすれば、単に「卑弥呼の墓=箸墓」問題のみならず、前方後円墳形式の「近畿→全国の伝播経路」にも大きな影響があるといえます。(前方後円墳の九州発祥説が有力になるなど)
それにしても、前方後円墳の伝播の最初の原形式が「最大規模の箸墓」という説には、かなり説明に苦しむ説と思います。なぜなら、「大→小という墓の変遷」というのは常識外れの判断で、小→大となり、あまり大きさを競うようになり再び→小というのが常識的判断、というものでしょう。
古墳時代も引き上げられる、として次のように述べられます。(p47-48)
【一九九七年から一九九八年にかけて天理市黒塚古墳から、なんと三三面もの三角縁神獣鏡が発掘された。二〇一〇年になってメスリ山古墳から鏡の破片が八一面分出土し、中に「正始元年」銘の三角縁神獣鏡があった。このことは卑弥呼の邪馬台国がまさに奈良盆地南部のヤマトにあった可能性を強める。】
また、【これらの魏鏡は二四〇年前後に古墳に納められた可能性が高い(福永伸哉氏説)により、古墳時代の始まりも三世紀中葉に引き上げられることになり、この事は弥生時代の新しい年代観とも合致するのである。】と話を進められます。
三角縁神獣鏡と卑弥呼との関連について、【したがって、卑弥呼の遣使、鏡の賜与と古墳への埋納とは時間的に連続することになり、邪馬台国が東遷して大和にはいってから鏡の配布をしたとする九州説は成立しなくなったといえる。そして卑弥呼は二四七年頃没したので、最初の巨大前方後円墳である箸墓と年代がほぼ重なると考えられ、箸墓は初代の倭王卑弥呼の墓だという新聞報道がさかんになったのである。】というように言われます。
大津教授は、鏡の分有関係から見て卑弥呼は畿内にいた可能性が高く、古墳時代が引き上げられたことにより、九州にあった邪馬台国が東遷したとする九州説は成り立たなくなった。卑弥呼の死亡年代と箸墓の築造年代とも合う、ということになった。だから、新聞など報道機関も纏向遺跡に注目するようになった、と最後は新聞報道に判定を求めるかたちで結ばれています。(この新聞報道などについては後述)
前述のように「黒塚古墳」での多数の三角縁神獣鏡の出土状況は、疑問②に述べたように、問題があるのに大津教授は、あえて問題から目を逸らされます。 また後述しますが、「箸墓=卑弥呼の墓」説には数多くの疑問が投げかけられていることも大津教授は充分知っていながら無視されるのです。
しかし、大津教授の立論にはそれ自体に論理の飛躍を含んでいます。つまり、「三角縁神獣鏡が沢山古墳から出土した」ことが、「卑弥呼がヤマトにいた」ことの証明にはならないということです。大津教授が並べる資料から得られる結論は、大和地方の大王というか酋長というか、ともかく実力者が鏡の信奉者であり、鏡を製作し配布した、ということくらいまででしょう。
三角縁神獣鏡が卑弥呼の貰った鏡ではありえないことについての、古田武彦氏の意見を紹介しておきます。
【まず、伝世説への疑問。四世紀以降築造の所謂古墳期の遺跡から三世紀の鏡 (三角縁神獣鏡)が出土する。それを「これらは全て弥生期から伝世したものです」、と主張する学者がいる。なぜ、三角縁神獣神鏡は魏鏡と認定されたか、それには富岡謙蔵氏の意見(詳細略)が大きかった。
景初三年鏡を以て魏鏡の証拠ともされるが、この鏡の銘は「景□三年」であり、これを景初とすることは自ら字を補って自説の証拠とする手法「自補自証主義」と言える。(この「初」でなく「元」を入れると蜀の年号となるし、「帝」と入れると前漢の年代となり、「徳」といれると宋の年代となる。)中国・朝鮮で出土せず日本列島でだけ大量に出土する、このことだけでも国産は明らか。
なのに何故中国製とするかというと、ちゃんとした銘文があるから中国製だ、当時の日本には文字が到来していなかった、ということだろう。新しい見地からの三角縁神獣鏡の見方は次のようである。
(一)出土分布図から見て、三角縁神獣鏡は当然日本列島内での製作品である。
(二)しかし、これが、中国や朝鮮半島からの渡来人やその弟子の作品である可能性は充分ある。
(三)上質の銅で作られている場合、「輸入白銅」で作られた可能性もある。
(四)倭人伝から見ても、『記』『紀』の「王仁の『論語』『千字文』」伝承説話からみても、四世紀の日本列島に「文字」が伝わっていたことは確実である。“文字がある”という理由で三角縁神獣鏡を「非国産と見なすことは出来ない。
(五)逆に四~五世紀の日本列島(近畿領域)に“文字が知られていた”ことは、この三角縁神獣鏡という「文字ある銅鏡」の大量出土自体が遺憾なく証明している。】(古田武彦著『ここに古代王朝ありき』より抜粋) 以上です。
大津教授の「卑弥呼が部下に分配した」という仮説が全く成り立たないことが理解頂けるものと思います。
ところで、大津教授の大先輩、佐伯有清氏が『邪馬台国論争』2006年で三角縁神獣鏡について次のように述べられています。
三角縁神獣鏡と称せられる鏡が近畿地方の古墳から夥しく出土していて、これらの鏡が、『魏志』に記してある魏帝から下賜された鏡であり、したがって卑弥呼の国は近畿に相違ない、という邪馬台国近畿説について、同書の第五~六章にかけて、所謂三角縁神獣鏡と邪馬台国についての論争が述べられます。
古墳で有名な森浩一さんの、古墳時代の出土鏡は三世紀の魏鏡でないという研究結果を発表された、『日本の古代文化―古墳文化の成立と発展の諸問題』一九六二年 を紹介しながらも、結論的に佐伯氏は次のように締めくくられています。
【二〇世紀百年を経た邪馬台国論争は、二一世紀に入ったいま、どのような方向に深められていくのであろうか。恐らく三角縁神獣鏡をめぐっての邪馬台国論争が、いっそう熾烈なものになることは間違いないであろう、云々。】(同書 188)
この佐伯さんの期待にこたえたのか、大津教授が「三角縁神獣鏡は卑弥呼の鏡に間違いない」と発展させられているのはさすが東京大学国史学科の佐伯さんの後輩の面目躍如です。この佐伯有清さんの『邪馬台国論争』批判を当HPで発表しています。リンクを貼ってきましたのでクリックし、ご参照ください。
★銅鐸について
それにしてもこの大量の銅鏡の材料をどうやって確保したのでしょうか?また、この近畿地方から数多く出土する銅鐸、これについて大津教授は何も述べられません。
近畿地方には「王権の象徴」として「神器 銅鐸」が存在していたのではないでしょうか。鏡は全て中国からの輸入というわけではなく「仿製」つまり国産を認めておられるのですから、鏡の材料、銅の入手についても考えを巡らすべきではないでしょうか。
先述の三角縁神獣鏡疑問点④にも上げましたが、銅鐸を検討すれば、三角縁神獣鏡舶載説の根拠は崩れてしまいます。だから、とは思いたくないのですが、大津教授は銅鐸について述べたくないのでしょう。
もうひとつ重要なことは、弥生後期の大型銅鐸が、奈良県には殆んど出土しないという考古学上の謎があります。このことについて大津教授の古代王権史からの見解をお聞きしたいものです。 このような祭祀器具の変更は王権の交替と考えるのが理性的だと思いますし、ヤマト政権の発生と関係があると思うのも合理的推測でしょう。
以前のヤマトの王者が銅鐸信奉者であり、後に銅鏡信奉者にとって代わられ、銅鐸は集めて鋳潰され、銅鏡に生まれ変わった、というのは合理的推論と思うのですが大津教授如何でしょうか?
この出土分布の異常さについては、著名な考古学者佐原真氏(故人 元国立民俗歴史博物館長)も、邪馬台国大和説に立たれながら、説明に苦慮されたようです。 『銅鐸が描く弥生時代』という本があります。考古学者として著名な金関恕氏(天理大名誉教授)と佐原真氏の共著となっていますが実質的には佐原さんと、そのお弟子さん的な寺沢薫さんなど六人の共著です。
奈良県の銅鐸不出土問題に直接答えているわけではありませんが、佐原さんに代わって寺沢さんなどが、「なぜ銅鐸は消滅したのか」、という推論を述べています。ことわっておきたいのは、これらの方々は邪馬台国九州説とは無縁の方々ということです。 何故壊されたのか、何故消滅したのか、について概略次のように言われています。
【破片となった銅鐸出土は「見る銅鐸」でそれも近畿式銅鐸に多い。破片出土の銅鐸が全て故意に裁断されたとはいえないし、再利用された場合もある。弥生終末期にはより急激な社会変動を来たしたようだ。集積・埋納され一部は破壊破棄され銅鐸祭祀は終焉する。これは、広域社会の崩壊を意味し、新たな地域社会の幕開けと理解できる。】
これも当HP上で紹介しています。次のURLです。クリックしてご参照ください。
http://www6.ocn.ne.jp/~kodaishi/yaridama24doutaku.html
大和には初期銅鐸の出土はあっても所謂後期の「大型の聞く銅鐸」の出土がない。 銅鐸学者は何故、神武東征伝承を避けてとおるのでしょうか。この疑問への解として、古田武彦『ここに古代王朝ありき 邪馬一国の考古学』での古田武彦氏の意見を紹介しておきます。
【大和には初期銅鐸の出土はあっても所謂後期の「聞く銅鐸」の出土がない。銅鐸学者は何故、神武東征伝承を避けて通るのか。 ヤマトにおいては弥生中期では、「銅鐸盛行の時代」として「銅鐸」そのものや鋳型が出土する。
ところが「無金属期(銅鏃を除く)」に近い「弥生後期」(ことにその前半)を経て、「銅鏡盛行の時代」が始まる。この「銅鐸~銅鏡」の変転について、これを同一地域の、同一種族による(自然なる)変転とみなすことは、人間の理性、その常識において困難だ。
「銅鐸という自己の地伝来の『宝物』(神器)を捨て、他地域(北部九州)の『宝物』(神器)たる銅鏡を取る。」というには、単なる「流行の変移」などにあらざる、決然たる意志が不可欠である。】
このように、折角、民族の伝承、記紀に残る神武東征の物語を、考古学的出土品と関連して考える事のできない、「皇国史観」の自縄自縛を批判されています。 大津東大教授にも、トロイの遺跡と神話を見事に結合し昇華させたシュリーマン同様に、もっと大きく目を見開いてもらいたいものです。
★古代の男女政権について
大津教授は話を次に「男女政権」に話を進めます。 【卑弥呼も男弟がいて「男弟ありて国を治む」と倭人伝にある】、と紹介しています。【 『記・紀』や各種『風土記』などから、宇佐の莬狭津彦・莬狭津媛、阿蘇の阿蘇津彦・阿蘇津媛、吉備の吉備比売・吉備比古などの例を引き、古代は男女二重政権だっただろう。】(p48)とされます。
そのこと自体はともかく、それから話は神功皇后もその例ではないか、という風に話が進みます。 そして【神功皇后の日本書紀の記事と倭人伝の卑弥呼のシャーマン的な記事と重ね、神功皇后と仲哀天皇の夫妻が、卑弥呼と男弟と同様の二重主権だったと考えられる】(p50)、とされます。
その後の、推古天皇が神祗を祭った記事、皇極女帝の雨乞いの記事などを上げ、【 天皇には卑弥呼以来の呪術の能力を、おそらく男帝も、継承している】(p52 後出)、と話を進めるのです。
この男女王権とシャーマン的な王という問題について、なぜか大津教授は「兄弟王権」ということについて足を踏み入れないのです。単に「男女」というペアだけでなく、「兄弟」というペアの王権が資料に残っています。『古事記』に伝わる小碓命の熊曾建兄弟征伐や、金石文として残っているのが、大津教授も紹介されている和歌山県の隅田八幡の鏡の銘文です。
そこには、「大王と男弟王」とはっきりと記されています。また、隋書に書かれている「多利思北孤」の「日が出るまでは兄が仏に仕え、日が出た後は弟が政事を行う」兄弟施政の例など、『記・紀』にその例がみられないので大津教授は取り上げたくないのでしょう。しかし、この大津教授の本は「天皇の歴史」というメインタイトルです。是非大津教授の見解をお聞きしたいものです。
★卑弥呼の鬼道について
もう一点の話は、卑弥呼のシャーマン的な倭人伝の記事です。「倭人伝」には“卑弥呼は鬼道に仕え衆を惑わす”というように書かれています。三世紀当時の「鬼道」という意味はどのようなものであったのかチェックする必要があるでしょう。
先ほど引用しましたように大津教授の見方は、現代風に「シャーマン的」つまり、超自然的存在と直接接触・交流・交信する役割を主に担う役職で、呪術者・巫女・祈祷師などと同様にとられているようです。 大津教授は大略次のように書きます。
【 皇極元年(642)にはひでりが続き、さまざまな雨乞いの行事が試みられ、蘇我入鹿は仏教により大雲経を読ませ、自らも香炉を焚いたがあまり効果がなかった。そこで皇極女帝が“天皇、南淵の川上に幸して跪きて四方を拝む。天を仰いで 祈ひたまふ。即ち雷なりて大雨ふる。遂に雨ふること五日。溥く天下を潤す。
是に天下の百姓、倶に称万歳びて曰さく「至徳の天皇なり」とまうす。”と自ら雨乞いに成功した。『日本書紀』には天皇の日常の宗教活動は記されないが、卑弥呼以来の呪術の能力を継承しているのである。(おそらく男帝も) 】(p51~52)
なんとなく、大津教授は「天皇」を特殊人間視しているようにもとれます。
大津教授は、この『天皇の歴史01』の最初の章で「天皇研究の出発」という項目を立て、日本史にとって最大のテーマ・戦前から戦後への古代史研究について網野善彦氏の”王権論からの考察”などを紹介されています。
【網野善彦『異形の王権』、黒田日出男『王の身体 王の肖像』が刊行され、後醍醐天皇の分析など、絵画資料を用いながら王の「異形」や「身体」を考察している。(中略)エルンスト・カントーロヴィチの王には物理的肉体と別に永続性のある次代の王に継承される身体が、つまり二つの身体があるとの指摘などもふまえて、「王権論」が日本中世史に導入されたといえる。】(p20)
このように、「天皇論」は神秘主義に同意するかのような大津教授の論調で進められていることに留意しながら、この本は読む必要があるようです。
「倭人伝」がいう鬼道とは端的にいうと「敵を祭る」ということだ、と古田武彦氏は説きます。
【論語に「鬼神に事える」という言葉が出てくる。よく使われる「断じて行えば鬼神も之を避く」などもある。鬼神とは、「孝を鬼神に致す」という言葉に在るように「先祖の霊」を鬼神と孔子は言っている。
卑弥呼の「鬼道」はどういう意味なのか。同時代の遺跡「吉野ヶ里遺跡」では沢山の首なし甕棺が出土している。これは「敵を祭った」のであろう。同時代の崇神天皇の説話「建波邇安を殺したあと、彼の出身地の河内の豪族を神主として、大物主大神を祭らせた」というのも「敵を祭る」という行為として、卑弥呼の「鬼道」と同様な精神だ。
神道の大祓の祝詞にも「天つ罪、国つ罪」の双方を「祓へたまひ清めたまへ」も天つ神、国つ神双方の罪を許すようねがっている、これも同様な精神の流れであろう。(続けて)楠正成の千早城に敵方の立派な墓碑が、乃木希典の対ロシア軍人に対して、第一次大戦の対ドイツ兵に対して、日清戦争における清国兵に対して建立された墓碑等にその精神が公的に受け継がれている。】(『日本評伝選 俾弥呼』古田武彦 p324~332から抜粋)
大津教授は、卑弥呼の鬼道について「シャーマン的」という現代人の感覚的なもので解釈されているようですが、三世紀のわが国は「敵を祭る」という鬼道があったこと、それが引き継がれていることを理解した上で、天皇家の儀式の底に在る精神を理解しなくてはいけないのではないでしょうか。
★ヤマタイコクの読み方と纏向遺跡
そして話は「邪馬台国が大和にあった可能性」という、いわば「邪馬台国論」の花道へ到るのです。大津教授は次のように書きます。
【邪馬台国が大和にあったとすると、後の大和政権につながることになる。卑弥呼により大和政権が成立し、卑弥呼が大和王権の初代の王・大王ということができるだろうか。】(p52)と問題設定をされます。
つづいて、【邪馬台国は、ヤマタイコクと訓むが、これは便宜的にそうしているので、本来ヤマトに中国人が邪馬台の字をあてたもので、ヤマト国である。そのヤマトは、大和国の中の地名ヤマトに起源があり、おそらくは山(三輪山)のト(ふもと)の意だろう。】(p52)と「邪馬台国」の国名の起源についても断定的に述べられます。
ヤマトは山の麓乃至入り口の意でしょうし、大和国だけでなく、全国に沢山あることでしょう。大和に起源があるとどうして断言できるのでしょうか、東大教授なら断言できる権限をお持ちだと錯覚されているのでしょうか。東大教授らしく、理に基づいた学問の大道を歩いて欲しいものです。
Tokyo古田会NewsNo.147(2012年11月)に平松健氏が、”「邪馬臺は「やまと」と読めるか”という論文を発表されています。棟上寅七よりももっと深い資料探索をされての結果を発表されていますのでお知らせしておきます。
ところで、三輪山のふもとの纏向の地に「箸墓古墳」が存在することについて、大津教授は概略次のように述べられます。
【 箸墓古墳が最初の巨大前方後円墳とされるだけでなく、それに先行する纏向型古墳といわれる帆立貝型の古墳が分布する。さらに纏向遺跡からは巨大な溝や祭祀遺跡が発見され、日本列島の各地から土器が持ち込まれ、多くの他地域の人々が集まり住む都市的な場であることを寺沢薫氏が詳しく論じている。近年大型建物遺構が発見され、纏向の地に王宮があったとの推定を大きく支持することになった。】(p53-54)と。
それでは卑弥呼が天皇系譜に位置づけられるのか、というとそこまでは言えないとされます。その理由として次の事を挙げられています。
【 卑弥呼の死後について倭人伝は「邪馬台国連合は、卑弥呼を共立しその呪術力によってようやく治まったが、その死後、別の男王を立てたが治まらず、ようやく台与(壱与とも)という十三歳の少女を王として治まった。卑弥呼の宗女とあるが、卑弥呼には夫はいないので、血縁はあるかもしれないが娘ではなく、やはり呪術力が期待されたのだろう。」とあり、明らかに記紀の伝える「天皇」家のような世襲王権は未成立である。王権の次元が違うことに留意すべきである。つまり天皇家がここに成立したとはいえず、世襲王権の成立にはなお時間が必要だろう。】(p55)と述べ、
【 日本書紀には垂仁天皇が纏向の珠城宮、景行天皇の纏向の日代宮と伝えている。個別断片的には大和政権の発祥の宮の記憶をつたえているのかもしれない。】(p56)とされます。そして、【 日本書紀は神功皇后を卑弥呼にあてているが、「三韓征伐」」は卑弥呼の時代とあわないし、次に立てられた男王に応神天皇を比定することは無理といわざるをえない。】(p56)とギブアップ状態となり、次に話を三種の神器などの「レガリア」から天皇位の継承を見ていこう、ということになります。
しかし筆者は、纏向遺跡は大津教授も「垂仁天皇が纏向の珠城宮、景行天皇の纏向の日代宮などの『日本書紀』の記述を紹介されているように、『記・紀』の伝える天皇の系譜と繋がっている可能性は高いと思うのですが、大津教授は卑弥呼との繋がりを一生懸命探そうとされます。そして、卑弥呼は天皇系譜に位置づけられるのか、と大津教授は自問されます。
【大和王権の発生の地が纏向だとして卑弥呼が大和政権の初代の王であり、のちに天皇制へつながっていくといえるだろうか。天皇の歴史の始まりになるのかというのが本書にとっての課題である。わかりやすい問いにかえれば、たとえば卑弥呼を、「記紀」の伝える天皇系譜の中に位置づけることが可能なのか、そういう試みに意味があるのか、である。】(p54)
しかし、後述のように、神武東征神話を検証すると、邪馬壹国の分流が大和に侵入し、三世紀にはそれなりの地方政権を建てた可能性は非常に高いのです。そうなると卑弥呼と同時代に活躍していると思われる崇神天皇あたりと箸墓との関連性を検討することは、『天皇の歴史』にとって大きな意味があることと思いますが、大津教授如何でしょうか?
津田左右吉大先輩以来の「創作説」の金縛りにあっているのは痛ましい限りです。大津教授の言う【 王権の次元が違う】が、「万世一系」的な王権を「あるべき王権の姿」としているのであれば本末転倒の論議に思えます。
★「壹」と「台」について
【卑弥呼の死後、宗女台与(壱与とも)を立てた】、というように大津教授は書いています。(p54ー55) 倭人伝には「壹与」とはっきりあるのに、何故「トヨ」になるのでしょうか。
壹と台(臺)の問題について、まず検討してみましょう。「壹と臺(台)」、これは実はいわゆる「邪馬台国」問題の基本なのです。三国志の版本には全て邪馬“壹”国となっているのに、なぜか壹は臺の誤り、として歴史教科書などでも、邪馬臺国ないし邪馬台国と記しています。
なぜか、ということで古田武彦氏が史学雑誌に発表されたことは先に述べました。 「壹を台と読む」これも、後に出てくる稲荷山鉄剣銘文の「獲加多支鹵」を雄略天皇に持っていきたい為に「ワカタケル」と読む、その精神と同じです。邪馬壹国では「ヤマト国」と読めない、邪馬台国なら「ヤマト国」と読める、という恣意的な誤字説なのです。
しかし、この倭人伝の中には、邪馬壹国・壹与(三回)・壹拝と、臺(因って臺に詣り)などと、臺と壹とは完全に書き分けられています。「臺」を「ト」と奈良時代以前に訓んだ例は見えないのですが、「台」は「ト」と訓じた例もあるのです。だからヤマトと読みたい人は邪馬臺国と書かず、邪馬台国を使うのです。大津教授もその先入観念に捕われた囚人のお一人のようです。
魏志倭人伝には「壹與」とはっきり書いてあります。なぜこれが「台与」になるのか、大津教授は頬かぶりで済ませています。一般には「壹は臺の書き誤り」として済ませていますが、大津教授もおそらくは、この通説に無定見に乗っていらっしゃるのでしょうが、理由も何も言わないのは傲岸無礼という言葉を失礼ながら思いだしてしまいました。
しかし、「壹」を「臺」と書き換えても邪馬臺国ではヤマト国とは読めないのです。そこでもうひと捻り加えます。「臺」を使わず「台」を使い邪馬台国とすると、やっとヤマト国と読めるようになるのです。 現在「台」は「臺」の略字として使われているのですが、元来は別の文字なのです。
「臺」が「ト」と読めるか、という問題について古田武彦氏は次のように解説されます。氏が、「臺がなぜトと読めるのですか」と、漢和大字典を編纂された藤堂明保氏に聞かれたそうです。その経緯について、概略次のように『邪馬壹国への道標』で述べておられます。
【奈良時代以前に「臺」を「ト」と表音文字として使われた例はないのに、どこから、この読みを、との問いに、藤堂先生は次のように答えました。日本の歴史学者の皆さんが、「邪馬臺」は「ヤマト」と読まれるので、と。】
漢和大字典には藤堂先生編集の、「ト」を表す漢字一覧表があります。確かに漢和大字典では乙類の「ト」の一覧表に、一番下に一線を画して臺もトと読む類に分類されています。
著者は安本美典氏の『虚妄の九州王朝』という本を、このHPで批評したことがあります。興味ある方は「槍玉その19 虚妄九州王朝」批判にリンクを貼っておきましたのでクリックしてみて下さい。
安本美典氏は、藤堂明保先生編集の『漢和大字典』「ト」を表す一覧表を出されていますので、参考に転載しておきます。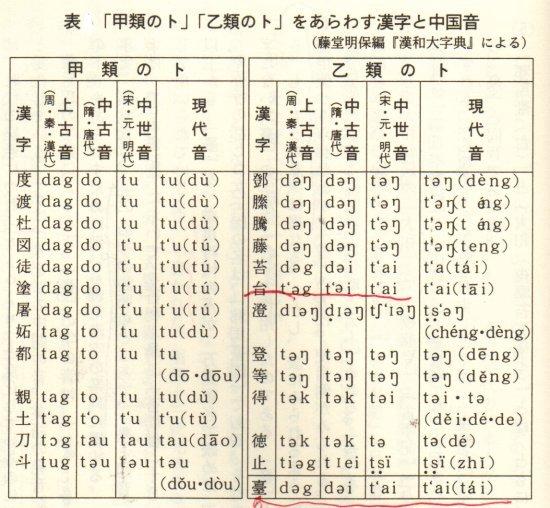
★森浩一氏の「壹と臺」と「景初三年」論
大津教授が邪馬壹国を邪馬台国と何の断りもなくつかわれるのは、ひょっとしたら、古代史で一定の評価がある森浩一氏の減筆説もあり、それに乗っていらっしゃるのかもしれません。 森浩一氏は『魏志』にある壹は臺の略字(減筆による)と堂々と主張します。
森浩一氏の減筆説をご存知ない方もいらっしゃるでしょうから、本筋からは外れますが、「臺は壹の間違いではない」という説明の例として紹介しておきます。 倭人伝の誤記誤写関係で「景初二年問題」も出ていますが、大津教授も【景初二年は三年の誤り】(p40)としていますし、参考に森浩一氏批判を引用します。ちょっと長くなりますがお許し下さい。
森浩一『倭人伝を読みなおす』ちくま書房 2010年 の倭人伝の誤記誤写の箇所について
(A)。景初二年の遣使は三年の誤りとされます。
森浩一氏は、倭人伝が卑弥呼の遣使を景初二年としていることについて次のように説明されます。 【景初三年の遣使としているのは『日本書紀』が神功皇后の三九年の条に引く『魏志』であり、このほうが本来の『魏志』の文章を伝えているとみられる。『魏志』は日本でも早くから読まれていた。】
しかし、森浩一氏はこの本で「倭人伝」の参照原本として、乾隆四年の「乾隆欽定本」を上げているのです。そこには「紵」が、糸扁に右の旁が、ウ冠の下が「丁」でなく「一」となっているのです。これを減筆の例と挙げられます。
他の版本、「紹興本」(南宋紹興年間 、刊行された)、「紹煕本」(南宋紹煕年間(1190-94) の刊行とされる)、には全て「紵」とありますし、異字体として辞書にも見えません。これは誤刻と取るのが学者としての判断であるべきでしょう。
しかし、森浩一氏は数ある倭人伝関係の史資料の内から、わざわざ「乾隆欽定本」を上げています。ところが、皮肉なことにそこには景初「二」年とあるのです。だとすれば、森浩一氏はなぜ、「乾隆欽定本」に逆らって「三」年とされるのか、その理由を説明する責任があると思います。しかし、森さんは口をつぐんでいます。
著者が推し量るに、「乾隆欽定本」に「紵麻」の紵が左下図のような異常な字が使われていることに、森さんが着目したからでありましょう、「これは使えるぞ!」「減筆の例に!」と。 これは、中国の辞書にもみられない異字体で、誤写ないし誤刻は明らかだ、と思われるのですが、それは森浩一氏にとっては持ってこいの「減筆の流行」の例であったのでしょう。

前述のように、森浩一氏が参照原本として全文掲示されている「乾隆欽定本」には、卑弥呼の魏朝への遣使の時期は、景初「二」年とあります。それがなぜ、景初「三」年に増筆されたのか、古代学者森浩一氏の見解は、【『日本書紀』の編集者が参照したであろう『魏志』の記事に三年とあった】と、「二」を「三」とされるのです。
「倭人伝」より五世紀も後の、『日本書紀』編集者が、どのような史料を参照したのか分からないのに、中国の史書を後世の日本の史書の記事に基づいて修正する、これでは中国の歴史研究家は勿論、理性ある歴史家には納得できないことでしょう。
この『日本書紀』引用の『魏志』については、佐伯有清氏も『魏志倭人伝を読む』の中で、誤りがあると指摘しています。【『日本書紀』神功皇后摂政三十九年の条に引用されている『魏志』には、「大夫難斗米」に作る。「斗」は「升」の誤記であろう。】(同書下巻p68)と。
このように、『日本書紀』の引用する『魏志』の記事の正確性には疑問があります。 又、森浩一さんは折角、参照原本として「乾隆欽定本」を上げているのであれば、そこにある景初二年をそのままにしておいても何ら差し支えないと思います。差し支えがあるとすれば、古代史関係の学会が「二年は三年の誤り」としている不文律に触れる、ということなのでしょう。
景初二年は誤写・誤刻ではなく、それが正しいとされる古田武彦氏の説明を紹介しておきます。
まず、『日本書紀』の記事について、その間違いを指摘されます。【日本書紀の「明帝景初三年六月」というのはおかしい。明帝は景初三年一月に死んだ。明帝の景初三年六月はありえない表記だ。】(『「邪馬台国」はなかった』より)。
年号などの史書の記載方法に疎い筆者には、もう少し突っ込んだ説明が欲しく調べてみました。 魏志では、景初三年一月に明帝が死に、翌年が正始元年になっています。だとすれば、景初三年六月という表記は存在したと言えます。事実『魏書』「三少帝紀第四」に「景初三年十二月」の詔勅の記事があります。つまり、次の皇帝、(斉王)景初三年六月として表記されるのが筋であり、『日本書紀』が書くように明帝景初三年六月というように「明帝」が頭に付くことはあり得ない、ということがわかりました。
古田武彦氏は『「邪馬台国」はなかった』で、【景初二年にはまだ公孫氏との戦いは終わっていなかった、その時点での卑弥呼の遣使だから魏の皇帝は非常に喜んだ】と説かれます。【戦争が終わってからの遣使なら、あれほどの下賜品を与える理由がないのではないか】と。説得力がある説明と思います。
森浩一氏は、考古学者らしくなく、「倭人伝」が記す魏と倭国の交互の贈物についてあまり言及されません。勿論、卑弥呼のささやかな献上品と、魏朝からの豪華な下賜品との差については、全く言及されていません。森浩一氏の景初三年説には、説得できる根拠がなく、『日本書紀』の編集者の判断に責任を被せるという姿勢には、古代学者と自称する資格があるのか疑われます。
(B)。邪馬壹国は邪馬臺国の誤り
森浩一氏は、邪馬壹国は邪馬臺国のあやまりであり、それは「減筆」によるもの、とされます。 この「減筆によるもの」という説明がその著書『倭人伝を読みなおす』には数多く出てきます。その内最大のものは、「邪馬壹国は邪馬臺国のあやまり」を「減筆」のせいとされるのです。つまり、臺を壹としたのは当時の「減筆の流行」によると言われます。
これは、森浩一氏の独創かどうか知りませんが、森浩一氏が史家としての鼎の軽重を問われなければならないくらいの暴論でしょう。『三国志』で臺を壹と減筆していた例があったとは、浅学かも知れませんが今まで聞いたこともありません。(書き間違えた説はありますが)
邪馬臺国→邪馬壹国を、「国名の減筆の例」として挙げていることについての傍証としたいのでしょうか、志賀島の金印について、で次のような説明があります。 【金印の読み 漢委奴国王 は木簡で伊委之と委がワと読まれたと思うので、「漢の倭の奴国王」でよいと思うが、中国での公式の使用において国名を減筆した例があるかどうかの検討が必要となる。】と言われます。
そのくせ『魏志』に初めて出てくる「卑彌呼」は人扁つきの「俾彌呼」なのですが、これはどうしてなのか、「減筆」の例として上げても良さそうなのに、森浩一氏は何も言いません。氏は、「倭人伝」だけを読んでは理解できない、と次の様に言われているのです。【著者の陳寿は自分よりも後の時代に『三国志』を読む人は、最初から順々に読んでくれることを前提に書いている。】と。
読者が『魏志』の本文のところに、人扁つきの「俾彌呼」の遣使記事があることを気づかないとナメてかかっているようにもとれます。人扁が取れた「卑彌呼」となぜそうなったのか、『魏志』本文には「倭国女王」と出てくるので、「狗奴国抜きで倭国王」等あり得ないという森浩一氏の立場としては、そこに読者の眼の焦点を向けたくなかったからではないか、と思われます。
これは、【「俾彌呼」は倭国から魏朝への国書に書いた自署名で、「卑彌呼」は陳寿が用いた「卑字」であろう】と、とされる古田武彦氏の推論が正鵠を射ていると思います。
森浩一氏はこの「減筆文字」の延長で、壹与と臺与問題も述べられます。【今日みる倭人伝では臺与でなく壹与にしている。この壹は臺の減筆を示すのであろうから、イヨとするよりトヨと発音したものとみられる。】と。
これは無茶苦茶、暴論に過ぎるのではないでしょうか。『三国志』の中には「臺」は沢山用いられています。「倭人伝」以外で「臺」が「壹」と減筆されている例を上げてみられたら如何でしょうか。その上で、「臺」が「ト」と読むことが出来る、ということを論証しなければならないでしょう。「減筆」で、「壹」の読みを「ト」と、読みまで変えてしまうとは、大した大道香具師ぶりです。
詳しくは当ホームページ、「槍玉その45森浩一 倭人伝を読みかえす」にリンクを貼っておきましたのでクリックしてみてください。
倭の女王壹與(壱与)に関する問題として、この「壹」は一字姓ではないか、という古田武彦氏の問題提起もありますが今回は割愛します。
★大津教授の邪馬台国論の破綻
なぜ大津教授が卑弥呼と天皇との関係の考察にギブアップ状態になったのか、その原因は簡単な話です。「 卑弥呼が纏向に居た」という大津教授の仮説が間違っていたからです。
「纏向の地に宮殿遺構も発見され、近くには巨大前方後円墳があり、かなりの権力者がここに居た」ということはまず間違いないことでしょう。それを無理やり卑弥呼に結びつけようとするからどうにもならなくなるのです。むしろ、垂仁天皇が纏向の珠城宮、景行天皇の纏向の日代宮などの伝承を掘り下げて検討する方向性を出すのが妥当な結論だと思います。
大津教授は【「箸墓は卑弥呼の墓」という新聞報道がされた】(p48)ということで自説の正当性をカバーされるようです。ここで少し話を変えて、当時の新聞報道批判を、ネット上で筆者が試みた事があります。大津教授の言われることと、どちらに合理性があるか読み比べて頂きたいと思います。

子供たちにも分かるように理路整然と簡明に答えるためには、一度文章にしてみよう、自分の勉強も兼ねて、「邪馬台国は纏向遺跡ではないよ、ここですよ」という小記事にまとめることにトライしてみることにしたものです。
中学生の皆さんへ
この朝日新聞の子供向けの「箸墓卑弥呼の墓?」という記事は、二〇〇九年五月に国立歴史民俗博物館が箸墓を炭素14年代測定法で測定した結果、築造年代は三世紀後半で、卑弥呼の没年と一致する、という発表を受けたものです。
このジュニア向け記事は、「邪馬台国は纏向遺跡であり卑弥呼の墓は箸墓である」、という歴史民族博物館春成教授の説に合う形で作られています。私は今回の朝日新聞の記事を読んで、これはおかしいなと思いました。なぜ?という説明を皆さんにしてみたいと思います。
(a)昔の国の姿
縄文時代から弥生時代へと人々の生活はつながっています。それぞれの時代に人々は、住みやすい、外敵から身を守りやすい場所に集まります。それは日本全国どこでも共通です。それは 出雲(いずも)(島根県)であれ、吉備(きび)(岡山県)であれ、関東平野でもそうであったでしょうし、讃岐(さぬき)(香川県)でも筑紫(ちくし)(福岡県)でもそれぞれ集団で生活をしていたことには間違いありません。
今、奈良県で纏向(まきむく)遺跡の発掘が行われています。建物の基礎が出たり、木のお面が出たり、多くの土器などが出土しています。最近の科学的調査法、炭素14年代測定法という方法で調べたら、その遺跡の中でも最大の、箸墓古墳が造られたのが三世紀後半という結果が、国立歴史民俗博物館から発表されました。
中国の史書魏志倭人伝という本に、卑弥呼の死んだ年(三世紀後半)と、その墓を造ったことが書いてあります。それでこの箸墓が卑弥呼の墓ではないか、と一部の学者が主張しています。 しかし、倭人伝には、朝日新聞の記事にもあるように、『気候温暖で、一年中生の野菜がたべられた』ことからいっても、近畿地方ではなくて、日本の西南部であろう、ということは容易に察せられます。
(b)箸墓は卑弥呼の墓ではありえません
倭人伝にはいろいろ書いてあります。卑弥呼に錦を贈ったことや卑弥呼からも日本製の錦を贈ったことも書かれています。錦とは絹織物のことです。この絹が弥生遺跡から出ているのは福岡県北部地方が主で、近畿地方には全くといってよいほど出ていません。このこと一つからでも卑弥呼の国が纏向遺跡ではありえない、北部九州地方の可能性が非常に高いと言えます。
次の問題は箸墓が卑弥呼の墓の大きさと形の問題です。倭人伝には「径百余歩」と書かれています。箸墓は前方後円墳といわれるもので円部の径は百五十米、長さは二百八十米あります。 この魏の時代の一歩の長さは二十五センチ程度という数学者の説によりますと、墓の大きさは三十米の円墳かもしくは方墳となり、大きさからいって箸墓ではありえないことになります。そのサイズの墓でしたら大きさが合う古墳は沢山あります。
別の説では、漢の時代の長さの基準書から、一歩は六尺で一.八米とも言われます。しかも、その説に従うと百余歩と倭人伝に書かれている卑弥呼の墓は百八十米以上の大きさということなり、箸墓のサイズに近い、ということになります。これが、「箸墓が卑弥呼の墓説」の人たちの主張です。このような数学的な問題と思えることも、古代史の学問の世界ではなかなか決着が付かないのは不思議ですね。
もう一つの問題は「径」と倭人伝には書いてあることです。もし箸墓のように前方後円墳という、丸と台形の組み合わせの中国では見られない特徴のある形でしたら、径百余歩という表現にはならなかったことでしょう。このことだけでも箸墓が卑弥呼の墓ではない証拠といえるでしょう。
(c)「邪馬台国」のありか
「邪馬台国」はどこにあるのかなぜ分からないのでしょうか。「邪馬台国」への行路が分からないのは、読み方を間違えているからです。なぜ読み間違えたのでしょうか。その原因の大きなものに地名比定いうことが上げられます。昔から大和が日本の政治の中心だったから、中国の史書に日本の首都が書いてあれば「ヤマト」の可能性が高い、という 先入観(せんにゅうかん)で倭人伝を読むことにあります。実は倭人伝には、「邪馬台国」ではなく「邪馬壹国」と書いてあるのです。つまり、倭人伝にある邪馬壹国をヤマト国と読みたい、ということから邪馬臺国と読み替えていることがあげられます。もう一つは中国文に句読点がないのでいろいろと文章の解釈ができる、ということが上げられます。
八世紀以降、大和王朝が日本を代表する政権となったことは、中国の史書からも明らかです。しかし、それ以前が不明なのです。中国の史書によると、朝日新聞の記事にもありますが、三世紀ごろは西日本の国々が集まって「邪馬台国」を造ったように書かれています。それが何故八世紀には近畿地方が中心になるのか、そこがなかなか理解できないことなのです。それは八世紀に出来たわが国の史書、『日本書紀』の記述には、「邪馬台国」の流れの政権の歴史がカットされているからです。しかも、大和政権が作った『日本書紀』が書いているように「神話の時代から大和政権が日本全国を支配していた」、と無意識のうちに思い込まされているからなのです。
倭人伝の行路記事では、不弥国というところまでは学者の皆さんの読み方は、ほぼ一致しているのですが、不弥国の次の邪馬壹国が分からない、ということなのです。 なぜかといいますと、伊都国の斜め隣の国として「奴国」というわりと大きな国があるとされているのを、「ナ国」だとすることに原因の一つがあります。奴国とは昔、那の津と呼ばれた「博多」のことだと決めつけてしまっているので、邪馬壹国が分からなくなってしまっているのです。「奴国」とは「ノ国」であり、福岡の室見川流域の国と思われます。「倭人伝」を自然に読めば博多湾岸の不弥国の隣の国、邪馬壹国=御笠川流域福岡平野の国となるのです。
今年(二〇〇九年)、平城京遷都一三〇〇年ということで、奈良地方では活発に遺跡調査などが進められています。いままで述べたように、古代から人々は集団生活を送ってきたのであり、この地方の古代の中心の一つが纏向であったことは否定できないと思います。
しかし、卑弥呼の墓を箸墓であるということを証明するためではなく、本当に卑弥呼の国と墓のことを知りたいのであれば、今度の箸墓の年代測定に使われたのと同じ方法で、全国の古代の遺跡を調べ直すことが必要でしょう。特に、纏向遺跡と比較にならない 絢爛(けんらん)とした出土品がある福岡の、吉武高木・須玖(すく)岡本(おかもと)・三雲・平原・那珂八幡・立岩・一貴山(いきさん)などの遺跡が造られた年代を調べ直す必要があるでしょう。そういうことが分かった今回の国立歴史民俗博物館の調査結果であった、と理解するべきと思われます。
ともあれ、朝日新聞社という日本一と自負する新聞社の記事としては、ちょっとお粗末だったと言われても仕方がないようです。
★ところで「邪馬壹国」とは
邪馬台国と普通いわれていますが、『三国志』魏志には邪馬壹国とあるのです。全ての版本にこぞって「邪馬壹国」と書いてあるのです。それがなぜ「邪馬台国」とされるのか、これが問題です。
『三国志』は280年頃に陳寿によって書かれ、公になったのは陳寿の死(297年)後で300年前後です。卑弥呼が亡くなったのが248年頃、壹与の朝貢266年頃ですから、殆んど陳寿により同時代に執筆された記録と言ってよいのです。
また、この三国志には宋朝の歴史家の裴松之によって注釈が全編に亘って行われ、429年に完成しました。注釈の分量の方が本文より多いくらいの注です。その裴松之の注釈ですが邪馬壹国については、邪馬臺国の間違いとかそのようなことは何も書かれていません。
ところが、陳寿よりそれより150年後に、三国時代より前の後漢時代の史書が欠けていたので、范曄(398~445年)が432年に『後漢書』を著しました。その本では、わが国が「邪馬臺国」と表記されているようなところがあります。 この事実から言えるのは、魏の時代から約150年後に、我が国の名前が「邪馬壹国」から「邪馬臺国」に記載が変わっていた、ということでしょうか。
しかし、後漢書の記事では「大倭王は邪馬臺国に居す」と書いているのです。この文からは、全体の国の名は「大倭」であり、その都が邪馬臺国ということです。
又、邪馬壹国は邪馬臺国の書き間違い、という説が根強くはびこっていて、大津教授もそれに乗ってか、「邪馬壹国」など丸で無いもの同然の書き方です。これでは、中国の正史に対して失礼極まりないでしょう。
古田武彦氏が邪馬壹国か邪馬臺国なのか、版本での記載の違いを表にしています。 (『邪馬一国の証明』角川文庫p90 より転載)
右の表から分かるように、三国志はどの版本も「邪馬壹国」なのです。
ところが、我が国の歴史家は、『後漢書』の記述「邪馬臺国」が正しい、『三国志』魏志の「邪馬壹国」は誤り、と決めつけてしまったのです。その理由は、「臺」は「ダイ、タイ」と読みますが、その略字とされる「台」は「ダイ、タイ、ト」と読めるのです。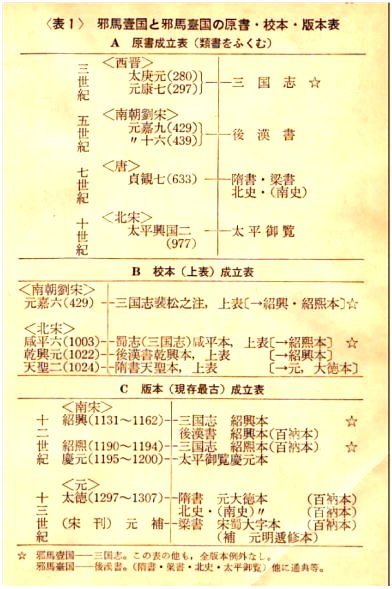
「邪馬台国」と書けば「大和国」(ヤマトコク)というわが国おなじみの国名になる、これに間違いなし、ということになってしまったのです。勿論、中国の史書に「邪馬台国」は存在しません。
歴史的には江戸時代の松下見林の『異称日本伝』一六八八年成立 でおおまか次のようにこの問題についての見解を示しています。
「外国の史料と日本書紀と合わないところは我が国記を基に取捨すればよい。倭人伝でも「日本書紀」によれば、景初・正始など魏の明帝の時期は、日本の神功皇后の時代である。だから、当然中心は「大和」である。だから「ヤマト」と読めぬ「邪馬壹」は捨て、「ヤマト」と訓むことのできる「邪馬台」を採ればそれでよい」というまことに明瞭な論理です。(邪馬壹国 『史学雑誌』78-9 昭和44. 9 古田武彦)
残念ながら大津教授もこの束縛から逃れることが出来ないでいるのです。 なぜこのようなことになったのか、古田武彦氏はおおむね次のように指摘します。
【『三国志』魏志倭人伝では、「南、邪馬壹国に至る。女王の都する所、・・・・七万戸なる可し。」とあり、『後漢書』倭伝では、「その大倭王は、邪馬臺国に居る。」とある。
この二つは同じ国を説明しているのではない。 『三国志』では七万戸の国全体の呼び名としての「邪馬壹国」で、『後漢書』では大倭王ひとりの居る場所が「邪馬臺国」である。つまり意味が違うのだ。
西晋の滅亡東晋の成立と中国では大きく政治が動くが、わが国でも邪馬壹国の都が、博多湾沿岸部から内陸へ遷った可能性が高い。論理的に「三国志」と『後漢書』との一見理解できないように見える「邪馬壹国Vs邪馬臺国」問題も、前後の文脈から論理的に考えるとこの様な帰結になる。】(『俾弥呼』古田武彦ミネルヴァ書房2010年)
その様に基本認識が間違っているのに、大津教授が「卑弥呼は纏向に居た」、とおっしゃるのはいくらかでもこの問題を聞きかじっている者にとっては空々しく聞こえます。
しかし、日本の最高学府のそれもこれが専門の国史学科の教授がおっしゃるのですから、「邪馬台国」問題も纏向で解決、と思われる方もいらっしゃることでしょう。誠に残念な現状と言えましょう。
★倭人伝の「里」の問題
大津教授は、【倭人伝とか文献学には自分はあまり詳しくはない】、とおっしゃいますが、倭人伝に記載のある「距離」の問題に目を向けないのは歴史学の教授としていかがなものでしょうか。
大津教授のこの『天皇の歴史01』での「里」についての記述を拾ってみました。 大津教授の『天皇の歴史01 神話から歴史へ』には、倭人伝の「里」については殆んど書かれていません。わずか一か所「邪馬台国」所在について、二つの説の説明のなかで、「倭の地を参問するに(中略)周旋五千余里ばかりなり」というところだけです。
あとは、次の右下図に「倭人伝」のコース、九州説のコースという説明図のなかに、倭人伝に書かれている各地点間の「里」が描かれているだけです。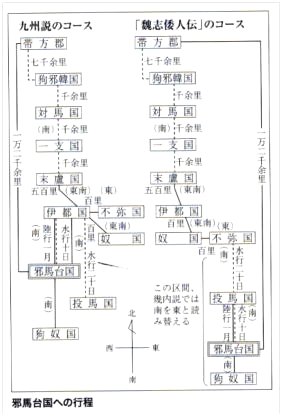
『三国志』の記述に在る「里」の問題、特に「倭人伝」では、その行路記事の里数から卑弥呼の都が何処にあったのかを定める大きな因子ともいえるでしょう。 大津教授の行路図は、【不弥国からの行程を“南を東に読み代えれば“邪馬台国は畿内にある、ということになる】、という説明図です。【 トータルとしては帯方郡から一万二千余里というところは九州説と同じ】とされます。
大津教授の「九州説」の行路図は、伊都国乃至不弥国から水行十日陸行一月で邪馬台国に着く、という説明です。
しかし、この大津教授の「倭人伝」の行路記事の読み方に決定的な欠陥があるのです。 状況が良く分からない中国の皇帝はじめ高官たちに上呈する歴史書です。未知の女王国への行程について、常識的にどのような報告をするでしょうか。どれくらいの距離があるか、どれくらい日数がかかるか、この二つが絶対必要条件でしょう。
そのミソもクソも同じ理解をしているから陳寿が詳しく女王国の在りかを書いているのに、「ヤマト国」に目をくらませてしまっていて行路が理解できないのです。 帯方郡から、一万二千余里の距離で、日数にしたら水行十日陸行一月というところに女王国はある、と陳寿ははっきりと書いているのです。
大津教授がこの理屈が理解できないので【 南を東に読み代えることは一定の根拠がある】(p43)などと邪道に走って、「卑弥呼は纏向にいた」というとんでもない方向に走ってしまうのです。四世紀の中国史官の文書を、二十一世紀の東京大学の現役歴史学教授が理解出来ないことを江湖に示す失態といえましょう。
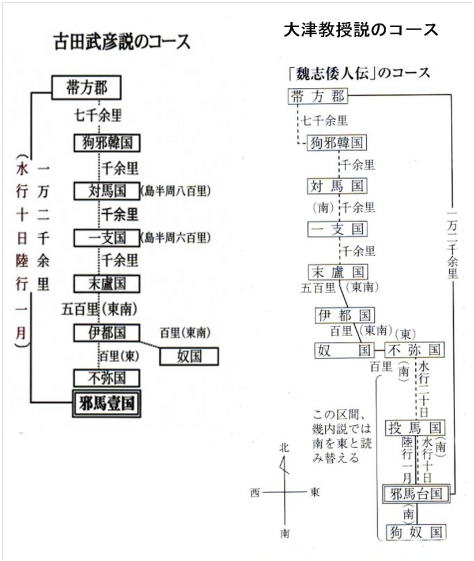
今から四十年前に、古田武彦氏が『「邪馬台国」はなかった』一九七一年朝日新聞社 で綿綿密密に検証されています。大津教授が出されている行路図と同様に「古田武彦説のコース」を作ってみました。すっきりして誰でも理解できる行路図と思いませんか?
今あらためて、ミネルヴァ書房からコレクション版として出ています。大津教授がお読みになられることを期待します。
★卑弥呼の墓の大きさと冢〈
「魏の時代の里」について大津教授は全く触れられていませんが、同じく長さ単位の「歩」についても何らコメントされません。それなのに、【 (卑弥呼の死亡時期と)最初の巨大前方後円墳である箸墓とほぼ年代が重なると考えられ、箸墓は初代の倭王卑弥呼の墓だという新聞報道がさかんになった】(p46)とされ、「倭人伝」に記載のある「径100余歩」を無視されています。
魏の時代の「歩」はどれくらいの長さであったのか、各説があります。前出の朝日新聞の記事の批判(槍玉その32)で、この問題について述べましたので改めてはのべません。(例えば藪田嘉一郎『中国古尺集説』によれば約25cm)
大津教授も【纏向の地には、箸墓古墳(280メートル)云々】(p53)とその大きさはご存知のようですから、「歩」の長さが分かれば自然、箸墓が卑弥呼の墓といえる大きさかどうかが判明するのです。
大津教授が、東京大学という最高学府の、担当する歴史学の教授としての自覚を持たれているのでしたら、魏の時代の「長さ」についての検証プロジェクトを立ち上げ、学際的にリーダーシップをとられては如何でしょう。もし成果が得られれば、坂本・井上師弟郡評論争よりも歴史に大津透の名をとどめることになると思うのですが。
もう一つの問題があります。「倭人伝」には卑弥呼の墓のところで、「大いに冢を作る」と書いてあります。大きな墳を作るとは書いてないのです。
冢と墳は違うと古田武彦氏は指摘されます。『邪馬一国の証明』1980年 角川文庫「邪馬壹国と冢」にて、『三国志』に冢と墳の違いが書いてある、と次の様に述べています。大津教授は「冢」という見慣れない語について調べてもみられなかのでしょうか。
【「山に因りて墳を為し、冢は棺を容るるに足る」 孔明の遺体は漢中の定軍山に葬られた。そのとき生前の遺言によって右のような質素な冢が 既存の山(定軍山)を墳に見たて、その一角に築かれた、というのである。
『三国志』では墳と冢の両概念は明晰に区別されている。「大君公侯墓」の場合は、通例「墳」であった(蜀志十四)。これに対し、「棺を容るるに足る」程度のものは、当然「冢」であって「墳」ではないのである。孔明は中国三分の非常時たるにかんがみ、多大の人力・経済力を消費する「墳」を、自分の遺骸のために築かれることをいさぎよしとしなかったのであろう。
こうしてみると、卑弥呼の場合、「大いに冢を作る」とあり、それは「径百余歩」の規模だった、という。よく知られているように(藪田嘉一郎著『中国古尺集説』にも書かれている)「歩」は「里」の下部単位であり、「一歩=三〇〇分の一里」である(後世は三六〇分の一里)。
従って「漢の長里=約435メートル」なら、百余歩(130~40歩)は、「180~200メートル」の巨大 古墳となろう。ところが、「魏晋朝短里=約75メートル」なら、「30~35メートル」となって、大き目の「冢」となる。この程度では到底「墳」とはいえないのである。
すなわち、陳寿がこの条に至って「径百余歩」と書いたとき、 その脳裏に描かれた規模は決して200メートル近い大古墳ではなかった。それなら必ず「大いに 墳を作る」と書いたはずであるから。逆に 30メートル前後のイメージ だったから、これを、「大いに冢を作る」と表現したのである。】と。
卑弥呼の墓は、大津教授が主張する箸墓古墳では、その大きさからいっても到底ありえないのです。
★三種の神器について
【なぜ剣と鏡が大和王権のレガリア、王位の象徴になったのだろうか】(p64)、 と大津教授は自ら設問されて、その解答を述べられます。 しかし、弥生期の代表的青銅器は、西日本の銅矛銅戈銅剣であり近畿以東の銅鐸です。
中国地方東部近畿地方西部には銅剣の出土もあり両者の文化が入り混じった地域とも言えるでしょう。 その様な中間地帯大和でで、大和朝廷の神器を論ずるのであれば、「銅鐸」がなぜ入らなかったのか、などを概観して頂きたいものです。
勾玉が天皇の即位にあたり奏上されるレガリアにならなかったのか、については駄じゃれ的な説明も入れて、次のように述べられます。
【八坂瓊曲玉も天皇の宝器であったが、勾玉は縄文時代以来の伝統的な日本固有の宝器である。玉=タマ(霊)であるから、祖霊のシンボルとして代々存在していた可能性は高いが、それだけでは天皇位を付与するレガリアにはならなかったのだろう。】(p68)と。
大津教授が王権のレガリアの説明資料として使われるのは「倭人伝」であり、石上神宮の七枝刀であり、稲荷山古墳鉄剣などです。 ここでは一応大津教授の流れに乗ってみることにします。
まず、「倭人伝」にかかわる問題について、大津教授の考えを拝見してみましょう。
「倭人伝」で神器にかかわるものは、先述のように、鏡・矛であり刀と珠でしょう。ところが、弥生期には近畿地方には銅鐸は沢山出ても、鏡・刀は殆んど出ていません。弥生期にこれらの出土が多いのは、圧倒的に北部九州なのです。『日本書紀』に出てくる三種の宝物、「鏡・剣・勾玉」の三種の神器がセットで出てくるのです。年代的には 吉武高木遺跡→三雲遺跡 →須玖岡本遺跡→井原遺跡→平原遺跡となると思われます。弥生期の近畿の古墳からはこれら三種の神器がセットで出た、ということは全くありません。
なのになぜか、大津教授はこれらの遺跡と「天皇」のルーツとを結びつけようともされないのです。 大津教授は「三種の神器」を取り上げてはいるのですが、北部九州の三種の神器を出土する遺跡には極めて冷淡で殆んど無視されます。
「記紀の説話は六世紀に創作された」説に乗るとしても、個々の伝承の内容にはそれなりの実体が反映している、ということは自説に都合が良い限りにおいては、認められるようです。まして、現実に遺跡から三種の神器が出土しているから、古代史学者としての意見があってもしかるべきかと思うのですが、それに背を向けて、大和王権のレガリアという今風の衣を着せて大津教授の三種の神器談義となります。
【「倭人伝」に記されている魏朝から下賜されたもろもろの中には、五尺刀と鏡がある】と指摘され、【 王権のレガリア(王権を象徴する宝物)が剣と鏡】とされます。なぜか、魏朝から「親魏倭王」の印綬はレガリアの資格がないといわんばかりです。 そのあたりの大津教授の説明は次のようです。
【(魏朝から卑弥呼に宛てた)詔書で、卑弥呼は「親魏倭王」に任じられ、「金印紫綬」を賜り、魏の臣下となり官職に任命された―これを冊封という―ので、それは魏の権威により倭王の地位を国内・国外に認めさせるためだった。
まさにその目的で刀と鏡を特に賜り、刀・剣は「汝が国中の人に示し、国家汝を哀れむを知らしむべし」とあるように魏が卑弥呼に権威を与えたことを示すための宝物であり、倭王側の要望により特に下賜されたものだろう。
五尺刀はおそらく王権のシンボルとして用いられ(二口なのは卑弥呼と男弟の二人分か)、「銅鏡百枚」は、朝廷から下賜された三角縁神獣鏡が全国の古墳から出土していることから、各地の豪族に配布され、地方の首長の権威を支えたのだろう。】(p65)と。
この大津教授の意見には数々の疑問が涌きます。刀・剣だけでなく大津教授も紹介しているその詔書には、次の①に上げる品々が書かれています。
疑問を列記してみます。
①「紺地句文錦三匹・細班華罽五張・白絹五十匹・金八両・五尺刀二口・銅鏡百枚・真珠・鉛丹各々五十斤」という大層な下賜品です。卑弥呼が貢物として届けたのは、「生口男四人女六人、班布二匹二丈」でありその落差の大きいことに驚くのですが、大津教授は何とも感じられなかったのでしょうか。
②これらの内の「五尺刀二口と鏡百枚」のみが、なぜ倭王側の要請による、と判断されたのでしょうか。
③魏の皇帝は「これらの品々を国中の人に示せ」と指示しています。分配せよとは言っていないのですが、この魏朝に逆らって行ったという大津教授の判断の根拠は何でしょうか?
④『日本書紀』などが記す宝器は刀でなく剣なのですが、その事についても何も言われないのは何故でしょうか。
⑤西日本の各地から出土する広幅銅矛や、中部日本の銅鐸などの宝器と思われる弥生期の青銅器について、大津教授が無言なのは何故なのでしょう。「王権の象徴の宝器」の歴史を探るのには必要な検討されるべき弥生期の遺物と思いますが。
⑥何にもまして不思議なのは、三種の神器がセットで出土している弥生期の遺跡について、一言も述べないことです。これほどアンフェアーな態度でよくも『天皇の歴史』と堂々といえるものだ、と寒心させられます。この「三種の神器問題」は改めて述べます。
⑦倭奴国の金印といい、卑弥呼が貰った「親魏倭王」の印といい、王者は部下に与える「印綬」という形で支配権を行使しているといえるでしょうが、このことが「天皇の歴史」には無関係で良いのでしょうか。「玉璽」との関連ありなしも語られないのは不思議です。
神器と玉璽について大津教授は以上の事を発展させて、『古語拾遺』などを引き合いに自説を構築されます。しかし、何時の時代にか中国の冊封体制から離れた時に、「倭国」も自身の「国璽」を作成した(恐らく半島の諸国も)、とする方が、当然の思惟のなり行きではないでしょうか。
九世紀に書かれた『古語拾遺』に「八咫鏡及び草薙剣の二種の神宝を以て、皇孫に授け賜ひて永に天璽(所謂神璽の剣・鏡是れなり)と為たまう。」とあるから、それも注書の「神璽の剣・鏡」が天璽とあることから、【 律令規定の、天皇御璽・太政官印なども「神璽の剣・鏡」をさしているとすることもできる。】と大津教授がおっしゃるのはあまりにも飛躍し過ぎではないかと思います。
そして、大津教授は、【欽明・允恭・顕宗・清寧の各天皇の即位時に「璽印・璽」などを群臣が奉った、とあるがこれらは中国史料などにより潤色した表現であり、天皇位を象徴する玉製の印璽はなかった】(p63)と、何を理由にしているのか言われずに断定されます。東京大学国史学教授の私が言うことだから弁明不用ということなのでしょうか?
また、記紀に書いてあると、仲哀天皇が筑紫に来た時に岡県主の熊鰐や伊覩の五十迹が、賢木に鏡・勾玉・剣を掛けて迎えた、ということを挙げて、【 神器を捧げて配下になったことを示し、王は己の神器を下賜し主従関係を作って行く】というように書いています。【 これは司祭者的性格を持つ地方首長が祭祀権を天皇にさし出すことを示す、服属の儀礼である。】(p70)とも言われます。
この論理は自家撞着ではないでしょうか?なぜなら、大津教授は、 卑弥呼は魏から下賜された鏡を各地の豪族に分け与えて国を纏めていった、といわれるのに、もう既に各地のボス達に鏡が誰からか下賜されていた、ということになるわけですから。そうすると、例えば熊鰐は、仲哀天皇以前に誰からか、別の大王から神器を下賜されていた、ということになるのです。
この論理からいくと、大津教授が認めたくない西日本の別の大王の存在を認めなければならないのではないか、と思うのですが大津教授はそのことに気付かれないようです。
大津教授は神武天皇架空説を信奉されているせいなのでしょうか、『日本書紀』からいろいろと沢山引用されますが、なぜか神武紀には冷淡のようです。
神武紀には東征中、近畿でニギハヤヒ一族に出会って「同族の印」として弓の靫の模様を見較べるシーンがあります。敵味方の見分けは古代にあってはとても大事なことであったと思います。仲哀紀の話もこのような意味、「我々は同族である、敵ではない」という意思伝達だったととるのが合理的判断でしょう。
大津教授は前述のように、なぜ、剣と鏡が王権の象徴となったのか。卑弥呼に贈られた五尺刀二振りと銅鏡100面が倭王側の要請によって送られた、と、されます。
この説明を聞いて不審に思うのは、五尺刀が王権のレガリア、であるのなら何故纏向遺跡から出ないのか。特に五尺刀については、弥生期の出土例は大和には皆無で北部九州から多数出土している、ということについて大津教授は口を噤んでいます。
古田武彦氏によれば弥生期の鉄刀の出土状況は次のようです。 その中の福岡県前原町上町出土の大刀は長さ1.19mで魏尺の五尺(1.21m)と同じといってよいものである、などと指摘されています。(『ここに古代王朝ありき』第一部邪馬一国の考古学第二章「倭都の痕跡」より転載)
★三種の神器問題の結論
大津教授が「剣と鏡」の二種の神器のように論じられるのは、津田左右吉大先輩の説を継承されているからのようです。この点も含めて古田武彦氏は次のように述べていますのでご紹介します。
【「三種の神器は天皇家の宝器として、戦前は万世一系の証拠物のように喧伝された。津田左右吉は是は記紀成立期の造作とみなし、『古語拾遺』の二種の神器や『日本書紀』崇神紀の「神璽鏡剣」の記事を本来形とした。
しかしながら近畿の和泉黄金塚古墳や、福岡県の一貴山古墳、熊本の江田船山古墳からもこの三種の神器セットが副葬品として出土している。そして、弥生期の遺跡、福岡県の三雲・井原鑓溝・須玖岡本・高木吉武・平原からも「三種の神器」のセットの副葬品が出ていて、津田左右吉の「後代の造作」との判断は明らかに早計であった。(筆者注:大津教授は無批判に受け入れているようですが)
ま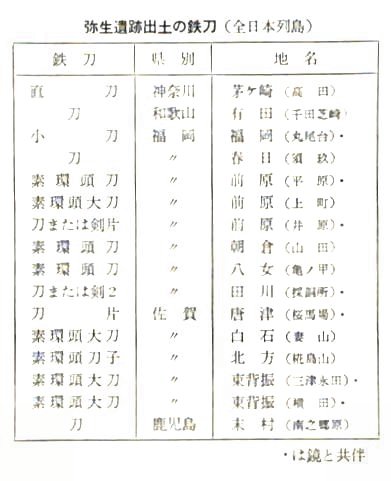 た、近畿地方の古墳からの「三種の神器」セットは、九州地方のに比べると明らかに貧弱だという事実もある。 「三種の神器」の出土事実から、『記・紀』の叙述が真実で、近畿天皇家の万世一系論が復活出来るかというとそうではない。
た、近畿地方の古墳からの「三種の神器」セットは、九州地方のに比べると明らかに貧弱だという事実もある。 「三種の神器」の出土事実から、『記・紀』の叙述が真実で、近畿天皇家の万世一系論が復活出来るかというとそうではない。
この出土事実から、明らかに弥生期の権力のシンボル「三種の神器」から古墳期へという“文明伝統の継受”があったとしか考えようがない。つまり本流は一貫として九州にあり、近畿に分流したのである。
このように、考古学的出土物の実証する「三種の神器」セットも歴史的出土状況と分布は、天皇家を日本列島の永遠の主流とみなす「万世一系論」などを支持していなかった。戦前の皇国史観流の論者の架構するところ、いわば空中の楼閣に過ぎなかったのである。】(以上『風土記にいた卑弥呼 古代は輝いていたI』朝日文庫より要約)
また古田武彦氏は「三種の神器」について次のように『昭和天皇独白録』寺崎英成 文春文庫を紹介されます。
【「三種の神器」は現在の天皇家にも伝えられ歴代天皇が崇拝の対象としている。一九四五年の日本の敗戦時に、昭和天皇が心配したのは、三種の神器が敵国アメリカ軍に奪われることであったといわれます。
アメリカ軍が伊勢湾付近に上陸すれば、伊勢・熱田両神宮が直ちに敵の制圧下に入り、神器の移動の余裕が無くその確保の見込みが立たない。これでは日本の国体護持が難しい。故にこの際私の身は犠牲にしても、講和をせねばならぬと思った。】(『失われた日本』第十二章「空白の三種の神器より。」
このように「三種の神器」と「万世一系の国体」は、現在の天皇方まで束縛されている思想のようですし、キチンと解明する必要があると思いますが、大津教授には、この『天皇の歴史 神話から歴史へ』を読む限りどうやら無理のようなのは誠に残念です。
ところで、この本を読んでいると、いろいろと大津透教授 が参照された本やその内容の引用が出てきます。井上光貞・直木孝次郎・土田直鎮・吉田孝・熊谷公男などの各氏です。 それらの方々が、今回の大津教授の『天皇の歴史 神話から歴史へ』という本と似たような本を出されています。
井上・直木・土田の各氏は中央公論社の『日本の歴史』シリーズ(中公文庫)の執筆者、熊谷氏は講談社のシリーズ『日本の歴史03 大王から天皇へ』など、いずれも同工異曲の歴史を語られている感じです。このようにしてわが国の歴史学者が再生産されていくのだなあ、と改めて感じ入りました。
(三) 金石文と我が国の歴史
★七枝刀問題
大津教授は、王権の象徴の例として七枝刀を挙げられています。この七枝刀に書かれている銘文は数少ないこの時代の金石文です。この銘文の解読が間違っていると、その銘文の理解によってなされる「王権の象徴論議」も的外れになることは自明の理です。
大津教授は刀が王権の象徴になった例として七枝刀を写真付きで次のように紹介します。
【石上神社に伝わる七枝刀には「泰和四年五月十六日丙午」と東晋の年号(369)を記し、東晋の意思をうけて百済王世子の奇生が倭王旨のためにこの刀を作ったとの銘文がある(川口勝康説による)。倭王はこのような中国・朝鮮からの下賜刀を保有し、後述する江田船山古墳鉄刀などのように刀剣の分与によっても倭国内の秩序を形成した。
剣も鏡もともに中国や朝鮮からの下賜をその権威の源とし、支配を行ったと考えられる。『日本書紀』神功皇后五十二年に、百済の使者久氐らが千熊長彦に従って日本国王に「七枝刀一口・七子鏡一面、及び種々の重宝」を献上し、日本に長く朝貢しようと誓ったことを記す。】 (p66)
この大津教授の説明文を読んで、「東晋の意を受けて百済王子が倭王旨の為に作った」というフレーズに問題点がある、ということを理解できる人は、失礼ながら少ないのではないかと思います。
大津教授はまた、“下賜された刀であるのに、「百済が日本に長く朝貢しようと誓った」”、という『日本書紀』の取り扱い方を紹介しています。このことは、『日本書紀』の記述が粉飾されているということを言いたいのかな、ともとれますが、何か奥歯に物が挟まった言い方です。
『日本書紀』は、大和朝廷が天下に君臨していて、外部から物が送られてくれば、「朝貢」であり、先方にものを贈れば「下賜」という、大義名分で書かれていることはいわば常識です。このあたりの理解のために、ちょっと面倒と思われるかも知れませんが「七枝刀」について整理しておきます。
天理市(奈良県)にある石上神宮に神宝として伝わる珍しい枝分れした、古代の鉄刀があります。その表と裏に金文字の象嵌があり、明治の初期、石上神宮の菅政友宮司が世の中に紹介しました。
その象嵌された銘文にはいくつかの判読不能の文字もあり、何人もの古代史学者がこの銘文の解読に努めました。今回、大津透教授が説明されている前述の解読文は、川口勝康氏の説によるとされています。この七枝刀については大津教授の著書にもあるように、『日本書紀』にその伝来の記事もあります。
まず、銘文をご紹介します。原文は次のような文章です。 表面 泰和四年□¹月十□²日丙午正陽造百錬鉄七支刀□³辟百兵冝供供矦王□□□□⁴作 裏面 先世□⁵来未有此刀百滋□⁶世□□⁷生聖□⁸故為倭王旨造傳示□⁹世
以上の判読が不確かな文字について (1)と(2)は日付の文字であろうことは容易に察せられます。 (3)は「生」という字であろうということは学者間でも異論はあまりないようです。 (4)は作者名だろうということでしょう (5)は「以」の旧字体ではないか (6)は「王」ではないか (7)「子」と「奇」ではないか (8)「音または晋」ではないか (9)「後」ではないか というのが諸学者の意見のようです。
読み方の上で意味が大きく違ってくるのは、(8)の「音」又は「晋」というところです。大津教授は、河口勝康首都大学教授(東大修士卆)の意見を取り入れる形で、(8)の不明字を「晋」と解し、泰和という年号は東晋の年号と判断されて、【 東晋の意を受けて百済の皇子が倭王旨に贈った(下賜した)】という風に理解されたのです。
しかし、「泰和」という年号は百済の年号にも存在していること、倭王旨というのは誰を指すのか、ということを曖昧のまま「七枝刀」は王権のレガリアの象徴とされるのは如何なものでしょうか。
この銘文の中に矦王という言葉が出てきます。大津教授は全くこの言葉について注意を払っていません。古田武彦氏によれば、【矦王は候王と同義であり、『漢書』に「異姓諸候王表」があり、中国の天子のもとにある諸王に対して用いられている用語】と指摘されます。
つまり、この銘文で百済王(候王)が倭王(候王)に贈ったもので、「献上」や「下賜」でなく対等の立場での贈り物であることを示しているのです。古田武彦氏はさらに、【倭王旨は、中国の一字姓を見習っていた当時の倭国の王であろう】、とされます。
勿論そのような伝統の無い「大和王朝の大王」ではなく、「倭の五王」で倭讃から倭武の五人の王たちと同じ王朝の王、倭王旨であったと古田武彦氏は推論されるのです。ご承知のように、倭王旨という人物は『日本書紀』には出ていません。ですから大津教授は、この倭王旨について、大和朝廷の誰かだろうという以上のことを述べることが出来ないまま説明が終わります。
このように、七枝刀の金石文の解明を充分にせず、『日本書紀』の記述を頼りに判断し、『日本書紀』の記述に見えない「倭王旨」については不明のまま、その上で大和王朝の「王権のレガリア」の象徴としています。これは論理的に飛躍が過ぎます。
石上神宮にいつの時代に納められたのかという伝承の無い七枝刀でもあることから、この刀は百済から大和ではなく「倭の五王」の王朝、倭王旨に贈られ、それが何らかの理由で後年奈良の石上神宮の宝物になったもの、と古田武彦氏は推定されていますが、確度の高い推測でしょう。(以上の七枝刀についての説明は『失われた九州王朝』古田武彦に拠るものです)
★「百済記」の貴国と沙至比跪
この七枝刀の『日本書紀』の記事のところに、百済とわが国との間にイザコザが生じ、わが国が襲津彦という人物を派遣し解決しようとしたとあります。百済の歴史書では「沙至比跪」がトラブルメーカーであったような記事となっている、ということについて大津教授が次のように意見を述べています。
大津教授は、まず葛城一族と天皇家との関係について述べ、葛城襲津彦という人物が『日本書紀』の神功紀・応神紀・仁徳紀に合わせて四回登場し、勇将として描かれている、と書かれています。
そして『日本書紀』に分注として「百済記」が引用されている、としてその一部分を紹介しています。その説明に【 「百済記」は百済滅亡後日本に逃れてきた百済人が百済の記録を基にしながら百済が日本に協力した事蹟を述べようと提出したもの(坂本太郎説)】とされます。
その証拠として、【 日本のことを「貴国」と称していること、「天皇」という号が用いられていることから、天皇号が定まった推古朝以降に作られたことがわかる。その「百済記」に沙至比跪という人物が出てくるがこれは葛城襲津彦と同一人物であり実在した可能性が高い】、というように述べています。(p157~159要約)
大津教授はこのような論理の組み立て方をして、上記のように葛城一族の繁栄の基を判断し、天皇家との関係に言及されていきます。
この大津教授の発言の中の、(a)『百済記』の貴国とは何を指すか、(b)襲津彦と沙至比跪が同一人物か、などの疑問点について検討してみます。
(a)『百済記』の貴国とは何を指すか
『日本書紀』に引用されている百済系史書には、『百済記』のほかに、『百済新撰』『百済本記』がありますが、いずれも現存していません。『日本書紀』に引用されていることによってこれらの史書の存在していたことを知ることができる貴重な史料なのです。
その『百済記』を【 日本のことを貴国と表現しているから、百済の渡来人がこの『百済記』を作って献上した。】というように大津教授は主張しています。つまり、百済から戦難を逃れて我が国に来た百済人が、我が国の求めに応じて百済とわが国との通交の歴史を綴ったので、「貴国」という表現になった、と言われるのです。
しかし、この『日本書紀』の『百済記』からの引用文の「貴国」についてみてみますと、その様に「日本を貴国と敬称として書いた」という様なものではないのです。『日本書紀』にあります「貴国」の記事を上げてみます。
(イ)神功紀四十六年(本文)是に卓淳の王末錦旱岐、斯摩宿禰に告げて曰はく、「甲子年の七月中、百済人久氐等三人我が土に到りて曰はく、『百済の王、日東の方に日本の貴国有るを聞きて臣等を遣して、其の貴国に朝でしむ。・・・』といふ。時に久氐等に謂りて曰はく『本より東の方に貴国有ることを聞けり。然れども未だ通ふこと有らざれば其の道を知らず。・・・』という。仍りて曰ひしく『若し貴国の使人、来ること有らば、必ず吾が国に告げたまへ』といひき。如此いひて乃ち還りぬ」といふ。(百済の王)「吾が国に多に是の珍宝有り。貴国に貢らむと欲ふとも道路を知らず。・・・」とまうす。
(ロ)神功紀六十二年(分注) 百済記に云はく、壬午年に新羅、貴国に奉まつらず、貴国沙至比跪を遣して討たしむ。
(ハ)応神紀八年(分注) 百済記に云へらく、阿花王立ちて貴国に礼无し。故に我が枕弥多礼及び峴南・支侵・谷那・東韓の地を奪われぬ。是を持って王子直子を天朝に遣して先王の好を脩む。
(ニ)応神紀二十五年(分注) 百済記に云はく、木満致は、是木羅斤資、新羅を討ちし時にその国の婦を娶きて生む所なり。其の父の功を以て任那に専なり。我が国に来入りて、貴国に往還ふ。制を天朝に承りて我が国の政を執る。権重、世に当れり。然るを天朝、其の暴を聞しめして召すといふ。
これらの「貴国」が日本のこと敬称として言っているとしたらおかしくはないでしょうか? 特に(イ)では「日本の貴国」とあります。「日本の日本」などという表現はあり得ません。
『日本書紀』は日本という語が使われていない時代の叙述でも、我が国の表現は日本とせよ、倭武尊は日本武尊というように書きなおされています。「倭国」は全てといってよいほど日本に書きなおされています。 つまり『百済記』の「日本の貴国」は元の文章は「倭の貴国」であったものに違いないと思われます。
また、この文章は、卓淳国の王に百済の王が貴国との通商の仲介を頼んでいるのです。その中で第三者の日本の事を「貴国」という表現はあり得ないと思います。
ところが、『日本書紀』の編者は「貴国」を日本と書き直すと「倭の貴国」の場合、「倭」は「日本」と書きなおす原則があることから、「日本の日本」となってしまい、文章として成り立たなくなるので、そのまま「貴国」と書いたと思われます。
では、我が国が「貴国」と呼ばれていたことがあったのか、という証拠があるか、という反論がされるかも知れません。 それでは、日本のキ国と呼ばれる地域があったのでしょうか。
現在まで残っている地名でキ国に該当するのは、和歌山県の「紀伊半島」、岡山県の「鬼ノ城」、福岡県の「基肄郡」などが上げられます。詳しく調べればもっと有ることでしょう。
朝鮮半島と地理的にも近く通商関係を結ぶなどを考えると福岡県の基山という古代山城遺跡のある基肄郡の「基肄」が貴国の有力候補と云えるかと思います。
古田武彦氏は『日本書紀』岩波本が熱田本(卜部本系列)という古写本に基づいているが、北野本という別の古写本によると、この「百済記」の「貴国」の記事が『日本書紀』とは違っている、と指摘されます。(『失われた九州王朝』より)
『日本書紀』神功紀六十六年に「倭の女王貢献」の記事があります。 岩波文庫では、「是年、晋の武帝の泰初の二年なり。晋の起居の注に云はく、武帝の泰初の二年の十月に、倭の女王、訳を重ねて貢献せしむといふ。」 北野本ではこれは「是の年、晋の武帝の泰初三年初の起居注に云う。武帝の泰初の始、二年十月、 貴倭の女王、重訳を遣して貢献せしむ」と。
明らかに「倭の女王」と「貴倭の女王」と異なっています。 この北野本と卜部本のどちらが『日本書紀』の原形を残しているのか、という考察を『失われた九州王朝』でされて、北野本の方だ、とされます。詳しくは同書をご覧ください。
その中で北野本の方が卜部本より古形を保つ例として挙げられているのに、『日本書紀』天智紀四年九月の「百済将軍」(卜部本)があります。北野本では「百済禰軍」です。古田武彦氏は『三国史記』に「司馬禰軍」という官職名があることを挙げ、その事を知らぬ卜部本の書写者が禰軍は将軍の誤りと誤断したもの、と推論されています。
この「百済禰軍」という呼称を持つ百済の軍人の墓誌が西安で発見された、と2011年10月23日の朝日新聞が報じていました。古田武彦氏の推論が正しかったことが約四十年後に、金石文という形で確かめられたことになります。もし、百済将軍と墓誌に出ていたら、古田武彦氏はボロクソに批判されていたでしょうが、その推測が当っていたらマスコミは全く古田のふの字も出しません。
ところで、この『晋書』の「貴倭の女王」というのは、その記事内容から邪馬壹国の壹与のことにまず間違いありません。となると、貴倭=卑弥呼の国で北部九州の国という帰結になるのです。 つまり、三世紀の邪馬壹国から~貴倭国~大倭国~俀国(六~七世紀)~日本(八世紀)という国号の変遷の過程の一部を、この「貴(倭)国」問題は示していると云えましょう。
このような「貴(倭)国」についての認識が、全く見られない大津教授の著書『天皇の歴史01 神話から歴史へ』なのは残念です。
(b) 襲津彦と沙至比跪が同一人物か
百済系史書と『日本書紀』の記事の違いについての大津教授の受け取り方を見るために、もうひとつ「葛城襲津彦」の件を取り上げたいと思います。 大津教授は、“「帝紀」からみた葛城氏”という項を立てて葛城襲津彦の伝承を検討しています。その結果、【 「帝紀」が、その襲津彦の検証によって正しかったことを示せた】、と言います。
その論拠にされるのは、井上光貞氏の『古事記大成』一九五六年という論文です。【 この論文は、五十年前のものだけれど今も色あせしていない(p155)(つまり自分も同意)】といわれます。
具体的には次のように葛城の襲津彦について述べられています。 (以下p157-158要約)
【『古事記』の仁徳天皇のところで、「葛城の曾都比古が子、葦田宿彌が女、名は黒比売の命を娶りて生みたまへる御子、市辺の忍歯の王、次に・・・・」とある。 「帝紀」によれば、倭の五王時代、三人の后妃が葛城氏出身であり、仁徳の子の履中・反正・允恭・市辺忍歯王、また雄略の子清寧がいずれも葛城氏を母にしたのである。五世紀に葛城氏は天皇家外戚として大きな政治的勢力を持った事が伝えられている。 『日本書紀』には襲津彦について四つの伝説がある。
①神功紀五年に、新羅が日本に贈っていた人質、微叱許智の物語がある。新羅に人質を帰すことになり、襲津彦をつけて本国に送らせようとしたが、人質は襲津彦を騙して逃げ帰った。襲津彦は怒って新羅へ攻め入り多くの捕虜を連れ帰ったという話。
②神功紀六十二年 新羅が朝貢しないので、襲津彦を遣わし新羅を討たせた。そして分注として「百済記」が引用されている。“壬午年に、新羅、貴国に奉らず、沙至比跪を遣はして討たしむ。新羅人、美女二人を荘飾りて津に迎へ誘る。沙至比跪、その美女を受けて、反りて、加羅国を伐つ。加羅国王己本旱岐(中略)、その人民を将て、百済に来奔ぐ。” この分注については後述。
③応神十四年と十六年条で、弓月君が帰化し引き連れて来た120県の人夫は、新羅人に拒まれて加羅国にとどまったため、ソツヒコを加羅に派遣して人夫を召そうとした。しかしソツヒコは三年たっても帰ってこなかったので、平群宿禰らを派遣して新羅に兵を進め、ソツヒコも人夫もともに日本に帰国した。
④仁徳四十一年条で、紀角宿禰が百済に派遣され、国境等を定めたが、百済王族の酒君が無礼を働いたので鉄鎖でゆわえ、ソツヒコをして献上させた話である。】と。
そして、②の分注として『日本書紀』に出ている「百済記」の話の内容を、大津教授は次のように解説します。 (p158)
【新羅がそむいたので沙至比跪を派遣したが、彼は美女に惑わされ、かえって加羅を討った。そこで加羅の国王、一族は人民をひきいて百済へ逃げこんだ。さらに国王の一族が大倭に訴えたので、「天皇、大きに怒り、即ち木羅斤資(百済の将)を遣はして、兵衆を領ゐて加羅に来集しその社稷を復せしむ」と記している。】と。
この説明は中途半端です。「百済記」の引用は【 ・・・・百済に来奔ぐ。】で大津教授は端折っていますが、説明は【 さらに国王が大倭に訴えたので・・・】と大津教授が言及しながら、「百済記」の引用をしない部分が『日本書紀』には記載されています。
大津教授にどのような魂胆でこのような中途半端な引用をして、引用していないとろの説明を付け加えているのか、不思議です。この件については後で「襲津彦と沙至比跪問題」で詳細に見てみることにします。
さらに、【②の分注に見える「沙至比跪」は「襲津彦」と同一人物と考えてよいだろう】、と大津教授は述べます。
【 この様に日本に伝わる「帝紀」「旧辞」とは全く別の系統の百済に伝えられた記録に「沙至比跪」の活動が伝えられているので、『日本書紀』に記されている「襲津彦」が実在の人物である可能性が高い】、とも大津教授は書き、
【 年代については、『日本書紀』が卑弥呼と神功皇后の活動期を合わせる為に、干支二運繰り上げているので、神功62年壬午年を262年に当てているが、382年のことだろう】、とされます。
次に、【③の応神紀の伝説も内容的に「百済記」の沙至比跪と大枠で一致していて同じ話であろう。襲津彦は伝説上の人物であるが、実在の人物が伝説化されたものである。好太王碑文に見える391~404年の日本の朝鮮半島での積極的な関与とほぼ重なるだろう。
「百済記」には日本本国への裏切り者として描かれるが、それは百済側の修飾であり、多くの捕虜を日本に連れ帰った勇将であったと考えられる。 このように、襲津彦の活躍時代を応神の頃とすれば年代も合う。ここから仁徳をめぐる「帝紀」すなわち皇統譜は一定の史実にもとづいている。】と結論づけます。
以上の大津教授の意見は、その様に即断してよいのかな、という疑問が起きます。まず、①この伝承から襲津彦は「勇将」といえるのか。②襲津彦と沙至比跪と同一人物といえるのか。③沙至比跪が仕えた天皇は誰か。などの疑問が出てきます。
応神紀の記事からみると、襲津彦は加羅に派遣されましたが『日本書紀』によりますと、三年もの長期間成果を上げられず帰国できなかったのです。そこで平群木莬宿彌等を派遣して目的を達成した、というような記事で、とても「勇将」と褒めそやす話ではないのです。
おまけに、大津教授は所謂「情報開示」をしていません。前述のように『百済記』の沙至比跪の記事は、肝腎なところが述べられていません。改めて『日本書紀』神功紀六十二年のところの、「百済記」の問題の全文を出してみます。 現代文では次のようになります。
【新羅が貴国に朝貢しないので沙至比跪を派遣した。沙至比跪は新羅から献上された二人の美女にたぶらかされて、新羅ではなく加羅を征伐した。加羅の国王たちは百済に逃げ込んでその庇護をうける。加羅の国王の妹が大倭に「天皇が沙至比跪を派遣して新羅を討つことを命じられたのに、沙至比跪は新羅の策略にはまって反対にわれら加羅を攻め滅ぼし、われわれは流浪の民となってしまった。」と申しあげた。
天皇は怒って木羅斤資に精兵を付けて派遣し加羅の国を復興させた。そして、沙至比跪は天皇の怒りを恐れ、こっそり帰国し隠れ住んだ。沙至比跪の妹が後宮にいたので、比跪はひそかに使いをたてて、妹に天皇がまだ怒っているか問い合わせた。妹は、天皇に夢話に託して「今夜沙至比跪の夢を見た」と話した。天皇は怒って「比跪がどの面下げて顔だし出来るのか」と言った。この事を兄に知らせてやると、比跪は、自分は許されないことを知って、石穴に入って死んだという。】
古田武彦氏が『ここに古代王朝ありき』のなかで、古代史についていくつかの著述がある兼川晋氏の言を紹介しています。
【天皇の皇居の近くまでひそかに帰って来て、妹に頼んで天皇が自分にまだ怒っているのか聞いて貰う。夢にことよせて聞いてみたら天皇はまだカンカンになっている、もう駄目だ、とはかなんで、「石穴」に入って死んだ、この話から、皇居と石穴はさほど遠くないところ、ということになれば、どこだろうか。大和の地に「石穴」という場所はないが、太宰府が都だったとすれば、太宰府近くの「石穴」現在の太宰府市石坂の「石穴神社」であろうか。】と。
いずれにせよ、沙至比跪は勇将どころか、女に溺れ、任務を全うできなかった男であり、自分を恥じて死んだ男、なのです。無理に、葛城の襲津彦と沙至比跪と同一人物として論じることは、襲津彦にとっても失礼な話であり、天皇家と沙至比跪の出自と大津教授がされる葛城氏と歴代の繋がり云々と言うように発展させることは小説の世界であって歴史学の論理からみて飛躍していると思います。
岩波文庫本でのここのところの解説は、「同一人が日本側に伝わって襲津彦、百済側に伝わって沙至比跪と記録されたものと考えられる。ソツヒコのソはサチヒコのサに、前者のツは後者のチに、まま交替する音。」としているのにそのまま大津教授は乗っているようです。
また、この説話からみると、沙至比跪は「天皇」の命令で働いているのです。その「天皇」は沙至比跪の妹と男女の仲なのです。とても「神功皇后」の命で働いた襲津彦と同一人物とは思われません。大体名前からして違っているのを同一人物にしたい、という気持ちが無意識の中に働いているようです。一方は「ソツヒコ」もう片方は「サチ(シ)ヒキ」です。
ところで余談ですが、この『百済記』では、沙至比跪を略称で「比跪」と呼んでいます。わが国の場合、襲津彦を略称で「彦」と呼ぶのかなあ、略称で呼ぶなら一般的な「ヒコ」でなく頭をとって「ソ」または「ソツ」になるのでは、と思われるのです。ただ、『百済記』では他にも人名に、 職麻那那加比跪など「比跪」が使われているので「彦」と同じように「比跪」が男子の名の接尾語的に使われていたと思われます。
しかし、当時の百済で「跪」を「コ」と発音されていた、というのは納得し難いところです。「跪」の読み方について調べてみると、清朝時代の三跪九叩頭の礼、明朝の小説水滸伝で跪伏礼などのいずれも「キ」という発音と思われるものです。
もっと古い用例をと調べたら、四世紀の事績を述べた、高句麗の好太王碑文第二面「六年丙申」の条にありました。好太王が百済を討伐し、百済王を跪王とし奴隷同様に仕えさせた、というような記事です。朝鮮半島での用例で「跪王」とあります。これも「キ」でしょう。
岩波文庫版『日本書紀』が「比跪」に振り仮名「ヒコ」と書いているのを、学者さん達が無批判に引用し続けますと、新版漢和辞典に、「跪」の読みに「コ」が加わって、それを疑問に思って、その漢和辞典の編集者に問い合わせると、「岩波書店が「跪」を「コ」としていて学者さん達も同意されているので」という返事、というマンガ的な状況も生じるのではと危惧します。
襲津彦の娘(磐之媛命)が仁徳天皇の後宮に入っていて皇后になった、と『日本書紀』は記しています。沙至比跪と同一人物ならば、このような問題児の娘を皇后に仕立てるには、何らかのエクスキュースが『日本書紀』にあっても然るべきと思いますが、『日本書紀』編者は沙至比跪を勇将と程遠い人物として紹介しています。
これらのことを大津教授は頬かぶりで、葛城熊襲津彦勇将説を特出評価して、天皇家との繋がりを強調するのは如何なものかと思われます。 つまり、大津教授には、原本が残っていない『百済記』よりも『記・紀』の「帝紀」「旧辞」など記録が信用できる、とされる大前提があるのではないか、と疑われます。
その前提を崩したくないので、襲津彦を勇将とし、葛城氏が歴代天皇の后妃を輩出した有力氏族である、としなければならないのでしょう。ですから、『百済記』の全体の記事を読者の前に顕わにしたくなかったのでしょう。
「三種の神器」の話に戻りますが大津教授は、【三種の神器から勾玉が外れ、鏡と剣の二種がレガリアになった】、と言われます。【 奈良時代には、勾玉が天皇家の宝物として存在していたことは疑う余地はないが、玉と剣・鏡とは、少なくとも役割や機能が異なっていたことに注意すべきである。】(p60)とも言われます。
ならば同様に、古墳時代は鏡の埋納が盛んだったのがなぜ止まったのか、せめてその考察があるかと期待したのです。銅鐸の消滅についても大津教授は無言でしたが、鏡の埋納の消滅についても考察はありません。
葬祭儀礼の変動と天皇系譜との関係など素人には興味があるのですが、大津教授は全く興味を示されません。興味を引かないのか、分からないことは話したくないのか、何も書かれていません。 いままで見て来たように大津教授の史資料の読みとり方は、理解に苦しむところが多いようです。次の項目「高句麗の碑文」の読みとり方はどうでしょうか。
★高句麗好太王碑文
四世紀の史料として高句麗好太王碑文があります。広開土王とも呼ばれる、高句麗王の碑文です。 この碑は第十九代高句麗王、好太王の業績を称えるために息子の長寿王が414年に建てたものです。
のち1880年頃に地元農民により発見され、明治十七年(1884年)に陸軍砲兵大尉の酒匂景信が拓本を取り、日本に持ち帰り解読し参謀本部に報告しその内容が発表されました。好太王碑は、当時は高句麗の支配下にあった現在の中国吉林省集安市に建っていて、碑の近くに好太王墓も発見されています。
碑の高さは6米強で幅は150糎の四角状の石碑であり、その四面に総計1802個の文字が刻まれています。文章は漢文での記述ですが風化によって判読不能な箇所もあります。 碑文には沢山の「倭」が出ています。
大津教授はこの碑文に出てくる「倭」について、次のように熊谷公男著の『大王から天皇へ』という本の「好太王碑文」の所の訳文を引用され掲出しています。
【百残(百済)・新羅、旧より属民にして、由来朝貢す。而るに倭、辛卯の年よりこのかた、海を渡りて百残(百済)を破り新羅を□□し、以て臣民と為す。六年丙申を以て、王躬みずから水軍を率ゐて、残国(百済)を討伐す。】 この読み方は果たして正しいのか、検討してみたいと思います。
この部分の原文は次のようです。永楽五年(395年)「百残新羅旧是属民由来朝貢而倭以辛卯来渡海破百残□□新羅以為臣民」
辛卯の年というのは永楽元年(390年)です。この碑が建てられた永楽五年の四年前に倭の侵入があった、ということです。
【この高句麗大王の功績をたたえる記念碑に「他国(倭)がわれわれの属民だった者たちを臣民にした」、という語を刻むのはおかしいのではないか、これは好太王が、倭が侵入してきて四年間ほど百済新羅から朝貢は途絶えたが、やっと永楽五年になって渡海作戦の成功により高句麗の臣民とした、と解すべき。】、と古田武彦氏 は主張しています。(『失われた九州王朝』「第三章高句麗王碑と倭国の展開」より)
これは、事の本質から見れば日本側の通説(大津教授を含む)とは180度異なった解釈です。(韓国学会の読み方とは似通っています。後述) この大津教授の本を読んだ方には、大津教授が依拠される熊谷さんの『大王から天皇へ』で実際どのように書かれているか知らないと思いますのでそのエキス部分を紹介します。
【日本に広開土王碑が知られるようになったのは1884年に、参謀本部の砲兵大尉酒匂景信がその拓本を持ち帰ってからで、その後碑文の解読も参謀本部で進められた。参謀本部にとって、辛卯年条は、日本が太古の昔に半島南部を支配下に置いていたことを示す動かぬ証拠と映ったのである。このことが、その後の碑文研究に大きな影響を及ぼしていく。
その後明治大学の李進熙氏が碑文改竄説を唱えたが、中国吉林省の研究所長王健群氏が詳細な調査の結果「碑文改竄説」の間違いを証明した。しかし王健群氏は「倭」を北九州の地方勢力、ないしは後世の倭寇のような海賊とみているが賛同しがたい。(中略)広開土王碑に見える倭が、列島を公的に代表する倭政権であることはもはや確実といってよいであろう。】(同書p39~043要約)
つまり、熊谷さんは、酒匂景信はスパイだった、などの刺激的な言葉を発しながらも、昔の参謀本部の解釈が正しかった、と言っていることになります。
ただ不思議なのは、大津教授は、【 日本書紀の神功皇后紀にある三韓征伐は、八世紀はじめに新羅は日本に従属する「蕃国」であるという律令国家の理念により潤色されたもので、事実ではない。しかし四世紀後半の、出兵したという神功皇后紀の記述は史実を反映しているのだろう。】(p80)と書かれます。
大津教授は何をおっしゃりたいのか、と素人は理解に苦しみますが、好太王碑文の「倭」は神功皇后の三韓征伐と見ていらっしゃるように取れます。そして大津教授は、新羅の服属は事実ではないとも言われますが、『宋書』を読むと事実ではないか、と推察されるのです。何を根拠にして『宋書』の記述を否定されるのか、示して貰いたいものです。
これについては、後で「倭の五王」のところで、もう一度見てみることにします。
ネットで調べましたら、韓国の歴史学会では、次のように碑文を解釈しているようです。【好太王碑は好太王の高句麗の業績のために造られており、好太王の業績を礼賛する碑だ。そこに、倭が主語となって百残、加羅、新羅を破り臣民としたと記述されるのは間違いだ】と主張し、以下のような解釈が韓国学会の定説となっているようです。
百殘新羅舊是屬民由來朝貢而倭以耒卯年來渡>海 破百殘■■■羅以為臣民 【新羅・百残は(高句麗の)属民であり、朝貢していた。しかし、倭が辛卯年(三九一年)に来たので(高句麗は)海を渡って百残を破り、新羅を救って臣民とした。】
「倭人伝」もそうですが、中国文の解釈は難しいと思います。おまけに、この碑文の場合は欠落字がありますので、特に難しいと思いますが、文全体の本質を掴んだ理解が必要でしょう。
この高句麗の好太王の活躍した時期は、四世紀末であり倭王讃の若い時代に対応します。(讃の朝貢記事413年~430年 没年は不明だが子の珍の即位は438年)つまり、倭讃の宋書の記事と好太王碑文の「倭」についての記述とは時期的に対応している、と言えます。
碑文改ざん説について大津教授は、熊谷公男氏が詳しく検討されている、として『大王から天皇へ』の書名を上げています。(p79) その熊谷公男氏の『大王から天皇へ』では改ざん説を次のように説明します。
【戦後、朝鮮人民共和国・韓国・また在日の歴史家から、碑文の改ざん説がでた。参謀本部が石灰を塗布して碑文を改ざんして拓本をとった。(中略)その後、中国の王健群氏が詳細な調査を行い、碑文の改ざんは為されていないことを証明した。西嶋定生氏によると、頭書の読みになった。】(同書p39-40)
その上で、問題部分の説明は、戦前のままで「倭が半島の人々を臣民にした。」ということになっているわけです。これは西嶋氏に責任を被せる形での説明です。 しかし、西嶋定生氏の論文『広開土王碑文辛卯の条の読み方について』(平凡社1985年)は、この碑文の論争が一段落した以後のものなのです。
実は、この碑文の改ざん説についての熾烈な論争が繰り広げられた時期があります。この碑文の論争が行われたのは一九七〇年代前半で、古田武彦氏が改ざん説の李進熙氏と度重なる論争の結果、改ざん説が根拠ないものであったことを論証されたのです。大津教授はこのことについて全く触れていません。(”好太王碑文「改削」説への批判 李進熙氏『広開土王碑文の研究』について”『史学雑誌』82-8 1973年8月)
大津教授の碑文の解釈の受け取り方は、戦前の解釈と殆んど変わらず、神功皇后の三韓征伐と関連付けされていますが、それだけでは済まないものをこの好太王碑文は示しているのです。
ところで筆者は、随分前にネット上で江上波夫著『騎馬民族国家』を検討したことが有ります。好太王碑文を「倭が新羅・百済の人民を臣民にした」という解釈を広げて、騎馬民族国家征服説が一時古代史を賑わせました。この江上波夫説についてもこのHPで批判していますので、下記URLをクリックしてみて下さい。
http://www6.ocn.ne.jp/~kodaishi/yaridama25kibaminzokukokka.html
大津教授は、「好太王碑文」について、【金石文は、この時代の歴史を描く第一次史料】とされます。(p38)
【碑文の内容は三段に分かれ、第一段は高句麗の始祖鄒牟王の創業より始まり碑を建てた由来におよび、第二段は好太王一代の功業を述べ、第三段は、守墓人の烟戸を細かく書き記している。史料として役立ち、注目されるのは第二段である。】(p78)とされて、「倭が渡海して云々」の論議となったわけです。
では、第三段は「天皇の歴史」に関係ないのでしょうか。東アジアの雄であった高句麗王の「守墓」体制を、日本列島の王者達が意識しなかったとは思われません。勿論、文化の流れは一方向とは限りませんが、相互に影響しあったことでしょう。
「第三段」としていますが、この第三段部分は「全体四面の碑文の内、第三面の半分と第四面を占めていて、この碑文の主目的はこの守墓制度をキチンと示すことを目的としている、といっても良いと思われます。
原文の紹介、釈文の紹介は煩雑ですので省きますが、高句麗が属国とした諸国の捕虜や従属民から守墓人を任命し、それに対する給付を規定しているのです。
古田武彦氏は、これについて次のように書きます。【日本の天皇陵よりずっと小さい好太王(広開土王)の陵墓にすら「守墓人」問題が重視されていたのに、日本側では、「作りっぱなし」で「墓守り」など、いなかった。必要としなかった、などとあなたは信じますか、わたしには信じられません。】と、陵墓と守墓について言われます、
そして、古墳の分布と被差別部落分布とが重なることに注目され、被差別部落の淵源は陵墓の守墓制度と考察されています。(『失われた九州王朝』ミネルヴァ書房コレクション版 「日本の生きた歴史(二) 第八 高句麗好太王碑と天皇陵」より)
現実から目をそむけて「天皇の歴史」が語れよう筈もありません。大津教授は、見たくないものから目をそむけて、上っ面だけの、いわば偽りの「天皇の歴史」を述べていると断じざるをえないでしょう。
★稲荷山鉄剣銘の大王は雄略か
大津教授は、p89ー92にかけて稲荷山古墳と江田船山古墳から出土した鉄剣銘について、要約次のように言われるのです。
【稲荷山鉄剣が出土し、その銘文の解読により、九州の江田船山古墳出土の鉄剣銘も雄略天皇のものとわかった。それにより雄略天皇が全国的な支配権を構築していたことが判明した、】と言われます。そして【 宋書の倭武が雄略天皇であり、雄略天皇は国から離れ、独自の秩序を形成した】、と断言されます。
それ程の価値ある「金石文」の出土ですから、その内容には充分吟味する必要があります。 「好太王碑文」の解釈でも、大津教授はご自分の史観に合うような論文を我田引水的に利用されていますので、そのあたりに充分注意を払って『天皇の歴史01 神話から歴史へ』を読まなければならないでしょう。
「ワカタケル」という銘文の読みについて、まず発見の歴史から言うと古い九州中部、熊本県菊池川沿岸の「江田船山鉄剣銘」の解読から入ります。 銘文は次のようにかなり判読不明の文字が多いものです。
「治天下①②③④⑤大王世奉⑦⑧⑨人名无⑩弖八月中用大鐺釜幷四尺■力八十錬六十捃三寸上好⑪刀服此刀者長寿子孫⑫々得其恩也不失其所統作刀者名伊太⑬書者張安也。(■=延繞に手 廷の壬が手になっている字 )
福山敏男氏の読解 ①は蝮の虫扁がけもの扁の字、⑤は歯、⑧は典、⑫は注、⑬は加。 この銘文の一番の問題点は治天下①②③④⑤大王という最初のフレーズです。昭和三十年代まではこの、福山敏男氏の、【最後の字⑤が「歯」に似ているとして、イミナに「歯」がはいるのは反正天皇の、「瑞歯別」ミズハワケだけである。最初の字をマムシと読み、多遅比瑞歯別宮、とタジヒ(蝮)のミズハワケ宮に反正天皇は天の下治しめしたので合う。】というのが有力な説とされていました。
大津教授も次のように江田船山古墳から銀象嵌銘の鉄刀が出土した、と述べられます。【その冒頭は「治天下蝮□□□歯大王」と読まれ、蝮之宮瑞歯とあてて、「多遅比瑞歯別天皇」=反正と解釈されてきた。ここに「獲加多支鹵大王」が発見されたことにより、この釈読も改められることになった。】と、それまで蝮之宮瑞歯大王と読み解いていたものが、稲荷山鉄剣銘の読解に合わせて「獲加多支鹵大王」とされた、といわれるのです。
五文字の内、最初の字がけもの扁の字、最後の字が歯か鹵か判別のつかない字、それで「獲加多支鹵」と読ませるのは、「可能性はある」、ということ位しか言えないと思われます。
鹵の字の付く王様は、わが国では見つかっていませんが、百済にはその時代に蓋鹵王というれっきとした王様が存在しています。この銘文の頭書部分を、「治天下復百済蓋鹵大王世」と読む説もあります。(堤克彦 熊本大学社会文化科学研究科研究紀要『江田船山古墳被葬者他』2010.5刊)
http://reposit.lib.kumamoto-u.ac.jp/bitstream/2298/15155/3/KumaTK-Tutumi201005r.pdf
ところで、大津教授の稲荷山鉄剣銘の読み方は次です。
【115字からなる長大な文章である。五世紀史の基本史料であるので、書き下して掲げる。辛亥の年七月中、記す。ヲワケの臣。上祖、名はオホヒコ。其の児タカリのスクネ。(中略)其の児、名はカサヒヨ。其の児、名はヲワケの臣。世々、 杖刀人 の首と為り、奉事し来り今に至る。 獲加多支鹵大王の寺(朝廷)シキの宮に在るとき、吾、天下を左治し(佐け治め)、この百錬の利刀を作らしめ、吾が奉事の根源を記すなり。 】 (p90)
つまり、「オホヒコから七代目のヲワケの臣がこの銘文を記した。歴代杖刀人の首であり今もそうだ。その杖刀人の首の私がワカタケルの治世に天下を左治した。」ということになります。
まず、このように、稲荷山鉄剣の銘文の読み方も大津教授が「獲加多支鹵」と振り仮名をふっていらっしゃいますが、これはかなり無理なよみ方ではないでしょうか。
獲はワクと読めますが、雄略天皇=倭王武であれば、「ワ」には「倭」を使うことでしょう。この字自体が「獲」でなく別の字ではないか、という説もあります。
第四文字の「支」も「キ」ないし「シ」と読めますが、「ケ」と読んだ例が、例えば万葉仮名などで、あるのでしょうか?
同じく「鹵」は□のなかは※でなく九のような字なのです。それを「ル」と読んだ例もあるのでしょうか。
以上のことを考えると、せいぜい言えても、無理すれば「ワカタケル」と読める、ということでしょう。それに加えて雄略天皇が「ワカタケル」と呼ばれていた証拠は何もないのです。強いて探せば雄略天皇の幼名「ワカタケ」です。それに、「武」の読みとして古代一般的に用いられたと思われる「タケル」、これを組み合わせて「ワカタケル」に持って行った、ということになります。
そして遠く離れた熊本の江田船山の鉄剣銘も「ワカタケル」と読めば、雄略天皇が関東から九州まで支配していたことを示せる、雄略天皇が全国を支配していた、ということが言える。その様に持って行きたいという前提に合わせた立論で、それが歴史家達のいわば暗黙の談合で定説化した、と言うことの様です。
大津教授は【 倭武=雄略が中国から離れ、独自の秩序を形成した(p89)】、そして【 稲荷山鉄剣銘が五世紀の基本史料である】(p90)と言われますが、この稲荷山の鉄剣銘文には「ワカタケル」の読み方以外にも数々の問題点があるのです。
第一に、その出土した礫床墓は古墳の副墓位置からであり、粘土槨の主墓(過去に盗掘にあってる)からではない、ということです。つまり、この鉄剣を副葬された被葬者は主墓の被葬者と主従関係にあった、と見るのが道理と思われること。(つまり、ワカタケルはここで亡くなったということになる。)
次に、鉄剣銘には、「斯鬼宮」とありシキ宮ということはまあ間違いないと思われます。しかし、雄略天皇の『記・紀』の記述にはハツセの朝倉宮とありシキ宮ではないこと。「シキ」という地名は全国的にみればかなり存在するでしょう。垂仁天皇は「師木の玉垣宮」にいた、というようにちゃんと古事記には出ています。
しかし、古田武彦氏が稲荷山に近い栃木県藤岡町に「磯城宮」という地名が残っていて、現在でも大前神社というお宮がそこにある事を指摘されました。
これ以外にも、第三に、寺が宮に在るという問題があります。中国古代では、天子のいる宮殿は「臺」、将軍たちのいる役所は「府」、その下の小さな役所が「寺」です。雄略が倭王武だとすれば、配下の乎獲居臣が「府」でなく「寺」といっているのはおかしいことです。なぜなら、特に倭王武は宋朝に対し「開府儀同三司」の権限を名乗っていたから認めろ、と宋に要求している人物なのですから、部下のヲワケ臣の役所は「寺」ではありえないのです。
第四の問題として、「杖刀人」「杖刀人首」の問題があります。『記・紀』のどこにもそのような役職はないのです。つまり、これらの役職は「ヤマト王権」のもとでの役職ではありえず、武蔵地方を統轄していた大王の定めた役職と思うのが論理的と思います。
その他にも、「意富比垝」という人名を「オオヒコ」と読んで古事記に出てくる「大彦命」にあててよいのか、そのまま読めば「イフヒキ」若しくは「オホヒキ」となる、近くにある地名「比企」との関連を考えるべき、などの問題があります。 (以上 古田武彦『関東に大王あり』「宮殿の所在地」より)
大津教授のおっしゃることには無理があり過ぎます。どれもこれも、稲荷山の獲加多支鹵を雄略天皇とする無理、その無理を江田船山古墳の鉄剣銘の不明の五文字に当てはめるという無理の二乗となっています。
「分からないことは分からない」とするのは、たとえ大学教授という地位にあっても、何も恥ずかしいことではありません。それなのに大津教授は意富比垝を大彦とし、『記・紀』に出てくる四道将軍の大彦命にあてて、論を発展させています。どうしても近畿の人物に当てないと納まらない大津教授のサガなのでしょうか?
【上祖オホヒコは有名な伝承上の人物である。崇神紀には「大彦命を以て北陸に遣はす。云々」とあり、印綬を授けられている将軍である】(p146)と『日本書紀』の記事を引用しています。これなど仮説の上に仮説を何段にも積んだいわば小説の世界でしょう。
その上で、【 ヲワケの臣は中央豪族であり、自ら鉄剣を作らせ、それを「杖刀人」として上番してきた武蔵の豪族に「杖刀人首」として下賜したもので、(中略)中央豪族において大王に奉仕するウヂの組織が形作られてきたと考えておきたい。】(p148)とされます。
では、主墓の被葬者と鉄剣との関係はどうなるの? 武蔵の豪族と主墓の被葬者との関係は? 杖刀人とはどのような役目だったの? などこれらについて大津教授は一言の示唆もありません 。
肝腎の重要問題としては、この銘文の最初にある、「辛亥年七月中記」とある「辛亥」を大津教授は次の理由で四七一年とされることが上げられます。【 倭武の上表が昇明二年(四七八)であるので、その七年前の辛亥年四七一年であると考えたらよい。】(p91)と書かれます。
鉄剣銘の不確かな推定からワカタケル=雄略天皇とし、中国史書にある倭王武が四七八年に宋朝に上表している、従って、倭王武を雄略とすると、全て辻褄があう、とおっしゃりたいのでしょう。
論理が逆立ちしています。 鉄剣銘が記す「獲加多支鹵」が雄略でなく、倭王武も雄略でなかったら、この辛亥年は決まらないわけです。この古墳は五世紀末から六世紀前半と言われているので、四七一年か五三一年ということになります。出土した他の品々の鑑定や年代年輪法、放射性炭素法に依る測定その他、の手法で年代を決めたら五世紀後半であった、という結果があればそれをまず示されるべきでしょう。
指摘しておきたいのは、その辛亥年と大津教授がされている年に倭王武が在位していたのか、という肝腎な点の確認が抜けていることです。後で述べますが、『宋書』の「倭の五王」の記事を検討すると、この辛亥年には倭王武の一代前の倭王興が在位しているのです。
学問の最高峰と目される東京大学歴史学教室で、このような非科学的な、神話より質の悪いSF小説的な歴史観が罷り通っていることについて驚きを通り越して呆れかえります。(この倭王武の在位と雄略の関係は、『宋書』「倭の五王」であらためて詳しく論じます)
その他にも大津教授の「稲荷山鉄剣銘」の解釈には沢山の問題があります。例えば①「吾左治天下」の意味は?、②稲荷山古墳の主棺の主人公は?、③昭和四四年の埼玉県の古墳調査報告書が、十年後に書き換えられた問題、④「臣」の問題。『日本書紀』によれば、武蔵国造は「臣」ではなく「直」である。⑤江田船山の銘文の主人公の文字は、稲荷山のそれとは違っているし、馬や花の模様が入っていて銘文の質が違う。
これらの問題についてお知りになりたい方は、古田武彦著『関東に大王あり』創世記社をご覧下さい。
大津教授の読み下し文は先にあげました。古田武彦氏のそれも上げて、この両者を比べてみたいと思います。
古田武彦氏の読み下し文:【辛亥の年、七月中の記。乎の獲居の臣、祖を上る。意冨比垝、その児多加利足尼と名づく。その児・・・・。世々杖刀の人首と為りて奉事来至す。今加多支鹵大王寺を獲て、斯鬼宮に在りし時に、吾左けて天下を治す。)】(『関東に大王あり』創世記より)
大津教授の読み方の問題としては、「獲加多支鹵大王」の解釈・「寺」が朝廷を意味するのか・「杖刀人」とはどういう役職か、などが上げられます。 古田武彦氏は、定説となっている読み下し(大津教授のも同様です)に対して、次のような四つのことを証明して貰いたい、と言います。
【第一に、「大王の寺―宮に在り」という文例。第二に、「左治天下」を田舎豪族や門番(杖刀人)の頭などが使えるのか。第三に、稲荷山古墳と指呼の間にある「磯城宮」がなぜ不適格なのか。第四に、副棺の位置の礫床から出た鉄剣が、近畿の天皇ワカタケルのことばかり書いていて、肝心の粘土槨の主について無視しているのはなぜか。】 これらについて、大津教授は答えることが出来るでしょうか。
実は、次の『宋書』とわが国の歴史の章で、倭王武の即位と雄略天皇の在位年代との食い違いという問題が出てきます。根本的に稲荷山の鉄剣銘の「辛亥年」には倭王武は即位していないのです。
つまり、稲荷山鉄剣銘の獲加多支鹵大王は倭王武ではないし、倭王武=雄略天皇とはならない、というのですから、獲加多支鹵大王=雄略天皇と見なしたいということ自体が無駄な試み、と言えます。
(四) 『宋書』と我が国の歴史
★倭の五王
次に好太王碑文と同時代史料『宋書』の「倭の五王」問題に入ります。
大津教授はこの本の 第一章 3 倭の五王と大王 で「中国的な姓秩序の中の倭王」の項を設け、中国風一字姓に関係した話をされます。その冒頭で次のように書かれています。
【 南朝の宋が建国された翌年の四二一年に倭は初めて宋に遣使朝貢して叙爵された。二六六年に倭の女王(台与か)が西晋に朝貢して以来、一五〇年ぶりに中国に朝貢し、中国の正史にあらわれる。以後、讃・珍・済・興・武の五人の王が宋に朝貢している。】(p81)
そして、倭の五王とは誰かという古代史上の大きな話題について、大津教授は大略次のように『宋書』に書かれた倭国関係の記事をまず紹介されています。 (p81-82)
【もっとも詳しい記事は四七八年の倭王武の年の朝貢記事である。『晋書』に、四一三年に倭国と高句麗が東晋に方物を献じた記事もあるが、倭の貢物が貂皮・人参であったと記され日本産でないので、高句麗が倭国の使者を随伴した、あるいは高句麗が倭国を従属させたことを示すため倭の使者と称して戦いの捕虜を連れて来たと推測されている。
百済の助言・協力のもとで倭は宋へ朝貢を始めたのだろう。なお四七九年に南斉、五〇二年に梁が、武王に鎮東大将軍、征東大将軍を授けているが、後述のように遣使したのではない。】 として『宋書』の倭の五王関係の記事一覧が掲げられます。 (熊谷公男氏『大王から天皇へ』からの引用として)
421 倭王讃、朝貢して叙爵される
425 倭王讃、司馬の曹達を遣わし、国書と信物を献上する。
430 倭国王(讃か)、遣使朝貢する。
438 倭王珍、遣使朝貢し、自ら使持節・都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事・安東大将軍・倭国王と称して、その除正を求めるが、安東将軍・倭国王に任じられる。また倭王の臣下の倭隋ら13人に、平西・征虜・冠軍・輔国の将軍号の除正を求め、認められる。
443 倭国王済、遣使朝貢し、安東将軍・倭国王を授かる。
451 倭国王済、安東将軍に使持節・都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事を加えられ、倭王の臣下の23人が申請通り軍・郡(将軍号と郡太守号)を授かる。
460 倭国、遣使朝貢する。
462 倭国王の世子興を安東将軍とする。
477 倭国王(武か)、遣使朝貢する。
478 倭王武、自ら使持節・都督倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事・安東大将軍・倭国王と称し、遣使して上表し、自称の開府儀同三司と他の官爵の除正を求める。百済を除かれ、使持節・都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事・安東大将軍・倭王に任じられる。
この記事一覧自体は一見文句はないように見えますが、四七七年の遣使が「(武か)」と書きこまれていることは、後に述べますが重大な問題が含まれています。なぜ、「武か」と書きこまなければならなかったか、ということは「稲荷山鉄剣銘」との整合性が保てなくなるからです。これについては後に詳しく述べます。
上記の大津透教授の説明の末尾の、「後述」の部分は、七頁後(p88-89)に次のように書かれています。
【宋は四七九年に滅び南斉が建国される。『南斉書』には「使持節・都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事・安東大将軍・倭王武」に新除し、「鎮東大将軍」としたとある。さらに南斉には内乱が起き五〇二年に梁が建国される。梁の武帝即位二日後に、高句麗王高雲を車騎大将軍に、百済王余大を征東大将軍に、鎮東大将軍倭王武を征東大将軍に号を進めたことが描かれている。
しかしこれらには遣使朝貢している記事はない。両者とも、新帝即位に際して諸国王にいっせいに進号したのであろう。したがって五〇二年になお武王が在位していたかも疑問であるが、重要なことは、武王は四七八年以後は中国に遣使して官位を求めなくなった、つまり中国中心の冊封体制から離脱したことである。】
ここで感じられるのは、大津教授が『南斉書』『梁書』の記事について冷淡ということです。この記事に従うと、雄略天皇の没年のはるか後年に中国が授爵した、という不具合が生じるからでしょう。中国の大帝国が、相手の国王の生死も分からぬまま授号することがありうるのか、という常識的な判断に対して大津教授はどう説明されるのでしょうか、中国史書のいい加減さ、でしょうか?
中国の史書によれば、雄略が没したあと二〇年間に、大和朝廷の大王は何人もいた筈なのに、一切朝貢せず、授号せず、いきなり「死者(雄略)への授号」というのは誠に奇妙です。
大津教授は【 重要なのは四七八年以後は中国に遣使して冠位を求めなくなったこと】と言いますが、倭王武の最後の遣使の一年後の、四七九年には雄略天皇は亡くなっているのですから、この意見は「倭王武=雄略」と両立しにくい意見、ということに大津教授は気付かれていないのでしょうか。
ところで、大津教授のこの本には、五世紀の好太王碑文の記事の「倭」と関連付けて考える視点が全く見えません。
好太王碑文で見てきましたように、倭は高句麗と半島で争ってきています。大津教授が紹介するように、413年に倭と高句麗が共に東晋に朝貢してきた、というのは、412年に好太王が亡くなり半島で一時的に平和が訪れていたことを示すことだと思われます。倭が朝鮮北部の産物を貢物としたのは、半島北部にも倭の勢力範囲が存在する、ということを中国に認識させたかった、とも言えるのではないでしょうか。
大津教授はこれらの所謂「倭の五王」について、【この五王の続柄については、『宋書』倭国伝には珍と済の間の続柄の記述がない。なお『梁書』には彌(『宋書』では珍)と済を父子関係だとするが、史料的には『宋書』をもとにしたもので、信憑性が高いとはいえない。王統が異なるという説もあるが、中国側が知らなかったか、『宋書』が書きもらしたのかもしれない。】(p83)とされます。
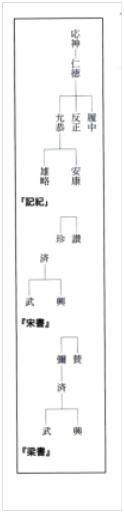
大津透教授は、この「倭の五王」と大和王朝の天皇の系譜と一致しない問題、親子関係 兄弟関係 親子同時に死亡、の問題について【 倭王讃について各説あり】(p85)と書かれ、それ以外の四王については丸で問題ないという書きようです。中国の史書に特筆大書された「使持節・都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事」などが、日本の史書に全く影も見せない不思議さ、大津教授には不思議と思われないことが不思議です。
【『宋書』倭国伝では、最初に「倭讃」と記したあと、「珍」以下四名に「倭」がないのは、姓を省略しているのである。したがって珍と済の間に続柄が記されていなくても、同じ倭姓であり、王家一族であることは疑いないであろう。】(p84)と書き、次のような系図を掲げられます。
つまり、『宋書』にある五人の王は、応神天皇から雄略天皇までの七人の天皇の内誰かだ、雄略だけは間違いない、ということで問題解決というような書き方なのです。『天皇の歴史』と銘うっている本なのにこんないい加減なことで良いのでしょうか。
★安本美典説批判
この「倭の五王」について、筆者は「倭讃が応神天皇」という前田直典説をネット上で批判したことがあります。この場合、応神=倭讃、雄略=倭武ですから、五人の王に対して七人の天皇となります。
仁徳=倭讃とすると五人の王に対して六人の天皇でやはり数は合いません。合わせようとすると、倭讃=履中となるのですが、それでは『日本書紀』に書かれている履中の在位年代と『宋書』の倭讃の活動年代とが大きく違ってくるのです。
なぜ、このような不都合が生じたのかでしょうか。『日本書紀』は『三国志』や『晋書』を参考にしたことが、神功皇后紀に書かれているように明らかです。それよりずっと後世の『宋書』『梁書』『南斉書』に【倭国の五人の王やその配下に将軍位などを叙爵した】と書かれているのに、『日本書紀』には全く書かれていないのは不思議です。
この一大不思議をそのままにしておいて、大津教授が『天皇の歴史』を叙述しようというのは、不遜と言われても仕方がないでしょう。
在野の古代史史家安本美典氏は雑誌『季刊邪馬台国』に依って独特の古代史史観を発表されています。その著書に『倭の五王の謎』という現代新書の一冊があります。「倭の五王は応神~雄略」という前田直典氏の説を安本氏独特の古代天皇一代十年説で補強して述べています。
安本美典氏は邪馬台国九州説論者としても知られています。安本氏の場合、卑弥呼は天照大神であり神武が東征し大和王朝を建てた、という説ですから、「倭の五王」は大和王朝の大王たち、ということになります。
ひょっとしたら大津教授は、邪馬台国九州説論者も倭王武=雄略天皇に異論をはさむわけはないし、誰からも批判されるわけはない、と高をくくっているのかもしれません。
大津透教授の著書の「倭の五王」についての記述はコマ切れですし、安本美典氏の『倭の五王の謎』の方が問題点を鮮明に出来ると思い、それの批判を紹介したいと思います。それによって、倭王武=雄略とした場合、年代が合わない、親子・兄弟関係が合わない、なぜ日本書紀に書かれていないか、などの謎解きをします。
安本美典氏の古代史観は氏独特の「古代天皇平均在位十年説」に基づいているのですが、これについて本論からはずれるので極力省略し、「倭の五王の謎とき」部分を中心にします。
(詳しくは当HPで安本氏の著書『倭の五王の謎』、『虚妄の九州王朝』『大和朝廷の起源』について、それぞれ批判していますのでそちらをクリックしてご参照ください。)
大津教授の著書では「倭の五王問題」の全体像がはっきりしません。そこで大津教授の著書の記述の引用箇所と重複するところがありますが、「倭の五王問題」とはどういうことか、と簡単にまず触れておきます。 五世紀に倭国に王がいて、種々中国との交流があった、と中国の正史『宋書』『梁書』に五人の王の名が記載されています。
ところが、日本の史書に全く顔を見せません。これらの王達は誰なのか、大和王朝のどの天皇にあたるのか、というのが日本古代史上の大きな謎とされてきました。 その倭王の名を古い順番から上げますと、讃・珍(彌)・済・興・武 の各倭王です。
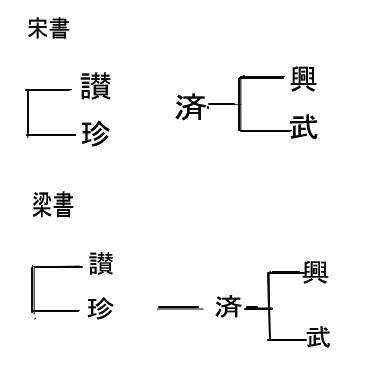
五人の王の相関関係は、史書によって若干異なり、一番古い『宋書』(486年成立)と『梁書』(636年成立)とでは若干異なりますが次のような関係です。(左図参照)
ところが、この『宋書』および『梁書』の記事がわが国の史書『古事記』・『日本書紀』に出てないのです。それより古い、中国の正史『三国志魏志』の卑弥呼朝貢などについては、『日本書紀』に出ている、というのに出ていないです。このことも大きな??で、一応それは後ほど取り上げますが、古来より、この五人の王達を大和朝廷の誰に当てるか、その研究が進められてきたのです。
今までの通説では、讃が仁徳若しくは履中天皇、武が雄略天皇とされてきました。残る中の三人は、その間の在位された天皇を当てているわけです。 何が、謎なのか、つまり記・紀の各天皇に五人の倭王を当てはめてみると、活躍した時代が合わない、親子兄弟関係が合わない、というような問題に直面するのです。
”そんな馬鹿なこと”が、と常識人は思うと思いますが、現実に、”そのような馬鹿”なことがまかり通っているのです。これを安本美典氏は、『倭の五王の謎』という著書で“解明できた”、としているのです。
安本美典氏は、結論的に言いますと、倭王讃は応神天皇、倭王武は雄略天皇だ、といいます。 さて、安本氏の組み立ては、まず、倭の五王の内の、「讃は応神天皇」とするこの道の先覚者、前田直典氏の事に触れられています。前田説を紹介し、それに同意し、倭の五王の最後の王、倭武を、ご自分の数理文献学に基づく天皇の平均在位年数から、雄略天皇が年代的に合うとしています。その間に珍・済・興の三人の王を入れ込んでいる、と、ざっと言うと、このような組み立て方です。
武=雄略の年代の補強材料に、埼玉の稲荷山の鉄剣の銘文の解析を、かなりのページを割いて述べられています。この点は大津教授と全く同様です。又、応神天皇の在位年代の補強史料として、朝鮮の古代史書から、朴堤上(パクゼサン)の説話を、これも詳しく述べています。
安本美典氏といいますと、古代史に文献統計学と名付けた、「科学的・合理的・常識的な判断」を持ちこんだ、と自身が主宰される邪馬台国の会というサイトで主張されています。安本美典氏は、この『倭の五王の謎』では、倭王讃=応神天皇の前田説に同意する旨の論旨を述べられた後に、結論的に“私は、前田氏の、考証の力よりも、洞察力のほうを、高く買うものである。正しい結論を見通しながら、その結論を立証する方法に不備があった。”と記していらっしゃいます。
つまり『合理的・常識的な判断』でなく、『立証が不十分な結論をも正とされる手法も、時には取る』、と書いているのは、標榜される「科学的・合理的・常識的な判断」と矛盾していますが平気で書いていらっしゃいます。
『倭の五王の謎』の本の内容は、同書の終章 おわりに の項で下記のようにまとめてあります。
(1)AD400年前後の新羅との接触は神功皇后伝承と、朝鮮側の史料にも合い、記紀などの 日本側の史料とも一致する。(大津教授もそのような意見です)
(2)讃は応神天皇である。百済の直支王が日本に人質として来たころの人である。直支王のことは日本・朝鮮双方の史書に共に記されている。
(3)讃=応神とすれば、珍・済・興・武はそれぞれ仁徳・允恭・安康・雄略の各天皇になる。
(4)稲荷山鉄剣の銘文に見える獲加多支鹵大王は雄略天皇をさす。銘文に見える辛亥の年は471年で、雄略天皇の時代に合致する。ここからも雄略天皇と武は同時代の人 となる。(これも大津教授と同じ)
大津教授と違っているのは、「倭の五王」に比定した各天皇の活躍時期の推定を、グラフ化して載せてあることです。安本氏は、倭讃は応神天皇、倭武は雄略天皇と、ご自分で考案された「平均天皇在位年数」で年代を推定し、決定されているわけです。
★古代天皇在位十年説
ここで安本美典氏が、倭王武=雄略の比定に有力な道具として使われる「古代天皇在位十年説」についてその当否を検証しておきたいと思います。
まず疑問に思うのは、古代から現代までの権力者を、「天皇」という共通因子でくくってよいものかどうか、ということです。一般的に、「天皇」は八世紀になって実際に呼称として用いられた、とされますが、権力の対象範囲が時代とともに変遷している、ということを安本さんは全く無視しています。
『古事記』・『日本書紀』は、「天皇」と書いていますが、実態はかなり変化しています。「天皇」じゃなく、せいぜい「族長」乃至「地域の親分」の弥生期の時期と、管轄範囲が大きくなり始めた、三世紀以降の「大王」期、八世紀以降の列島統一期の「天皇」期を、「天皇」という同一のファンクションで統計処理しようとする、その根本にそもそもの問題があります。
安本氏は「卑弥呼の謎」で、何だかだと統計的文献学について述べられます。そして前段の部分では、『十個の基礎的事実があって、その一つ一つについて二通りの解釈が出来るのなら全部で1024通りの解釈が可能である。仮説の提出よりも検証の方法を考えてみる必要がある』、と至極まともなことを言われています。
しかし、具体的な所になると、そうは取れないような前提を置かれます。例えば、【『記・紀』の諸天皇の「代の数」は信じられるが、「父子継承」は信じられない、八世紀の頃と同じ様に、兄弟間の継承があったものとする】、という仮説で「平均在位年数」を求めています。
この短い安本さんの文章の中で、既に、「代の数は信じられるかどうか」、「父子継承は信じられるかどうか」というように、二個の仮説の提出がなされているわけです。 安本氏は、それらについて、特に「数理統計的」とか「科学的手法」を使って仮説を立て、その仮説の妥当性を検証することなく、説明することなく、「代の数は信じられ、父子継承は信じられない」という仮説を、定理のように使って次に進まれます。
また、「天皇」の代を日本書紀の系譜で数えるのですが、ご承知のように、古代の天皇の系譜は、父子相続・夫婦相続・重祚・兄弟相続など入り乱れています。そこから得られた平均の在位年数が約一〇年であることを、定数として図化する、という科学的という皮を被せた似非科学的な説と言えます。
また、安本美典氏は大津教授同様に、「天皇が余る」ことに無神経です。讃=応神、武=雄略としますと、天皇「七」代になり、倭の「五」王に対し二人余ることになることです。都合が悪いことは頬かぶりです。中の三人の珍・済・興は、応神天皇と雄略天皇の中に入れ込み、仁徳・允恭・安康とそれぞれの天皇にあてはめています。
しかし、『古事記』・『日本書紀』に記載されている履中天皇・反正天皇のお二方が余ることについては神経をお使いになっていらっしゃいません。
安本美典氏はその上で、天皇間の姻戚関係の『記・紀』の記述が『宋書』に合わないことは、古代天皇の系図が間違っているのだ、と自説にあう学者先生を動員してこの本の中で説明させています。前に述べた、前田直典、山根徳太郎、西田長男、筑紫豊など各氏の名前を挙げて倭王讃=応神天皇説を補強されています。
しかし、安本美典氏の看板の、合理的科学的な謎の解明には程遠いものです。 その上で安本美典氏は、「応神天皇と仁徳天皇は『記・紀』の言うように、親子ではなく実は兄弟であった、とすれば中国側の資料と合う」、と結局『記・紀』を自説に合うように大改竄して辻褄を合わせています。
★「倭の五王」の正解は
疑問点はすでに述べましたように、『記・紀』の天皇系図と全く合わないことと、『記・紀』にこれほどの大事件が全く記載されていないのは何故なのか、ということでしょう。
何と言っても中国の皇帝から、新羅ほか五ヶ国の朝鮮半島の軍事支配権を与えられている大事件が大和朝廷の記録にないのですから、それを聞いたら、歴史家ならずとも、誰しも驚くことでしょう。これほど晴れがましい「倭の五王」の記事が何故『記・紀』にないのか、については、安本美典氏も大津透教授も不思議に思われないのか、自分の手に余るのか何も言いません。
何故『記・紀』にないのでしょうか。東アジアの当時の状況を見てみますと、宋が建国したのが470年です。『宋書』に最初の倭王の朝貢の記事が出るのが471年です。当時の倭国の外交感覚も鋭いものです。
又、『魏志』の卑弥呼に関する記事は『記・紀』にも載せられています。『日本書紀』の編集年代から言って、『魏志』も『宋書』も「百済系史料」も、『日本書紀』の編集者の手元に参考書としてあったのはまず確実でしょう。単に、歴代の天皇の伝承に無い、系図に合わないということで、『日本書紀』の編集者も無理に取り入れなかったのか、と思いましたら、そんな簡単なことではないようです。
安本美典氏は、中国の記録にあって日本の記録が合えば、それは使える、九州に王朝があったのなら、その記録が現地になければそれは存在しなかったということだ、と言います。中国の記録(『宋書』など)にあって、何故日本に記録されていないのかに考えを廻らすべきではないでしょうか。
古田武彦氏の「倭の五王」についての説の骨子は、【『宋書』に記載のある倭国は九州にあった、と見なければすべて辻褄が合わない、逆に云うと、倭国が九州にあった国とすれば全て辻褄が合う。「倭の五王」は倭国の王たちであり、その倭国は九州にあった。近畿王朝の天皇とは全く関係ない。】ということです。
又、『宋書』には倭王武は、その上表文に戦に苦労している旨述べ、“親兄弟共になくし”と書いてありますが、安本美典氏は自説にとってまずいと思ったのでしょう、全く触れていません。『記・紀』には、雄略天皇の親の允恭天皇や、兄弟の安康天皇が“親兄弟共になくし”というような不自然死を遂げた、という記事はありません。
ではなぜ日本側の記録にないのか、安本美典氏も大津透教授も答えることが出来ていません。『日本書紀』の編纂時の状況を考えれば明らかである、と古田武彦氏は次のように説明します。
【時の中国の王朝「唐」は魏・晋・北魏・北周・隋の所謂「北朝」の流れの王朝である。一方「宋」(斉・梁・陳も)は北魏・北周と対立した「南朝」の流れである。北朝の唐にとって宋は匪賊であり、「王朝」として認めることのできない国である。
今、日本は唐の傘下に入るべく遣唐使などを送っている状態の時に、『宋書』『梁書』といういわば匪賊の書に記載されている授号記事などを日本の正史に取り上げるわけにはいかない、というのが根本原因である。おそらく、「倭の五王」の「倭国」の歴史書には記載されていたであろうが、日本が倭国を併合した時に禁書となり闇に葬られた。(続日本紀に禁書令の記事がある)】と。(『失われた九州王朝』より抜粋)
九州に本拠を置く倭国が、朝鮮半島で六国安東大将軍の称号を南朝劉宋から受け、南朝の系統が北朝の隋にとって代わられたのを見て、中国の冊封体制から離脱し、多利思北孤の「天子」宣言となります。その権威維持のために払った代償が、後年の白村江の敗戦から倭国の滅亡に至るわけです。
しかし、この「倭の五王」時点では、九州の倭国王朝は厳然として存在していたことを『宋書』は示していると言えるでしょう。
★倭王武の上奏文の評価
大津教授は、宋書の倭王武の上奏文を次のように評価しています。【ちなみに、この上表文には『春秋左氏伝』『毛詩』などの古典の字句が使われている。それだけ当時の倭王宮廷の漢文のレベルの高さを示し、帰化人が外交文書の作成にあたったのであろうが、逆にいえば、たとえば「自ら甲冑をつらぬき山川を跋渉す」という印象的なフレーズは『春秋左氏伝』成公十三年条にある表現であり、ここから導かれる軍事カリスマというイメージはかなり割引く必要があるだろう。】(p88)と。
遠い倭国の地で、中国最古の詩篇『詩経』や『左氏伝』を読み、その教養が滲み出る名文だったから、『宋書』にも特筆掲出された、と思うのが自然でしょう。夷蛮の王が一千年以上前の書物を読んでいる、ということだけで驚いたのではないでしょうか?
上奏文の、最初の出だしに、「自ら甲冑をまとい、山川を跋渉し」という『左氏伝』のフレーズを使ったことは、先方、宋の朝廷に、「ああ、こやつナカナカの男だ」と思わせたことでしょう。出だしで、全体の文章のトーンを見事にまとめあげている名文、となぜ評価できないのでしょうか? 倭王武の高句麗に対しての戦いに臨む悲痛な叫びも聞こえてくるような立派な文章と思います。
『左氏伝』とか『毛詩』とか大津教授が引用されますので、こちらは調べるのにも結構手間がかかります。結局は我々が「四字熟語」を文章に使うと同様なことなのです。大津教授の言いたいのは【 倭王武の言っていることは誇張に満ちている。なぜならば、『日本書紀』などにその様な大規模な半島侵略の歴史が書かれていない。】ということなのでしょうか。
邪馬台国九州甘木説で有名な安本美典氏は、この倭王武の上奏文は宋朝に対して堂々と自分の要求をしている、この文から悲痛な感じは伝わってこないという感想を洩らされています。(『虚妄の九州王朝』より)
原文と棟上寅七の読み下し文を参考までに披露させていただき、「堂々と要求している」のか「悲痛な状況状況の中での」上奏なのか、判断して頂きたいと思います。
〔宋書〕「封國偏遠、作藩于外。自昔祖禰、躬擐甲冑、跋渉山川、不遑寧處。東征毛人五十五國、西服衆夷六十六國、渡平海北九十五國、王道融泰、廓土遐畿、累葉朝宗、不愆于歳。臣雖下愚、忝胤先緒、驅率所統、歸崇天極、道遙百濟、裝治船舫。而句驪無道、圖欲見呑、掠抄邊隷、虔劉不已、毎致稽滯、以失良風、雖曰進路、或通或不、臣亡考濟、實忿寇讎、壅塞天路、控弦百萬、義聲感激、方欲大擧、奄喪父兄、使垂成之功、不獲一簣。居在諒闇、不動兵甲、是以偃息未捷、至今欲練甲治兵、申父兄之志、義士虎賁、文武效功、白刃交前、亦所不顧。若以帝徳覆載、摧此彊敵、克靖方難、無替前功。竊自假開府義同三司、其餘咸假授、以勸忠節。 詔除武使持節、都督、倭、新羅、任那、加羅、秦韓、慕韓六國諸軍事、安東大將軍、倭王。」
現代語訳 宋の順帝の昇明二年(四七八年)に、倭国王武が使いを遣わして国書を奉ってきた。それには次のように書いてあった。
『私、武が治めよ、と朝廷から封じられた倭国は、皇帝陛下のおられる都よりずっと離れた辺鄙な土地にあります。皇帝陛下の威光を示す範囲を、ずっと帝国の外側へと広げてまいりました。昔から、私たちの祖先は、自らも甲冑を装い、山河を渡り歩いて戦い、ゆっくり休むこともありませんでした。その結果、東は毛人の国々五十五カ国を征伐し、西は衆夷の国々六十六カ国を服属させ、海を北に渡って平らげた国々は九十五カ国に及びます。帝国の進む道は安泰になり、帝国の領土はますます拡がっています。
私ども倭国累代の王たちは、ずっと長い年月道を誤らず忠節を尽してきました。皇帝の臣であります私、武も、愚かな者ではありますが、先王たちの歩んだ道通りに統べるところは率先し、常に崇敬する方向を間違えず、帝都への道は百済の国を隔ててはいますが、常に船による航行ができる準備は整えています。しかしながら、高句麗は道理を無視し、武力を持って侵略を図り、国境周辺を略奪・侵略を繰り返しています。おまけに侵略した後、その地に留まるので、その地域が宋朝廷に対する忠節心が失われるようになっています。私たちの朝廷への道も、時には妨害され通じなくなったりしています。
私、武の亡き父、倭王済が、この天朝に通じる道を、高句麗が侵略し閉塞したことに怒り、百万の弓弦を準備し、諸国の義勇軍の応援もあり、まさに高句麗に戦いを挑んだその時に、父済と兄とを共に亡くしてしまい、あと一歩というところで成功しませんでした。その後は皇帝陛下の服喪期間となり、兵を動かせず、したがって戦いは休止していて高句麗に勝つことが出来ていません。やっと今となり、兵も武器も充分に準備し、父や兄の果たせなかった目的達成に向かうことを宣言したいと思います。諸国義勇の士も、諸国の政ごと・軍事ともに整え、白兵戦もみな厭わぬ心構えも出来ています。もし皇帝陛下の御徳を戴き、この強敵高句麗をやっつけることが出来、方々〈ほうぼう〉の被侵略地の回復が出来れば、私たちの父兄の勲功を落としめることはない、と断言できます。
それですから、自分に、従来父に与えられていたと同様の「開府儀同三司」の権限があるものとみなしていただき、配下の諸国王そのた功臣にもそれぞれの位官を仮に授け、以って皇帝陛下への忠節を励まさせたい。』と。 それで、順帝は詔勅を下し、武を「使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事・安東大将軍・倭王」に叙すことにした。
★倭王武=雄略天皇=ワカタケル論の破綻
いろいろと、「倭の五王問題」で脇道に入ったりしましたが、倭王武は雄略天皇ではあり得ず、『日本書紀』の編者たちが忌避したように、倭の五王の記事は大和王朝の王達の事績ではなかったのです。
倭王武と雄略天皇の在任や中国史書の関係記事を年表にしてみました。これを見れば、倭王武=雄略天皇説は明らかにおかしい、と言うことが一目瞭然と私には思われます。
日本の歴史学会、古代史先生方の中でも論客として知られる、大津教授の先輩でもある吉田孝先生は、倭王武=雄略は間違いないと断言されるのです。(『日本の誕生』岩波新書2006年)
著者は、ネットでこの本の批評も書いています。(槍玉その17『日本誕生』批判 http://www6.ocn.ne.jp/~kodaishi/yaridama17yosidatakashi.html
をクリック下さい)
東大国史学科を中心の学者さん方は、「倭の五王は、近畿のヤマト王朝の歴代の天皇でない筈がない」、という信念に凝り固まって、赤い真実は赤いフィルター越しには見えないのと同様、真実が見えなくなっているのではないかと思われます。未だに、麻原某を生き仏と信じる方も存在しているのと同様かなあ、とは一老書生寅七の慨嘆です。
倭王武と雄略天皇関係年表
西暦 中国史書の記事 日本書紀の記事 備考
413 倭国王朝貢 梁書(諸夷伝)
425 倭国王讃貢献 宋書(倭国伝)
438 倭王珍授号 宋書(帝紀)
443 倭国貢献 宋書(帝紀)
451 倭王済進号 宋書(帝紀)
456 雄略天皇即位 日本書紀
460 倭国貢献 宋書(帝紀)
462 倭王興授号 宋書(帝紀)
471 (辛亥年 稲荷山鉄剣銘文)
477 倭国朝貢 宋書(帝紀)
478 倭王武授号(即位か) 宋書 (倭国伝)
479 雄略天皇歿 日本書紀
479 倭王武進号 南斉書(倭国伝)
480 清寧天皇即位 日本書紀
485 顕宗天皇即位 日本書紀
488 仁賢天皇即位 日本書紀
498 武烈天皇即位 日本書紀
502 倭王武進号 梁書(帝紀)
507 継体天皇即位 日本書紀
この表から見てとれます様に、倭王武の即位の時期ははっきりしません。しかし、『宋書』帝紀の477年の朝貢記事に倭国王の名前がありません。ですから、これは常識的には前回同様の倭王興の遣使ととってよいと思います。次の倭王武の「上表文」の遣使、478年が、倭王武が即位した後の挨拶を兼ねての第一回目の遣使であったのは間違いないことでしょう。
つまり稲荷山鉄剣が作られた「辛亥年」471年には倭王武は即位していないのです。まだ倭王興の時代なのです。 最初に大津教授が掲げた「倭の五王」に関係する年表に「477年の遣使は倭王武の遣使か」と大津教授の書き込みは問題がある、と指摘しました。これは「倭王興」の遣使の可能性大なのです。
他にも、上の表を見ていただきますと分かりますように、雄略の治世は23年ですが、武は40年前後程度在位と中国の記録にあります。多くの古代史家が指摘するように、雄略天皇は479年に亡くなっているのに、502年に梁の皇帝から朝鮮半島の任那を含む六国諸軍事・安東大将軍の称号を受けています。死者への授号です。
やはり、倭王武と雄略天皇は別人と見るのが、理性的判断ではないでしょうか?
それにつけても、「何故、『記・紀』に倭王の記事がないのか」、ということに疑問を全く感じない大津教授はじめ多くの古代史学会専門家の頭は、地動説が理解できなかったカトリック司教達と同じ頭の持ち主のように、私には思われます。
古田武彦氏が、高校生にも理解できるように噛んで含めて、“倭王武は雄略天皇ではありえない”、と 『失われた九州王朝』でも『よみがえる九州王朝』でも論証されていることを、大津教授筆頭に現在の古代史学会が無視されるのは理解に苦しみます。
大津教授が「倭王武は雄略天皇である」と力説され、その大間違いを基礎にいくら4~5世紀のわが国の統治機構の歴史などを説かれても、正に砂上の楼閣にすぎません。
筆者が百舌を尽くすより古田武彦氏の歯切れのよい論証をご紹介して「倭王武は雄略天皇に非ず」の締めくくりとします。
【第一に、『宋書』の倭国伝の前にある記事、●大明六年(462年)三月、「壬寅、倭国王の世子興を以て安東将軍となす」●昇明元年(477年)「冬十一月己酉、倭国、使を遣わして方物を遣ず。」●昇明二年(478年)「五月戊午、倭国王武、使を遣わして方物を遣ず。武を以て安東大将軍と為す。」
この記事を見た中国側の読者は、昇明二年時における倭王を誰と思うだろう。直前の記事の、「大明六年」の記事の倭王は興である。とすれば、当然項目の列次として直後の「昇明元年」時の倭王も興と見なす他はない。
まかりまちがっても、次の記事に初見の武を、逆に“遡らせ”て、「昇明元年」時の倭王だと考える中国の読者は一人もいないであろう。書物は前から後ろへと読むものだからだ。すなわち、『宋書』は読者によってそのように理解されるように叙述されている。
しかし、そのような自然な、否、必然的な理解をするとき、「武=雄略」説は成立しえない。なぜなら雄略の在位年代は「456~479」(『日本書紀』)であり、“478年時より後の即位”では、到底妥当しえないからである。
第二としては有名な『梁書』の武への授号記事である。●天監元年(502年)鎮東大将軍倭王武を征東将軍に進号せしむ。(武帝紀中)●高祖即位し、武を進めて征東将軍と号せしむ。(倭伝)
これをもってしても、「武=雄略」説は成立しえない。なぜなら雄略は479年に没し、右の502年までには「清寧―顕宗―仁賢―武烈」の四人の天皇が在位しているはずだからである。(後略)】この問題について、精しくは古田武彦「多元的古代の成立」-「史学雑誌91―7所載、『多元的古代の成立―邪馬壹国の方法』京都駸々堂所収、参照ください。
★「平西将軍」問題
倭王珍の臣下が授号した「平西将軍」について、大津教授は、下記にご紹介するように、『宋書』の平西将軍は九州の将軍を意味する。従って九州説は成り立たない、と言われます。
ここで初めて、倭=九州 説が出て来ました。実は、大津透教授の『天皇の歴史01 神話から歴史へ』には「古田武彦」は全く顔を見せません。九州王朝説も出てきません。「邪馬台国論争」での近畿説に対する九州説という説明の中では、「九州から畿内へ遷都する」、というのが九州説とされます。
東遷したとされるのは倭国(邪馬壹国)のいわば分派であって、倭国本流は北部九州に依然として存在した、という古田説は、まるでそんなもの存在していないかのように全く説明されません。
しかし、大津教授の頭の中にはこびりついているのではないか、と思われます。その現われと思われるのが、『宋書』の倭王珍が「倭隋等十三人を平西・征虜・冠軍・輔国将軍の号に除正せんことを求む・・・」の記事の「平西将軍」についての大津教授の次の文章です。
【注目すべきは、倭隋以下十三人に、平西以下の将軍号の授与を求め認められたことである。(中略)なお平西将軍を求めたことについて、武田幸男氏が、この人物は倭国王より西方に置かれていたからで、北九州あたりにおかれたのだろうと指摘している。倭は北部九州にあったとする説は成り立たない。】(p86)と。(ここで初めて、倭=北部九州 説が出て来ています)
この武田さんの説については、古田武彦氏が『邪馬一国の道標』で詳しく述べています。氏はこの本で”平西将軍の謎”という章を設け、武田幸男氏から疑問を呈されたことについての意見を247~255頁に亘って詳しく述べられています。
その骨子を紹介します。 【『宋書』全体を調べ、「平西将軍」に任じられた刺史の例、三十二例を見てみる。それによると、都(建康)からみて”西方に当る地域”の刺史に与えられている。倭国の場合、「東夷」だから、この宋都の視点ではありえない。これは明らかに”倭国内部”からの視点だ。倭王の視点で、自分の部下に平西将軍の称号を与えることを求めている。
倭国は『三国志』の時代から一大率を(その都からみて西方の)伊都国に常駐させて諸国ににらみを利かせていたということとも符合する。】と。
これは、倭王が自分たちの領域での宋朝に準じる支配権の行使を求めている姿勢ともこの「平西将軍問題」は符合しています。 ところがなぜか、大津透教授は【倭は北部九州にあったとする説は成立しないだろう。】と「平西将軍」で古田武彦説の首をとったようなことにのみ焦点が絞られているようです。
この『天皇の歴史01 神話から歴史へ』での今までの大津教授の論述の中では、「倭は北部九州に八世紀初頭まであった」とする説について、「倭人伝」でも「好太王碑文」での各説の説明でも一度も出てきていないのです。「倭は北部九州にあったがその後近畿へ東遷した」という九州説を説明しているだけなのです。
古田武彦説は知っているが触れたくない、とここまで来ていて、「平西将軍」でやっと古田説を否定できる証拠が見つかった、という喜びが滲み出ている文章と思うと情けなくさえ感じます。「倭国」=「古代より日本列島を一元的に支配していた大和政権」という思い込みが、怜悧な頭脳の持ち主である筈の大津東大教授の判断を誤らせているのでしょう。
この古田武彦氏の「古代は近畿王朝一元ではなかった」とする意見について一言述べておきます。これは、素人が雑誌や著作に発表した、というものではありません。古代史に関して朝日新聞社から1971年から順次刊行された『「邪馬台国」はなかった』『失われた九州王朝』『盗まれた神話』は、その後角川文庫、朝日文庫、近年のミネルヴァ社のコレクション版と次々に刊行されていて、古代史関係本として最も周知されている本と言えるでしょう。
しかもそれにまして学術誌にも、朝日新聞社刊行の諸著作以前から、掲載されているのです。1969年東京大学『史学雑誌』78―9「邪馬壹国」を発表、以来、京都大学『史林』55―6、56―1での邪馬壹国論争、『史学雑誌』91―7に「多元的古代の成立」が掲載されています。そのほか『日本書紀の史料批判』が東北大学『文芸研究九五集』1980に掲載されているなど、決していい加減な立論ではないのです。
自説に合わない説を無視する、という悪しき因習に東京大学国史学科が汚染されているのであれば、除染の必要がありましょう。
(五) 『日本書紀』『古事記』の伝える天皇
★大津教授の『記・紀』批判の問題点
今まで、外国史料や鉄剣銘などの金石文によって「天皇の歴史」を述べて来た大津教授は、次に、第二章“『日本書紀』『古事記』の伝える天皇“という章を設けて論じられます。
まず「記紀神話の意味と津田史学」という項で、歴史的事実でない『記・紀』・記紀神話のあらすじ・各地神話を総合し王権の正当性を説明・タカミムスヒからアマテラスへの皇祖神の転換・氏族の祖先神の活躍・津田左右吉による記紀研究の方法・『記紀』は八世紀の作品か―という順に説明されます。
津田教授の記紀論のまとめとしては、神功紀から遡って神武天皇までの記事は「観念的モチーフによる叙述」としています。
結論的には【 その大枠は六世紀前半の欽明朝にまとめられ、その後異伝が発生して各氏族の伝承もとり入れられ、さらに天武朝での整理、八世紀の『記・紀』の完成などにおいて潤色が加えられたと、長い曲折に満ちた歴史的所産として理解すべきである。
全体として天皇家への各氏族の奉仕の起源を説く大和朝廷の氏姓制度を支えるエネルギーが横たわり、八世紀においてもなお律令国家の成立にもかかわらず、氏姓制度的イデオロギーが必要だったということなのだろう。】(p112)とまとめています。
この様な大津教授の『記・紀』についての記述を読みますと、次のように断定されている事柄が問題点として浮かび上がって来ました。
①歴史的事実でないから、雄略天皇以前の天皇は高校の教科書にも出ていないのだ。
②『記・紀』は各地の神話を大和政権の側で再構築し、国生み―出雲神話―天孫降臨―東征―建国という大きな構想を作りあげたのだ。
③応神天皇以前の『記・紀』の記述には天皇の系譜を含めて史実の記録と呼べる部分はなく、全く史料価値がないのだ。
④このような津田左右吉の研究方法は『記・紀』を、又その個々の部分を、その成立において問うという正当な研究方法である。
ところで津田史学の後継者的存在の井上光貞氏の『日本の歴史 神話から歴史へ』という、この大津教授の『天皇の歴史』と同じようなタイトルの本があります。
そこでは、【神武天皇は実在ではない、という津田左右吉の「日向などの膂宍の空国のような未開地が皇室の発祥地でありえただろうか」というように、神武東征物語は何らかの事実に基づくものではなく「天孫降臨」に続く「日本神話の一部」である。しかし考古学上の事実からみて、皇室及び大和朝廷が北九州となんらかの関係がありそうだ。】(同書254~257頁)ということで、井上光貞氏は邪馬台国九州説だとされています。
大津教授は井上大先輩の「考古学上の事実から大和朝廷が九州と関係がありそうだ」という意見を克服した上での、邪馬台国纏向説なのでしょうか?
まず、津田博士の「日向の膂宍の空国」の基本的認識が正しいのか、という問題を検討しましょう。
津田博士の「このような宮崎地方という未開地が皇室発祥の地ではありえない」という認識は、日向=宮崎地方という固定観念から生じています。あとで「神武東征神話」で詳しく検証しますが、天孫降臨の地の高千穂を、宮崎県の高千穂や鹿児島県の霧島連峰に比定したこと自体に問題があるのです。
天孫降臨神話は、外部からの日本列島(北部九州)への侵略譚に他ならないのです。『記・紀』が物語る神話の舞台は出雲を除き北部九州が殆んどです。福岡県に「日向」も「高千穂」も「クシフル岳」も「空国」も存在します。
この津田博士が引用する「日向の膂宍の空国」のフレーズは、二ニギの命が天孫降臨後に日向(糸島)から空国に向かう時の表現です。空国とは、出雲神話にもしばしば登場する古い国、宗像でしょう。
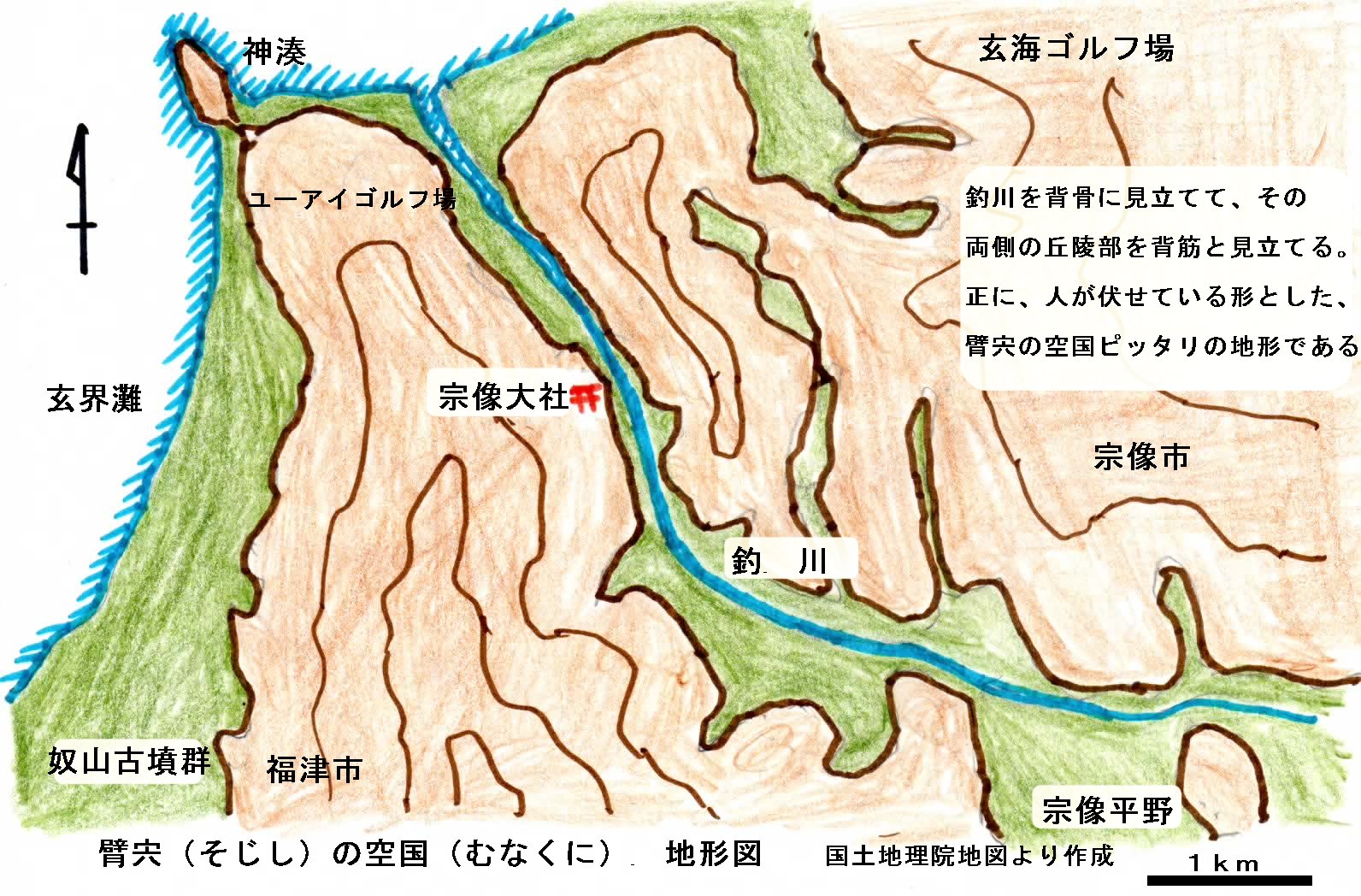 宗像の地形は、筑紫の他の河川河口部平野の形と違っています。現在でも宗像大社の横を流れる釣川という川が、玄界灘に流入する河口付近に、五キロほどにわたって両側に丘陵地がせまっています。「膂宍」とは「背中の肉」という意味ですが、その地形は人が伏せた形をしていて、古代人の表現力に驚かされます。
宗像の地形は、筑紫の他の河川河口部平野の形と違っています。現在でも宗像大社の横を流れる釣川という川が、玄界灘に流入する河口付近に、五キロほどにわたって両側に丘陵地がせまっています。「膂宍」とは「背中の肉」という意味ですが、その地形は人が伏せた形をしていて、古代人の表現力に驚かされます。
津田博士は、天孫降臨を文字通り天から高い峯に降りた、それも南九州というとんでもないところに、と解したため全くの荒唐無稽な神話とされたようです。 このように根本のところで誤った認識をしてしまった、津田博士~井上博士の「皇室発祥の地であるはずがない」という判断に大津教授も盲目的に従われてしまっているのです。
膂宍の空国と呼ばれた宗像大社を中心とする地域の地形図を、国土地理院の二万五千分の一の地図から色分けしてみました。貯水池やゴルフ場・宅地開発などで古代とは状況はかなり変わっていると思いますが、全体の骨格は、「釣川を背骨に、丘陵地帯を背中の筋肉と見立てたというのがお分かりになれるかと思います。
『古事記』についての考えを、大津教授は概略p112-115に亘って、次のように述べています。
まず『古事記』編さんの経緯について。
【その編纂の経緯については序文に記されている。和銅四年(711)九月に詔が下って翌年正月に太安万侶が献じたとある。序文偽書説もあったが一九七九年に太安万侶の墓碑銘が出土し、序文の内容も信用出来ると考えてよい。
序文によれば、天武天皇が、国家組織・政治の基本である「帝紀」「旧辞」に虚偽が多く、このままでは滅んでしまうとして、正しい歴史をつくろう、と詔している。しかし、いったん目で見れば口で暗誦し聞けば忘れない稗田阿礼に命じて「帝紀」「旧辞」を誦み習わせて定本を作らせようとしたが、おそらく天武の死により完成しなかった。そこで元明天皇が和銅四年に安万侶に命じて完成させたのである。】
次いで古事記の特徴。
【元明天皇から命を受けた安万侶は、稗田阿礼の習誦の帝紀・旧辞を渾然一体のものにアレンジしながら、文章を均整化し、完結統一体としての作品『古事記』を生み出した。その際に漢文体を借りずに、日本の古語・古意で表記することを試み、本文を定めたのである。】 (p117)
しかし、大津教授はこの『古事記』を史料として取り扱うのに基本的なことを忘れているように思います。それは、そのような経緯で生まれた史書がなぜ日の目を見なかったのか、改めて『日本書紀』が編纂されなければならなかったのか、ということについての判断をした上での『古事記』の内容の引用がなされる必要があると思います。
大津教授が引用される『古事記』ヤマトタケルの「国偲びの歌」にせよ、『日本書紀』では景行天皇の歌となっているように、景行天皇の旧辞が両書で大きく違います。『古事記』では、雄略天皇は朝鮮半島と全く関係がないようですし、武烈天皇も別に悪逆非道な天皇と書かれていません。まして序文には天武天皇の壬申の乱での働きについて特筆大書しています。
どうしてこの天武の詔で書かれた『古事記』が没となったのでしょうか。このような、史書の基本的な検証なしに安易に引用し、その上で『天皇の歴史』を構築される大津教授の姿勢で、果たして本当の『天皇の歴史』が浮かび上がるでしょうか心配です。
★神武東征伝承と古代の年暦について
ところで、先述した大津教授の『古事記』理解の問題点、①~④の諸点を取り上げることも考えましたが、それよりも具体的に「神武東征神話」は六世紀頃の官僚が創作したのか、ということを検討して、本当に正当な研究方法によって「史実の記録がない」、といえるか見てみます。
又、大津教授は『記・紀』の紀年や年齢などについての認識が、この『天皇の歴史』に散見されます。この基本的な紀年・年齢・暦などについての大津教授の認識を確かめておいてから先に進むことにします。
大津教授のこれらについての記述を集めてみます。
【まず、神武天皇何年という編年体記述に信用性がないであろうことは、そのころ暦があったかという点から明らかである。『魏志』倭人伝の注の『魏略』逸文に「其の俗正歳四時を知らず、ただその春耕秋収を記して年紀とするのみ」とあり三世紀には中国的な暦年はなく、農耕生活による自然暦の状態にあったらしい。】(p122)
【『古事記』では崇神168歳、垂仁153歳と不自然な長寿が目立つが、神武即位を繰り上げたため治世を無理に引き延ばしたらしい。】(p125)
【雄略はその23年に没する。雄略が没したのは『日本書紀』紀年では己未(474年)であるが、『古事記』は己巳年(489年)の崩年を伝え、こちらの方が正しいかもしれない。ただし伝える没年は124歳という荒唐無稽なものである。】(p186)
【建内宿禰は『日本書紀』では三百歳もの長寿を保ったことになり伝説上の人物である。】(p204)
と、以上の四か所で天皇方の寿命などについて述べています。 大津教授がまず、『魏志』倭人伝の記事を引用されていますので、この件から検討します。
「倭人伝」にはこの「春耕秋収を云々」だけでなく、倭人の年齢についての記事もあります。「その人、寿考、或は百年、或は八、九十年。」という本文の記事です。魏使が倭人に聞いて平均で約九十年生きる、と聞いて報告したものでしょう。
二十世紀でもパラオ諸島では雨期と乾期でそれぞれ一年と数え、太陽暦一年に二回歳を取っていたそうです。神道の大祓の祝詞は六月と十二月二回読まれます。倭人は、春と秋の二回歳をとるとか、太陰暦の月の満ち欠けでそれぞれ一月(一年は二四ヶ月)という暦で生活していた可能性もあります。そう考えると、不自然と大津教授が指摘される、古代天皇の長寿も伝承に従って記された、ということで何も荒唐無稽ではないということです。
実は大津教授も神道の年に二回行われている月次祭については、次のように紹介されているのです。
【畿内勢力による全国支配について関晃の研究を早川庄八氏が引き継ぎ1970年代に肉付けをしていく。早川氏は、律令国家の最大の祭祀とされる祈年祭をとり上げて、それが畿内の範囲の特定の神社を祭る年二回の月次祭と同じ形であり、それを全国を対象に拡大して創設されたもので、旧来の畿内中臣の地域主権的王権としての性格を換えていないことをと論じた。】(p18)
この月次祭の淵源について、大津教授がより一層の考察を進められた形跡はありませんし、倭人伝の記事と関連があるなど夢にも思われなかったことでしょう。
ところで、『古事記』には古代天皇の崩年が記されています。神武天皇137歳から雄略天皇124歳の21代の方の崩年記事から平均を取ってみますと、91.3と驚くほど「倭人伝」の記事に合うのです。
そうなると、大津教授が言われるような「神武即位を繰り上げたため荒唐無稽な長寿をでっち上げた」という理由は成り立たなくなります。欠史八代の天皇たちも神武即位の年代合わせに創作された、という主張もおかしくなります。
考えて見ればおかしな話で、神武即位の年代に合わせる為に架空の天皇を創作するのなら、8人でも28人でも入れ込めばよいわけでしょう。 この古代の二倍年暦という概念を入れると、大津教授が一生懸命説明される、神武即位辛酉革命説に合わせた古代天皇の長寿や八代の天皇を造作して入れ込んだ、などの説明も申し訳ないですが、馬鹿馬鹿しく思えてきます。
二倍年歴で年紀を使っていたのはいつまでか、ということについて『記・紀』の伝承から必ずしも明らかではありません。しかし、武烈天皇と継体天皇の間には王朝の断裂があると疑われていますが、そこでの継体天皇の崩年が大きく違っています。『古事記』では43歳、『日本書紀』では85歳です。この時点で『日本書紀』の伝えていた二倍年紀による天皇の崩年伝承は終了した、と考えてもおかしくないと思います。
この『日本書紀』の崩年は『百済本記』との照合がされています。「百済本記」が“日本天皇太子皇子ともに薨ず”と伝える辛亥年は531年です。次の安閑天皇元年は534年です。この安閑即位と神武即位(紀元前660年)との差は1194年となります。これを一倍年暦に直しますと597年です。つまり、神武天皇即位は紀元前63年となります。
従来の論者が主張するように、『日本書紀』の編集者が「神武天皇即位の年を辛亥年に合わせる」という作用をしたとすれば、第二代綏靖天皇の崩年が『記・紀』で大きく違いますから、そこで調整した、という可能性はあると思います。また、神功皇后を卑弥呼に擬すために干支で二運つまり120年遡上させたということも考え合わせると、神武即位はAD50年前後となってきます。
そうすると神武東征神話が記しているさまざまな武器などの器物・社会状況などと合致することになり、何も「荒唐無稽」ということでなく、われわれの祖先は、忠実に伝承を後世に伝えていることを評価し尊敬しなければならないでしょう。尚、古田武彦氏は神武東征の時期はAD1世紀頃かと推定されています。
神武天皇架空説は果たして正しいのでしょうか。戦後の史学は、戦前は国賊扱いされた、津田左右吉博士の“記紀は造作が多く、原則として信用できない。中国側の史料と一致しなくても差し支えない”に始まり、その流れに乗った井上光貞氏が、アカデミズムの主流としてリードしていったと云ってよいでしょう。
では、神武天皇架空説を唱えられた、国史学会の大御所井上光貞氏のご意見を見てみます。井上光貞著『日本の歴史I』から、その神武伝承批判の要点を、古田武彦氏が『盗まれた神話』「神武は虚構の王者」か?で纏めていますので引用します。
【神武天皇が日向を出発点としているのはおかしなことである。長い間大和朝廷の領域に入っていなかった日向や大隅・薩摩の地方、また、『日本書紀』に“膂宍の空国”と背の肉のように痩せた地と書かれたような未開地が、どうして皇室の発祥地でありえたであろうか。又、東征の経過にもおかしいところがある。
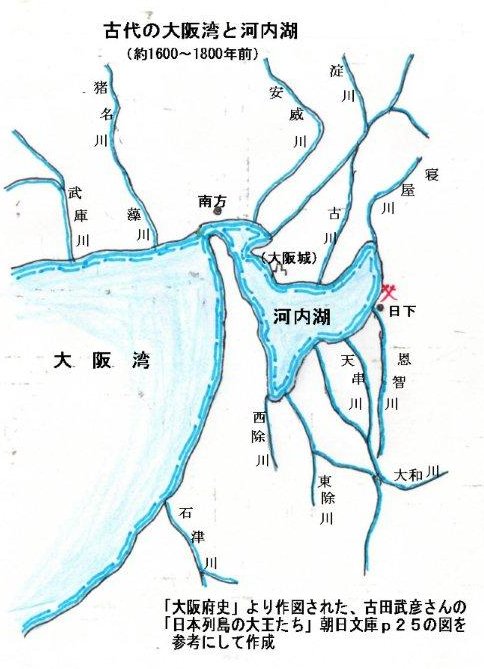
なぜなら、中間の地方は、ただ行幸途上の駐在地としてのみ記され、あらたにその地を征略したような話が少しも見えないからである。従って、これは厳密にいえば、東方に向かっての征定ではなくて、単に都を九州から大和にうつしただけのことである。ところが、神武たちの大和における活躍は、東遷の話とは違って一つの征定であり、またきわめて具体的である。
しかし、記紀の一般的性質から判断すると、これらの話は大部分が神異の話や地名説話、歌物語などの寄せ集めである。これらのもとの話は、個々のものとしては、大和のそれぞれの地にあった伝承であるかもしれないが、それらは、神武伝承を肉付けするために取り入れられたものにすぎない。
だから、それを取り去り、また人物を除いてみると、この神武東征物語は、ほとんど内容の無い輪郭だけのものである。 】
このように井上先生のおっしゃるのが正しいのでしょうか、当方の頭が粗雑なのでしょうか、神武東征の話は読んでみますと、これが後世の創作とはとても思えないくらいのリアリテイを感じます。八呎烏やら熊の化身やら神話的な部分は多いのですが、大筋では、いかに苦労して征服したか、がよく伝わってきます。
特に古事記の記述は、右下に掲載しています、古代の大阪湾と河内湖の状況図にもよく合致していますし、とても後代の創作とは思われません。
考古学的出土品にしても、近畿地方で奈良県だけは弥生後期の銅鐸の出土例がきわめて少ない、という大きな謎があります。しかし、最初に神武軍が征服した大和盆地内では、ナガスネヒコ王国(漢書にある東鯷国でしょうか?)の祭祀品の銅鐸は、隠す暇も無く、潰され鏃などの武器に変換された、とみれば謎は解けます。
中国の文献にも、古代の日本列島には”倭国”以外にも王国が存在していたことが、中国の史書「漢書」にあります。●(A)楽浪海中、倭国有り。分かれて百余国を為す。歳時を以って来り献見すと云う。(『漢書』地理志、燕地) ●(B)会稽海外、東鯷人有り。分かれて二十余国を為す。歳時を以って来り献見すと云う。(『漢書』地理志、呉地)
この二つの文章の内、なぜか(A)のみが、歴史研究書に引用され著名ですが、(B)は殆んど取り上げられません。この二十国の分国を持つ東鯷国は、次の魏志以降には現れません。つまり卑弥呼の時代には滅亡していたか国名が変わったものと思われます。
東鯷国は、その漢字の意味からして、東の端の国、であり、倭国より東にあった国と思われます。東鯷国については、その存在した位置について、まだ定説として固まっていないようですが、存在したことは間違いないことでしょう。詳しくは、古田武彦『日本列島の大王たち』古代は輝いていたII 朝日文庫・第一部 銅鐸の国家・第二部近畿王朝の萌芽と発展を是非お読み下さい。
ところで、『古事記』の「神武東征」のところを見ますと、“坐高千穂宮而議云坐何地者平聞看天下政猶思東行即自日向発幸行筑紫故到豊国宇沙之時・・・”とあります。
岩波文庫では、”高千穂宮に坐して議りて云りたまひけらく「何地に坐さば、平らけく天の下の政ごとを聞こしめさむ。なほ東に行かむ」とのりたまひて、すなはち日向より発たして筑紫に幸行ましき。故、豊国の宇沙に到りましし時・・・”と訳しています。
そこで神武の言葉としては、「東へ行こう」と云っているわけで、出発地が宮崎県だとすると、東へ向かえば太平洋です。宮崎から筑紫へ行くのに東に行くというのもおかしな話です。古田武彦氏は、古事記の中の、神武歌謡といわれる、神武記のなかの数々の歌謡の歌詞の分析から、神武たちの出発地は、神武の発進地とされた宮崎県(日向国)ではなく、福岡県の日向とされ、『神武歌謡は生きかえった』新泉社 に詳しくその分析・検証結果が述べられています。
★「神武東征」のお話とは
神武天皇の実在性および神武東征を、簡単に纏めるのは大変ですが、『記・紀』の述べること、考古学的出土状況などから、天孫降臨~神武東征~崇神天皇までのストーリーを、古事記の記事を基に、棟上寅七なりにまとめてみることにします。
☆1.天孫降臨とは、壱岐対馬を活躍の場とする、天(海人)国が、筑紫の博多湾に侵攻したことの伝承が神話に仕立てられた。
☆2.神武の祖先とされるニニギの尊は主流でなく傍系(主流は兄の天照国照火明命)である。
☆3.しかもその後の筑紫は、筑紫の王者たち(例えば漢の光武帝から金印を下賜された委奴国王)の縄張り内であり、ウガヤフキアエズ一家はうだつが上がりそうもなかった。
☆4.神武兄弟は、東の方にはまだ自分達を受け入れてくれる余地のある地があるのでは、と東に向かって出発した。
☆5.彼らは、日向(福岡県糸島郡日向)を出発し、東へ日向峠を通り、筑紫に向かいご本家の了解を取って、宇佐に向かった。宇佐津彦・宇佐津媛の厚遇を受け、足一騰宮(四本の柱のうち一本が川に立てられている家屋)という住居も作って貰ってしばらく滞在する。(宇佐~安芸、宇佐~吉備への根回しが行われたのでしょう)
☆6.そのあと、関門海峡を通過し、遠賀川下流の岡田宮に立ち寄る。おそらく、同行者(久米部の軍団を呼び寄せた?)も募ったことでしょう。
☆7.それから、安芸のタケリ宮に寄航し、その後吉備の高島宮に身を寄せる。ここに4年(古事記には8年とありますが、その半分の期間でしょう、二倍年紀の世界ですから)滞在し、勢力を蓄える。
☆8.この吉備の有力者・瀬戸内の王者がいわば神武兄弟のスポンサーとなった。(この戦闘軍団をここに居つかせるより、けしかけて仇敵の銅鐸圏を攻め取るように勧めたか?)
☆9.銅鐸を宝器とし繁栄する一大文明圏に侵入し、新しい支配地を樹立しよう(さもなくば死か)という賭けに出た。吉備から出発し、浪速で初めての戦闘が始まります。筑紫を中心とする細剣の勢力範囲を越え、銅鐸文化圏に入って戦闘が始っていることに注意が払われるべきでしょう。(考古学的出土品の分布状況によく合っています。)
☆10.大阪湾に突入し、「日下」というところでナガスネヒコの軍と戦い、敗戦し「南方」から湾外に逃れ、紀州に撤退する。この時、神武の兄五瀬命は戦死します。『記・紀』の記事によりますと、「日下」(盾津)とか「南方」とか、『記・紀』編集時の八世紀時点では、船で行けないところを船で行って戦った、と記述しているのです。近年分かったことですが、この対ナガスネヒコ戦の紀元一世紀?かの古代の大阪湾には、奥に河内湖があったのです。(前掲古代の大阪と河内湖の湾図参照)
☆11.『記・紀』が編集された八世紀には「日下」は既に陸化されています。その記紀編集時の約千年前のことを、史官が想像のみで記述できるとは、とても思われません。このことは、神武説話は弥生期に語られたので、弥生期の自然地理と合致しているのです。
☆12.兄を失い、神武が統率し、熊野経由で大和盆地に侵入します。奈良に入るのは紀ノ川を遡るのが自然ですが、神武は、迂回による奇襲作戦を選び、熊野川を遡ることにします。
☆13.神武たちが、道なき道を進み、大和盆地への進入は成功します。この戦闘・殺戮・だまし討ちなどを、『記・紀』の記事が生々しく伝えています。(筆者には具体的に記述する勇気が無い位)
☆14.それまで大和盆地に鳴り響いていた銅鐸の響きは止み、銅鐸は隠され、あるいは溶かされ銅鏃・銅鏡となり、銅鐸文化は消滅することになります。
☆15.そして、橿原で新しい統治(大和地方の)の宣言を行ったのです。つまり、なんとか神武は、大和橿原に拠点を構えることができたわけです。
☆16.以後150年くらいでしょうか、この地を治めるのに専念する。初代の神武陵墓も、それからの八代の陵墓も、土饅頭的なものですが、筆者は、むしろそのことが、厳しかった統治初期の状態をよく示していると思います。そして北部九州との連絡も充分にいかず、鉄文化も北部九州に遅れをとります(鉄鏃の奈良での出土が見られない)。
☆17.しかし、その間徐々に筑紫との連絡も取れるようになり力も付けてきます。名前に「大倭」という邪馬壹国の官職名が付けられていることにも関係が見て取れます。魏志倭人伝に出てくる21ヵ国の邪馬壱国の構成国で、奴国が二度出てきます。最後の奴国が、この神武が建設した、奴国の分国という可能性が高いように思われます。
☆18.第十代崇神天皇は、その名「ミマキイリヒコ」から見て、任那(みなま・狗邪韓国)の要害の地(城・き)から来た王子であり、単なる大和地方の「大倭」ではなく強大な力があったようです。神武の正統な後継者であったと思われる兄タケハニヤス王を排除し、東国や、出雲まで勢力を張れるようになり、陵墓も立派に作られるようになりました。(守墓人問題については先述)
大津教授は、神武東征説話や、その後の八代の天皇方は後世の史官の創作として省みられません。しかし、そのように簡単に無視してしまってよいのでしょうか。そのような「面倒なことは避けて通る」態度で「天皇の歴史」を語るのはおこがましいと思われます。
筆者はこの問題について、検討したことがあります。紀行文作家の宮脇俊三氏の『古代史紀行』批評の「神武東征」・「欠史八代」に関してのところをご紹介します。当HP「槍玉その7 『古代史紀行』批判」 をクリックしてみて下さい。
★大嘗祭について
昭和天皇から平成へと時代が変わり、大嘗祭が古式にのっとって行われました。この大嘗祭について『記・紀』にはあまり記事がありません。大津教授がこの著書の中で大嘗祭について即位儀礼に関連して、大略次のように「序章の古代史の儀礼研究」で述べています。
【王権儀礼の中核である皇位継承儀礼について研究は少なかった。なんとなくそれは日本固有の習俗である大嘗祭であるという思いこみがあって、神道史の扱う特殊分野であるという感じで敬遠されていた。
井上光貞氏が律令制度研究の一環として即位式を分析し践祚儀が九世紀初めに開始されたこととその意義を解明した。岡田精司氏は中国から取り入れた新しい儀礼と考えられていた即位式の方が、大嘗祭よりも古い伝統をもつことを明らかにした。】(p28)と。
具体的には、p60-61で大略次のように述べています。【天皇の即位の儀式では剣・鏡の神器の伝達が行われた。古代において、即位後最初の新嘗祭を大嘗祭といい、一代一回行われる。その大嘗祭が神武天皇即位において行われた、と『古語拾遺』という九世紀初頭に斎部広成よって著された古文書にある。それによると大嘗祭では八咫鏡・草薙剣の二種の宝器を天皇から皇太子へ渡す、としている。
古代天皇の代替わり儀礼としては、大嘗祭と即位式がある。践祚儀として、即位式とは別の儀礼が平安時代になると成立する。また、大嘗祭よりも即位式の方が王位継承儀礼の中心であるとの意見もある。律令には神祇令で、「凡そ践祚の日には、中臣、天神の寿詞を奏し、忌部、神璽の鏡剣を上れ」と規定された。】と述べています。
『日本書紀』には大嘗祭の記事は他にもあります。 大津教授はp337-338で次のように書かれています。
【天武朝に派入り、奈良盆地を対象とする班幣祭祀の原形が作られ、六月と十二月のの月次祭も整備される。持統即位にあたっては、神祇令にもとづく即位儀式と天神地祇への班幣が実行され、畿内七道の全官社の班幣祭祀が行われた。
天武二年(763)十二月に大嘗に奉仕しした人々などに褒賞があたえられたなどの記事がある。天武朝においては、一代一度の大嘗祭ではなく、新嘗祭など、令制祭祀としての大嘗祭が整えられたのもこの時期である。】と。
古田武彦氏が指摘しています。 【 『日本書紀』で大嘗祭が明確に出現するのは、持統紀である。持統は『日本書紀』の一番最後の天皇、その最後の天皇で初めて大嘗祭の記事がまともに出現する。実は天武紀にも大嘗祭の記事がある。「十二月の壬午の朔丙戌に、大嘗に侍奉れる中臣・忌部及び神官の人等、并て播磨、丹波、二つの国の郡司、亦、以下の人夫等に、ことごとくに禄賜ふ。因りて郡司等に、各爵一級を賜ふ。」と。 つまり大嘗祭に参加した人たちにご褒美をやったという記事だ。これが明確に『日本書紀』に「大嘗」という言葉が出てくる最初だ。
(筆者注 清寧天皇の時にも出ていますが、内容的に新嘗祭ととれます。 清寧天皇二年十一月の条に「大嘗供奉る料に依りて(中略)伊予来目部小楯云々」とあるのです。しかし、同じ行事の記事が次の顕宗天皇即位前紀に「白髪天皇の冬十一月に、(中略)伊予来目部小楯、親ら新嘗の供物を弁ふ。」とあり、内容からして大嘗祭でなく新嘗祭ではなかったか、とか、写本によっては大嘗祭とないものもあり、まだ定着した即位儀式ではなかった、というような諸説あるようです。)
天武紀には大嘗祭をやったという記事がない。大嘗祭に参加した人に褒美をやったという記事だけである。持統紀には、「十一月の戊辰に、大嘗す。神祇伯中臣朝臣大嶋、天神寿詞を読む。」と ここで、初めて「大嘗す」という言葉が出てくる。
なぜ、神武から天智までは「大嘗す」という記事がないのか。大嘗祭は新嘗祭とは違い、中心権力者が即位して初めて行う新嘗祭だ。論理的に考えれば、当然、天皇家が中心権力者ではなかったからである、(近畿王朝の上部組織の「大嘗祭」に参加した者たちへの褒賞記事)と、こういう答えになる。】(古田武彦『失われた九州王朝』朝日文庫版あとがきより抜粋)
古田武彦氏は概略次のように追加してのべます。【祝詞「大嘗祭」の文言には皇御孫つまりニニギのミコトを中心に大嘗祭を行うことを宣言している。天孫降臨の地、つまり筑紫にて大嘗祭は「倭国」滅亡まで行われていて、持統天皇に至って近畿にて行われるようになったのだ。】と。(詳しくは『失われた九州王朝』コレクション版「補章 九州王朝の検証 大嘗祭の断絶」参照)
この大嘗祭は今上天皇の場合、平成2年11月22日の深夜から23日にかけて行われ、持統天皇から連綿として現在まで伝承されています。しかし、大津教授はこの古代における大嘗祭問題について触れると、否が応でも「古田武彦」の問題提起にかかわらざるを得ません。大津教授の大嘗祭軽視姿勢の根本に「古田武彦」があると思われますが、思いすごしでしょうか。
★マヘツキミ論
大津教授は舒明天皇の即位の時に「マヘツキミ」に推される形をとっていることについて、これが天皇即位儀式の典型だろうか、と次のように述べ、結局このケースは特異であろうとされ、否定的な判断をされます。
【『日本書紀』舒明天皇即位前紀に、蘇我の蝦夷がマヘツキミたちを呼んで会議を開いた、とある。田村皇子か山背大兄王かどちらかを天皇に、とマヘツキミに意見を求めたのだ。結局蝦夷は実力で、反対する境部臣を殺し、田村皇子が推されて天皇になった。蝦夷は最初から田村皇子に決めていたのだが、大臣であっても、大夫の会議の意見がまとまらないと皇位は決められなかったのである。(p211~213要約)】
しかし、大津教授が「マヘツキミ」が誰たちを指すのか、歴史的な変遷の有無などについての考察はみられず、マヘツキミ=大夫論を展開されます。 一応古代天皇制の統治組織が固まり始めたとされる、雄略~舒明期の「マヘツキミ」「マヘツキミタチ」や同様な文字で別の読み仮名が付けられている例を、『日本書紀』から拾い上げてみます。なお訓読は「岩波文庫」に依りました。岩波の解説には、大野晋氏が古写本を参照されての訓読とあります。
①巻十四(雄略紀) 「群臣」14例、「卿」4例、侍臣1例、大夫(身毛君大夫)1例、 ②巻十五(清寧・顕宗・仁賢紀)「群臣」3例、「諸臣」1例、「公卿」1例、「公卿大夫」1例 ③巻十六(武烈紀) 該当なし ④巻十七(継体紀) 「群臣」1例、「将相」1例、「諸臣」1例 ⑤巻十八(安閑・宣化紀) 「群臣」1例、「大夫」1例、⑥巻十九(欽明紀) 「群臣」3例、「大夫」1例、「諸臣」「諸臣等」5例、「臣」「臣等」8例、「大臣」2例、「臣下」1例、「卿等」1例、 以上計 四八例。
また、「マヘツキミ」の特別な例として、景行紀の「魔弊菟耆瀰」があります。これには『日本書紀』編者の判断に問題があります。(別項を立てて後述します)。
ところで「マヘツキミ」という言葉は、口伝されて後世文字化されたものと言えるでしょう。その口伝された文章として信頼性が高いと思われるものに神道の祝詞「大祓」があります。そこには、【集待れる親王たち、諸王たち、諸臣たち、百の官人等 諸々こしめせ・・・】とあり、マエツキミは大王の直系の子たち(親王)・傍系の王たち(諸王)・その下に位置するマヘツキミ(諸臣)・その下に官人たち、という順位付けとなっています。(『まぼろしの祝詞誕生』古田武彦 神泉社より)
。
大津教授は、p207-208で大略次のように述べ「マヘツキミ=大夫」論を展開されます。【崇峻即位前紀(587)には、「炊屋姫尊と群臣と、天皇を勧め進りて、天皇の位に即かしむ。蘇我馬子宿禰を以て大臣とすること故のごとし。卿大夫の位、また故のごとし。」と即位に伴って馬子の大臣再任とともに「卿大夫」の位の再任が見えている。】とされ、【 関晃氏の『日本書紀』をみると、大化のころに「大夫」と記される一定の上流豪族層があったことは確かであるが、「大夫」の語があてられるマヘツキミ(マチキミ)とよばれる実体があり、一定の政治的地位を示す語であることを論じたのである。(中略)
その地位は冠位十二階の大徳と小徳の者によって占められ、『翰苑』に引用される括地志に、十二等の官の第一に「麻卑兜吉寐」華言に大徳とあり、大徳冠がマヘツキミ(大夫)に対応することを示すと、今から五〇年前に論じたのである。】と。
今まで大津教授が難しい「史書」を引用されるときには、我田引水の傾向があるように感じていましたので、今回の『括地志』もチェックしてみました。
まず『翰苑』は太宰府天満宮に「巻卅夷蕃伝倭国」のみが残っていて、貴重な史料として国宝に指定されています。その『翰苑』に引用されている『括地志』は唐代に編集されている大規模な地理書です。 このところの原文は次のようなものです。
【因禮義而標袟即智信以命官 括地志曰 倭国 其官有十二等 一曰 麻卑兜吉寐 華言大徳 二曰小徳 三曰大仁 四曰小仁 五曰大義 六曰小義 七曰大礼 八曰小礼 九曰大智 十曰小智 十一曰大信 十二曰小信】と、このように、倭国の冠位について述べています。
この中の「一曰麻卑兜吉寐 華言大徳」というところを大津教授は取り上げて、 マヘツキミ=大徳=大夫という論法で、中国の史書にもこのようにある、とされるのです。
しかし、「麻卑兜吉寐」=マヘツキミでしょうか。そう読みたいという心がそう読ませているのではないでしょうか。「麻卑兜吉寐」をそのまま読めば「マヒトゥキッミ」=「まひときみ」ではないでしょうか。
つまり「真人君」といっているのでしょう。天武朝の八色の姓で「真人」姓があり皇族とされているのです。大津教授も、【 息長氏は古事記で応神の系列に加えられていて、「意富々杼王」を始祖とする氏で天武八姓で真人が与えられた。】(p193)』としていますが、その天武自身の謚号は「天渟中原瀛真人天皇」であり、「真人」が入っています。これも『日本書紀』の謎のひとつです。
大津教授はこの天武の謚号について、【 仙境瀛州に住む真人(神仙)の意がこめられているとされる。 】(p255)とされますが、八色の姓との関連有りや無しやについては無言です。
古田武彦氏は次のように解かれます。【天武天皇の「真人」と同じように、藤原鎌足が「朝臣」という姓を「八色の姓」の発布以前に亡くなっているのに与えられていた。(『万葉集』巻一、一六の題詞に天智天皇が内大臣藤原朝臣に詔して・・・とある)これらから見て、天武天皇以前に「八色の姓」は制定されていた、と思わざるを得ない。
この謎をとく鍵は『旧唐書』倭国伝の九州を中心とする「倭国」の存在である。「八色の姓」は筑紫で発布されていて、鎌足も天武天皇もそれぞれ「朝臣」、「真人」という姓を与えられていたのだ。】(『人麿の運命』「八色の姓の矛盾」より)
大津教授は古代史研究者にとって有名な「天武の真人姓」問題について、八色の姓で、「真人」が有ることについては何も述べていないのは問題から逃げているとしか思われないのは残念です。
ところで、大津教授がこの「麻卑兜吉寐」を「マヘツキミ」と読むことだけでも我田引水ですが、上記のように、この『括地志』の十二階の冠位は、『隋書』が伝える順序と同じであり、『日本書紀』が記す順位とは違っています。
この『括地志』の冠位記事によれば、隋書が伝える俀国の冠位記事は大和朝廷のものではない、という傍証にもなるのです。大津教授が『括地志』を引用されるのであれば、その史書批判もおこなった上で慎重にやっていただきたいと思います。
結論的に云いますと、『日本書紀』(岩波文庫)には前述のように「群臣」「諸臣」「卿」「大臣」「大夫」「臣」などなどに「マヘツキミ(タチ)」と「読み仮名」が振られています。これは、歴史的にいろいろな学者が「読み仮名」を付けているのであって、あくまでも原文は「諸臣」「群臣」「卿」「大臣」「大夫」とあり圧倒的に多いのは(六〇%以上)「群臣」「諸臣」です。
大津教授のように出現例五%程度の「大夫」のみを「マヘツキミ」の代表のように取るのは如何なものかと思います。第一「群臣」「諸臣」はその意味からして複数形であり、大津教授のように「群臣=大夫」ととること自体に問題があります。
まして、「大夫による合議制」が形成された、と辻のような感想を述べられるのは先走り過ぎと思われます。
【崇峻四年(591)には「任那」復興について諮問がなされた。 天皇、群臣に詔して曰く、「朕、任那を建てむと思ふ。卿等何如に」とのたまふ。群臣奏言して、「任那の宮家を建つべきこと、皆陛下の詔したまふ所に同じ」とまうす。
ここにみえる「卿」「群臣」はマヘツキミをさしており、こうした大夫の会議は、序章でも触れたように、律令制の太政官合議制へつながる古代天皇制の特徴といえるだろう。宣化元年の阿倍臣大麻呂を大夫に任ずることが記され、もちろん一人だけを大夫にしたというのは不審であるが。六世紀中葉には大夫制が形成されていると考えてよいだろう。】(p209-210)
この大津教授のマヘツキミ=大夫説は、先輩吉田孝氏の影響によるもののようです。この本の冒頭で「天皇研究の歴史」を概観されるのですが、その中で次のように、吉田説を肯定的に紹介しています。
【早川庄八氏は、天皇と太政官合議制との緊張関係を考え古代天皇制の権力が制約されている、としたのに対し、吉田孝氏は、「天皇は畿内豪族のなかで、特定の役割を果たすために共立された首長であり、けっして畿内豪族と並立すべき立場になかった」「七世紀の天皇は、すでに特定の世襲カリスマを持った特殊な存在として、畿内豪族層の承認を得ていた」「天皇は畿内豪族に共立された司祭者的首長としての性格を色濃くのこしている、と早川氏を批判している。】(p24)
もともと「マヘツキミタチ」という言葉の意味は、大昔、大王の前に集合した関係者のうち主だったものが前の方に着座していたので、「前の方にいる有力者たち」という単純なものではなかったでしょうか。
★ 景行紀の「魔弊菟耆瀰」
ただ、『日本書紀』に一つだけ異なる「マヘツキミ」が景行紀にあります。景行天皇が九州巡狩の時に詠まれた歌が出ていますが、その中の「マヘツキミ」が「群臣」としてよいのか、という問題です。
景行紀一八年【秋七月の辛卯の朔甲午に、筑紫後国の御木に到りて、高田行宮に居します。ときに僵れたる樹有り。長さ九百七十丈。百寮、其の樹を蹈みて往来。時人、歌して 曰 はく、「朝霜の 御木のさ小橋群臣い渡すも 御木のさ小橋」。】
この歌の原文は次です。 「阿佐志毛能 瀰概能佐烏麼志 魔弊菟耆瀰 伊和哆羅秀暮 瀰開能佐烏麼志」。
たしかに第三句目は「まへつきみ」と読めます。しかし、近畿から来た天皇が討伐中の行宮に朝廷の百寮という官人たちが行きかう、というのはおかしい。マヘツキミという語に、「群臣」という複数形の言葉を当てるのも不自然。また、天皇に対してならともかく、群臣に「い渡たらすも」という荘重な響きの敬語使いもおかしい、と、この「魔弊菟耆瀰」はマヘツキミでも「群臣」ではなく、「前つ君」という九州の大王ではないか、と考証されたのが古田武彦氏です。
『古事記』には存在しない景行天皇の九州遠征は、卑弥呼の後継王朝の「前つ君」の九州の東部から東南部の征討譚を、おそらく『日本旧記』から『日本書紀』編者が取り込んだものであろう、とされます。
そう考えると、この遠征の途次「日向国」を通るのですが、『記・紀』によれば神武東征発進の地なのに、景行天皇は一言の感慨もない不思議さにも合点がいくのです。詳しくは『盗まれた神話』第四章「蔽われた王朝発展史 その名は前つ君」をご覧ください。
★継体紀の問題
『天皇の 歴史01 神話から歴史へ』の第三章 大和朝廷と天皇号 で継体天皇が出てきます。継体紀の紀年問題についての大津教授の発言は次のようなものです。
【継体紀の最大の問題は、継体崩御の年である。本文では二十五年(531年)二月に天皇の病気と記すが、分注には、或本には二十八年(534年)崩とあるのに、二十五年としたのは、「百済本紀」をとって文としたのであるとして「百済本紀」の文章迄を引用している。】(p196-197)
また、【坂本太郎博士の、即位から大和に入るまで20年を要した、と『日本書紀』は記しているが、年月だけでなく、個々の遷都にどの程度信用性があるか疑わしい、とするのは傾聴すべき。】(p197)と、大津教授は、国内の伝承紀年は信用できず、「百済記」の記事が信用出来るとされているようです。ところで、この継体天皇の場合の即位儀礼について大津教授は何も云われません。
『古事記』では簡単に、武烈の姉と結婚させて天の下を授けた、としています。『日本書紀』では、樟葉宮に入った男大迹王に鏡・剣をたて奉ったが、もっと賢い者を選べ、と何度も固辞したけれど結局受けた、とあります。しかし、大嘗祭などの他の即位儀礼の記事はありません。継体天皇については、単に没年記事や年紀の問題だけではありません。『天皇の歴史』にとって肝心の皇統の断絶という問題など沢山あるのです。それらは次の様なものです。①継体天皇は応神天皇五世の孫となっていて、これは新たな王朝ではないのか。
②継体天皇が大和に入るのになぜ二十年かかったのか。この『日本書紀』の記述が信用できるのか。③継体天皇の歿年齢が『古事記』と『日本書紀』で大きく違っていること。④継体天皇の没年記事の問題(大津教授も問題視している) ⑤継体天皇紀の百済関係記事は史実といえるのか。⑥継体紀の国内記事で「磐井の乱」のみは史実と大津教授はいわれるが、果たしてそうなのか?
まず、①について、大津教授は日本書紀の編者と同様に、「皇統が続いた」という立場で史書を解釈されています。 『記・紀』ともにただ応神天皇の五世の孫というだけで中間の系譜を欠いているが、鎌倉時代の卜部兼方による『日本書紀』の注釈書『釈日本紀』には、『上宮記』という聖徳太子の伝記を引用している。それによると若野毛二俣王以下中間四代の系譜があり、母方も垂仁天皇の七世の孫である】(p190)、と紹介しています。しかし、『日本書紀』に見られるような武烈天皇の悪逆非道ぶりは異常と言えましょう。(古事記にはこの様な叙述はありません)。このこと一つを見ても、継体天皇が皇位を簒奪しなければならかった言い訳、ととるのが自然でしょう。のことは、同じく、応神から武烈に至る仁徳・雄略など各天皇方の悪行の露出も同様でしょう。応神~彦主人王~継体の血筋が正統と主張している、とみれば納得できるのです。(後に述べますが、『万葉集』編集方針も同様と思われます。)
古田武彦氏は次の様な例を上げて、この様な場合も「皇統は続いた」と言えるのか、と問います。【『記・紀』は、それぞれの豪族が天照大神の血を引く、ということを主張していると云ってもよい史書であり、継体と同様な系譜はありふれていたであろう。例えば、平将門は桓武天皇の五世の孫であり、源義家は清和天皇の六世の孫である。継体が天皇の位に即いたということは、平将門や源義家が天皇になったのと同じことなのだ。これで果たして正当な即位といえるだろうか。】と。(『日本列島の大王たち』より要約) ②については、【坂本太郎博士の、即位から大和に入るまで20年を要した、と『日本書紀』は記しているが、年月だけでなく、個々の遷都にどの程度信用性があるか疑わしい、とするのは傾聴すべき。】(p197)と、大津教授は云われます。そのような、自分の意見に合わない所の『日本書紀』の記事は信用できない、合う所だけは信用できる、という態度で「史料批判」と云えないでしょう。
古田武彦氏の意見は次のようなものです。 【武烈の歿後継体は長期間大和盆地の北・西部をうろつき『日本書紀』によれば二十年後に大和に入っている。このことは、大和盆地は長期間皇位継承の大乱があったことを示している。武烈を悪逆天皇に仕上げ、不法の簒奪者の汚名を濯ぐ為の正史編纂であった。】(『日本列島の大王たち』より要約)
このことは、『日本書紀』が正史とされ、天武が『古事記』を編纂させながら、継体記の記述への不満から、『古事記』が日の目をみる事が出来なかった理由の一つでもあろう、と思われます。
読者諸兄姉は、大津教授の言われるように『日本書紀』の記述はいい加減なものなのか、古田武彦氏が言われるように、北から来た継体天皇が大和全体を掌握するのに長い年月がかかった、というのは正しい、つまり武烈と継体の王朝には断絶がある、というのとどちらに軍配を上げますか? ③の継体の没年年齢が『日本書紀』と『古事記』で大きく違っていることに大津教授は全く注意を払われません。『日本書紀』によれば八十二歳で、『古事記』によれば四十三歳です。これが説明できる仮説は、先述の「古代の二倍年暦」で述べたように、『日本書紀』では継体紀で二倍年暦は終わる、『古事記』では既に一倍年暦伝承となっている、ということでしょう。ただ、崩年干支などが合いませんのでもっと検討してみる必要があるとは思いますが。
④、⑤については『日本書紀』と「倭国」・「日本旧記」との関係で、あとで検討します。⑥の磐井の乱問題 磐井の乱について大津教授は『日本書紀』の記事を引いて次のように説明します。
【大和朝廷の形成と同時に、この時期に地方への支配機構も形成される。地方豪族を従属させ、中央に貢納させる体制ができてくる。その国造・屯倉制が成立してくる一つの画期となったのが、六世紀後半に九州北部で起きた筑紫国磐井の反乱である。継体天皇二一年(五二七)、朝廷は「任那」での倭国勢力後退を防ぐため近江毛野の率いる六万の軍兵を朝鮮半島に派遣した。
これに対して筑紫を本拠とする磐井は、火(肥前・肥後)、豊(豊前・豊後)二国の勢力を集めて反乱を起こし、毛野の軍をさえぎって渡海できないようにした。朝廷は物部麁鹿火を大将軍として派遣し、翌年磐井を斬り、その子の葛子が糟屋の屯倉を献上して贖罪を願うことで、磐井の乱は終わった。
仁賢以降は系譜だけで本文がない『古事記』だが継体天皇段に、「竺紫君石井」が無礼なことが多かったので、物部荒甲・大伴金村の二人を遣わして殺したという記事があり、反乱は大規模だったことは疑いない。】(p219)と。
また、『筑後国風土記』逸文ににある記述を次のように紹介されています。
【 磐井の墓とされる岩戸山古墳の附属する別区(衙頭=政所)に、石人(解部=裁判官)が立ち、その前に裸の男(偸人)が地に伏して、側に石猪四頭(贓物=盗品)がある。岩戸山古墳の石人が磐井の裁判を再現していたように、国造は独自に裁判を行った。
国造制は個々の豪族の特徴によって差も大きい。一つのタイプは、吉備臣・出雲臣、あるいは筑紫君・毛野君など、臣・君姓を持つ国造で、伝統的にきわめて大きな力を持ち、反乱の伝承もあるように、大王家と対等の関係を持つ地方豪族だったのだろう】(p220)、などと言われます。
ということは、臣・君姓を持つ国造は、大王家と同じ権力を持つ地方政権ということになります。まあ継体紀を読むとそれに近いことが書いてあることには間違いありません。
大津教授はあくまでも、【 磐井という国造の罪が糾弾されて屯倉を差し出して罪を贖ったのだ】、とされていますが、もう一歩踏み込んで、「臣・君」が付く国造は地方独立政権に近かった、とどうして表現出来なかったのかな、と思います。まあ、そうなると当方もその批判の切り口を見つけるのにより苦労することになりますが。
古田武彦氏も、この「磐井の乱」が近畿と九州との大戦争で近畿が勝利したのであれば、そのあたりで土器その他の出土品に変化があってしかるべきだし、葛子が親の墓を修復しなかったというのも解せない、と大規模な政権の変更が生じたということは疑問だ、と指摘されます。
筆者も、これらの疑問点について、田村圓澄・小田富士雄・山尾幸久三氏共著の『磐井の乱』の批評した「槍玉その12 磐井の乱」で意見を述べたことがあります。
葛子が墓を修復しなかったのではないか、ということについては、天武七年(679)の大地震の影響で、もし葛子が修復したとしても石人像などは全て倒壊したものでしょうし、物部軍が磐井を捕えられなかった腹いせに墓を破壊した、という風土記の記述について真偽を確かめる手立てが今のところありません。
ただ、『宋書』が記す倭王武当時の倭国から、『隋書』が記す俀王多利思北孤の間の時期に、大和と筑紫で一方の政権の滅亡という大変異が起きたのでしたら、近隣諸国の史書などにその片鱗が残るのではないかと思います。
【日本天皇、太子皇子倶に死す】と関係ある記事は『記・紀』に見えません。武烈天皇に子供があって倶に死んだとすれば、話の筋の整合はつきますが小説の世界でしょう。 倭の五王の王朝から多利思北孤王朝の間に【日本天皇、太子皇子倶に死す】という状況が生じた、という推論までが現段階ではないでしょうか。
ところで、『日本書紀』には継体天皇が、物部麁鹿火を大将軍に任命する時に、「社稷の存亡是にあり」、と言って天皇が斧鉞を授けながら「長門より東をば朕制らむ。筑紫より西をば汝制れ」というシーンがあります。大津教授は天皇のレガリアとして剣を授けるというようなことについて、多くの言を弄されますが、なぜか、この象徴的なシーンについては何も取り上げられていません。
★わが国の仏教受容の歴史
教科書などでは「仏教公伝」として六世紀中ごろに百済王から仏像・経典が送られてきたことを書いています。 大津教授はこの問題について、『日本書紀』の物部氏と蘇我氏の争いに焦点を当て、仏教受容の歴史を述べています。
しかし、この「仏教」が「天皇の歴史」にどのような影響を与えたのか、それが残存しているのか、等についての考察は何も述べられません。興味があるのは『日本書紀』と他の史書とその百済王からの仏像などの伝来記事の年代が異なるので、継体歿後の皇統譜が信用できなくなる、ということのようです。
大津教授は仏教受容の歴史についておおまか次のように述べます。
【『日本書紀』は、欽明十三年(552)条に仏教伝来を記し、天皇が群臣に礼拝の可否を諮り、蘇我稲目は賛成したが物部尾輿らは反対した。稲目に私的に礼拝を許したが、疫病がはやったので、尾輿らは天皇の許可を得て仏像を難波の堀江に捨てた。
その後敏達天皇十三年(584)鹿深臣が百済から仏像をもたらしたのを機に蘇我馬子が仏教を再興する。馬子は高句麗僧恵便を播磨から探して師となし、仏殿をつくり、彌勒石像を安置した。『書紀』は「仏法の初め、これより作れり」と記している。ところが翌年馬子が病になり、物部守屋と中臣勝海が敏達の許しを得て再び仏像を難波堀江に捨て、二度目の破仏となった。
用明二年、(587)に、仏教受容をめぐって、“天皇群臣に詔して曰はく、「朕、三宝に帰らむと思ふ。卿等議れ」とのたまふ。”(中略)物部守屋らが反対し蘇我馬子は天皇に従うべきとし、ついに守屋殺害にいたる】、と説明します。(p229~231)
また、【仏教公伝の年を『書紀』では欽明十三年とするが、『上宮聖徳法王帝説』や『元興寺伽藍縁起』では538年になる。これでは、欽明期ではなく宣化天皇の時代になってしまう。このあたりの皇統譜には問題があるのではないか】(p229)、と喜田貞吉氏他の説を紹介しています。
それから60余年後の孝徳紀即位前紀に【仏法を尊び、神道を軽〈あなず〉りたまふ】とあるように、孝徳天皇(在位645~654年)の時代には、天皇家に仏教が深く入り込んだとみられます。
また、、その時に天皇候補者の一人、古人大兄皇子は天皇の意向が自分でないのを知り、「出家して、吉野に入りなむ。仏道を勤め修ひて、天皇を祐け奉らむ」と言って吉野に行きます。このように、天皇家に仏教は大きな影響を与えるようになっていたようです。
その仏教がどのようにわが国に入り、皇室に入り込んだのかということは、大津教授が言うように、【 単に552年の公伝であったら用明だ、538だったら欽明だ。公伝の時期は皇統譜に関わってくる】というだけの問題でないと思います。
その百済聖明王からの仏教公伝というものについて、『日本書紀』には次のように記されています。【百済の聖明王、西部姫氏達率怒唎斯致契等を遣して、釈迦仏の金銅像一躯・幡蓋若干・経論若干巻を献る。別に表して流通し礼拝む功徳を讃めて云さく、云々】と。
古賀達也氏が古田史学会論集1で報告していますが、追手門大学の中小路駿逸教授が指摘されているように、百済聖明王からの仏教公伝というものは、仏像と経本をもたらしただけのことということです。
高句麗や百済への仏教伝来では中国からそれぞれ高僧によって伝わったとその名も残っています。わが国の場合、仏教が大和朝廷に伝わったのは『日本書紀』にあるように584年「播磨」から高句麗僧恵便によってなされた、ということでしょう。
三世紀に卑弥呼~壹与の時代の邪馬壹国から派遣された難升米や都市牛利たちは、洛陽の寺院について興味を持ちそれらについて知識を集めて持ち帰ったことは想像に難くありません。
四・五世紀からの百済と倭国の緊密さぶりからみて、百済への仏教伝来からそれ程遅れず、倭国においても仏教が伝来したことは疑いないことでしょう。
古賀達也氏は概略次のように報告しています。【わが国仏教史には一大欠落がある。それはこの日本列島に仏教を齎した僧の名およびその伝承である。(文字伝来の項、略)仏教伝来の欽明十三年(552)説と『上宮聖徳法王帝説』の戊午年欽明七年(538)がある。然し最澄も指摘しているように欽明期には戊午年は存在しない。
『日本書紀』が記す仏教初伝は敏達紀十三年にあるように「播磨の恵便からの伝授」である。つまり、百済王からの仏像・経典の到来は「わが国」へであっても「大和朝廷」へのものではなく「倭国」へである。戊午年(418)にもたらされたということになるが、即位七年が戊午年の天皇は允恭天皇である。なぜシキシマ宮の欽明天皇になったのか、倭国にシキシマ宮があったのか、今後の研究課題である。
推古紀三二年の記事に仏教が中国~百済~わが国へと伝わった経緯が書いてある。(百済僧観勒の上表)これを検討すると、
①インドから中国へ仏教が伝来して三百年を経て百済に伝来(384年)した。
②この上表の時期は百済に仏教伝来して百年とあるから、484年頃である。
③わが国に仏像・経典が伝わって百年未満、と上表にあるから、“百年未満”を70~90年とすると、仏教伝来は394~414年となる。(筆者注:これは戊午年(418)説を補完する。)
九州における仏教伝来の伝承には、英彦山霊山寺の縁起『彦山流記』に、開基を「教到元年」531年としていて、『日本書紀』の552年や『法王帝説』の538年よりも古い。その他、大分耶馬渓の檜原山正平寺には、五世紀末の百済僧正覚の開山と『豊前国志』に残っている。福岡県糸島郡の「雷山千如寺」縁起によるインド僧清賀による仏教伝来記事もある。
九州のみでなく那智の裸行上人の景行期の渡来伝承、などさまざまな仏教伝来伝承がある。仏教を正式に国教的に取り入れたのが六世紀の俀国の菩薩天子を名乗った多利思北孤王である。大和朝廷の蘇我馬子との仏法対神道の記事はあるが、正式にどの程度まで取り入れたのか。】と。
残念ながら、純粋に学術的な研究というものはわが国には存在しないのか、この「わが国仏教受容史」が、表立って取り上げられていません。大津教授が真の歴史探究者であれば、この千如寺の史料評価のシンポジウムなどを開いて、多元史観論者などを木っ端微塵に撃破すれば、たとえ撃破出来ずとも、名は千載に残ることでしょう。
しかし、『日本書紀』頼りの論述が殆どの大津教授の『天皇の歴史01 神話から歴史』を読む限り、木に魚を求めることと同じことかも知れませんが。
このように天皇家に受容された仏教が、天皇の儀礼儀式などにどのように影響を与えたのか、そしてどのように払拭されたのか、ということについて大津教授は一言も述べません。
【安閑・宣化・欽明朝には、大王の喪葬儀礼も整備されていく。勿論五世紀には巨大な前方後円墳が造られていたのだから、巨大な儀礼が行われたのに違いないが、殆んど知られない。かわって六世紀に入ると、死者の遺体を埋葬するまで安置する殯宮で皇位継承にかかわる儀礼が行われ、謚号が献呈されるようになる。(中略)殯宮の儀礼として、誄が男性から奉られ、最後に皇統譜というべき日嗣が読み上げられ和風謚号が献上された。】(p217)
と、このように述べますが、仏教的な要素は見えないことについての感想はありません。 『日本書紀』に書いていないから言う種がないのでしょうか、先輩たちも述べていないから問題なし、としているのでしょうか。
東の菩薩天子を自称し、夜が明けるまで結跏趺坐し仏法に勤しんだ、多利思北孤王が、たとえ一般的にいわれている推古女帝であろうと、聖徳太子であろうと、国政に仏教の影を留めている筈です。
聖徳太子が制定したとされる十七条の憲法に、仏教に基づくと思われる「和を以て貴しとす」「篤く三宝を敬へ」があります。
しかし、大津教授は、【仏教思想が中心のように考えられることがあり、また道徳の訓誡ととらえられることもあるが、やはりこれは儒教を中心において国家の法として考えなければならない。推古朝の国家・官僚制の創出期においては、法が訓誡の形の段階をとらなければならない段階だったということであろう。】(p244)と憲法と仏教の結合説には反対のようです。
大津教授の先輩石母田正氏は、【憲法と大化改新詔を比較した場合、改新詔が王権支配の正当性をその歴史的・神話的伝統によって固めているのに対し、十七条の憲法はその様な痕跡が全くみえず、国際文明の普遍的基準の仏教を統治の精神的基礎に据えている。
しかし、既に推古朝に存在した体制を拠り所としていたのであって、憲法が推古朝の国家や支配層の現実を反映していないという理由で、それを疑う見解は支持しがたい。】(『日本古代国家論第一部』より抜粋)と述べています。
この石母田説の方が、大津教授説よりまともな解釈と思われます。ただ、石母田先生も「倭国」という別の王朝が存在していた、という認識はお持ちでなかったので、憲法と改新詔の矛盾についての解釈には苦心されているようです。
大津教授は、推古天皇のシャーマン的なところと仏教とがかみ合わないという方向で検討されます。いろいろ学者方の意見を参照されながら、次のように納得されているようです。
【 わが国最初期の仏法は、学問尼に受容され、最初の寺院も尼寺で、いわば巫女による仏法であったとし、推古は、神祇祭祀だけでなく、釈迦仏を祭祀する学問尼も統轄していたのである。こうした宗教的特質は女帝の本質を継承していて、推古女帝は仏教興隆に大きな役割をはたしたのである。】(p240~241)
しかし、東の菩薩天子を自称した多利思北孤王がはたして誰なのか、大津教授がうやむやで済ませていますが、それで『天皇の歴史』を論述する資格があるのか疑われます。
この本の始めの方に、【本シリーズでは、時代ごとの通史的な冠は、政治的な叙述が中心になるので、それ以外に、神祇祭祀など宗教について独立巻を設けた。】(p30)と述べられ、宗教とのかかわりについては担当外、というような前置きがあります。
しかし、今迄で見て来たように、天皇と仏教の関わりなどについてかなり述べていらっしゃいますから、菩薩天子を自称した多利思北孤王がはたして誰なのか、なぜ十七条憲法に仏教的内容が盛り込まれているのか、等についての基本的な考察まで避けるのは如何なものでしょうか?
十七条の憲法の発布者は、筆者としては、仏法を国教としたと思われる俀国多利思北孤王もしくは利太子だと思うのですが、大津教授如何でしょうか。大津教授は、【 石母田正氏の議論によれば・・・】と言いながら十七条憲法と改新詔の矛盾についての石母田先生の説明は紹介されていません。
(六) 『隋書』とわが国の歴史
★『隋書』俀国伝とは
大津教授のこの『天皇の歴史01 神話から歴史へ』の後半は、『隋書』「俀国伝」と『旧唐書』「倭国伝」・「日本伝」から、いくつもの箇所が引用されています。まず、大津教授の『隋書』の理解を知って頂くために、『隋書』「俀国伝」の大まかなところをまず掲載しておきます。
なにしろ大津教授は原文の「俀国伝」を何の断りもなく、「倭国伝」と変えて平然とされている態度に驚いたことをまず述べておきます。
『隋書』俀国伝
・俀国は百済・新羅の東南にある。水陸三千里、大海の中にあって、山島に依っている。(中略)
・漢の光武帝の時、使いを遣わし入朝し自らを大夫と称した。安帝の時、又使いを遣して朝貢した。之を俀国という。(中略)
・魏から斉・梁代に中国と相通じた。開皇二十年、俀王、姓は阿毎、字は多利思北孤、号は阿輩雞彌が使いを遣して都に 詣った。帝は役人にその風俗を訪ねさせた。使いが言うには、「俀王は天を兄とし、日を弟としている。天が明けない内は出座し跏趺坐して政を聴き、日の出よりすなわち理務を停め、我が弟に委ねよう、という」と。 高祖は「此れは義理無いこ太し」といって是を改めるよう訓した。
・王の妻は雞彌 と号する。後宮には女が六七百人いる。・太子を名付けて利歌彌多弗利とす。・城郭は無い。
・内官に十二等あり、一を大徳、次は小徳、大仁、小仁、大義、小義、大礼、小礼、大智、小智、、大信、小信、、定まった員数はない。
・軍尼が百二十人、中国の牧宰のようだ。八十戸に一伊尼翼を置くが、今の里長のようなものである。十伊尼翼は一軍尼に属する。その服飾は・・・・(中略)。
・阿蘇山がある。其の石は故無く火が起き、天に接するは俗をもって異となし、因って禱祭を行う。如意宝珠があり、その色は青く鶏卵の大きさで夜は光を放つ。これは魚の眼精なり。新羅・百済は、みな俀を珍物が多い大国としてこれを敬仰し、恒に通使往来する。
大業三年(607)その王多利思北孤が使いを遣して朝貢した。使者が言うには「海西の菩薩天子が重ねて仏法を興すと聞く。故に遣して朝拝させ、兼ねて沙門数十人を送り仏法を学ばせたい」と。其の国書に言うには「日出處天子致書日没處天子無恙云々」と。帝は之をみて悦ばず、鴻臚卿に「蛮夷の書無礼あり、以て聞することなかれ」と。
・明年(608)帝は文林郎裴清を遣わして俀国に使させた。百済を渡り竹島に行き、南は 耽羅国を望み、はるか海中にある都斯麻国をへて、又東に行って一支国に至りまた竹斯に至る。また東に行き秦王国に至る。其の住民は華夏に同じく夷州とするが疑わしく明らかではない。また十余国を経て海岸に達するが竹斯国以東みな俀に附庸する。
・俀王は、小徳阿輩台を遣し数百人を従え太鼓・角笛を鳴らして迎えさせた。のち十日、また大礼哥多毘を、二百余騎を従えさせて遣して、 郊労させた。
・既に彼の都に至った。その王は裴清と互いにまみえ、大いに悦んで言うには「我は海西に大隋礼儀の国があると聞いていた。故に遣して朝貢した。我は夷人、海隅に僻在して礼儀を知らない。そこで境内にとどまって互いにまみえなかった。今、道を清め館を飾って大使を待っている。願わくは大国維新の化を聞かんことを」と。裴清が答えて言うには、「皇帝は、徳は二儀に並び、沢は四海に流れる。王は化を慕うの故を以て使者を遣して来させよう」と宣諭した。既にして裴清を引いて館に就かしめた。
・その後、裴清は人を遣し、其の王に言うには、「朝命は既に達した。直ちに塗を戒めるようお願いする」と。そこで、宴享を設けて 裴清を遣す。また使者を裴清に随い来って方物を貢した。
・此の後、遂に絶えた。
大津教授の『隋書』の理解は
ここで取り上げる大津教授の理解されている『隋書』の問題と思われる箇所をあげてみます。
a)「俀」という『隋書』の字を説明もなく「倭」と読み替えていること。(前出)
b)阿毎多利思北孤とは誰か。
c)太子利歌彌多弗利とは誰か。
d)俀国の兄弟政治について
e)多利思北孤の国書と推古天皇の国書。
f)冠位十二階、軍尼、伊尼翼などの冠位官職について。
g)隋の使者裴世清の応対について。
h)「遂に絶つ」なのに「犬上御田鋤の遣使」とは。
上記の内、a)、b)、c)の3項についてまず検討し、あとの5項目は、のちほどそれぞれ独立の項を立てて検討します。
(a)「俀」という『隋書』の字を説明もなく「倭」と読み替えていることについて。
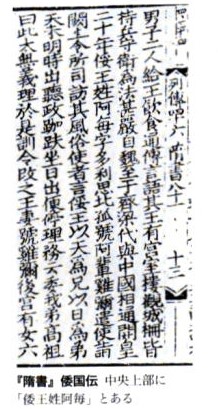 大津教授の『隋書』俀国伝に対する基本的な問題として、「俀国伝」を何ら説明もなく、「倭国伝」と変更されて話を進められることが上げられます。
大津教授の『隋書』俀国伝に対する基本的な問題として、「俀国伝」を何ら説明もなく、「倭国伝」と変更されて話を進められることが上げられます。
この大津教授の本の249頁に『隋書』の一部分の写真が左のように載せられています。そこには記事の3行目に「俀王」とはっきり出ています。 この『隋書』の部分コピーは大津教授の『天皇の歴史01 神話から歴史へ』に掲出されているものです。
明らかに”俀〈たい〉王” とあります。又、”多利思「北」孤”とあり、”タリシ「比」コでないことがはっきりと分かります。「俀」と「倭」は似ていますが別の字であることは間違いありません。
それなのに大津教授は、【 隋書に「倭王姓阿毎」とある】、などと理不尽にも強引に、「俀」を「倭」と読み替えさせます。
『後漢書』に記載のある「倭奴国」を「俀奴国」と『隋書』には記載しているので、意味としては倭国=俀国であることに違いないと思われます。しかし、読みは倭(ワ、ヰ)国、と俀(タイ)国と明らかに違うことと、『隋書』本文に、別の「倭国」と思われる国も登場しています。これについては後で、h)「遂に絶つ」問題で詳しく述べます。
この点を古田武彦氏は次のように指摘しています。
【「俀」その発音は「タイ」であり、『後漢書』にある「大倭王」の「大倭(タイヰ)」から「俀(タイ)」という国名になったのではないか。「大倭」という国名を隋の煬帝が小癪なといって、「弱い」という意味がある同じような発音の「俀」を使わせたのではないか】と。
大津教授は国際人として、例えば中国の古代史のシンポジウムなどで、俀国は倭国の書き誤りなどと説明したら、先方の正史の記述を理由もなくいい加減な史書とけなした、という問題に発展しかねません。俀=倭という説明をご自分の言葉でなさっていただきたい、と希望します。
(b)阿毎多利思北孤とは誰か、という問題
科書に必ず出ている「日出ずる処の天子書を日没する所の天子に致す恙無きや」の国書とそれを送ったとされる俀王「多利思北孤」とその太子の問題です。
【600年の第一次遣唐使は、『隋書』に、“倭王、姓は 阿毎 、字は多利思比孤、阿輩雞弥と号す、使を遣はして 闕に詣らしむ。”とある。
アメとタリシヒコを姓と名とするが、これは受け取った側の解釈で、本来「アメタ(ラ)リシヒコ」という倭王の称号と考えられる。意味は天の満ち足りた男子の意で、欽明天皇の 謚号にも「天を含むことから、この時「アメタラシヒコ」という称号があった。大王を天つ神の子孫とする思想が成立していたことをも傍証するというのが通説であろう。 】(p248)と大津教授は述べます。
しかし、大津教授は通説の、多利思比孤は推古天皇、若しくは代理の聖徳太子論を述べることなく、「倭王の称号」という一般論で、逃げています。
この古代史の一番の謎「多利思北孤とは誰か」という問題に正面から向き合えない東京大学国史学教授には情けない限りです。分からないなら分からないと率直に、『日本書紀』の編集者が継体天皇の没年について判断が出来ず、「後の世の人はよく調べかつ考えあわせて欲しい」と書き残していますが、それだけの分別もないのでしょうか。
正史の『隋書』に、姓は「阿毎」(アメもしくはアマでしょうか)と書いてあるのに、大津教授はそれは間違いではとされて、「アメタラシヒコ」と、全体が天皇の名前と推測の自説を述べられています。しかし、大津教授は書かれませんが、『隋書』だけでなく、次の正史『旧唐書』にも、その次の『新唐書』にも「姓は阿毎」とあります。
大津教授の国内の史学仲間には通じる議論なのかも知りませんが、国際的にとても通用しない議論ではないでしょうか。
とくに、多利思北孤は隋の煬帝に「国書」を出しているのです。当然「自署名」があったはず、と古田武彦氏は指摘されています。氏は「阿毎多利思北孤」の読みについて、「アメのタリシホコ、天の足りし矛」であろう。筑紫矛で知られた地の大王の名としてピッタリの名前、と言われます。 (『失われた九州王朝』より)
(c)太子利歌弥多弗利とは誰か
これについて大津教授は、聖徳太子である、と次のようにいわれます。
【『書紀』は推古天皇即位元年(593年)に「厩戸豊聡皇子を立てて皇太子とす。 仍りて 録さに摂政らしむ。万機を以て 悉に委ぬ。」と聖徳太子が皇太子について、摂政となったと明記する。(中略)
★裴清世問題について
「号は阿輩鶏彌」とあることについても大津教授は同様に、【天皇ないし大王の意味を説明したものだろう。読みはオホキミで当時の日本の君主号大王を記しているのだろう。】(p249)と、これもいい加減な史書の解釈をされて平然とされています。
この「阿輩鶏彌」の解釈方法は、隋の使者裴世清の対応についての解釈でも取り入れられています。
例えば、多利思北孤の号「阿輩鶏彌」の解釈で前にもちょっと書きましたが、【オホキミとよむ説と、アメキミと読む説がある。(中略)天皇ないし大王の意味を説明したものだろう。同じ『隋書』に「小徳阿輩台」に迎えさせたとあるのが、「大河内直糠手」の姓を記していることなどから、やはりオホキミで、当時の日本の君主号大王を記しているのだろう。 】(p249)というように。
つまり、裴世清を出迎えた我が国側の人名が『隋書』では小徳阿輩台と記していますが『日本書紀』にはその人物の名前はないのです。『日本書紀』の記事では次のようです。
【六〇八年隋朝は裴世清を俀国へ派遣することにした。四月に筑紫に、六月に難波津に、八月京へ、と裴世清はわが国にやってきた。】とあります。ところが、この時の応接した人物が『隋書』と『日本書紀』では丸で違うのです。
『隋書』では、「小徳阿輩臺、大礼可多毘(田扁に比)」と、『日本書紀』では、「難波吉士雄成、中臣宮地連鳥摩呂、大河内直糠手、船史王平、額田部連比羅夫、阿倍鳥臣、物部依網連抱」と人物名も人数も異なります。そして出迎えたのは『隋書』の「数百人、二百余騎という出迎え」、に対し『日本書紀』の「飾り船三十艘」と全く違うのです。
ところが、大津教授は、「阿輩鶏彌」の解釈に、阿輩台=大河内直糠手という前提で、【阿輩台は大河内直糠手の姓を記している、したがって阿輩鶏彌はオホキミで当時の日本の君主号を記している】、とされています。大河内云々の姓(直)がなぜ阿輩台と結びつくのか理解できませんし、“したがって阿輩鶏彌はオホキミで君主号”という説明はどう考えても論理的に納得出来ないものです。
普通に考えても、『隋書』が小徳という冠位を付けて紹介している人物を、出迎えた日本側の第三番目の人物と字の一字が似ている、「阿」と「河」の一字が似ているから、とその人物とすること自体がまず問題でしょう。おまけに難波吉士雄成は裴世清を送って行った人物で当然隋側にも知られていた人物ですから、出迎えにその「乎那利」が居たら書かないわけがないでしょう。
この問題に対し、岩波文庫隋書倭国伝石原道博訳には、【『北史』には何輩台とする。『日本書紀』巻二二にみえる掌客のひとり 大河内直糠手(オホシカウチノアタイヌカテ)の音の一部をあらわしたものか。難波雄成か。不詳。】と 説明があります。
岩波文庫でも「不詳 分からない」と しているのをそこのところは無視して、『北史』に阿輩台でなく何輩台とあることで、接待役の三番目の人物の名前のうち、読みが同じ「河」があるからといって、同一人と決め込んでしまう のです。その上で これを「阿輩雞彌」の意味するもの 云々と解釈を 発展させる、この論理の組み立て方の粗雑さ 強引さに呆れます。
そして、隋側は姓(君主の場合号)を記すようだから、阿輩雞彌は君主号である、と持って回った言い方をしています。つまり、真意は逆で、阿輩雞彌の説明にことよせて、阿輩台=大河内直糠手ということを納得させようとしているようです。
阿輩雞彌は君主号である、阿輩台も同様に号=姓であろう。従って、大河内直糠手の姓が阿輩台であってもおかしくない、と言いたいのでしょう。仮説の上の仮説でトンデモない結論が導かれているのです。
また、大津教授は言及していませんが、隋朝が俀国に派遣した斐世清と異なり、大和朝廷が記す斐世清は小野の妹子とともに渡来した唐からの使者なのです。従って、隋朝当時のと唐朝での斐世清の肩書は違っているのです。
斐世清の肩書は、隋では「文林郎」、唐では「 鴻廬寺の掌客」です。大津教授は、 斐世清の別々の二度の渡来を一緒くたにしているから混乱しているのです。
大津教授の論理の組み立て方が一方的と思えることの原因の最大のものは、中国の史書に我が国関係の記事があれば、『日本書紀』等の史書になくても、それは大和朝廷の業績である筈、という思い込みです。
例えば大津教授は、【 推古八年に『日本書紀』には隋へ遣使したことが記されていないが、『隋書』に倭国から遣使の記載があるので、遣使がなされた、】(p248)と、『日本書紀』に書かれていなくても中国の史書に遣使がされた、とあれば大和朝廷からの遣使に間違いない、と無条件にされていることが上げられます。
これについても先述のように、『隋書』には「俀国」からの派遣団について記録しているので、「大和朝廷」からのものではなかった、という簡単な理由なのですが、この簡単な理由が大津教授には理解不能のようなのです。
★俀国の兄弟政治について
俀国の政治のありようが『隋書』に書かれていることについて、大津教授は次のように述べます。
【倭王は使者に「天をもって兄となし、日をもって弟となす。夜が明ける前に出て政治を聴き、日が昇ると仕事をやめて、弟に委ねたと云う」と述べさせたが、隋の文帝に「これ太だ義理なし」として改めるように命じられた。この遣使自体が『書紀』に載っていないのは、倭王が未開の段階にあるとして隋の皇帝に叱られたことを恥じたためだろう。 】(p250)
このところの原文は「高祖曰此太無義理於是訓令改之」です。確かに、「 太だ義理なしと改めるように訓令した」としています。
しかし俀王がそれに従ったとはありません。それどころか、そのあと例の「日出づる処の天子日没する処の天子云々」の国書を出して煬帝を怒らせるのです。煬帝の「訓令」を聞いて改めた、とどうして大津教授は理解されるのでしょうか。
大津教授は先述のように、姉弟共同政治については多弁ですが、この兄弟政治については何も述べられません。俀国では仏法と俗事について役割分担している、と隋書は記しています。
金石文は第一級の史料といわれる大津教授ですが、法隆寺の釈迦三尊の光背銘については無視されます。そこに「上宮法皇」という語が刻まれていることは有名で、従来これは聖徳太子のこととされていました。辛巳などの紀年があり、多利思北孤と同時代の史料です。
この「法皇」と多利思北孤の関係はどうなのかとか、後世の上(法)皇と天皇との役割分担共存執政にも通じるところもあるのでは、とは素人考えでしょうが、大津教授には説明不能なのでしょうか、全く無視されるのは残念です。
★俀王多利思北孤の有名な国書について
「俀国伝」にある「日出づる処の天子云々」の国書についての大津教授の理解は、次のようです。
【(遣隋使の)第二回は、隋の煬帝が即位した後の大業三年、607年で、今度は形式が整っている。『隋書』によれば、使者は「海の西の菩薩天子が仏教をふたたび興隆させているのを聞いたので、使者を遣わし、僧侶数十人に仏法を学ばせてほしい」として有名な国書を提出する。
その国書に曰く「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す、 恙無きや、と云々」。帝これを 覧て 悦ばず、鴻臚卿に謂ひて曰く「蛮夷の書、礼無き者有り。復た以て聞するなかれ」と。 煬帝はこの国書をみて無礼だと怒ったのである。何故怒ったかについては、(諸説あるが)(中略)、しかし問題は、倭王が「天子」を名乗ったことだった。(中略)
倭は隋と対等という主張をしたのだが、では対等の外交だったといえるだろうか。『日本書紀』は推古十五年七月に「大礼小野臣妹子を大唐に遣わす、鞍作福利を以て通事とす」とだけ記し、この国書のことは、次の遣隋使のものは載せるのに、書いていない。(中略)
『日本書紀』が意図的に載せなかったのであり、倭王が「天子」を名乗る立場を撤回したためだったのだろう。それは、八世紀の日唐関係につながっていく。 】と。(p250~252)
多利思北孤の国書は『日本書紀』に載っていませんが、推古天皇から隋への国書について、大津教授は次のように言います。
【このような夜郎自大な倭の国書に煬帝は怒ったのだが、しかし翌年裴世清を小野妹子に伴なわせて倭に派遣した。(中略)
(推古天皇一五年)八月に唐客が入京し朝廷において出した国書は、『日本書紀』に記されている。それは「皇帝、倭皇を問ふ」で始まる、皇帝が蕃夷の首長に対して下す形式の図書であった。
この裴世清ほか十二名を送り返すためにもう一度妹子を遣わしたのが、608年の第三次遣隋使である。この時の国書は、『日本書紀』に載せられている(隋書にはみえない)。
「東の天皇、敬みて西の皇帝に白す。使人、鴻臚寺掌客裴世清等至りて、久しき 憶ひ、方に解けぬ。(中略)今大礼蘇因高、大礼乎那利等を遣はして往でしむ。謹みて白す、具さならず。」
この国書は、書簡体であるが、尊い人に恭しく出す形式である。「つつしみてもうす」は、へりくだった言い方で、前年の「書を致す」という対等の言い方に比べて、軌道修正したのは明らかである。】(p252)
以上の遣(隋)唐使や国書問題に見られるように、大津教授の解釈はしどろもどろで一貫した解釈が出来ていません。煬帝に怒られたので軌道修正した、など丸で子供騙しの説明です。
これはなぜか。『隋書』が記す「俀国」を「大和朝廷」と思いこんでしまっている為に生じた錯乱なのです。 『隋書』に記された俀国の国書と、『日本書紀』に記されている大和朝廷の国書は明らかに別の国書です。
多利思北孤の国書は対等の立場であり、『隋書』でもこの俀国は昔の俀奴国のころより通交のあった国という認識です。
しかし、『日本書紀』に書かれている国書は、単にへりくだっているというだけでなく、「久しき思い正に解けぬ」とあり、「以前から通交したいと思っていた願いが叶った」とか、使節の派遣が出来るようになったことを喜んでいるのです。
このことからも、大津教授が「第一回の遣隋使」と書かれている派遣団は大和朝廷からのものではなかった、ということになり、当然『日本書紀』には書かれていないのです。この様に大津教授が俀国と大和朝廷とを同一視していることからくる錯乱に、付き合わされる読者は迷惑極まりないといえましょう。
★冠位問題
冠位十二階と、大津教授が何故か『隋書』に記載されている官職、軍尼・伊尼翼に触れない問題です。 大津教授は中大兄皇子が定めたとされる冠位十二階について、次のように書きます。
【推古天皇十一年(603)十二月に「はじめて冠位を行ふ」として十二階の冠位を定め、翌年正月に冠位を諸臣に賜い、四月に「皇太子親ら肇めて憲法十七条作りたまふ」と矢継ぎ早に官人の秩序を定めた。
冠位十二階は、大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智からなり、徳という儒教の最高の徳目に、仁礼信義智の五常を加えて十二にしたもので、儒教をもとにした名称である。
これは『隋書』倭国伝にも「内官に十二等有り」として記されていて、推古朝に制定されたことは疑いないが、『隋書』は徳のあと、仁義礼智信の順にしていて、かえって中国にも通用するように、儒教徳目を用いたのであろう。 】(p241)と。
この『日本書紀』の記述のように、推古朝に冠位が定められたかどうかについて諸説があるようです。しかし、「諸説」とも根本のところの思い違いがあるのです。『隋書』の記述と『日本書紀』との食い違いは、『隋書』は「俀国」の冠位について書いていて、「大和朝廷」のことではないのです。違っていても別に不思議ではありません。
【 『隋書』に俀国に冠位制度があるとしているから大和朝廷に十二階の冠位が制定されたことは疑いない】という論理は今まで述べて来たように、基本が間違っているのでそれに基づいた大津教授の意見は的外れになってくるのです。 ですから『隋書』が記す俀国の官職についても説明が出来ないのです。
『隋書』には、俀国伝に書いてあるように地方官や軍管の職責が書いてあります。【軍尼が120人、丁度中国の牧宰のようだ。80戸に一伊尼翼を置くが今の里長のようなものである。10伊尼翼は一軍尼に属する。】と。
この、古代天皇の統治組織についての貴重な史料を一顧だにされない、大津教授のその姿勢には驚きを通り越して呆れます。
大津教授の先輩石母田正先生は、【隋書倭国伝の80戸に一伊尼翼を置き云々の記事は、その実数は別として、少なくとも大化前代の先進 地帯において、百姓の戸の地域的一般的な把握が行われたことを示しており、部民制の人民の族制的把握とは異なった支配類型の成立を示唆している。】(『日本古代国家論第一部』より) と述べています。
この石母田説には、「伊尼翼」を日本書紀にある「 稲置」にあわせて無理やり、「尼」を「な」、「翼」を「ぎ」と読むなど沢山の問題はありますが、ともかく問題には取り組まれています。 大津教授が置かれた立場からすると、先輩の姿勢を見習いかつ発展させる義務があると思うのですが。
★「遂に絶つ」と犬上御田鋤派遣問題
大津教授が俀国と大和朝廷を同じ国とされているために 、理解できない『隋書』の記事があります。その一つが大業六年の倭国(俀国ではない)朝貢記事と、もう一つが「俀国伝」の最後にある「この後遂に絶つ」の記事でしょう。
『隋書』本文では大業六年(推古十八年610年)に、「倭国」からの朝貢を記しているのです。この記事も『日本書紀』には載っていません。
大津教授は「第一回遣隋使」として、中国の記録にあったものは『日本書紀』になくても「大和朝廷」が行ったとされています。同じく中国の歴史書にあって『日本書紀』にない、この大業六年の遣使については何も言われないのは、首尾一貫を欠くと云われても仕方ないでしょう。
もっと重要なのは、「遂に絶つ問題」です。『隋書』「俀国伝」には、大業六年に俀王の使節が方物を献じた(裴世清が同行)、と書かれていて、その後に、印象的なフレーズ「この後遂に絶つ」と、俀国との通交が切れたことを記しています。
大津教授はご自分の手に負えないと思われたのか、この「遂に絶つ」のフレーズについて解説もなく紹介すらされません。俀国=大和朝廷とすると解けない問題なのです。もし、無理に解こうとしますと、「中国史書の書き間違い」という路線を歩まなければなりません。
大津教授は流石にそこまでは踏み切れずに、問題点があることを知らせないように「遂に絶つ」の記事を「見ない」ことで済ませようとされているのでしょう。大津教授が教えている学生さんたちはよく質問しないものだ、従順な学生さんばかりなのだろうか、と先々の国史学のために心配します。
『隋書』を素直に読めば、「俀国」と大和朝廷とは別の国であること、俀国が隋朝と関係を絶った時期に、別の倭人の国(大和朝廷)が継続して通交を求めていたことが分かるのにな、と思います。 従って、推古二十二年(六一四年)の大和朝廷の犬上御田鋤派遣記事が、『隋書』「俀国伝」に出ていないのは当たり前のことなのです。
しかし、大津教授は大略次のように述べます。
【推古二十二年(614年)に第四次遣隋使として犬上御田鋤らを派遣した。この年は煬帝が第三次高句麗遠征を強行した 年で、既に反乱がおきていたが、遠征終了時に本格的蜂起となる。(御田鋤らは翌二十三年帰国と記す)618年に隋煬帝が殺され唐の建国となるが、624年にはほぼ国内は治まり武徳律令を公布する。
この年に朝鮮三国はそろって隋の冊封を受ける。倭は、その二年前に聖徳太子が、その二年後に大臣蘇我馬子が亡くなり、推古朝の末年の倭は対応できなかったらしい。】(p267~268)
俀国は大和朝廷ではない、という理解ができれば、このような大津教授の理解 がピントはずれであることは明白となります 。
朝鮮三国は唐の冊封を受けたのになぜわが国が受けなかったのか。これはなにも聖徳太子や蘇我馬子の死亡とは関係なく、多利思北孤王は「俀国」が隋~唐に対して、此の時点では冊封を受けようという意思がなかった、「こちらも天子だ、同位だ」という意思の表れということでしょう。
(七) 『旧唐書』と我が国の歴史
時代は隋から唐へと代わり、『旧唐書』が重要な史書となります。 大津教授の歴史叙述を追って検討してきましたが、読者諸兄姉には分かり難くかったのではないか、と思います。 隋~唐の、七~八世紀の中国とわが国との通交を年表風にまとめてみます。
★中国との通交の記事一覧
600年 推古八 多利思北孤遣使 隋書
607年 大業三 多利思北孤国書持参の遣使 隋書
607年 推古一五 小野妹子派遣 日本書紀
608年 大業四 裴世清派遣 隋書
608年の のち (「遂に絶つ」の記事) 隋書
610年 大業六 倭国朝貢(俀国ではない) 隋書
614年 推古二二 犬上御田鋤派遣 日本書紀
618年 (唐の建国)
630年 舒明二 御田鋤・薬師惠日派遣 日本書紀
631年 貞観五 倭国遣使(俀国ではない) 旧唐書
631年 貞観五 高表仁派遣 王子と礼を争う 旧唐書
632年 舒明四 御田鋤と共に高表仁来国 日本書紀
633年 舒明五 高表仁帰国 日本書紀
644年 貞観一八 唐太祖高句麗侵攻 旧唐書
645年 貞観一九 倭国朝貢 旧唐書(日本書紀になし)
648年 貞観二二 倭国新羅に附して表を奉ず 旧唐書(日本書紀になし)
653年 白雉四 吉士長丹派遣 日本書紀
653年 白雉四 百済豊璋王子来朝(人質) 日本書紀
654年 白雉五 高向玄理派遣 日本書紀
654年 永徽五 倭国瑪瑙等を献ず 唐会要
659年 順慶四 斉明五 倭国蝦夷国と共に朝貢 冊府元亀・日本書紀
659年 順慶四 倭国日本国使節相争う 旧唐書
660年 順慶五 斉明六 百済鎮将蘇定法派遣(百済滅亡) 旧唐書・日本書紀
663年 天智二 (白村江の戦) 日本書紀・旧唐書
665年 麟徳二 (泰山の封禅の儀) 冊府元亀・旧唐書
670年 咸享元 倭国遣使 冊府元亀
701年 日本国遣使 大臣朝臣 冊府元亀
702年 長安二 大宝二 日本国遣使 旧唐書
703年 長安三 日本国遣使 粟田真人 旧唐書・続日本紀
713年 開元一 日本国遣使 阿倍仲麻呂 旧唐書・続日本紀
この年表を一見して驚くのは、中国正史と日本正史に同一記事があるのは、百済滅亡以降ということです。つまりそのあたりまでは、大和朝廷は日本列島の代表王者として認められていなかった、ということを示しているのです。(白村江の戦いを含む百済復興の戦については後述)
★高校教科書では
『旧唐書』の時代に入るまえに、この「日本の非常識」の俀王多利思北孤を推古天皇とする不合理な通説を生徒に教え込まなければならない、高校・中学の教師先生方の気持ちをご紹介しておきたいと思います。
石川昌康先生という河合塾の先生がいます。カリスマ的な人気を誇っています。
その先生の講義録を読んでみますと、この『隋書』の記事や「高句麗好太王碑」などで受験生に「おかしいんだけれど、(受験の為にはそこは目をつぶって)教科書のように覚えなさい」というように云っているわけです。石川先生の講義録を読んだ感想を報告します。
石川先生の日本史講義録に目を通しますと、改めて所謂通説が定説化されていることに、感心させられます。一九四六年生まれの石川先生は、予備校の歴史担当の先生の内で最も人気のある先生のようです。
石川先生は、教科書を受験生の頭の中に入れる作業を担当されているわけですから、教える内容がおかしいよ、といわれてもご自分の責任ではない分で、むしろ、理性では、理解できない歴史の定説なるものを、生徒に教えなければならない、その“とまどい”がこの講義録から窺えます。
例えば次のように述べられています。 まず好太王碑文の「倭」については、『考えてみれば変な話だね。日本国内では何が起こったかは文字史料ではわからないんだけれど、今の中国に碑が立っていて、大和政権の軍が攻めてきたことが記録されているわけですからね。』と。
つまり、日本書記などの日本の史書にまったく記載されていないのはどうもおかしいのですが、という感じで石川先生は説明されているわけです。
また隋書倭国伝に出てくる、倭王多利思北孤については、次のように言われます。
『六〇〇年に「倭王姓は阿毎、字は多利思比孤、阿輩雞弥と号す云々・・」 倭王が使いを送ってきた。「阿毎」、「多利思比孤」は天皇(大王)と考えておくしかない。(中略)文帝は役人に日本の様子を尋ねさせた。日本側には記録がないので、詳しくはわかりません。この時の倭王、倭の支配者は推古天皇ですけどね。使者の名もよくわからないし書いてあるのはただこれだけ。』
つまり、日本の史書には高句麗との熾烈な戦いは記録されていないのに、先方の金石文には倭国との戦いとして残っている。また、『隋書』の記載の倭王は、その時代の推古天皇は女性であるが、この俀王タリシヒコには妻もいる男王とある。この矛盾がある歴史記述を生徒に押し付けることへの、石川先生の戸惑いも露わな、忸怩たる思いが伝わって来ます。
このような現場の教師に戸惑いを生じさせる原凶は「文部科学省の学習指導要綱」であり、直接的に大津教授の考えではない、という理屈はあるかもしれません。しかし、東大国史学科の現役教授が主張していることが、学習指導要綱に大きな影響を与えるであろうことは言を待ちません。
筆者の高校生の孫の日本史Bの教科書をたまたま見かけ、古代のところを読んでみました。 倭王武・雄略天皇・稲荷山鉄剣銘の三題噺が出ているかと思ったら出ていません。出版社は三省堂でした。筆者が今までいわゆる「定説」の参考にしていた高校教科書は山川出版のもので、そこにはしっかりと「三題噺」が書き込まれていたのです。
だとすると、雄略=倭王武説に疑いを持つ執筆者グループもいるのでしょうか? ちなみに山川出版の方は東大系、三省堂は学芸大+私学系の執筆者陣でした。
★学習指導要綱では
ついでに我が国の古代史について「学習指導要綱」が教師たちにどのように教育するよう指示しているかについて記しておきます。
高等学校学習指導要綱日本史B
【(2)原始・古代の社会・文化と東アジア
原始社会の人々の生活の変化、大和朝廷による統一、律令に基づく古代国家の成立と推移及び文化の形成について、東アジア世界の動きとも関連付けて理解させる。
ア 日本文化の黎明
自然環境や大陸からの文化の影響による生活の変化に着目して、旧石器文化、縄文文化及び弥生文化の時代の社会について理解させる。
イ 古代国家の形成と東アジア
我が国における国家の形成と律令体制の確立の過程、隋・唐など東アジア世界との交流に着目して、古代国家の展開と古墳文化、天平文化などの文化の特色について理解させる。
ウ 古代国家の推移と社会の変化
東アジア世界との関係の変化、荘園・公領の動きや武士の台頭など地方の動向に着目して、古代国家の推移と国風文化の展開及び中世社会の萌芽について理解させる。】
この指導要綱の基本のところが心配です。
七世紀終わりまで「倭国と日本国が同時に日本列島に存在していた」ということを理解できないと、今までみてきましたように、大津教授というレッキとした東大教授でも、歴史認識がグチャグチャとなります。
まして、そのグチャグチャの教科書記述を学生に教え込もうとすると、教わる学生たちにとっては単に教科書の年号を暗記するだけの日本史の授業となる、という現状になってしまっているのです。
★『旧唐書』について
ところで、隋から唐へと王朝が変わります(618年)。『日本書紀』によれば、この時期の天皇は推古天皇(在位593~628年)です。その後欽明~皇極~孝徳~斉明(重祚)~天智(称制~即位)~天武~持統~文武~元明~元正~聖武(在位724~749年)あたりまでを大津教授はこの『天皇の歴史01 神話から歴史へ』で取り扱っています。
この時期の外国の史書としてはまず『旧唐書』が上げられます。大津教授の理解がどのようなものか見ていきますが、その前に読者の皆さんに『旧唐書』について若干説明しておきたいと思います。
この『旧唐書』の原文はあまり長くはないのですが、内容的に「倭国伝」「日本伝」というような二国の記録がある重要な史料といえましょう。一応読み下し文をまずご紹介して、そのあとで、この『旧唐書』を大津教授が、どのように説明されているのか、問題点としてどのようなことが上げられるのか、そのような手順で検討していきたいと思います。
『旧唐書』倭国日本国伝 (読み下し文は岩波文庫による)
〈倭国伝〉
倭国は古の倭奴国也。京師を去ること一万四千里、新羅東南の大海の中に在り、山島に依って居る。東西は五月行、南北は三月行。
世々中国と通ず。其の国居るに城郭無く、木を以て柵と為し、草を以て屋と為す。四面に小島、五十余国あり皆附属す。
其の王、姓は阿毎氏なり。一大率を置き諸国を検察させ皆之に畏れる。十二等の官を設けている。其の訴訟する者は、匍匐して進む。当地は女多く男少なし。
頗る文字有り、俗は仏法を敬う。皆跣足で、幅布でその前後を蔽う。貴人は錦帽を戴き、百姓は皆 椎髻〈にして冠帯無し。夫人の衣は純色・・・(中略)衣服の制は頗る新羅に類す。
貞觀五年(631年)、使いを遣して方物を献ず。太宗其の道の遠きをあわれみ、所司に勅して歳ごとに貢せしむること無し。
また、新州の刺使高表仁を遣わし、節を持って往きて之を撫せしむ。表仁 綏遠の才無く、王子と礼を争い、朝命を宣べずして還る。
二十二年(648年)に至り、また新羅に附し表を奉じて以て起居を通ず。
〈日本伝〉
日本国は倭国の別種なり。其の国日辺に在るを以て名と為す。或いは曰う、倭国自ら其の名の雅ならざるをにくみ、改めて日本と為すと。或いは云う、日本はもと小国、倭国の地を併せたりと。
其の人、入朝する者、多く自ら 矜大、實を以て 對えず。故に中国これを疑う。
又云う、其の国の界、東西南北各々数千里あり、西界南界はみな大海に至り、東界北界は大山ありて限りを為し、山外は 即ち毛人の国なり、と。
長安三年(703年)その大臣朝臣真人来たりて方物を貢す。朝臣真人とはなお中国の戸部尚書の如し。進徳冠を冠むりその頂きに花をなし、(中略)真人好んで経史を読み、文を属するを解し、容姿温雅なり。則天之を麟徳殿に宴し、司膳卿を授け、放ちて本国へ還らしむ。
開元の初(713年)、又、使を遣して来朝す。因って儒士に経を授けられんことを請う。四門助教趙玄黙に詔し、鴻臚寺に就いて之に教えしむ。(中略)得るところのたまもの、そのことごとくで文籍を買い、海に浮かんで還る。
其の偏使朝臣仲満、中国の風を慕い、因って留まりて去らず。姓名を改めて朝衡と為し、仕えて左補闕・儀王友を歴たり。衡、京師に留まること五十年、書籍を好み、放ちて郷に帰らしめしも、逗留して去らず。
貞元二十年(804年)使を遣して来朝す、学生橘免勢、学問僧空海を留む。(以下略)
★王子と礼を争った、その王子は誰
旧唐書の倭国の記事でまず目につくのは、「王子と礼を争った」という高表仁事件でしょう。 大津教授は【高表仁の父は隋建国の功臣で表仁自身も唐代になり、鴻臚卿(三品官)から新州刺史(四品官)と左遷されているが、当時の朝鮮三国の遣使は五、六品官であるのに対し、高いランクで重要な任務を担っていたと推測できる。
しかし、『日本書紀』は(632年)10月に難波で唐使を迎える儀礼を行ったと記したあと、翌年正月に突如帰国の記事に飛んでいて不自然な記述である。朝廷で起きたトラブルを意図的に隠ぺいしていることは、先の『旧唐書』の「王子と礼を争い云々」から明らかになる。この「王子」は、あてはまる適当な人物がいないから、『唐会要』や『新唐書』のテキストにある「王」かもしれない。
礼を争うというのは、たとえば天子を代表する唐使が上位で、殿上に登り南面し蕃国王は殿を降りて唐使に向かい北面して国書などを受けなければならないが、舒明はそうした礼を拒んだということだろう。】(p270~271要約) と書きます。
しかし、この高表仁の『日本書紀』の記事は『旧唐書』の記事とよく照らしてみると、同じ派遣と取れないのです。
『日本書紀』では、高表仁は632年8月に対馬に来て、難波に十月に到着しています。『旧唐書』は631年に高表仁を「倭国」に派遣し、王子と礼を争った、と書いているのです。
『日本書紀』では、大和に来て何のトラブルもなく、「高表仁も、風寒まじき日に船艘をよそおい迎え賜うことを悦ぶ、と言った」、というように『日本書紀』に書かれています。(なぜかこの『日本書紀』の「高表仁も悦んだ」という記事を大津教授は紹介していません。)
煬帝と多利思北孤王との不和は、『隋書』で俀国と「遂に絶つ」と書かれる結果に終わります。
この国交断絶の原因としては、『隋書』流求国伝にある、隋国による琉球侵略が考えられます。この件については割愛しますが、ともかく隋と大倭国とは国交が絶えるのです。
しかし、新しい唐王朝としては、向こうから貢物を持ってきた機会を利用して、過去の関係修復の可能を探ることが必要でした。それが高表仁の主任務であったと見るのが自然でしょう。
『旧唐書』の記事を素直に読めば、日出づる処の天子の王子は、倭王と唐の天子とは対等、という立場を崩さず、「礼を争い」不首尾に終わった、とすんなり理解できます。
この件でも、二つの国があったとしなければこの大津教授のように、【当時の舒明には王子がいない、「王子」でなく対応したのは「王」であったのでは、舒明天皇だったのでは】、などと『旧唐書』の書き間違い、という路線に進まないと説明が不可能になるのです。
前に指摘しています様に、この時期の大和朝廷は舒明期ですが、『旧唐書』を素直に読むと、「王」は「姓は阿毎」と『隋書』でいう俀王多利思北孤王の姓を記しています。つまり、多利思北孤王の系列の王であったと思われます。
大津教授は金石文は重要な第一史料とおっしゃりながら、法隆寺の釈迦三尊の光背銘については全く言及されません。詳しくは古田武彦氏の『法隆寺の中の九州王朝』で解析されていますが、その中に「上宮法皇が辛巳の翌年に亡くなった」という記事があります。それは「多利思北孤王が622年に亡くなった」と論証されています。
それに従うと、高表仁が派遣された631には多利思北孤王は亡くなり、利皇子の時代になっていたことでしょう。利皇子の又その王子などの資料は残っていませんが、「阿毎」一族であることは間違いないことでしょう。
中国の史書に書かれていることは、700年以前は『日本書紀』になく、『日本書紀』に書かれていることは中国の正史には書かれていません。『隋書』の「俀国」(『旧唐書』の「倭国」)と、『旧唐書』の大和王朝の「日本国」と、中国の正史では別国として書き分けられていることが歴然としています。
ところで、この『旧唐書』の「倭国伝」と「日本伝」の記事によると、648~703年の記事がありません。これは本紀によっていくらか補完することが出来ます。
この間の最大の事件は663年の白村江の敗戦で終わる百済復興の戦いです。そこで、『隋書』にある「俀国」(大倭国)が消滅し、もう一つの倭種の国によって併合され、名前も「日本」になった、というわけです。(日本国の起源については後述)
『旧唐書』を読みますと、粟田真人や阿倍仲麻呂の人物の資質が中国側に気に入られたことが良く分かります。特に阿倍仲麻呂は朝衡と中国名を名乗り、中国の官僚になって五十年を過ごしています。日本の情報について中国朝廷に、いろいろと意見具申をしたであろうことは間違いないことでしょう。そのせいでしょうが、「倭国」の領域、「日本国」の領域については間違いようのない記述です。
『旧唐書』の東夷伝以外で、本紀にもわが国関係記事がありますので補完用に記しておきます。
●(本紀巻四、高宗上)永徽五年(654年)倭国、琥珀・碼碯を献ず。
●(本紀巻六、則天皇后)長安二年(702年)日本国、使いを遣して方物を貢す。
この「本紀」記事をみましても、明らかに「倭国」「日本国」が700年あたりを境に書き分けられています。日本列島の主役の交代、「倭国(九州王朝)」と「日本国(大和王朝)」の交替はこの間に行われたのは確実と思われます。
★泰山封禅の儀
ところで、唐朝の国際的イベント「泰山封禅の儀」の参加者リストから、当時の倭国の国際的な位置などが判断できるのではないかと思われます。大津教授は、泰山封禅の儀について次のように書きます。
【『日本書紀』は劉徳高の帰国のあとに、「是歳、小錦守君大石等を大唐に遣はすと云々」と記し、第五次遣唐使が派遣された。守君大石は百済救援軍の後将軍に任じられた人物である。
また注には、第三次遣唐使で派遣された坂合部連石積なども使節団にいたと記し「蓋し唐の使人を送るか」とあって、送使にすぎないとする。本文の「云々」との書き方も、これが正式の使者ではないかのような書きぶりである。それはこの使節が『書紀』としては記したくない、屈辱的な任務を負ったからだろう。
高宗は、百済を滅ぼし倭を破った翌664年7月に、二年後の正月に山東省の名山泰山において封禅の儀をおこなうことを予告した。(中略)665年の劉徳高、あるいは前年の郭務悰の使命の一つは、この封禅への参加を促すことだったのだろう。
『冊府元亀』巻981に、665年の百済と新羅との会盟を記したあと、是に於いて、仁軌、新羅・百済・耽羅・倭人四国の使を領して、海に浮かびて西に還り、以て太山の下に赴く、と記す。(中略)
『冊府元亀』巻36によれば、前年10月に洛陽を出発した高宗の行列には、突厥・ 于闐・波斯など多くの使者が従った。そこには倭・新羅・百済も従ったとあるが、それは泰山の下で合流したと考えても構わないだろう。
百済征討を機に実現した今回の封禅には、倭と朝鮮諸国の使者の参加は不可欠であろう。その使者に敗軍の将、救援軍将軍だった守君大石があたったのは実に適任だった。まさに服属儀礼だったのである。
したがって派遣は12月では遅すぎ、唐使の送使ではない。 】と。(p317~318)
これは、大津教授は何を言いたいのでしょうか。余程このあたりの事情が分かっている専門家でないと理解できないと思います。
この辺の事情を説明しますと、一つには、守君大石は時間的に泰山封禅の儀に間に合わなかったのでは、ということがあります。666年の泰山封禅の儀には、後に唐軍と共に突如帰国する「筑紫君薩夜麻」が倭国の代表として参加したのではないか、という説に暗に反論をしたものでしょう。尚、薩夜麻の帰国は天智十年(671)です。
中国史書には、泰山封禅の儀には倭国酋長が参加、と書かれています。守君大石では役不足ではないか、という意見にも一生懸命反論している感じです。
古田武彦氏は守君大石では役不足というだけでなく、この儀式に間に合わなかった、「倭国」の代表として参加したのは白村江で捕虜になった筑紫君薩夜麻であろう、と『失われた九州王朝』でつぎのように大略述べています。
【『冊府元亀』によると、六六五年十月に洛陽を発った高宗に従駕した夷蕃諸国の中に「倭国」も加わっている。
「麟徳二年十月丁卯、帝、東都を発し東嶽に赴く。従駕の文武の兵士及び儀仗・法物相継ぐこと数百里。営を列し幕を置き、あまねく郊原に亘る。 突闕〈・于闐〈・波斯〈・天竺・罽賓〈・烏萇〈・崑崙〈・倭国、及び新羅・百済・高麗等、諸蕃の酋長、各、その属を率いて扈従す。・・・十二月丙午、斉州に至りて停ま〉ること十日。丙辰、霊厳の頓〈を発し、太嶽の下に至る。」とある。
ところが『日本書紀』天智紀にはこれに対応する記事が無い。この絢爛たる盛儀に大和天皇家の使者が参列していたとすれば、それに関した記事が皆無であることは不可解きわまりない。
わずかにこの年の十二月に十四日以後に帰国した劉徳高に随行したとみられる守君大石の記事があるだけである。 十二月に出かけた守君大石が、十月に泰山に向かう倭国の代表ではあり得ない。明年一月の泰山封禅の儀に十二月十四日以降に出発したのでは到底間に合わない。
第一、高宗の命は、十月に洛陽に到着し、高宗に随行せよ、ということだった。 「駆けつけて間に合えばいい」と言った 体のものではない。通説では、(棟上 注:大津教授も同様です。)泰山の麓 で合流出来ればよい、と辻褄を合せているが、一年半前から予告されていた盛儀に「遅参」という理由は通らないだろう。
通説の諸学者の混乱の原因はハッキリしている。“「倭国」の国使とは大和朝廷の使者以外にない”こういう「不動の信念」がこの問題を考究する諸学者を苦境に追い込んだ真犯人なのである。
この泰山の封 禅の儀は『日本書紀』の編纂のわずか五十五年前の出来事がなぜ記されていないのか。しかし、これはなんら解きがたいものではない。唐朝が「倭国」と呼んでいるのは大和王朝ではない九州にあった 多利思北孤王の流れをくむ王朝であったのだ。
その泰山の封禅の儀に参列した「倭国」の代表者は百済復興戦で捕虜になった筑紫君薩夜麻であった。だから『日本書紀』に記事が無いのは当然のことだ。 】
この古田武彦氏の説明の方が大津教授の説明よりも、はるかに論理的な推論といえるでしょう。
★第一次遣唐使問題(『旧唐書』には記載がない)
「王子と礼を争う」のところで述べましたが、高表仁が送ってきた犬上御田鋤の派遣を、大津教授は次のように第一次遣唐使とされます。
しかし、この大和朝廷からの派遣記事は中国側の記録にないのです。 【舒明は即位すると、すぐに二年(630)八月に御田鋤と薬師惠日を第一次遣唐使として派遣する。(中略)『旧唐書』巻一九九倭国伝には、貞観五年、使いを遣はして方物を献ず。太宗その道の遠きを 矜(あわ)れみ、所司に勅して歳貢せしむるなし。 (中略)太宗は、倭の遣使に対して毎歳朝貢する義務を免除した。 】(p269)
この『旧唐書』に書かれている「倭国」は今まで見て来たように、『隋書』「俀国伝」にある「俀国」であり、「大和朝廷」の国ではないのです。安易に『隋書』の「俀国」を「倭国」と読み替えたことが、『旧唐書』東夷伝倭国条の当事国を間違ってしまったのです。
「大和朝廷」は『旧唐書』東夷伝日本国条に書かれています。 大津教授が云われる「第一次遣唐使」は、貞観五年(631)では時期が合わないのです。残念ながら、『旧唐書』の「倭国」が派遣したものではなく、唐王朝が未公認の大和朝廷が派遣したものだったので、『旧唐書』という正史に記録されなかったのです。
ですから、大津教授が続けて書かれる、
【 しかし第二次の遣唐使は白雉四年(653)五月の 吉士長丹〈きしのながに〉を大使とする二船の派遣である。毎年朝貢しなくてよいといわれたとはいえ、20年以上の空白は異様である。太宗の意向を拒んだ(舒明が冊封を受けなかったと思われること)こともあり、トラブルの余波が残り太宗在位中は遣使できなかったのであろう。 】(p272)
というような見当違いの大津教授の感想となるのです。
この653年の遣使についても、先の『旧唐書』に記録がありません。何度も言いますが、まだ大和朝廷は倭人の国の代表として認めて貰っていないので従って、「舒明が冊封を受けなかった」のではなく、「多利思北孤が冊封を受けなかった」のです。
★「倭国」と「日本国」は別の国
この「倭国」と「日本国」が別の国だ、ということは、大津教授がこの本で何度も引用される中国の別の史書『冊府元亀』にも書かれています。
大津教授は都合が悪いと思われたのか、この部分を引用されていませんので紹介しておきます。
☆【日本国は倭国の別種なり。其の国、日辺に在るを以ての故に、日本を以て名と為す】とあります。(『冊府元亀)外臣部、種族)
および、 ☆【咸亨元年(670年)三月、罽賓国、方物を献ず。倭国王使いを遣し、高麗を平ぐるを賀す。
長安元年(701年)十月、日本国使いを遣し、其の大臣朝臣、人を貢し方物を献ず。】(冊府元亀外臣部 朝貢三)と記しています。
日本国は倭国の別種・670年は倭国・701年は日本国と、ちゃんと書き別けています。
『旧唐書』の「倭国」と「日本国」の書き分けの件で、鑑真上人の『唐大和上東征伝』にその書き分けの事実が鑑真上人の言葉として出ています。
『倭国とはII』(九州古代史の会編集)で荒金卓也氏が紹介している『唐大和上東征伝』の、「倭国」「日本国」に関係する箇所は次のところです。 僧栄叡と普照が唐に行き、鑑真上人を日本に来てもらうべく訪れた時のシーンに、「倭国」と「日本国」が次のように述べられています。
【栄叡師らは大明寺をおとずれて大和上の足下にひれ伏して頭を地に付けて拝み、つぶさに次のように言った。
「仏法は東に流れ 日本国に到りましたが、その法は有っても仏法を伝え広める人がいません。本国には昔、聖徳太子という人がいまして、“二百年の後に、聖教が日本に興きる”と言いました。現在、この運びにあり大和上に東遊のうえ教化をお願いするものです」と。
大和上はこう答えました。「昔聞いたのだが、南岳の思禅師が死に際にあたって、“死んだ後は 倭国の皇子に生れ変り仏法を興隆し衆生を済度する”と」
「また、 日本国の長屋王は仏法を崇敬して千の袈裟を造って、中国の大徳衆僧に施したと聞く。云々」】
参考に原文もあげておきます。
【榮叡普照至大明寺,頂礼大和上足下,具述本意曰:佛法東流至日本國,雖有其法而无傳法人。本國昔有聖德太子,曰:二百年後,聖教興於日本。今鍾此運,願和上東游興化。大和上曰:昔聞南岳思禪師遷化之後託生倭國王子,興隆佛法,濟度衆生。又聞日本國長屋王崇敬佛法,造千袈裟,來施此國大德衆僧。】
このように、昔の「倭国の太子」のリカミタフリと、今の日本国の長屋王と、ちゃんと書き別けていると思います。ただ、大津教授の「倭国から日本国に名前が変わった」という説を完全に否定できるかと迄は言えないようですが、一つの傍証にはなると思います。
★『新唐書』にみえる「倭国」と「日本国」
ところで大津教授は、『新唐書』については後述の「蝦夷朝貢問題」で引用されるだけで、他は何も述べられていません。
『新唐書』は『旧唐書』が書かれて115年後の1060年に、「唐の後期部分が旧唐書の記事は不十分」ということで書かれたものです。そこには、AD701年以前の出来事は「倭国」、その後の記事は「日本国」と書き別けられています。
大津教授は平安時代に書かれた中国の史書だとして参考にされていないのかも知れませんが、「倭国」と「日本国」という問題は七世紀のことですから参照されるべきと思います。
例えば、【『新唐書』「百済伝」では、白村江の戦いを叙述する際、高麗・倭と連和す。とか(百済の偽王子)残衆及び倭人を率いて命を請う。】のように、まだ「倭国」です。 また、「倭国」は筑紫城を本拠とし、代々「阿毎」を名乗り、その三十二代に分流が大和州に移りその初代が神武天皇、というように書いています。
原文は次の通りです。 【其王姓阿毎氏、自言初主號天御中主、至彦瀲、凡三十二世、皆以「尊」為號、居筑紫城。彦瀲子神武立、更以「天皇」為號、徙治大和州。】
このように、「倭国」と「日本国」は、明らかに別の国として中国では認識されていることがはっきりします。大津教授のように、「倭国」から「日本国」へと単に名前が変わっただけ、という認識では、その説かれる歴史物語は、真実に程遠いものとならざるを得ないでしょう。
そのような目で大津教授の説かれる所を見ていきますと、いろいろと「皮」が剥げていくことになります。
次いで、大津教授の「大化の改新」・「蝦夷国遣使問題」・「百済救援の意図」・「白村江の戦い」・「その戦後処理」・「天智天皇(称制)の甲子の宣」についての考えを見ていきます。
★大化改新と郡評問題について
古田武彦氏は、「倭国」の消滅と「郡評問題」について次のように説明します。
【隣国の『旧唐書』『新唐書』のいずれもが八世紀初頭の「倭国」の「日本国」の併呑を記録しています。 また、わが国の地下から出土する木簡類が明白に語るように、七〇一年をもって「評制」が終了し「郡制」となっている。しかし、『日本書紀』には全く書かれていない。つまり「評制」を隠したのです。】(『失われた日本』「不動のONライン」より抜粋)
大津教授はこのことについて、【戦後、大化の改新の詔で置くとしている郡・郡の大領・少領という用字がそのままかという検討を中心に研究が深められた。
『日本書紀』以外の金石文や古系図によると、大宝令〈以前には郡ではなく評〈が置かれ、評造〈あるいは評督〈・助督〈の官がみられ、改新詔はのちの大宝令によって大きく修飾され、原詔そのままでないことが井上光貞氏によって論じられた。
のちに藤原宮の発掘によって出土した木簡により、701年を境にそれまでの評が郡に変わることが明らかになり、改新詔には評とあったのが大宝令により郡と修飾されたことが確かめられ、この郡評論争に決着がついた。(中略)
『常陸国 風土記』を分析した鎌田元一氏などにより孝徳朝に全国に評が設置されたこと 天下立評が解明された。 】(p281)と述べます。
これは全く「歴史学者」と思われない叙述です。「評」は誰が何時定めたのでしょうか。「郡」を定めたことは『日本書紀』に書かれていますが、「評」については全く書かれていません。
大津教授がいう「評造」という語は『常陸国風土記』から引っ張りだされたのでしょうが、正史『日本書紀』にはありません。評督など大和朝廷が定めたという記録がないものを、“出土した木簡により評が郡に変わることが明らかになった”というのは、本末転倒ではないでしょうか。
“出土した木簡で明らかになったのは、『日本書紀』に書かれていない「評」という制度があった”、ということだけです。
「評督」なども上げられますが、『日本書紀』にもある「筑紫都督府」との関連、「評督」と「都督」との関連などにも考えを巡らしてほしいものです。大先輩坂本太郎博士の真摯な郡評問題への取組み方を見習ってほしいものです。
この坂本博士の郡評問題論争について説明しておきます。
『日本書紀』では大化改新(646年)で「郡」という統治組織があるようになっていますが、出土する木簡には700年までの木簡には全て「評」と書かれているのです。それに各地の風土記にも、大津教授が紹介する常陸国風土記のように、「評」とあって「郡」ではないのです。
かって、古代史学会では坂本太郎・井上光貞の師弟論争がありました。津田左右吉博士が、改新之詔の信憑性を疑う論文を昭和初期に発表され、それに対して坂本太郎氏が反論し昭和十三年に「改新之詔」の信憑性は保証される、という論文を発表されました。
この坂本論文に対して再批判したのが弟子の井上光貞氏で、昭和26年に東京大学史学会の発表会が坂本太郎博士の司会の下で行われました。
井上氏は「大化改新詔の信憑性」という題で、「郡司」や「郡」などが大化改新詔で使われているが、各種の金石文や史料に「評」「評督」等が出ている、と反論。
その後坂本博士の再反論、井上氏の再々反論があり、結局藤原宮跡から出土した木簡から、文武四年(700)以前は「評」以後は「郡」とあり、井上説が正しい、という決着となったのです。
しかし、坂本博士は、自説が誤っていたことを認められた上で、【『日本書紀』がどうして「郡」という字に限って「評」という字を使わないで、後世の用字(郡)を原則としたか、という疑問を私は未だに捨てることができない。】と『古代史の道 考証史学六十年』という著書で述べていることを古田武彦氏は紹介しています。(『法隆寺の中の九州王朝』第六部権力の交替と郡評論争 より)
そのように、「郡評論争」は終わっていないのです。
大津教授は、【風土記や金石文に「評」とあるが、大宝律令以降では「郡」となっている。従って「大宝」以前は「評」、以降は「郡」になったのは明らか】、という論の進め方です。
しかし、大宝律令では「評を廃して郡と為す」というような文言はみえません。何時誰がどのようにして「評」を「郡」にしたのかわかっていないのが実情です。『日本書紀』孝徳紀になぜ「郡」だけが用いられ、実際に使われていた「評」や「評督」が使われないのでしょうか。その研究は続けられなければならないでしょう。
同じことが「県」についても言えます。『古事記』や「風土記」には多くの地方統治組織単位の「県」が出てきます。『天皇の歴史』に無関係と思えないのですが、大津教授はこの方面にはなぜか無関心のようなのは理解に苦しみます。
大津教授は「金石文は第一史料」と言われます。井上先輩も取り上げている、那須国造碑に見られる「評督」について、大津教授は全く無言です。これでは二枚舌と謗られてもしかたないのではないでしょうか。
★蝦夷国遣使問題
蝦夷国遣使問題について大津教授の書かれているところを読んでみます。
【斉明五年(659)、第四次遣唐使が派遣されるが、このとき、道奥の蝦夷男女二人を連れていき、唐の天子に見せている。(中略)
「伊吉連博徳書」という遣唐使随員の手記には皇帝との問答が残っていて、ここに居るのは我々に近い熟蝦夷で毎歳わが国の朝廷に入貢します、などと話している。『新唐書』日本伝には、天智が立った明年のこととするが、「使者、蝦夷人と偕に朝す」とある。この倭の使者の答えは、誇張も多く、また毎歳朝貢するとあるのも事実ではない。
しかし、倭が異民族の蝦夷を朝貢させているという主張は、ただ蝦夷を連れて行って唐の皇帝を喜ばせるためだけではなく、自らの国力の誇示にも繋がっていたのである。 中国は自国を中華とし、周辺諸国を蕃国・夷狄として朝貢させる構造をとり、日本なども国家形成にあたっては同じ国家モデルを目指したのである。
倭は「任那」と称する加羅・加耶地域への支配権を主張していたが、562年の任那の滅亡以降、「任那の調」を献上させることで、「任那」が日本に服属する形式を維持した。
しかし、大化二年(六四六)に至り「任那の調」を廃止した。おそらくこのことに関わり、蝦夷の朝貢は、斉明朝の大和政権の帝国構造を支えるものとして重視されたのであろう。 】(p308~309)
しかし、蝦夷国問題は、『旧唐書』の記事にはないのですが、『冊府元亀』には出てきています。
そこに書かれている「蝦夷」についての記事は、基本的なところで『日本書紀』の記述と異なる、と古田武彦氏が次のように指摘しています。(『失われた九州王朝』第五章九州王朝の領域と消滅 より)
【顕慶四年(659年)十月、蝦夷国、倭国の使いに従いて入朝す。と『冊府元亀』に書かれている。つまり「蝦夷国」の国使として入朝した、と言っている。
これは、『日本書紀』の「伊吉連博徳書」によると、唐の天子は「此等蝦夷国有方」(蝦夷国はどの方向に有るのか)と聞いている。この点、『冊府元亀』と同様に「蝦夷国」という“国号”でとらえている。
それを『日本書紀』の編者は“蝦夷の男女を大和朝廷からの献上物”のような蔑視的表現に書き換えている、】と。
大津教授はそのような『日本書紀』の史料批判も行わず、『日本書紀』編者と同様な目線で判断されているのは、現在の国史学最高峰の現職教授であられるのに、誠に残念です。
★百済救援の意図(白村江の戦い)
なぜわが国が百済を救援したのか、その意図を大津教授は次のように述べます。
【高宗は655年以来の高句麗征討が成果を得られず、高句麗の同盟国百済を先に討つ作戦にでた。(中略)義慈王は七月に唐軍に降り百済は滅んだ。(中略)このあと百済遺臣の救援要請をうけて、倭は出兵し、唐・新羅軍に敗れるが、どうして百済復興に大軍を出兵したのだろうか。
改新政権は、親新羅・唐と明瞭にいえるかは別にしても、唐留学経験者をブレーンとし、新羅を経由して唐との関係改善を試みている。東アジア情勢を熟知していながら、なぜあえて戦ったのだろうか。
白雉五年(654)の第三次遣唐使は『唐会要』巻九九に記事が残る。“使を遣はして琥珀・瑪瑙を献ず(中略)。高宗、書を降して之を慰撫し、 仍りて云はく「王の国は新羅と接近す。新羅素と高麗・百済の侵す所となる。若し危急有らば、王宜しく兵を遣はして之を救ふべし」”と。(中略)
前年の第二次遣唐使が百済経由で、今回は翌年に新羅経由で派遣されていて、外交方針の乱れも感じられる。もし戦いになったら新羅を助けて出兵せよとの高宗の言葉は、結果としては黙殺された。しかし政権としてはある段階まではどちらにもつかず、中立または不介入の立場だったように思う。 】(p310~311)
大津教授が「第三次遣唐使」とされる使節は、『旧唐書』本紀に記載されていず『唐会要』という史書に書かれています。
ただ、『唐会要』(1050年頃成立)の他の記事などが、『旧唐書』(945年成立)とは、特に年月日で大きく違っているので、大津教授が云われるように「第三次遣唐使」と決めつけてよいのか疑問があります。
例えば、高表仁の来日について、『旧唐書』では貞観五年(631年)ですが、『唐会要』では貞観十五年(641年)というように十年も違っています。そのように史料としては間違いの多い『唐会要』ですが、そのことは一応置いて、この記事の内容からみますと、この使節は大和朝廷が派遣したものだろうと推測されます。
ですから「倭国」を倭人国の代表国としている正史『旧唐書』には掲載されていないのではないかと思われます。
唐と北方で覇権を争う高句麗と、その高句麗と通じる百済を敵視し、それに連なる「倭国」、それらを牽制するために新羅を助けたい、そのために新興国「日本」の意向打診、という唐朝の意図が見えみえな記事です。
大津教授のように頭脳明晰と思われる方が、なぜこのような東アジアの当時の政治状況を描き間違うのか、不思議にさえ思われます。 先述のように、この第三次遣唐使と大津教授が云われる派遣団は、日本国(近畿)が送ったもので、高宗とすれば百済・高句麗連合軍が新羅侵攻時に「日本国」に対してその反応を打診してみたものでしょう。
倭国と日本国という旧唐書の記述をそのまま理解すれば、何故戦ったのか?という疑問は氷解するのです。日本国は多数の兵を送ったと『日本書紀』は書いていますが、大和朝廷側の名だたる将軍の戦死や捕虜について全く記していません。ところが、筑紫君薩野馬という九州に関係する王族が捕虜となっていて、突如帰国する、という『日本書紀』の記事となっています。
この記事以外筑紫君については、『日本書紀』には全く説明が無いのです。後の『続日本紀』で、部下が身売りして帰国させた、というあまり芳しからぬ記事があるのみです。
斉明の死を奇貨として軍を引いたことが、大和朝廷が存続できた大きな理由と思います。
「倭国と百済」との長年にわたるいわば同盟国と「唐と新羅」との戦いなのですが、この四国の関係は次のような状況でした。
長年中国に歯向かっている高句麗と百済との関係がまず上げられます。百済の扶余王朝は高句麗の分派という歴史的事実があります。中国は、その百済の存在が高句麗攻略の障害になっているので取り除かなければならないと思っていました。そこに、百済と新羅の国境を巡る争いが始まりました。
新羅は百済とその同盟国「倭国」と単独で戦うのは状況不利と見て、唐に仲裁というか救済を求めたのです。唐は良い機会とばかりに、大水軍を送って百済を襲い、国王義慈王や大臣たちを捕え中国に連れ帰ったのです。ここで百済は滅亡したわけです。
「倭国」はかねての約定に従い百済王子豊章を立てて義勇軍として出ていったのです。かねてより「天子」を名乗る「倭国」を目の 敵と思っていた中国は良い機会と思ったことでしょう。再び旧百済の地に大水軍を送り、州柔の陸戦・白村江の海戦に大勝し、「倭国」を叩くことに成功した、ということです。
これに「大和朝廷」が、かなりの将兵を派遣したように『日本書紀』は書いていますが、実体はどうだったのでしょうか。白村江の戦の八年のちに「筑紫君薩夜麻」が唐の使節団と一緒にいわば先触れとして帰国してきます。
「筑紫君」とは、筑紫君薩夜麻以外に史書に出ている人物として筑紫君磐井、筑紫君葛子、筑紫君の火児などがありいずれも筑紫王者(『日本書紀』の立場としては地方の豪族としている)です。この筑紫の王者が捕虜となり敗戦になったこと自体が、この戦いは九州を地盤とする「倭国」が主体の戦いであったことの傍証といえるでしょう。
これに関して、備中国風土記(逸文)に邇磨郷について次のようにあります。【 「斉明天皇西征の時、従行した中大兄皇子が或る郷に下船したところ、村人の意気軒昂なる様を見て斉明天皇に申し上げた。天皇は詔を下し此の村で軍士を徴したところ、たちどころに精兵二万人を得て大層悦んだ。後に、天皇は朝倉宮で崩じたので、終に此の軍は遣はされなかった。】 とあります。
人数については多すぎるように思われ、地名のニマに懸けて二万としたものでしょうが、斉明が亡くなって、この徴ぜられた兵士達が行かずに済んだ、というのは事実を伝えているといえましょう。 これも、大和朝廷が斉明天皇の喪に伏すという理由で中大兄皇子が兵を引いたこと、への傍証となるでしょう。
★白村江の敗戦の戦後処理
旧唐書に見られる、百済復興の試みの挫折による「倭国」の消滅と「日本国」の正史への登場の時期について、大津教授の記述の概略をまずご紹介します。
【斉明天皇は百済支援に積極的であったが六六一年に亡くなる。『万葉集』を代表する額田王の名作、「熟田津に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今はこぎいでな」 は(中略)額田王が女帝に代って詠んだもので、西へ出航しようと全軍を鼓舞した歌である。『万葉集』をみると、女帝自身が積極的だったように感じられる。
『日本書紀』斉明六年十月条の注には、在る本に云はく、天皇豊璋を立てて 王〈とし、塞上(その弟)を立てて輔として、礼を以て発て遣はす、といふ。とあって、斉明天皇が豊璋を王に任命し、輔相も定めたことがみえる。 】(p312~313)
そして大津教授は、斉明歿後の天智の方針として次のように書きます。
【斉明の死去をうけて、661年七月に中大兄皇子は、称制して「水表(海外の意)の軍政〈」をとり、遠征軍を編成し、九月に別働隊五千余を派遣し豊璋を百済に送らせる。(中略)
翌天智元年には天皇の宣勅という形で百済王を即位させ、鬼室福信には爵禄を与えている。(中略)単なる百済の救済ではなく、唐に代わって倭の服属国を作ろうとしたのであろう。これが救援を決めた理由であろうが、唐を敵に回して戦うということの状況判断が甘かったことはいうまでもない。】(p313)
ところで大津教授は、何故か天智の「称制」という『天皇の歴史』に大いに関係があると思われる出来事に対して、何ら説明をされません。「七年間もの天皇不在」という異常事態であったわけですから、『天皇の歴史』というタイトルの本なのですし、大津教授は、最近の流行語ではありませんが、「説明責任」があるのではないでしょうか。
大津教授は、白村江の戦いについて、『日本書紀』と『旧唐書』の劉仁軌伝の記事を引用しながら状況を記述します。
【百済復興軍は、最初は連戦連勝であったが、唐が新たに七千人を派遣し新羅にも出動を命じ、豊璋と鬼室福信の間の内紛もあり形勢は逆転する。
唐・新羅軍は水陸両軍を率いて錦江(白江)下流で合流し、663年八月に 周留[州柔〈]城に迫った。このとき劉仁軌率いる唐の水軍が「白江口」で倭兵と遭遇し、決戦に及び、倭・百済軍の大敗に終わる。
『旧唐書』劉仁軌伝には「倭船四百艘を焚く。煙焔は天に漲り、海水皆赤し」とある。九月に周留城が降伏し、「百済の名、今日に絶えぬ」と『書紀』に記される。 】(p313~314)
大津教授は百済復興戦に負けたあとの戦後処理について次のように書きます。
【白村江の戦いの翌664年、唐は劉仁願を百済の鎮将とし、旧百済国の太子扶余隆を熊津都督とした。(中略)二月に扶余隆は新羅の文武王の弟金仁問と熊津において劉仁願の立会のもとで和親を誓った。
これをうけて五月に劉仁願は朝散大夫郭務悰ら(計130人だった)を倭に遣わし、「表函と献物を進る」。(中略)倭の朝廷は、彼らを劉仁願の私的な使いであるとして入京も許さず、文書も受け取らなかったが、九月には第四次遣唐使から帰国した津守連吉祥や伊伎連博徳を筑紫にやり、饗宴でもてなして帰国させた。
翌665年九月に「唐国、朝散大夫沂州司馬上柱国劉徳高等を遣はす」とあるように254人の大使節団で「表函」を進上した。『書紀』は十一月に饗宴し、十二月に賜物し、帰国したと記すだけだが、今回は入京を許し、表函も受け入れたらしい。劉徳高が大友皇人に会い、その風貌を褒めたというエピソードが伝わる。】(p315~316)
この白村江の敗戦後の唐とわが国とのやり取りについて、大津教授の説明では何のトラブルもなく和気あいあいと和睦が出来たという感じです。
しかし大津教授は読者に対して大きな情報を隠しています。 特に、倭国への唐軍の進駐について、大津教授は『日本書紀』の記述よりもなぜか、ぐっと小さくとっているようです。「 唐は254人の使節団を派遣」と大津教授は書きますが、二千人の唐人(軍?)については無視されています。
この二千人の軍団は二度渡来した、と『日本書紀』は書いているのです。日本書紀の編纂が終わったのが720年です。唐軍の来航はそのわずか60年前のことです。老年者にはまだ当時の記憶があり、『日本書紀』の書き誤りとは言えない状況だと思います。なぜ、大津教授はこの唐軍来航について口を噤まれるのでしょうか。
ここに、白村江の戦いからその後の動きについて年表にまとめてみます。
西暦年 事件
644 唐太祖高句麗侵攻
653 百済豊章王子倭に人質として来朝 (『日本書紀』)
659 倭国日本国使節団長安にて相争う (『旧唐書』)
660 唐百済鎮将蘇定法派遣 百済義慈王他捕虜 (『旧唐書』)
660 豊章帰国し扶余豊即位 倭国義勇軍派遣 (『日本書紀』)
661 唐の続守言を捕虜にし筑紫へ (『日本書紀』)
661 唐人捕虜一〇六人近江へ移送 (『日本書紀』)
同7月 斉明天皇歿 中大兄皇子称制をとる (『日本書紀』)
662 新羅と百済・倭との戦に唐が参戦 (『旧唐書』『日本書紀』)
663・2月 続守言を筑紫から近江へ移送 (『日本書紀』)
同3月 州柔の陸戦 倭軍二万七千、上毛野君ほか将軍参軍 (『日本書紀』)
同9月 白村江の海戦 倭船四百艘焼く (『日本書紀』)
664・2月 天智天皇(称制)部下へ叙位叙勲 (『日本書紀』)
同5月 唐の百済鎮将軍劉仁願・郭務悰ら来朝 (『日本書紀』)
同10月 郭務悰ほか来朝、同年十二月 郭務悰帰国 (『日本書紀』)
665・9月 唐国使劉徳高・郭務悰ら二百五十四人来朝 (『日本書紀』)
同12月 守君大石を唐へ派遣 (『日本書紀』)
666 泰山封禅の儀倭国代表参加 (『冊府元亀』にあるも『日本書紀』に記事なし)
667・3月 天智近江に遷都 (『日本書紀』)
667 天智各所に山城を築かせる (『日本書紀』)
同11月 唐、劉仁願・司馬法聡来朝 (『日本書紀』)
668・1月 称制七年の後、天智天皇即位 (『日本書紀』)
668 高句麗滅亡 統一新羅へ
同9月 新羅より金東厳来朝(十一月帰国) (『日本書紀』)
669 唐へ河内直鯨派遣 (『日本書紀』)
669 郭務悰ら二千人来朝 (『日本書紀』)
670 高句麗より遣使来朝(高句麗遺民か) (『日本書紀』)
671 唐、劉仁願・李守真来朝 (『日本書紀』)
671 唐 郭務悰ら六百人と送使一千四百人来朝 (『日本書紀』) (沙門道久・筑紫君薩野馬など四人も)
同10月 新羅 金万物来朝 (『日本書紀』)
同12月 天智天皇歿 (『日本書紀』)
672・5月 郭務悰に進物(ふと絹一千六百七十三匹・布二千八百五十二反・綿六百六十六斤)
郭務悰帰国 (『日本書紀』)
同6~7月 壬申の乱 (『日本書紀』)
674 新羅の三国統一なる
686 天武天皇歿 (『日本書紀』)
701 元号大宝 (『続日本紀』)
702 遣唐使 粟田真人 (『続日本紀』・『旧唐書』)
この表で特に目立つのが郭務悰の来朝です。『日本書紀』の記述では少なくとも五回来朝しています。(671年渡来とされる劉仁願は中国の史料によれば、当時彼は南方へ左遷させられていたので、この時は劉に代わって郭務悰が来たのではないかという説もあります。)
ともあれ、多い時には一度に二千人・四十七隻の船という大船団で来朝しています。二千人渡来は二回記録されています。
『日本書紀』によれば、郭務悰は筑紫に常駐したものとみえ、大和には一度も来ていません。この大船団というか大兵団が筑紫に常駐した任務は何であったのか、容易に想像できるところです。
戦後処理を話し合ったのでしょうし、そのための筑紫君薩夜麻を同伴帰国させたのでしょう。百済の場合は唐の属領とし、王子を都督に任じましたが、日本国では天智が称制を脱して晴れて天皇を名乗り「倭国」は消滅させられ、大和王朝がその「倭国」を併呑し「日本国」となれた、というのが論理の示すところでしょう。
『日本書紀』には筑紫君薩夜麻の帰国について、次のように書かれています。
【天智十年(671)十一月の甲午癸に、対馬国司、使を筑紫大宰府に遣はして言ふ。「月 生〈ちて二日に、沙門道久・筑紫君薩野馬・ 韓嶋勝娑婆〈・布師首磐〈四人、唐より来りて曰く、
『唐国の使人郭務悰等六百人、送使沙宅孫登等一千四百人、総合二千人、船四十七隻に乗りて、倶に比知嶋に泊りて、相 謂〈ひて曰く、”今、吾輩人の船数多し。忽然と彼に到らば、彼の防人、驚き駭〈みて射戦はむ”と。乃ち道久等を遣はして、 預〈め稍〈に来朝するの意を披き陳べしむ』と。】
この『日本書紀』が記す大部隊・大船団の来朝について、大津教授が口をつぐんでいるのはなぜでしょうか? 大津教授は、何故かこの唐軍の大部隊の駐留についてひとことも述べません。
大津教授は、【 白村江の戦いの翌六六四年、唐は劉仁願を百済の鎮将とし、旧百済国の太子 扶余隆を熊津都督とした。これは百済の人々を「招輯」するためと、百済と新羅の間の和睦を誓わせるためで、二月に扶余隆は文武王の弟金仁問と熊津において劉仁願立会いのもとで和親を誓った。
これを受けて五月に劉仁願は、 朝散大夫郭務悰ら(計130人だった)を倭に遣わし、「表函と献物を進る」。(中略)
倭の朝廷は、彼らを劉仁願の私的な使いであるとして入京も許さず、文書も受け取らなかったが、九月には第四次遣唐使から帰国した津守 連吉祥や伊伎連博徳を筑紫にやり、饗宴でもてなして帰国させた。 】(p315)と戦後処理について何も問題なかったように述べています。
大津教授は旧百済の王子、余隆が熊津都督に唐から任命されたことについては、書いてはいます。しかし、このことが中国・朝鮮半島・日本列島の政治バランスに与えた影響への評価などが、大津教授のこの『天皇の歴史』という本には全く見られないことは驚きです。
この唐朝による「熊津都督」任命で旧百済国が中国の属領同様になったわけで、これは新羅の民族意識を 逆
なでしたものと思っても間違いないでしょう。これらのことが原因で 唐・新羅間の調整に手間取り白村江の敗戦から唐軍の倭国進駐 までに時間がかかった、ととるのが理性的判断と思います。
倭国が百済復興戦で完敗したこと、その後唐軍が筑紫に到来して戦後処理を行ったであろうことについて、日本の史書は何も語りません。わずかに『万葉集』の山上憶良の貧窮問答歌や、柿本人麿の雷山の絶唱(後述)などから困窮生活ぶりを窺い知るのみです。
このような事情を隠す『日本書紀』の編集方針(『万葉集』も)は、二〇世紀の敗戦を終戦と言い替える現代にも通じるものがあると思います。大津教授はまあ義勇軍が白村江で負けたのである。それで、丸で何もなかったかのように、唐と国交回復ができたとされているのです。
20世紀で我が国が太平洋戦争に負けた時には「終戦」と、軍も官もマスコミも口を合わせて表現しました。敗戦後60余年の現在、アメリカと戦って負けたことを知らない若者が増えたことも、キチンと「敗戦」と認めなかったことにも原因の一つでしょう。
その遠因は七世紀で唐と戦って負け、九州を一時支配下におかれたことを認めない、『日本書紀』の記述を信じたことが上げられましょう。その『日本書紀』の編集者でも、二度の大兵団の来航を書いているのに、大津教授はそれすらも認めたくないのでしょうか。
文芸春秋誌2012年八月号巻頭随筆に立花隆氏が、「日本再生十六 ベトナムの真実」で昭和史家半藤一利氏の次の発言を紹介しています。
【ある女子大で講演を頼まれて「昔、日本はアメリカと戦争したことがあったんだよ」と言ったら、「エーッ」と驚きの声があがり、一人の学生が「それでどちらが勝ったんですか」】と。
「神州不滅」などという歴史的に見て間違っているスローガンに踊らされた20世紀の我々です。このような誤った認識を改めるためにも、白村江の敗戦とその後の戦後処理を、欠けた史料を掘り起こしキチンと整理し直さなければならない義務が、特に歴史家にはあるのではありませんか?
★天智天皇(称制)の甲子の宣
不思議なことに百済復興戦が敗戦に終わったにもかかわらず、天智天皇(称制)は甲子の宣と呼ばれる冠位制定を行います。
これについて大津教授は次のように述べます。
【白村江の敗戦の翌年、二月に、三項目の改革を宣布した。干支をとって「甲子の宣」と呼ばれる。
①大化五年の冠位十九階を二十六階の新制に改めたこと。
② 氏上を定めて刀・盾・弓矢を授けたこと。
③民部・家部を定めたことである。(中略)
改新詔では諸氏所有の「 部曲」をやめ、食封を支給すると宣言したものの、実際には進んでいなかったが、天智朝はようやくこの点に着手したのである。 】(p319)
この冠位のいわば増発は、白村江の敗戦直後と言う時期を考えると不思議です。天皇に即位もせず称制のままです。
これも、『旧唐書』がいう「日本国はもと小国、倭国を併せた」といういわば喜びの内祝い的褒賞増発と考えれば辻褄が合い、まだ唐との戦後処理、「倭国」の処理、「日本国」の責任の有無などが終わっていない時期での天皇即位はまだ早い、という判断が働いての「称制」の継続になったと思われます。
なぜ、天智が称制を続けたのか、大津教授には意見はないのですか? 『日本書紀』では、即位前は天智の発言は「我」と書かれ、称制七年の即位後には「朕」というように書き分けられています。
万世一系であるべき天皇制が中断されていることを、『日本書紀』自体が示している、いわば失態を示しているのは、編集者の迂闊さなのか、真面目さからくるものなのか、興味ある問題ではないでしょうか。
★天智の防衛策について
大津教授は白村江の敗戦の後のわが国の動きについて次のように述べます。
【天智六年(667)三月、畿内豪族の本拠である畿内を出て、 近江大津宮に遷都した。唐の高句麗征討が進む中、敵襲をさけて奥地の交通の要衝である近江に移った。(中略)
前々年に百済の亡命貴族に長門国に城を築かせ、同じく百済人を筑紫に派遣し大野城と基肄城を太宰府の北と南に造らせた。
六年十一月には対馬の金田城、讃岐の屋嶋城、更に倭国に高安城を築いた。
百済貴族の力を借りて、各地に朝鮮式山城を作り、防衛を固めたのである。】(p320~321)
しかし、先の年表を見て頂きたいのです。天智三年には唐から劉徳高などの使者が来朝しているのです。近江遷都は防衛(逃亡)の意図とも云えましょうが、その廃都になった奈良を守るための高安城の築造というのはおかしな『日本書紀』の記述です。
基肄・大野の両城の築造記事も考古学的築造年代からは、新築ではなく修復的なものであったようです。太宰府を中心にしていた九州各地の「倭国」残党に対する軍事施設とは言えるかもしれませんが。既に唐の使節団が到着して戦後処理を話し合う段階の時期に大々的な対外的防御施設の建設を行なうことが許されるわけがない、というのが論理的推論でしょう。
大津教授は引用されていませんが、『日本書紀』には太宰府の水城も防衛施設として築造された、と記しています。
【是歳(天智三年)、対馬嶋・筑紫国等に、 防〈と烽〈とを置く。又筑紫に大堤〈を築きて水を貯へしむ。名〈けて水城〈と曰ふ。】
この水城も古来からの「倭国」の首都太宰府の防衛施設として築造されていたことは考古学的調査資料の示すところです。(『太宰府は倭国の首都だった』内倉武久を参照ください。)
大津教授は無批判に『日本書紀』の記事をなぞるだけです。 この「天智天皇の防衛策」を語ったあと、大津教授は、中国史書とは一応無関係に、『日本書紀』の記事に基づいた形で、「乙巳の乱」・「大化の改新」・「郡評問題」などの古代史の問題点などを論じられます。
しかし、日本の古代最大の内乱ともいわれる「壬申の乱」はなぜか大津教授の『天皇の歴史』に関係ないと思われたのか、その「乱」の評価は全くこの本には見えません、不思議です。
★壬申の乱
大津教授が壬申の乱について述べられるのは、【天皇自身が神である「 現人神思想」は、壬申の乱を勝ちぬいた天武のカリスマ性によって生まれたが、 それは一般的な律令天皇制の性質といえるのだろうか。(中略)
しかし、このような思想は日本の天皇制の歴史の中では特異な例外的なあり方であった(戦前の昭和天皇は例外である)。 】(p341~342) ということだけです。
この「壬申の乱」は、『日本書紀』の記述によっても、「叔父が甥を殺害した」、それも正当な天皇を継ぐ甥の弘文天皇を実力で倒したのですが、どちらも舒明天皇の血統なので「天皇の万世一系」に問題ないと思われるのか、『天皇の歴史01 神話から歴史へ』に「壬申の乱」の大津教授の評価は全く述べられません。
天武の『古事記』の編纂命令、そして改めての『日本書紀』の元正期の完成、これらに深くかかわっているのが天武天皇であることは周知のことです。この「壬申の乱」を全くといってよいほど無視されるのは理解に苦しむところです。
なぜ「壬申の乱」が起きたのか、起きなければならなかったのか、古田武彦氏は『壬申大乱』でおおむね次のようにいわれます。
【亡き兄天智の遺言(大友皇子への補佐)と、大友皇子(弘文天皇)との決定的な対立、そのための決断をするために、唐軍の総司令官ともいうべき郭務悰に会いに行った。そしてそれは成功し、壬申の乱に勝利した。これらの経緯が万葉集の天武の御製「よき人のよしとよく見てよしと言ひし芳野よく見よよき人よく見」という謎々じみた歌に隠されている。】と。(同書p155~175)
つまり、唐軍として、大友皇子の戦後処理の方針よりも、天武の方が唐軍の方針に合っていた、というのが「壬申の乱」の原因であり天武が勝利した原因でもある、ということになります。
詳しくは『壬申大乱』東洋書林を参照下さい、通説とは全く異なる「壬申の乱」の姿を見ることができます。
大津教授には、664年、唐の百済鎮将軍劉仁願・郭務悰らの来朝以来、わが国は唐の監視下に置かれていたという視点が全く欠けているようです。
(八)天皇号・日本国号成立問題
★大王号の成立について
大津教授は稲荷山鉄剣銘文などに関連させて「大王号」の確定の証拠とされます。“倭国「天下」と大王号の成立”という項目をたてて次のように大略述べます。
【熊本県玉名の全長61メートルの前方後円墳、江田船山古墳から1873年に銀象嵌銘ある鉄刀が出土した。銘文冒頭「治天下蝮□□□鹵大王」と読まれ、 蝮之宮瑞歯とあてて、「 多遅比瑞歯別天皇」=反正天皇とされてきた。
しかし近年発見された稲荷山鉄剣銘で「獲加多支鹵大王」とあり、この江田船山鉄剣銘も「ワカタケル大王」と釈読も改められた。
この銘文の「大王」については、オホキミは美称であり、尊称にすぎず、大王も王に美称の大をつけたにすぎず、君主号たりえないとの批判もあるが、この二つの鉄剣銘に「大王」と記され、「治天下」が冠されるものであり、君主号として確立していると考えてよいだろう。
また、和歌山県橋本市の隅田神社蔵の人物画像鏡(仿製)の銘文にも、「大王」と「男弟王」 「意柴沙加宮 」にいたとき、「斯麻」という人物がこの鏡を作ったと解釈できる文がある。
「癸未年」を443年とする説と、503年説があり、決定できないが、前者なら「大王」のより古い例となる。
大王号のもとには中国から与えられた倭国王の爵位がある。王号は東アジア世界の中で機能しただけでなく、国内にも意味を持つことは、梁に五二一年に朝貢した百済王 武寧王の墓誌からもわかる。そこには冒頭に「寧東大将軍百済斯麻王」とあり、本名の斯麻の上に「寧東大将軍・百済王」を付していて国内の権威をはっきりしめしている。
王号の美称として高句麗においては「太王」号が派生して成立した。「好太王」がその一例である。高句麗についで成立したのが倭の「大王」だった。武王の上表文にみられる高句麗に対抗しようとする姿勢に共通するものである。「治天下・・・・大王」として「天下」と組み合わされることにより、倭の「天下」を支配領域とする独自な君主号としての意味を強めるのである 。】(p92~p95)
「江田船山古墳鉄刀銘」については先述しましたように、稲荷山鉄剣銘とは何ら関係がありませんし、「ワカタケル」とは無関係です。しかも大津教授が「大王号」の例とされる「隅田八幡人物鏡」についての発言は非常に曖昧です。『日本書紀』にない事物については物が言えないのでしょうか。
大津教授が述べることを纏めると次のようにいろいろと疑問が湧いてきます。
① 鏡は国産(仿製)とされる根拠は。(百済王からの贈りものではないと言いたいのか?)
② 「大王」と「男弟王」という兄弟執政体制に興味を示されないこと。
③ 「意柴沙加宮〈 〉」とは何処の宮殿なのか。
④ 斯麻と百済王とは同一人物なのか。もし同一人物ならば「癸未年」は503年できまるのに。
以上のことから推定されることは、大津教授はこの鏡は国産であり、倭人「斯麻」が作って大王とその弟王に贈った鏡という理解のようです。製作年代は443年ならば「大王号」の初見ということで意味があるが、503年であれば既に稲荷山鉄剣銘に「大王」があるし大して意味がある鏡ではない、という評価のようです。
大津教授はどなたの説を元にして言っているのか分かりませんが、一般に福山敏男氏の解読が有力とされていますのでまあ、それにならっているとみてよいでしょう。
福山説は、「癸未年八月日十、大王年、男弟王、在意柴沙加宮時、斯麻、念長寿、遣開中費直穢人、今州利二人等、取白上同(銅)二百旱、作此竟(鏡)。」と解読しています。
“この鏡の銘は大王(仁賢天皇?)の御代の癸未年(503年)に、ヲホトの王(継体天皇)がオシサカの宮にました時に(おそらくその臣の)シマが、河内の直の漢人、今州利の二人をしてこの鏡を作らしめたことをいっていると思われる”という説です。
ところが、それに対して、井上光貞氏は、「癸未年は443年で、大王は允恭天皇説」を唱えています。 大津教授の気持ちを勝手に忖度すれば、次のようなことでしょうか。
【1971年に百済武寧王斯麻の墓碑が出て来たが、井上先輩のこの問題についての発言は見られない。(1976年心臓発作で入院、1983年没)、どうもこの銘文の斯麻は百済王のように思えるのだけれど自信がない。斯麻は百済王ということは古田武彦がずっと前から言っているしそれに同意するのも癪だ】、というようなところでしょうか。
第一それに合う時代の日本の史料に、この鏡についての記録はなく、あるのは隅田神社の社伝の「神功皇后がもたらした物」だけで、大津教授としては何も言えないのでしょう。
古田武彦氏は、「金石文」という第一級の史料に対してその史家なりにどのように立ち向かうのか、という設問に答え得なければならない、といわれます。詳細は略しますが、『失われた九州王朝』第五章九州王朝の領域と消滅 二つの金石文 人物画像鏡と船山古墳太刀 をご覧ください。
結論として、「癸未年八月、日十〈大王年〈と男弟王が意柴沙加宮〈に在りし時に斯麻〈(武寧王)が、長寿を念じ、開中費直・穢人今州利の二人等を遣わし、白上同(銅)二百旱を取り、此の竟(鏡)を作らしむ。」と解読し、「武寧王と倭王とは対等なので、斯麻は無称号なのだ。日十大王年は時期からいって、倭王武と多利思北孤の間の大王であろう。勿論大和朝廷の人物ではなく九州にあった王朝の人物である。」と解説されています。
金石文の解釈から逃げていながら、「大王号」の成立時期を論じようという大津教授は、土台から間違っていると言えるでしょう。
稲荷山鉄剣銘文、江田船山鉄刀銘文、隅田神社鏡銘文それぞれに刻まれている「大王」と大和朝廷とを結びつける証は見当たらず、「大王」号は、稲荷山は「関東の大王」、江田船山は「九州の大王」、隅田神社鏡も「九州の大王」をそれぞれ示している、という結果になりました。
★ 『万葉集』天皇御製歌解釈について
大津教授は、「天皇」の意味というかその象徴するものを探るために、として万葉集などから古歌を紹介されています。
それらの引用歌は天皇の儀式や祖先を誇るため、などとされます。 第二章 『日本書紀』『古事記』の伝える天皇 3 ワカタケル大王とウジの成立 という項目のところで、大津教授は雄略天皇の歌を次のように出しています。
【万葉集』の冒頭、巻一の第一番歌は、雄略天皇(大泊瀬稚武天皇)の作歌である。
籠も〉よ み籠もち ふくしもよ みぶくしもち この岳〈に 菜摘〈ます児 家告らせ 名告〈らさね そらみつ 大和の国は おしなべて 吾こそ居れ しきなべて 吾こそ座せ 我にこそは 告らめ 家をも名をも
春の若菜つみの場面である。籠と掘串(土掘り用のへら)を以て岳で若菜をつむ娘に対して、われこそは、そらみつ大和の国を統治する王であると名のり、私に家と名を教えよ、つまり求婚した歌である。(中略)
『万葉集』は、最終的には八世紀後半になって大伴家持〈によってまとめられた。しかし構成・成立はきわめて複雑で、家持の個人的な歌日記の部分や、関東地方を中心とする東国の歌、東歌を再録した部分などもあるが、冒頭の巻一と巻二は、八世紀初めには編纂されていた公的な、つまり国家的な歌集であったと考えられる。
あとで触れるが、次の二番歌は、舒明天皇が天香具山〈 に登って国見〈 をした歌であり、この一番歌も私的な妻問い歌とは考えられず、国家的な意味を持つ儀礼の歌と考えるべきであろう。 】(p136~137)
大津教授は『万葉集』の巻一と巻二は公的な歌集であった、といわれます。しかし、『万葉集』については公的な記録は全くありません。大伴家持によってまとめられた、という記録もないのです。それなのに大津教授は何を根拠に「公的な国家的な歌集」と言われるのでしょうか。
『万葉集』の歌の紹介にも、「この歌は古集に出づ」という説明があったりしていて、この『万葉集』に先立つ『原万葉集』が存在していて、現在残る『万葉集』は『新万葉集』と思われるのです。それでも、十世紀になり村上天皇が『万葉集』のいわゆる万葉仮名と漢語混じりの歌に「訓〈
み」をつけるように勅命を発するまで、いわば大和朝廷の奥の院の女御達の間で生き延びていたと思われるのです。
『万葉集』には数々の疑問が昔から提起されています。後に、「元号問題」のところで詳述しますが、『万葉集』には正史『日本書紀』には存在しない「朱鳥七年」などの年号や、天武朝で制定された「八色の姓」が、例えば藤原鎌足が「朝臣」の姓を賜っていたというように、『日本書紀』の制定記事以前に使われていたと『万葉集』には記されているのです。
大津教授が言われるように「公的・国家的歌集」であれば、その根拠を示していただきたいものです。 たしかに、一番歌は雄略天皇、二番歌は舒明天皇の御製、それも歌集には極めて変則の「雑歌」がトップに来ている歌集に、その御製長歌二首が並びます。
この『新万葉集』の編集者は時の権力者におもねって、その様な構成を試みたということはできるでしょうが、結局は表に出ることは許されなかった歌集だった、ということになります。そういう目で見れば、時の大事件「白村江の敗戦」をうたった歌が全くないこと、唐の二千人を超す軍団の二度の来寇についての歌がないことにも納得がいきます。
大津教授は舒明天皇の御製、巻一 二番歌を、第四章 律令国家の形成と天皇制の冒頭の、1 舒明天皇と唐の成立で引用されています。【 『万葉集』巻一の第二番歌は、舒明天皇(高市の岡本の宮に天下治らしめる天皇)の作歌である。雄略に次ぐ第二の画期と考えられていたことがわかる。】(p262)と書かれます。
まず一番歌の意味が大津教授のおっしゃるようなものなのか、古田武彦氏は異を唱えています。
古田武彦氏は言います。【まず、前書きの問題、つまり作歌者と作歌場所などの説明に矛盾がある歌が多いこと。この一番歌も天皇の御製と決めてかかっているが果たしてそうなのか。古事記や万葉集に収められている歌は、後になると五・七・五が定型となるが、時代が上ると破格の長歌が多くなっている。この「籠よ」も時代的に古い歌であろうし、雄略期の頃の歌とは言えるだろう。
万葉集には歌と前書きが一致しないという疑いがある歌も多い。万葉集には、雄略天皇から次の舒明天皇の御製までの十二代の天皇方の御製がないが、その天皇方は歌をつくらなかったのか、という疑問もある。
この歌は雄略天皇の時代の頃に詠まれた、という伝承の歌というだけの歌であったのではないか。第一、娘さんに家や名を聞くのに、まず私は大和を統治する者だ、などというのはあり得ないし、歌としても野暮の骨頂の歌である。自分の名を名乗ってそして相手の名を聞く、というのが古今の流儀であろう。】と。(『古代史の十字路』より)
大津教授は『万葉集』にまつわる数々の疑問は当然ご存知のことと思います。先ほど上げた問題以外にも、①成立した時期、撰者が不明、②序がない、③歌と前書きの不一致、④中皇命の歌が四首あるが、『記・紀』に該当する人物がいない、⑤東歌はあるが筑紫歌がない、⑥白村江・州柔の戦の歌がない、⑦奥書がない、などの多くの謎があるのです。
大津教授も『万葉集』から歌を引用されるのであれば、【 冒頭の巻一と巻二は、八世紀初めには編纂されていた公的な、つまり国家的な歌集であったと考えられる。】(p137)と述べられるだけでなく、これらの疑問に国史学者大津透教授の観方を示して頂けなかったのは甚だ残念です。
古田武彦氏は、『万葉集』を大観して種々の不審があると次のように述べています。
【第一、「防人歌」で年代のわかっているものは全て八世紀であり、「七世紀以前」はない。天智~持統天皇の時代、白村江の時代であるだけに不審だ。
第二、九州や瀬戸内海領域で、その九州・瀬戸内海領域に住む人の歌が殆んどない。
第三、冒頭が「雑歌」で始まっている。「雑歌」「雑詩」は中国の『文選』に出ている分類だ。各分類の歌の後に出るべき「雑歌」だ。
第四、「白村江の戦」の歌がない。この上ない不審。
以上の不審を解くカギ、その根本命題は次のようだ。 「最初に存在したのは、筑紫を中心とした歌集、『倭国万葉集』であった。その「雑歌」としての“大和の歌”、それが次なる『日本国万葉集』の出発点となった。それが現存の巻一・二だ」と。この立場に立つと、先の不審は全て解消する。】(『盗まれた神話』「万葉の真相」より抜粋)
次に第二番歌です。
大津教授は、国見が天皇の支配者としての儀礼であることを示す歌とされます。
【天皇、香具山に登りて望国したまふ時の御製歌 大和には 群山〈ありと とりよろふ 天〈の香具山 登り立ち 国見をすれば 国原は けぶり立ち立つ 海原は かまめ立ち立つ うまし国そ あきづ島 大和の国は
(大和には群山があると、それを周囲にめぐらしている天の香具山に登り立ち、国見をすると、広々とした平野には、煙があちこちからしきりに立ちのぼっている。広々とした水面には、かもめが盛んに飛び立っている。素晴らしい国だ。大和の国は)。(中略)
天皇の国見は、一面で春の初めの予祝行事であり、一面で政治的性格を持つ支配者としての儀礼である。 】(p262)と大津教授はいわれ、仁徳天皇が高台で民家のかまどの煙の有無で民の暮らしを知った、という伝承も天皇の支配儀礼とみられる、などと述べられます。
続けて、国見儀礼の例の歌として次の倭建命の歌も紹介されます。 【倭建命〈の有名な歌(記三〇、紀二二番)、大和は 国のまほろば たたなづく 青垣〈 山隠れる 大和しうるはし(大和は高く秀いでた国だ。青々とした山が重なって、垣のように包んでいる、大和こそほんとうに美しい国だ)、もまた、国見儀礼での国讃め歌であろう。(中略)
こうしたヤマトの国讃め歌は、天平十五年(743)に聖武天皇が歌った様に、奈良時代にも伝統として継承されている。天皇の統治権の根源がどこにあったのかを示しているのだろう。】(p263~264)
この巻一の二番歌について検討します。誰でも不思議に思うのは、「海原は鷗立ち立つ」の一句でしょう。大和には「海」はありません。その疑問に対しては、「大和の香具山の脇の埴安池を海と歌人は詠んだのでしょう、琵琶湖も近江の湖〈うみ〉というし」、などと言う反論が返ってくるかも知れません。が、万葉集の中で、池のことを海原と歌った例は他にないのです。
原歌を見ますと、第一番歌と違ってヤマトの表記は「山跡」ではなく、「山常」です。前書きに「舒明天皇御製」とあるので無条件に「大和」と解釈しているのではないでしょうか。『万葉集』では「山跡」は他にも沢山見えますが、ヤマトの意味で使われたとされる「山常」はこの歌だけです。「山常」であれば「やまとこ」よりも「やまつね」であり「ヤマネ」ではないか思われれます。
天の香具山は、豊後の古名「安萬」であり、「海人」族の根拠地であった、大分県別府の地の、火の迦具土命を祭神とする神社がある鶴見岳ではないか。また、「ヤマト」はなぜ「あきつ嶋」なのか、ありえない。「蜻嶋」は安岐津の嶋で国東半島の根元の地名「安岐」の津でありましょう。
また、別府に多い「浜」の付く字地名であることを考えれば、「八間跡」は「やまと」でなく「ハマト」(浜跡)と思われます。このように作歌の場所を別府市付近とすれば、この歌は全て臨地性がある歌となります。
「国原は煙立ち立つ」も湯けむりが立ち昇る様を、「龍」を使って「立つ」という表現をしているのにはその表現力に驚かされますし、「海原に鷗立ち立つ」もそのものズバリで、臨場感あふれる歌ということになります。 原文(元暦校本)は下記です。
山常庭 村山有等 取与呂布 天乃香具山 騰立 国見乎為者 国原波 煙立龍 海原波 加万目 立多都 怜何国曾 蜻嶋 八間跡能国者
読み下しますと、山根〈 には 群山〈 あれど とりよろふ 天〈 の香具山登り立ち 国見をすれば 国原〈 は 煙〈 立ち立つ 海原〈 は 鷗〈 立ちたつ うまし国そ 蜻蛉〈あきづ〉島 浜跡〈 の国は となります。
現代語訳にしますと、【山並には多くの山々が群がっているけれど、なかでも一番目立ち、ととのっているのは、天の香具山だ。登り立って国見をすると、国原には煙が一面に立ち上がり、海原には一面に鷗が飛び立っている。すばらしい国だ。安岐津「あきつ」の島の、この浜跡の国は。】となります。(以上の和歌の解釈、出典は古田武彦『古代史の十字路』です。)
つまり、大和での国見の歌ではなく、九州別府湾の奥にそびえる鶴見岳からの、その地域を統括する大王の国見の歌でありましょう。作歌者は不明ですが、舒明天皇ではありえないことは明らかです。このことから、この歌を舒明天皇の御製として、【 雄略に次ぐ第二の画期と考えられていたことがわかる。】(p262)という大津教授の判断は的外れと言わざるを得ません。
たしかに、『万葉集』がその冒頭歌に雄略と舒明を持ってきたのは、『日本書紀』編纂方針と関係がある、というような大津教授の見方には一理ありますが、その見方の内容には同意出来ません。
『日本書紀』は継体天皇の正当性を強調するために、武烈天皇を悪逆非道の天皇とし、応神天皇以来の武烈天皇までの天皇の悪行を強調しています。とくに雄略天皇は「悪しき天皇と謗られた」と書きます。
『万葉集』の第一歌が継体天皇系列ではない雄略の女誘いの歌であり、第二歌が継体天皇系列の舒明天皇の真面目な国見の歌という配列に『万葉集』編纂方針が顕われている、とみてよいのではないでしょうか。
もう一つの「国のまほろば」の歌について、大津教授はこの歌を、『古事記』によって倭建命とされますが、『日本書紀』では景行天皇が日向国(宮崎県)に遠征した時の歌となっています。このあたりの検証は全くないままで、『古事記』の倭建命の歌として話を進められます。
なぜ『日本書紀』の景行天皇では駄目なのか、何か都合が悪いところがあるのでしょうか、大津教授は『古事記』の話で進められます。その原因を推測しますと津田左右吉博士が「景行紀は後世の官人の創作」とされている「クビキ」に従ったものではないか、と失礼ながら思われます。
日本書紀』での景行天皇の歌の原文は、「夜摩苔波〈 區珥能摩倍邏摩〈 多々儺豆久〈 阿烏伽枳〈 夜摩許莽例屢〈 夜摩苔之于屢破試〈 」(『日本書紀』 岩波文庫) です。
『古事記』では倭建命の歌となっていて、夜麻登波〈 久尓能麻本呂婆〈 多多那豆久〈 阿袁加岐〈 夜麻碁母禮流〈 夜麻登志宇流波斯〈 となっています。(『古事記』 岩波文庫)
ちょっと読んだだけでは分かりませんが、『日本書紀』では、「摩倍邏摩」を「まほらま」と振り仮名して「まほろば」の意味としています。しかし、そのまま読むと「まへらま」です。
古田武彦氏は、『盗まれた神話』で、この歌について次のように解説されます。【ヤマトは九州の山門だ、「まほろば」ではなく「まへらま」で「真へらま」である。『倭名類聚抄』では、「へらま」とは「鳥の心臓の近くだけれどもその脇にある柔らかい毛」と言う意味で、「ほろば」はその訛り。山門は(筑紫の)国の都近くの良いところという意味になる。】と。
ところが、『記・紀』ともに、「国のまほろば」となっていて、「まへらま」の訛化には遠い「素晴らしい場所」という解釈に変化しています。「大和」が国全体を示すとしますと、「大和は国のまほろば」が、「大和は、その脇にある良い土地」ということになり、意味が通じなくなります。ですから、これは意味が通るように意識的に、「脇にある」が抹消され変化させられたのと思われます。
これは、倭人伝の「邪馬臺国=やまとこく」と共通する問題があるようです。前にも書きましたが、古田武彦氏が「臺」が「ト」と読めるか、という問題で古代音韻研究者藤堂明保氏に直接お聞きした、と概略次のように述べておられます。
【”奈良時代以前に「臺」を「ト」と表音文字として使われた例はないのに、どこから、この読みを”、との問いに、”日本の歴史学者が、「邪馬臺国」は「やまとこく」と読まれるので”、と。】(『邪馬壹国への道標』より引用)
まへらま→まほろば も同様に、権力のある人たちが読みたいように読めば、それが後に定説となっていく、という恐ろしいお話です。
このように「大和のまほろば」という歌の意味も全く違ってくるのです。 この歌は、「山門は(筑紫の)国の脇の良い所、青々とした山が重なって、垣のように包んでいる、山門は麗しい国だ」ということになります。
しかしこの歌は単独の歌ではありません。次いで「命の 全〈けむ人は畳薦〈 平群〈の山の熊白檮〈が葉を 髻華〈に挿せその子」と「愛への方〈よ雲居〈起ち来も」の歌がついています。大津教授も、全体の考証をして「国のまほろば」の検証はされるべきでしょう。
詳しくは古田武彦著『失われた日本』第十章虚妄の「ワカタケル」説話 をご参照ください。「平群の山・・」という言葉から、この歌は大和の歌に違いないと思っておられる方々にとって驚くべき解説、「平群は筑紫の平群」があります。
大津教授が【こうした国讃め歌は天平十五年に聖武〈天皇が歌ったように、奈良時代にも伝統として継承されている。天皇の統治権の根源がどこにあったのかを示しているだろう。】(p264)という結論が空々〈 しく聞こえてしまいます。
★天皇号成立問題
大津教授は『日本書紀』に記されている隋朝への国書に「天皇」とあることについて次のように言います。
【(第三回遣隋使が持参した)国書によって隋への対応を軌道修正したことを、『日本書紀』は表現しているのだが、問題になるのは、ここにみえる「東天皇」である。是は後に書き改められたもので、本来は「大王」とか「天王」とかであったという説と、この時に天皇という文字が使われたという説に分かれるのである。天皇号はいつ成立したかという問題である。
天皇号の成立に学問的検討を加えたのは津田左右吉で、推古朝の金石文(法隆寺の薬師如来光背銘)に天皇号が見えることから、推古朝の成立とした。その薬師如来の光背銘は天武朝の製作である可能性が高い、などということから天武・持統朝の成立という説が提示され、教科書にも記され多くの研究者の支持を得ている。
しかし、天武・持統朝の成立にも疑問の点があり、近年では推古朝にやはり天皇号が成立したとする説が出され、筆者もそれでよいと考えている。 】(p252~256より要約)
大津教授はまた、【 天皇号成立の時期に関係すると、法隆寺金堂の薬師像の光背銘に「池辺大宮治天下天皇」「小治田大宮治天下大王天皇」(用明・推古)がみえ、これは丁卯(推古十五年)に造られたと記されている。
しかし、この製作年代に疑問(福山敏男説)がある。688年に葬られた船王後墓誌には、「阿須迦宮治天下 天皇」(舒明)などの天皇号がみえるが、「官位」などの語がみえることなどから天武朝以降の製作と推測される。
このようなことから、天皇号は天武・地統朝の成立という説が多くの研究者の支持をえている。】(p253~254)というように、わが国における「天皇」号の成立は天武・持統朝とされます。
しかし、『日本書紀』に外国史料の引用の中で「天皇」が出てくるところがあります。 継体紀の継体天皇歿年の記事に『百済本記』の引用があります。『百済本記』の現物は残っていませんので、この『日本書紀』の引用として「逸文」として残っている貴重な史料です。
【太歳辛亥の三月に、軍進みて安羅に至りて、乞乇城を営〈る。是の月に高麗その王〈安を弑〈す。又聞く、日本〈の天皇〈及び太子〈・皇子〈、倶〈に崩薨〈りま〉しむといへり。】(読みは岩波文庫による)と引用されています。
大津教授は、この『百済本記』が現存していないことから、この記事は『日本書紀』の編纂者が原文には「天王とか大王」とかあったものを「天皇」と書き換えた可能性を思って採用されていないようです。
しかし、『日本書紀』などの国内史料には、この時期に「天皇一族の多くが一斉に亡くなった」という記録は存在しません。このことは、この『百済本記』が伝える「倭国」の記事は大和朝廷とは無関係の記事であった、ということを示していると云えます。大和朝廷に先だって「天皇」号が使用されていた、など想像もつかないような、大津教授はガチガチの頭脳の持ち主なのでしょうか。
第二は、「船王後墓誌」です。大阪府柏原市の古墳から出土し、現在個人の所蔵となっているそうです。その墓碑文は「惟船氏故 王後首者是船氏中祖(中略) 即為安保万代之霊基牢固永劫之寶地也」の長文です。その中には三人の天皇と、当人船王後との関連が語られています。
大津教授は、この墓誌は後年の作製ではないか、とされますが、単に「天皇号の始まり」についてだけの史料ではないのです。古田武彦氏は次のようにこの「船王後墓誌」について説明されます。
【辛丑(641年)に本人の死亡。干支との関係から、「時限」が特定できる。ところが、関連する天皇名は ①乎娑陀宮 ②等由羅宮 ③阿須迦宮 の三天皇だが、従来当てられてきた三天皇 敏達・推古・舒明とは、ピッタリ対応 はしていない。たとえば、阿須迦天皇は推古でなく、舒明に当てざるをえない、等。
その上、致命的なのは三天皇間の用明・崇峻等の天皇名が「無視」されている点だ。この銅銘版は「天皇名と当人との対応」が主眼である点から見れば、不可解である。 さらに、当の船氏王後が「大仁」にして「品第三」という顕官であるのに、『日本書紀』に一切その名が出ていない。
このように、「同時代史料」としては、『日本書紀』・『続日本紀』とに一致しないことが明らかになった。
これに反し、九州には「天皇」に 対応すべき痕跡が多い。
たとえば、 (A)柿本人麿作歌 (『万葉集』一六七)には「神下し座せまつりて」「神上〉ぼり座しめ」と、「上座郡」「下座郡 」という、九州の筑前国(福岡県)の地名を 背景にして作歌されている。『万葉集』の表題「日並皇子尊(草壁皇子)の殯宮の時」と相反し、この歌の中の「天皇」は九州の筑前国に「座す」権力者なのだ。
(B)同じく、九州の「太刀洗町の下高橋官衙遺跡」出土の「正倉院」は、江戸時代の資料に、「生葉郡正倉院崇道天皇御倉一宇」とある。それが実際近隣の太刀洗町から遺構が出土したのだ。
(C) 「船王後墓誌」銘板の「乎娑陀、等由羅、阿須迦」は、それぞれ「曰佐(博多)・豊浦(長門)・飛鳥(筑前)」に当り、いずれも「神籠石」遺構配列の 内部に位置している。】と。 詳しくは 『年報日本思想史』第9号2009年「近世出土の金石文 (銘版)と日本歴史の骨格」古田武彦 を参照下さい。
もう一つ。【法隆寺金堂の薬師像の光背銘に「天皇」の銘文がある】と大津教授はいわれます。【用命天皇・推古天皇にあたる天皇の名があることから、その時代には「天皇」号が用いられていた】とされるのです。
しかし、法隆寺金堂には、釈迦三尊の像もあり立派な光背銘があることは有名です。その光背銘に一見奇妙な称号があります。「鬼前太后」、「上宮法皇」とか「干食王后」という「人名+称号」が出ています。
この「上宮法皇」を聖徳太子にあてるという説が一般的なようですが、これらの光背銘に記されている関係者と聖徳太子とは全く結びつかないのです。
おまけに、この銘文には法興元三十一年という不思議な元号も書かれています。これらの「称号」「元号」が『天皇の歴史』に大いに関係ある事柄と思われるのですが、大津教授には理解不能なものは取り上げない方針なのでしょうか、全く無視されているのは、「歴史学学者」としていかがなものでしょうか?
古田武彦氏は『法隆寺の中の九州王朝 古代は輝いていた III』で詳しく、薬師如来と釈迦三尊像の光背銘について考察された結果を述べています。大津教授と古田武彦氏の古代史の第一史料、金石文に対する態度の違いがよくわかる事例かと思います。
多利思北孤は天子を自称しましたが、倭王武以後中国からの冊封を離れ、天皇の呼称を使い始めたと仮定すると、以上の金石文に見える「天皇号」「元号」の問題は解決します。近畿王朝は701年に初めて「天皇号」・「元号」を使えるようになったのです。
天皇号の成立を「大和朝廷」のみ追いかけても、実体を捕えきれないのです。大津教授ももっと目を開いて「大和朝廷」のみならず、「わが日本列島全体」における「天皇号の成立」という視点で検討を進めて頂きたいものです。
★天皇の語源などについて
大津教授は、【天皇号天武朝成立説に、天皇は北極星を指していて、古くからの道教の神格あるいは最高神であり、天武朝には道教思想が浸透していたのでそれを真似した?、という説である。】(p255)といい、
【 史記』秦始皇本紀に、秦王政が天下を統一した紀元前221年、王に替わる称号を重臣たちに審議させ、皇帝号が創始される記事があるが、そこに候補として天皇が挙げられている。吉田孝氏は、推古朝の為政者が『史記』を参照して考え出したのではないかと推測している。
天皇号が推古朝に成立したとすれば、その本質は、律令制導入以前の大和朝廷の氏姓制度の中核であり、朝廷の神話や祭祀を支える存在だったということになる。のちに隋唐の律令法を継受して律令国家が成立するなかでも、そうした本質は保たれて行くのだろう。】とも述べます。(p258~260)
この大津教授の意見「天皇の語源」の問題について検討してみます。
「天皇」の称は中国では随分古くから見える、と古田武彦氏は言います。
1 古えに天皇有り、地皇有り、泰皇有り。〈史記、帝紀六、秦紀〉
2 天皇・地皇・人皇、兄弟九人、九州に分ち天下に長たるなり。〈春秋保乾図〉
3 夫れ越王勾践、東僻と雖も、亦、天皇の位に繋がるを得。〈越絶書・越絶外伝記呉王占夢〉
4 唐書高宗紀、上元三年八月壬辰、皇帝天皇と称し、皇后天后と称す。〈称謂録・天子古称・天皇〉 (中略)
このように淵源するところの古い「天皇」の語だから、日本列島内の王者が、四世紀乃至六世紀のころからすでに模倣しはじめていたとしても、別に不思議はない。『日本書紀』にも百済系史料の引用がありその中にも「天皇」が出ている。
「百済新撰」
(1) 天皇、阿礼奴跪を遣はして、来りて女郎を索はしむ。百済、慕尼夫人の女を荘飾〉らしめて、適稽〈女郎と曰ふ。天皇に貢進るといふ。〈雄略二年、458〉
(2) 辛丑年に、蓋鹵王、弟昆支君〈を遣はして、大倭に向でて、天王に侍らしむ。以て兄王の好を脩むるなりといへり。〈雄略五年、461〉 「百済本記」
(3) 日本の天皇及び太子・皇子、倶に崩薨〈り〉ましぬ。〈継体二十五年、531〉(前出)
右の(1)の阿礼奴跪を遣はしたというが、この人物は大和朝廷に該当者がない。このように、百済系史料に出てくる日本側の人名で、該当者が見つからないものがきわめて多い。(中略)「百済系史料」で記録された日本人名の多くは、日本側の代表的人物もしくは日本側から派遣された人物であるから、これほど該当者のいないことは異常である。
上記(2)では「天王」という表現が出ている。この表現は四世紀末に中国北朝に属する夷蕃の王朝「北涼」で「天王」の称号が用いられている。この北涼の天王呂光が位を譲ったあと、「太上皇」と称した。このようなことからみて、夷蕃の国が「天皇」「天王」と称する機運は四世紀には充分熟していたといえる。
論点を整理する。 「百済系史料」に出現する「天王」や「天皇」を、『日本書紀』編者の“書き換え”とみることはできない。なぜなら、「天王」という表記を、書紀の編者が造作するはずはないからである。
俀国伝・『旧唐書』倭国伝の記載内容からみて、『日本書紀』に引用されている百済系史料がいう「天王」「天皇」は大和王朝の王者でなく、九州の王朝の王者達であったのだ。(『失われた九州王朝』第四章 隣国史料にみる九州王朝 天皇の称号 より抜粋) 大津教授も、せめて『日本書紀』史料批判を充分に行った上で、「天皇号の成立」を論じてもらいたいものです。
大津教授は「天皇の読み方」について意見を述べられます。
【天皇は、奈良時代に何と読まれていたかといえば、スメラミコトであった。(中略)なお、スメラミコトと同類の語として、スメロキ(皇祖)・スメミオヤノミコト(皇祖母尊)・スメカミ(皇祖神)・スメミマ(皇御孫)など、スメの付く語がある。スメ(ラ)は記紀神話を背負う皇統を形容する語らしく、その語はスメラミコトを含めて推古朝以前の成立であろう。
こうしたスメラミコトに対応する語として、天皇号が考えだされたのだろう。日本で独自に考え出したとしても、天皇という語が中国語に存在することは前提である。】(p259~260)
奈良時代に天皇が何と読まれていたかについて論議しても余り実りがあるとは思えませんが、一応検討してみました。
まず、資料としては『万葉集』が上げられましょう。柿本人麿の歌「皇者神二四座者・・・」ではじまるいくつかの歌があります。五七五の和歌の音調から、「皇」はスメロキと一般に訓まれているようです。
『万葉集』では「大王」は「おほきみ」と訓まれています。ところが、「王」の場合も「おほきみ」と訓まれています。額田王の場合も「ぬかだのおほきみ」と訓まれています。
これらは、十世紀村上天皇が後宮の和歌所で『万葉集』の訓について読みを付け、「古点」として現代に残ったものです。しかし、上記の例からして古点は必ずしも正しいとは限らないようです。
『万葉集』巻七 1230番歌、に「志賀の皇神」と訳されている歌があります。その原歌では「皇神」は「須売神」とあり「皇」は「スメ」であることは間違いないようですが、「皇神」がスメロギという確証はないようです。むしろ「スメカミ」というのが論理的には正しいのではないかと思われます。大津教授は「スメカミ」は皇祖神とされますが、古訓に従うとそれは間違いのようです。
★日本国号の成立問題
天皇号の成立年代に絡んで、日本国号の成立について大津教授は次のように書きます。
【(天皇号を天武朝とする説の)状況論であるが、日本国号成立との関連がある。大宝元年(701)に任命された遣唐使は、702年に唐に渡り、唐に対して初めて「日本」国号を称し、「倭」を改めた。】(p255)
そして『旧唐書』に「倭国伝」と「日本伝」と二つあることについては、【律令国家の国号が日本だったことは、養老四年(720)成立の『日本書紀』から明らかで、701年の大宝律令に規定されていたことは確実である。(中略)約30年の空白をおいて派遣された大宝の遣唐使は「日本」という国号を称した。到着した楚州の役人はどうも説明は理解できなかったらしい。
『旧唐書』には、倭国伝と日本伝が二つ置かれていて、国家が変わったと認識されている。前者には貞観二十二年(648)までの、後者には長安三年(703)つまり粟田真人の朝貢以降の記事が載せられている。】(p353~354)と述べています。
日本の由来について続けて、【 『旧唐書』は「日本」の由来につき、「日本国は倭国の別種なり。その国、日辺に在るを以て、故に日本を以て名となす」。「倭国自らその名雅びならざるを悪み、改めて日本となす」。「日本は旧小国、倭国の地を併す」など三説を挙げ、「その人入朝する者、多く自ら矜大(おごりたかぶる)、実を以て対へず、故に中国これを疑ふ」と述べる。
遣唐使は国号の変更の理由について、はっきりと説明せずはぐらかし、唐の政府は納得のいく説明はえられなかったらしい。】(p354~355)と書きます。
この大津教授の説明では、『旧唐書』の「倭国」の項の説明を無視されています。大津教授は、『旧唐書』の記述は、中国の認識であって単に倭国が名前を変えたのだ、というのです。しかし、前章で検討したように、明らかに「倭国」と「日本国」は別の国なのです。「倭国」という国家が「日本」に変わったのではなく、「倭国」を併合して、なおかつ「倭国」がその雅名としていた「日本」を大和朝廷が名乗ったものでしょう。
大津教授の先輩吉田孝氏は、その著『日本の誕生』で「倭国」と「日本国」という『旧唐書』の記述について、【 旧唐書にある倭と日本の国号の変更についての記事は、唐側の誤解であろう】 (同書p6)とされます。
自説に都合が悪いことは「中国史書の誤り」とする悪習が、東大国史学仲間にははびこっているようです。
この吉田孝氏の『日本の誕生』という本を以前ネットで「槍玉その17」として批評しました。今回の大津教授の『天皇の歴史01』と基本認識は殆んど同じです。参考にURLを下記に添付しますのでクリックしてご参照ください。
http://www6.ocn.ne.jp/~kodaishi/yaridama17yosidatakashi.html
★則天武后の承認と「日本」の意味
大津教授は、「日本」の国号変更について次のように述べます。
【国号を変えたと宣言すればすんだかといえばといえば問題はある。唐の開元二十四年(736)張守節の『史記正義』に二つの記事がある。「武后、倭国を改めて日本国となす」「倭国、武皇后改めて日本国と曰ふ。(中略)凡そ百余の小国、此れ皆な揚州の東の東夷なり」と日本国号は則天武后が定めたと伝えている。(中略)
日本国号を中国に対し用い、定まったのは八世紀初めといえるが、国内で成立したのはいつか。天武三年(674)三月に対馬が銀を献上した記事に「凡そ銀の倭国に有ることは、初めてこの時に出えたり」とあり、このとき日本ではなく倭国だった。制度的に定められたのは、浄御原令か大宝律令であろうが、吉田孝氏は前者と推測している。】(p356~357)
大津教授のいわれるように、「日本」という意味からいうと、日本の西側から見て名付けられたということには間違いないでしょう。それは、太陽の出るところの意味であることには間違いないでしょう。
大津教授は、唐から見ての日の本だから、近畿でも該当する、とおっしゃりたいようです。しかし、実際に日の本などの地名が遺存しているのは福岡県が多いのです。 大分にある「日出」町という地名は、宇佐神宮のあたりから見たのかもっと西の太宰府あたりから見たのか、などと考えられましょう。
古田武彦氏は、1.筑前国那珂郡屋形原村日本〈ヒノモト〉、2.同郡板付村日ノ本〈ヒノモト〉、3.同早良郡石丸村日ノ本〈ヒノモト〉、4.筑後国生葉郡干潟村日本〈ヒノモト〉、5.同国竹野郡殖木村日本〈ヒノモト〉 というように福岡県に「日の本」という地名が密集していると指摘されます。( 古田会News May 2012 八王子セミナー講演録より抜粋)
これは、この筑紫を「日が出るところ」という地理的な位置、つまり西側にいる人の認識からの命名された地名でしょう。
中東の現トルコ共和国のあるアナトリア半島の名前の由来も、東ローマ帝国コンスタンチヌス七世の時代にコンスタンチノープルに首都を置き、アナトリア地方に軍管区を置き、「アナトリコン」(ギリシャ語で日出ずる処の意味)と名付けたことによるそうですから、地名の付け方は洋の東西を問わず、と言えるでしょう。
天孫降臨といわれる「天孫族」の筑紫侵攻の原点といわれる壱岐・対馬から見た「日の本」なのか、東日流外三郡誌にいう「中国舟山列島」から見たものか、大津教授が言うように中国大陸から、などいろいろと意見はありましょうが、「近畿」を「日の本」というのは無理があるでしょう。
以上の事柄を考え合わせると「日本国」を名乗ったのは筑紫を根城にする「倭国」という推論の方が、近畿王朝が最初に「日本」を名乗った、ということよりも論理的といえるでしょう。 それにしても、大津教授は『日本書紀』に出てくる次の「日本」関係記事について知らないふりです。
●雄略二一年三月の項に『日本旧記』という書名が注記として記されている。
●斉明六年七月の項に高麗の僧道顕の『日本世記』という書名が注記として記されている。
しかしこれらの書物については「日本」に関して書いてある本で、おそらく当時の権力者の大王たちと関わりあると思われます。しかし『日本書紀』にはそのあたりのことは何も書かれていません。大津教授は、『日本書紀』に書かれていないから、何も言えないのでしょうか。国史学者であれば何か言って欲しいものです。
また、大津教授は触れられていませんが、「日本」についての金石文があります。
「日本中央碑」という石碑が青森県に存在します。いつ頃建造されたかは石碑裏面が欠損していて判明しませんが、平安・鎌倉期に和歌集に「つぼの石ぶみ」という表現がある和歌がいくつもあるのです。例えば、西行法師の『山家集』(十二世紀)に“むつのくの 奥床しくぞ思ほゆる 壺のいしぶみ そとの浜風”があります。
この「壺のいしぶみ」が「日本中央碑」であるという考証をされた上で、なぜ青森県が「日本中央」なのか、これについて古田武彦氏は次のように推測されます。
東北の王者安倍一族が、『隋書』俀国伝にある天子多利思北孤の臣下として盟を結んだ。天子多利思北孤は大倭国を「その名が雅ならざるを悪み、改めて日本と為す」と『隋書』が記すように「日本」と改名した。安倍大王は、その勢力範囲が粛慎など北方に拡がっていることから、自分の居城地域が日本の中心だ、とそういう思想で立てられた「日本中心碑」であろう、とされます。(詳しくは『真実の東北王朝』第三章日本中央碑の思想 駸々堂 をお読みください。)
★君が代論
ところで、『天皇の歴史』と銘打っていますのに、また、沢山の和歌を引用されていますのに、不思議なことに、日本国国歌「君が代」の起源論が全く出てきません。
「君が代」の元歌は平安時代に編纂された『古今和歌集』にあるので、奈良朝までの天皇の歴史に関係ない、として取り上げられないのでしょうか。果たして、『天皇の歴史』を著述する姿勢としてそれでよいのでしょうか。
「君が代」の歌の淵源は、奈良朝いやそれ以前にあると思われるのです。 『古今和歌集』巻第七の先頭に、「題しらず」「読人しらず」として、“わがきみは千世にやちよにさざれいしのいはほとなりてこけのむすまで”(343番)が掲載されています。
大津教授は自分の受け持ち「奈良朝」ということにこだわっているのかも知れません。
この君が代論は、大津教授が言及されていないので、直接批判することは出来ません。しかし、言及しないということ自体で免責になるとは思いません。
この、「君が代」は「九州王朝の讃歌」であった、ことだけを指摘しておきたいと思います。詳しくは古田武彦『君が代は九州王朝の讃歌』をご覧下さい。
★元号問題
大津教授は「改新の詔」という項で次のように書いています。【孝徳即位とともに、皇極天皇四年を改めて大化元年とし、史上初めて元号を定めた。この年号は『書紀』以外にはみえず、どの程度実施されたかわからないが、一連の政治改革を年号をとって「大化改新」という。】(p278)と。
つまり「大化」という年号が定まったかどうか分からないが、一連の改革の名前として、「大化」を使っているに過ぎない、ということのようです。
元号は天子が使う、というのが中国を頂点とする冊封体制のいわば決まりの様なものでしょう。「天皇の歴史」を叙述するのに「元号」は不用なのでしょうか?
わが国の元号について『日本書紀』の伝えるところは理解がしにくい所が多く、大津教授の様な斯界の碩学が解説されるのかと期待したのですが、何も申されません。元号について調べていきますと不可解なことが多く、大津教授には理解不能となっているのではないでしょうか。
2011年3月、福島で原子力発電所が破壊しました。その災害対応について2012年7月、政府事故調査委員会の最終報告が出されました。それには「見たくないものは見えない」という原子力関係者・電力会社の根本姿勢があると指摘しています。(右は当時のTV番組のフリップです。)
元号問題でも、大和朝廷以外に元号を発布する組織が存在するなどあり得ない、考えたくもない、という古代史学会やそれに迎合するジャーナリズムの姿勢が、理性的な判断を妨げているというような状況があるのではないでしょうか。
我が国の元号は、『日本書紀』が記すところによれば、645年「大化」に始まって650年「白雉」と続き、32年の中断があり「朱鳥」が元号として復活します。しかし間もなく天武が亡くなり、一年と持たずに終了します。そして15年後の701年から「大宝」が使われ、以後中断することなく現在に至っているわけです。
この『日本書紀』の記述をそのまま読みますと、次のような推測ができるでしょう。孝徳天皇が、新羅も年号を持っているし、と自分も「大化」とつけ、650年に「白雉」と改元する。ところが、新羅が唐のお咎めを受けて唐の年号「永徽」を使うことになります。自分の方にも唐のお咎めがあるかもしれない、触らぬ神にたたりなし、とばかりに年号の使用を中止する。
白村江の敗戦処理がほぼ片付き、倭国年号を続けていた「倭国」を吸収する見通しがつき、年号「朱鳥」を定めたが、唐の意向に副わなかったようで持統天皇は年号を諦める。701年に至って唐則天武后の承認があり「大宝」が晴れて「日本国」の年号として認められた。そして、それまで使われていた「倭国」の年号は逸年号となり表舞台から消えた、ということでしょうか。
中国を盟主とする冊封体制の中で見てみますと、新羅では、536年の法興王23年の「建元」という元号を始めるぞという意気込みの年号から、以後連続して650年「太和」まで七代連続していましたが、唐の高宗が即位し元号「永徽」となったのを期に、新羅もこの「永徽」を使うことになりました。
高句麗では、広開土王碑で有名ですが好太王の「永楽」(391年)その子長寿王「延寿」(491歿)と続きその後は見えないようです。これも長年の中国との争いと無関係ではないということは容易に察せられます。
つまり、中国と張り合えるような夷蕃王は独自の元号を持とうとする、ということです。 翻ってわが国では・・・という視点を大津教授はなぜ据えることができないのでしょうか。
しかし、この『日本書紀』が伝える一連の政治改革、先述の天武朝の「甲子の宣」にしても、大和朝廷の事績なのか疑われる点が多いのです。年号の問題にしても『日本書紀』が記していることが事実なのか、検討してみる必要があります。
わが国の年号にはもう一つ隠された年号の問題があるのです。その一つが「白鳳」であり、「朱雀」です。 『続日本紀』に次の記事があります。聖武天皇神亀元年(724)十月 「詔報して曰く 白鳳以来・朱雀以前 年代玄遠にして尋問明らめ難し」と元号と見られる記事があります。
『続日本紀』(上)宇治谷孟 講談社学術文庫では、この白鳳・朱雀の所に括弧書きで(孝徳以後天武の諸朝)と意味が分からない注釈をしています。これが現在の通説をあらわしているようです。
又、大津教授が『古語拾遺』という史書を「大嘗祭」で引用されていますが、その『古語拾遺』にも 孝徳天皇の所に、「白鳳四年に、小花下諱部首作斯を以て云々」、とあります。大津教授は『古語拾遺』の大嘗祭については、「神武即位時に行われた」、と引用されますが、なぜか白鳳年号については無言です。
ところが大津教授は引用されませんが、多くの史料に六世紀から八世紀初頭まで連綿と続く「年号」暦が記載されています。その中に「白鳳」「朱雀」も存在しているのです。倭王武が中国の冊封体制から外れて「倭国」が独自の元号を使い始めたようです。それが百済滅亡後の復興戦で大敗し、新興の大和朝廷に吸収された、ということをこの九州王朝年号は示しています。
『万葉集』にも不思議な元年号がいくつも顕われています。
1、「日本紀に曰はく、朱鳥四年庚寅の秋九月、天皇紀伊国に幸すといへり」(巻一、34)
2、「日本紀に曰はく、朱鳥五年辛卯の秋九月己巳の朔の丁丑、浄大参皇子川島薨りましぬといへり」(巻二、195)
3、右、日本紀に曰はく、朱鳥六年壬辰の春三月丙寅の朔の戊辰・・・」(巻一、44)
4、右、日本紀に曰はく、朱鳥七年癸巳の秋八月、藤原宮の地に幸す。・・・」(巻一、50)
『日本書紀』によりますと、朱鳥は天武紀の終わりに元号が立てられ天武の崩御により一年で終わっています。それにもかかわらず、『万葉集』では朱鳥は少なくとも七年続いています。このように『日本書紀』の朱鳥記事と矛盾する内容を持つ『万葉集』が、後年の十世紀まで表に出ない歌集であったことと無関係ではないでしょう。
ともあれ、この元号問題をはっきりさせることができていないために、高校教科書などでも説明に苦しんでいるようです。 高校の教科書ではどうかというと、例えば山川出版『詳説 日本史B』では、「白鳳」は次のように出ています。
【飛鳥文化に続く七世紀後半から八世紀初頭にかけての文化を白鳳文化という。天武・持統天皇の時代を中心とする、律令国家が形成される時期の生気ある若々しい文化で、新羅から伝えられた中国の唐初期の文化の影響を受け、仏教文化を基調にしている。】と。
しかし何故「白鳳」と付けられているのか、の説明はありません。
文化勲章を授勳された俳句・和歌の批評家山本健吉氏の『日本名歌の旅』という好著(文春文庫)があります。そのなかで柿本人麿の歌の解説に、【柿本人麻呂 白鳳時代 生没年不詳】とあります。このようにいつの間にか「白鳳時代」とか「白鳳文化」という成語が認証されてしまっています。
『海東諸国記』という李氏朝鮮の時代1471年に成宗に奉勅された史書に「日本国紀」に日本の元号が掲げられています。522年「善化」に始まり以下元号が連綿と続いていて、そのなかに661年「白鳳」、684年「朱雀」も存在しています。
鎌倉時代初期に編集された『二中歴』という掌中辞典があります。その中の古代年号は、始まりが善化でなく継体とあるなどいくつかの点で『海東諸国記』と異なっていますが、「白鳳」「朱雀」は同じ時代に存在しています。
大津教授が、これらの『日本書紀』にない元号を検討すれば、正しい『天皇の歴史』の叙述が出来るでしょうに、誠に残念です。 ここに、「九州年号」とされるものを掲載している書物の代表格として、その「二中歴」と「海東諸国紀」の年号を掲げておきます。
二中歴 海東諸国記
(年号) (西暦)
継体 517~521 ―
善記 522~525 善化
正和 526~530 正和
教倒 531~535 発倒
僧聴 536~540 僧聴
明要 541~551 同要
貴楽 552~553 貴楽
法清 554~557 結清
兄弟 558~558 兄弟
蔵和 559~563 蔵和
師安 564~564 師安
和僧 565~569 知僧
金光 570~575 金光
賢称 576~580 賢接
鏡當 581~584 鏡当
勝照 585~588 勝照
端政 589~593 端政
告貴 594~600 従貴
願転 601~604 煩転
光元 605~610 光元
定居 611~617 ―
倭京 618~622 倭京
仁王 623~634 仁王
― 聖徳
僧要 635~639 僧要
命長 640~646 命長
常色 647~651 常色
白雉 652~660 白雉
白鳳 661~683 白鳳
朱雀 684~685 朱雀
朱鳥 686~694 朱鳥
大化 695~700 大和
― 大長
『二中歴』と『海東諸国記』に記されている「倭国」の年号は、編纂された国及び時期は異なりますが、上記のように殆んど同じと言ってよいほどの年号紀です。単に私年号とか逸年号とかで片付けて良いものではないでしょう。
この二つの史料にだけ、これらの年号群が書かれているのではありません。古田武彦氏によれば、【『麗気記私抄』僧了誉1401年、『如是院年代記』鎌倉末期成立、『襲国偽僭考』鶴峯戊申などがある。鶴峯戊申はその著書の中で「今本文に引所は、九州年号と題したる古写本によるものなり。」と記している】、(『失われた九州王朝』)と説明されています。
また、【平安時代には、この「倭国年号」を記した『二中歴』が書かれていた。ついで鎌倉時代や室町・戦国時代には各種の歴史・年代記録類にこの「倭国年号」は頻出する。“歴史上の意義”とは別に、「時の暦」としていわば「愛用」されていたのである。
江戸時代にはこの「倭国年号」は、絶好の論議の題材だった。歴史、古典、文献学者たちが「真作論」「偽作論」「地方豪族の建号論」相対立して、喧々囂々、相ゆずらなかったのである。
ところが、1868年、「天皇親政」を旗印とした明治政権の誕生と共に、一切の年号論争は見事に“消された”のである。「天皇家以外に年号なし」を歴史の根本理念としたからだ。】(『失われた日本』より抜粋)と、近畿天皇一元説によって「倭国年号」が闇に葬られたとされます。
大津教授も『天皇の歴史』を叙述しようとされるのなら、この一連の「九州年号」についても研究していただきたいものです。九州年号の研究により「年号問題」での、大化とか白雉・朱鳥などの年号が切れ切れに出現したり、『続日本紀』に「白鳳」「朱雀」などの『日本書紀』に無い年号が出てくる不思議さも理解出来ることになります。
『天皇の歴史』と『年号論』は結びついていると思うのですが、本当に「年号」について大津教授は何も言っていないのか再チェックしましたが、本当に何もいわれていなのです。大津教授は自分に高校生のお子さんがいらっしゃって、もし「年号問題」について聞かれたらどう返事されるのでしょうか?
★天皇を神とする思想
大津教授は「終章 天皇の役割と日本」で万葉集から四首の歌を引用され、天皇を神とする「例外的な」思想について述べたいとされます。現人神思想はカリスマ天武天皇の例外的な考えであり、そのことをもっと具体的に述べたい、と「皇は神にしませば」の第一句を持つ大伴御行の歌二首と柿本人麻呂の歌二首を、次のように紹介されます。
【万葉集の後半部分は大友家持の歌日記である。
皇は神にしませば 赤駒の腹ばふ田居を京師となしつ
大王は神にしませば 水鳥のすだく水沼を皇都となしつ
前者は壬申の乱での大将軍大伴御行の作だと記している。壬申の乱後、天武天皇を讃えて「大王は神にしませば」と歌われたことがわかる。
さらに柿本人麻呂の作歌の中にも見える。
皇は神にしませば 天雲〈の雷〈の上に盧〈り〉せるかも(巻3・235)
皇は神にしませば 真木の立つ荒山中〈に海を成すかも(巻3・241)
前者は、持統天皇が飛鳥の雷岳に御遊したときの歌で、丘に仮盧〈を作ることを、天皇が雷神を支配すると雄大に表現したもので、おそらく持統は雷岳で国見をしたのだろう。なお別伝では忍壁〈皇子に献ったとする。
後者は、天武の息子の長皇子が猟路〈の池にて狩猟のときの歌(反歌)で、山中の池を皇子の力によってできた海だと王子の霊威をたたえている。(中略)
このような天皇自身が神であるという「現人神思想」は、壬申の乱を勝ちぬいた天武のカリスマ性によって生まれたが、それは一般的な律令天皇制の性質といえるのだろうか。(中略)
しかし、このような天皇が即ち神であるという思想は、天武のカリスマ性にもとづき天武とその皇子たちに限られたもので、日本の天皇制の歴史の中では特異な、例外的なあり方であった(戦前の昭和天皇は例外である)。 】(p340~342)
大津教授が引用される四首のうち、前者の大伴御行の二首の歌は、あまりにも荒唐無稽という感じがします。この二首は天皇に対するおべんちゃら的な歌とは言えますが、同じく大津教授が引用し解説する後者、柿本人麻呂の歌に比べれば児戯に類するものといえましょう。
古田武彦氏は、柿本人麻呂のこの二首の歌について、そのようなおべんちゃらかつ、天皇の霊威などというものではない、写実性がありなおかつ当時の社会状況を詠みこんだ秀歌とされます。
次の古田武彦氏の解説を読まれて、大津教授の解釈とどちらが柿本人麻呂の歌を正当に評価されていると皆さんは判断されるでしょうか。この柿本人麻呂の二首の概略の古田武彦氏の解説をご紹介しますが、詳しくは『古代史の十字路』第八章「雷山の絶唱」をご覧ください。
まず最初の雷岳の歌です。この歌は奈良の明日香村の雷丘で詠んだとされますが、高々10メートルの丘であり、とても「天雲の」という形容詞は合わないのです。 原文は「皇者 神二四座者 天雲之 雷之上尒 盧為流鴨」です。 “すめろぎは 神にしませば、天雲のいかづちの上にいほらせるかも”で、そのまま読めば、「天皇は(亡くなられて)神となられたので、雲の上の雷山の社に休まれています」、となります。
この作歌の時期は白村江の敗戦の後の時期です。又、作歌場所を福岡県糸島郡の雷神社という神社が今も残る雷山(高さ995米)に置けば(この雷山は雷神社とともに千如寺が存し、明治維新前は「神仏習合」の一拠点をなしていたところ)、この歌が、「天雲の上に盧りする」問題も解決し、敗戦後の「民のいほりは荒れ果ててしまったが・・・」という背景での人麻呂の歌ということが理解できます。
人麻呂のもう一つの歌も同じです。 原歌は「皇者 神尒之坐者 真木乃立 荒山中尒 海成可聞」です。 これは長皇子の長歌に対する返歌という前書きが書かれています。その長歌に「猟路の池」とあるので、最後の句を「海をなすかも」と「池を海」と解釈し天皇が現人神という霊威の表現としています。 それにしても天皇に対する(この場合皇子に対して)これほどの阿諛追従の歌を柿本人麻呂が歌うのだろうか、と古田武彦氏は疑問を持ち、「海成」は「海鳴り」ではとされます。
その場合歌の解釈は全く違った姿を見せます。 “皇は 神にしませば 真木の立つ 荒山中〈に 海鳴りを聞く”となります。作歌時期・作歌場所は前歌同様、白村江の敗戦後の雷山でしょう。不気味な海鳴りは人麻呂にとって単に自然現象ではなく、白村江などで亡くなった死者の声を伝え、王朝の滅亡を予告していると聞き取ったのです。
このように、万葉集の柿本人麿の歌から「現人神」の思想を読み取る、という大津教授の考えは、根底から覆されるのです。
大体「皇は神にしませば」という句を万葉集全体で拾い上げれば、その句は「天皇はお亡くなりになりましたが」というように、「神=死者」の意味で使われているのです。大津教授が大伴御行の歌の天皇に対するオベンチャラ性を、人麿の歌と併せて掲載することで、皇=神の思想というように持っていくのは小手先の技巧であり、大津教授の万葉集の見方の浅さ、をあらわしている、といわれても仕方ないのではないでしょうか。
(九) おわりに
大津教授の『天皇の歴史01 神話から歴史へ』は次のような目次で叙述されています。
序章「天皇の歴史」のために
1 天皇研究の出発 2 天皇の歴史を考える 3 天皇と「日本」の成立
第一章卑弥呼と倭の五王
1 卑弥呼と邪馬台国 2 鏡と剣・・・王権のレガリア 3 倭の五王と大王
第二章『日本書紀』『古事記』の伝える天皇
1 記紀神話の意味と津田史学 2 「帝紀」「旧辞」から「記紀」へ 3 ワカタケル大王とウヂの成立 4 葛城ソツヒコと記歌人の伝承 5 王権の祭祀
第三章大和朝廷と天皇号の成立
1 継体から欽明へ 2 大和朝廷の形成と国造制 3 推古天皇 4 天皇号の成立
第四章律令国家の形成と天皇制
1 舒明天皇と唐の成立 2 大化改新の詔が描き出す国家体制 3 斉明女帝と白村江の戦い 4 天智から天武へ
終章天皇の役割と「日本」
1 シラスとマツル・・・祭祀の構造 2 マツロフとマツル・・・服属の構造 3 日本国号の成立
この大津教授の叙述に従って検討することも考えたのですが、結局基本の史資料の読み込みによって、歴史解釈は大きく変わってきます。
まず、大津教授の史資料の読み込みがどうなのか、というところを主眼にして検討を進めました。従って、大津教授が説かれる、氏姓制度・即位儀礼・祭祀の構造、などいわゆる「上部構造の細部」にまで至っていません。
大津教授が基本的な「史資料」及び、次の項目に記します「今回語られなかった」ことがらも含め、再検証をされて新しく『天皇の歴史01』を叙述されました暁には、改めて検討したいと思います。
★大津教授が語られないこと
この『天皇の歴史01 神話から歴史へ』で大津教授が触れられていない、歴史上重要な問題があります。
a)「倭人伝」では、「狗邪韓国」・「邪馬壹国」・「魏の短里」、
b)考古学的出土品との関係では、「三種の神器を出土した弥生墓」・「銅鐸文化」・神籠石、
c)『隋書』俀国伝では、「多利思北孤とは誰か」・「兄弟執政」・「軍尼と伊尼翼」・「流求国伝」・「遂に絶つ」、
d)『日本書紀』の記述について、「壬申の乱の評価」・「皇位争奪の歴史」・「二千人の唐軍の二度にわたる渡来」・「筑紫君薩夜麻」・「元号問題」、
e)『旧唐書』の「倭国と日本国」、
f)「九州本流近畿分流説」
g)『古事記』および『万葉集』の成立に係わる史料批判
以上のことについて、各章で述べてきましたが、『記・紀』が描く「天皇の歴史」には血なまぐさい権力争奪の経緯が書かれています。それらについての考察があっても然るべきと思いますが、大津教授にはそうは思われないようで、武烈と雄略以外については問題視されていません。
天皇の系譜について『記・紀』には物凄い量の皇位争奪が記せられています。万世一系を保持するため?何のために日本書紀の編者は書き記し、それを舎人親王が何故認めて元正天皇に奏上したのでしょうか? 是非『天皇の歴史01 神話から歴史へ』の著者大津透東大教授にお聞きしたいものです。
天皇が即位するために排除した主な例を一覧にしてみました。
天皇名 排除した相手 続柄 内容(古事記による) 日本書紀の場合の名前
綏靖 タギシミミノ命 異母兄 当芸志美美命の反逆 手研耳命
崇神 タケハニヤス王 庶兄 建波邇安王の反逆 武埴安彦
垂仁 サホヒコ王 后の兄 沙本毘古王の反逆 狭穂彦王
景行 大碓命 長男 弟、小碓命に殺させる 紀では大碓は殺されない
小碓命 次男? 遠国へ何度もの出征令 小碓尊
応神 忍熊王 異母兄 忍熊王の反逆 忍熊王
仁徳 大山守命 異母兄弟 大山守命の反逆 大山守皇子
速総別王 異母兄弟 速総別王の反逆 隼別皇子
履中 墨江中王 同腹の弟 墨江中王の反逆 住吉仲皇子
安康 軽太子 同腹の兄 軽太子のタハケ 木梨軽皇子
大日下王 叔父 軽太子に連座
雄略 目弱王 叔父の子 目弱王の乱 眉輪王
忍歯王 従兄弟 市辺の忍歯王の乱 市辺押磐皇子
継体 倭彦王 遠縁? 応神五世の孫
天智 有間皇子 異母兄弟 有間の謀反
古人大兄皇子 異母兄弟 (乙巳の変)
天武 大友皇子 兄の子 (壬申の乱)
大津教授は、天皇になるためにこれほどの流血が必要であったのか、都合の悪いから言えないのか、理解できないから言えないのかどちらなのかなあ、と素人古代史学徒は考え込まされてしまいます。
ここで私論を挟みたいのですが、
①武烈―継体天皇間の断絶で、応神~武烈の天皇たちの非行をあえて出し(創り)、
②天武天皇の甥排除の名分のなさを、過去の皇位争奪の非情さを出すことにより、己の正当性を示す、という『日本書紀』の判断ではなかったのでしょうか。その点に欠けていた『古事記』は正史たり得なかった、ということでしょうか。
特に兄弟間の皇位争奪が多いことは、多利思北孤王の兄弟執政とは基本的に異なる王権移譲の姿のようです。中世のオスマントルコ朝の伝統、兄弟が戦って生き残った方が王位を得る、という姿に似た古代の大和朝廷の姿が浮かび上がって来ます。
ともかく、大津教授の歴史叙述には、基本的な史料解析が不十分、というか誤認された上で、いかに「レガリア」「祭祀権」「即位儀礼」などと論を進められても、蜃気楼みたいなものでしょう。
大津透教授のこの『天皇の歴史01 神話から歴史へ』は次の文章で終わっています。 【八世紀に国際的に位置づけられた「日本」が、その後の列島の歴史を規定する枠組み、天皇制の構造は変化していく。(中略)平安時代に古典的国制が成立するが、それは本巻の担当を越えている。】(p359)
結論だけをみれば、確かに大和朝廷は八世紀になって国際的に認められ位置づけられた、と言えるでしょう。しかし、それまでの前史が、この本が描くような全く史資料を非科学的な、非論理的な検討で歴史を叙述しています。このような歪められた『天皇の歴史01 神話から歴史へ』が、東京大学国史学関係の教授によって世に広まることを大いに憂れうものです。
繰り返しになりますが、各項目で検討してきましたように、大津教授は史料の検討が不十分なまま、次のステップ、王権・レガリア・即位儀礼などに進まれています。
『魏志』倭人伝では、考古学的整合性はゼロなのに卑弥呼は纏向に居たと断定、『宋書』では、雄略の即位時には倭王武はまだ即位していないのに、武=雄略とする、『隋書』では、多利思北孤を時代が全く合わない欽明天皇にあてて、全く説明不能状態、『旧唐書』では、倭国と日本国の区別を無視する、 というように、全くお粗末な史料批判の上での大津教授の『天皇の歴史』の叙述です。
これでは「天皇のご先祖」が可哀想です。 この原稿を書いている間に読んだ、文芸春秋二〇一二年五月号の随筆欄に載った、江崎玲於奈博士の「人の心」という小文が心に残りました。人間の心はハートとマインドの両面がある、というようなことを論じていらっしゃいます。
夏目漱石の「こころ」を英文に訳すと、The mind of Things である。そして、定冠詞The と不定冠詞 A の話から、欧米人は会話の中でも「何が新しいか」を常に意識しているという話になります。 研究発表でも「A 超格子を論ずる」というのと、「The 超格子を論ずる」では大きな違いがある。つまり、リーダーは前者で後者はフォロワー(追従者)とされる。
サイエンスは「A 」を追及してやまないことは周知のとおりである、などと論じられています。
歴史学も社会科学の一部門と名乗っているようですが、日本古代史の分野では「サイエンス」には程遠いなあ、せめて魏の時代の「里」とか「歩」の、学際的な研究プロジェクトでも立ち上げればサイエンスに近づくのになあ、などと、東京大学大津透教授の『神話から歴史へ01 神話から歴史へ』を読んで感じているところです。
(十)『真の天皇の歴史01 神話から歴史』
大津教授の『天皇の歴史01 神話から歴史へ』を読んで、いろいろと意見を述べてきました。では、『本当の天皇の歴史 神話から歴史へ』がお前には描けるのか、というご意見があることでしょう。
今まで恐れ多くも東京大学現職古代史の教授殿の歴史の当否を論じてきました。その責任をとる意味で、非才を省みず今回意見をいろいろと述べてきたことの骨子を、『真の天皇の歴史 神話から歴史』としてまとめてみます。
★縄文期
まずそのためには、考古学的に日本列島に生きた人類の残した遺物遺跡から、「天皇」の原始的な姿を可能な限り復元してみる必要があるでしょう。
縄文時代の巨木遺跡や集落跡などから、その地域ではかなり高度な社会生活がいとなまれていたことが推察されます。 ただ、火山活動地殻変動による津波などの影響を受けやすい太平洋側よりも、四方を大陸と日本列島に囲まれている日本海という内海のほうが安定した生活が行われたのではないかと思います。
また、太古には豊かな生活を送っていた瀬戸内が、縄文海進によって壊滅されたり、九州及び西南諸島の火山の爆発などなどから、縄文時代の復元は極めて難しい面があります。しかし、縄文時代の貴重品、黒曜石の出土分布から、古代の日本列島の地域間の交流があったことが証明されると思います。
何と言ってもこの時代の大きな特徴は、日本海という内海での交流と、巨木建築と縄文土器でしょう。いずれも、かなりの数の人々の集団が存在し、リーダーシップをとるグループが存在しなければ出来上がらなかった、と言えるでしょう。
縄文時代といっても始まりは紀元前九千~一万年前ともいわれます。ここでは『天皇の歴史』という大津教授の著書に関係する縄文晩期(紀元前一千五百年ころ)からスタートしましょう。
縄文時代の巨木遺跡には、北から、青森県三内丸山・秋田県伊勢堂岱・新潟県寺地・石川県真脇、チカモリ、桜町他などが上げられます。これらの巨木遺跡と現在に祭典および建築として残っている諏訪神社・出雲大社などから、誰しもがこれらの遺跡遺構に、単なる村長的でない、巨大な権力を持つ支配者の存在を感じるのではないでしょうか。
それが『天皇の歴史』の始まりでしょう。
★弥生期と天孫降臨
縄文時代から弥生時代に入るのですが、ここで弥生時代の定義をはっきりさせておかないと、日本列島でどのように縄文から弥生に変わったのか、がはっきりしないことになります。
新石器時代つまり青銅器時代というように道具によっての区分ではないので難しい所があります。それに、わが国に鉄器が入って来たのも青銅器とそれ程遅れていず、ほぼ同時期紀元前四百年ころに入ってきています。
また、狩猟・採集時代から、大陸から伝来した水稲栽培による生産力増大による新時代に入った、といっても、日本列島ではかなり差があるのです。稲作によって文明が始まった、と考えると、農業に頼らない、東アジア北方民族の文明は?という疑問が生じます。
わが国の稲作の歴史は紀元前一千年に遡ると言われます。福岡県板付・野多目、佐賀県菜畑、高知県居徳、岡山県南溝手などなどの水田遺構や炭化米が発掘されています。水稲栽培による生産力増大が政治的変革(つまり国家の誕生)を生んだ、それが弥生時代という定義がおかしくなっているのが現状でしょう。しかし、ここでその論議をしていても切りがありませんので先に進みます。
国内の伝承として『古事記・日本書紀』の伝承つまり「神話」があります。古代史学の先達、津田・井上による「『記紀』神話は後年の史官の創作」、という極め付けから外れ、神話には真実の歴史が隠されているとみれば、新しい『天皇の歴史』も見えてきます。
後漢書に見えるわが国と中国の通交の記録に、一世紀~二世紀についてのわが国の状況について次の記事があります。五七年に「委奴国王に金印を下賜した」というのと、107年に「倭国王帥升が貢献してきた」という二つの記事です。 この「倭国」も漢委奴国王印という金印が福岡県志賀島から出土したことで有名です。
しかし、これらの倭王たちはわが国の伝承に残っていないようです。 『記・紀』の神話から見えるいわゆる「天孫降臨」はわが国が青銅器時代に入ってまもないころかと思われます。考古学的出土品から推定すると紀元前四~五世紀ころかと思われます。
『記・紀』神代部分の舞台は、殆んどが九州で、古事記では出雲もかなりの部分を占めています。 「天孫降臨」とは、「アマ(海人)族(天孫族)」が対馬・壱岐方面から九州北部に侵入に成功したのが「天孫降臨」神話となったものと思われます。そうすると、委奴国王も当然この天孫族一統であろう、と言うことになります。
『記・紀』神話において神々の系譜は記録され、神武から平成期まで繋がっています。ところが、神話に於いて神武の系譜を逆に辿ると、天孫族の正統ではないことが判明します。 金印を下賜された委奴国王、中国に遣使した倭王帥升は天孫族本流の王たちであった、ということになります。
★神武東征伝承と邪馬壹国
なぜ、これらの輝ける倭王たちが日本の史書『記・紀』に残っていないのでしょうか。『日本書紀』に奇妙な参考書名が出ています。その名は『日本旧記』です。おそらく天孫族本流の歴史を綴った『日本旧記』なる書物は、『日本書紀』編集者たちが参考にし、必要部分は取り込み、分流たる神武以降の流れを唯一とするために、不要部分は闇に葬られたのでしょう。
ところで、倭国王帥升の時代の『記・紀』の伝承と照合するとどうなるのでしょう。紀元一世紀ごろの状況としますと、神武天皇の兄たちが高千穂の宮で、ここにいてもうだつがあがらないから、どうしよう、東の狗奴国(銅鐸族)に攻め込もうか、と計画し実行したころになります。
別天地を目指すことは倭国王帥升にとっても悪い話ではないので、いろいろ根回しもしてやったことでしょう。 そして神武東征と後に伝承されるように大和の一角に天孫族分流が根拠を持つことが出来た、ということになります。
一世紀~三世紀にかけて倭国は動乱の時期があった、と中国の史書は書きます。天孫族と銅鐸族の戦いが続いていたのでしょう。その後の姿が三世紀の『魏志』「倭人伝」に描かれています。但し、九州近傍エリアが対象ですが。 そこには邪馬壹国(いわゆる邪馬台国)が朝鮮半島南端部と対馬・壱岐および九州島に女王国が君臨していたことを書いています。
この邪馬壹国は委奴国の後裔の国です。 そこには百余国の小国が乱立していて、その内の三十国がまとまって邪馬壹国となり、卑弥呼という女王が男弟と共に治めていた、とあります。その女王国と対立していた狗奴国と戦争になり、卑弥呼は魏朝に応援を求めます。
魏は二四七年に塞曹掾史張政を派遣します。卑弥呼が死んで男王が立ったのですが国が治まらず、卑弥呼の宗女(養女か)壹与を立てて治まります。壹与は266年に張政を送り届けた、と書かれています。張政は十九年という長い時を邪馬台国で過ごしたことになります。
この卑弥呼の時代の統治組織として注目されるのは「姉弟統治」です。壹与の場合について史書は何も書いていませんが、即位時に十三歳という若さから考えると、誰かとタッグを組んでの統治であったろう、と想像されますが、確証はありません。 この時期のことについて国内の伝承(『記・紀』)からみてみますと、神武から八代を経て崇神か垂仁天皇あたりになろうか、と思われます。
倭人伝にその他の旁国の最後に記載されている「奴国」=「神武が建てた国」と思われ、代々の天皇の多くは「大倭」という邪馬壹国の官職名を名乗っています。
崇神天皇はその名「ミマキイリヒコ」から見て、若い時分狗邪韓国(任那)で過ごし、邪馬壹国の協力を得て兄タケハニヤスを排除し強大な政権を立てることができたと思われます。
『日本書紀』では倭人伝の女王たちを「神功皇后」にみたてているようですが、神功皇后の伝承内容と卑弥呼のそれとは、年代も含め全く合いません。卑弥呼は九州地方の女王であり、神功皇后は近畿地方の女王なのです。
★好太王碑文と『宋書』の倭の五王
次の好太王碑文に出てくる「倭」はどこを本拠にしていたのでしょうか。 好太王と同時代のわが国の伝承についてみてみますと、応神・仁徳天皇あたりになります。
応神天皇の父、仲哀天皇は海の向こうに国があることも知らない天皇で、九州に来て地元の賊の矢に当って死んだとされますし、母の神功皇后は新羅の出身で新羅に遠征したとありますが、その北の高句麗(高麗)と戦ったという伝承はありません。
応神天皇の時代には新羅人の渡来・百済照古王から馬一番が贈られてきたことを『古事記』は記していますし、『日本書紀』には葛城襲津彦の百済派遣の記事など朝鮮半島関係の記事が多く記されています。これらを検討すると「倭国」の記事を近畿大和朝廷の事績として取り込んでいます。しかし、高句麗(高麗)との戦闘については全く記されていません。
次の仁徳天皇にしても『古事記』には外国との通交を伝える記事は皆無です。『日本書紀』には、新羅が朝貢しないのを咎めたとか、百済の酒君が無礼なふるまいがあり葛城襲津彦が連れ帰った、呉・高麗が朝貢した、とか沢山の外国の通交記事がありますが、高句麗(高麗)との戦闘記事はありません。
この好太王碑文の「倭」は、『宋書』にある倭の五王の倭王讃の九州を主地盤とする「倭国」以外にはありえないのです。 『後漢書』の委奴国~『魏志』の邪馬壹国~『好太王碑文』・『宋書』の倭国と一貫として外国史料は九州に本拠を置く「倭国」として認識していて、近畿の大和朝廷は表には出ていない、と言えます。
倭の五王の最後の倭王武について、近畿王朝の雄略天皇ではないか、九州の江田船山古墳出土の大刀の銘や関東の稲荷山古墳出土の鉄剣銘にワカタケルとあるのがその証拠、と通説ではされていますが、検討の結果そうではなく、むしろそれらは、それぞれの地域の大王が存在した証拠だったのです。
百済王から贈られた七枝刀の銘文にある「倭王旨」も、近畿王朝に該当する人物を見いだせないのも道理で、この「一字名」を名乗る伝統が存在した「倭の五王」の系列の「倭王」であったのです。 倭王武の時代に中国では南朝系「宋」が滅亡し以後「斉」「梁」「陳」と禅譲で帝国は続きますが、「倭国」が朝貢した記録はありません。
★継体期の王統断絶から推古期の阿毎多利思北孤
近畿の大和朝廷の記録では武烈天皇(在位498~507年)に子がなく、応神天皇五世の孫、継体天皇の登場を記します。常識的にみてこれは王朝の断絶です。
『日本書紀』はこの継体天皇即位の正当性を強調するために、悪逆非道の武烈天皇をはじめ、仁徳・履中・允恭・雄略各天皇の悪行を記しています。
継体紀に『百済本記』の「日本天皇・太子・皇子倶に薨ず」という記事があります。この記事が継体の没年とすると、その干支年と継体天皇の国内伝承の没年が合わないので、『日本書紀』編集者も後年の研究者にまかせたい、旨を記しています。
この『百済本記』の記事と継体紀にある「磐井の乱」の筑紫君磐井の一族の死と結び付けようとする試みが、多くの研究者によってなされていますが、まだ確証を得るには至っていないようです。『日本書紀』によっても、物部アラカヒに「長門から以西はお前がとれ、以東は自分が、・・」と言っているし、磐井の子、葛子が粕屋の屯倉を献上し罪を許された、とあります。
『日本書紀』の記事がその通りであったとしても、倭王武以降の王朝もまだ命脈は保たれた、といえるでしょう。
六世紀になって北朝系「隋」が成立します。『隋書』に登場する「俀国(大委の意でしょう)多利思北孤王」は、六世紀末から七世紀初めに在位していた、と思われます。
当時の近畿王朝では推古朝になります。推古天皇は女帝であり、妻子がある多利思北孤ではあり得ません。まして、日の出までは自分が、そのあとは弟に政をまかせる、という兄弟執政は近畿の大和王朝には見られません。
聖徳太子が代理を務めたのではないか、としても太子の名は「利歌弥多弗利」と『隋書』にありこれも無理で、謎とされます。しかし、今まで見て来たように、九州に本拠をおく「倭国」の多利思北孤が天子を名乗ったのであり、太子はカミタフの利という名で、謎でも何でもないことになります。
★倭国から日本国へ
その俀国は数度の遣隋使を派遣のあと、610年の記事の最後に「遂に絶つ」と国交の絶えたことを記しています。
「隋」のあと建国した「唐」の『旧唐書』には、「倭国」と「日本国」が併記されています。「倭国」は委奴国~邪馬壹国~倭国~大委国( 俀〈国)という繋がりの国で、「日本国」は倭人国の別の国で「倭国」を併合した、とあります。
白村江の百済復興戦(663年)で敗戦し、筑紫君薩夜麻が捕虜となり、「倭国」は滅亡したのです。
当時の近畿王朝は斉明女帝でした。「倭国」と共同して百済復興の戦いに参戦する構えでしたが、斉明女帝の死去により、中大兄皇子は喪に伏すと軍を引きます。白村江の敗戦で唐との戦後処理が見極められるまで天皇位は空席とし、七年間「称制」として天皇制を中断し、天智天皇が即位するのは六六八年です。
701年(文武五年)に大宝律令を定め、唐の則天武后の承認も得て元号大宝と定め、晴れて天孫族分流が世界史の表面に出てきて、現在の平成時代の今上天皇に至った、ということになります。
天孫族本流の末裔筑紫君薩夜麻のその後については、続日本紀に部下が身を売って唐軍の先触れ役として帰国することができた、と記されています。このような不名誉な役回りをさせられて以後の消息は不明です。
一応、便宜的に、神武天皇・雄略天皇・継体天皇・天智天皇などと、「天皇」という称号を付けて述べてきました。しかし、今まで見てきましたように、701年になって文武天皇が晴れて天皇位を名乗れるようになったのであり、それ以前の大王達には天皇位を追贈された、ということ、つまり天皇ではなかったのだ、ということを記しておきます。
★終わりに
このような、日本の古代の支配層の流れ、九州から近畿へ分流が居着き、本流は朝鮮半島に干渉して唐によって潰され、最終的に分流の大和王朝が残った、ということになります。
この流れの中に、出雲・吉備・関東・東北などの地方王朝が吸収されていったことになります。
一番の問題には、天武天皇が史書編纂にあたって「削偽定実」という方針が、新王朝に役立つものを採り、そうでないものは偽王朝のものとして削除した『日本書紀』を、後世の史家たちが唯一の正史として疑わなかったことが上げられます。
大津教授が、このような真実の流れを確かめ、あらためて、『天皇の歴史01 神話から歴史へ』を再構築されたならば、後世に名を残すことになるのは間違いないと思っています。
難しい願いかも知れませんが、一老学生としてはこのホームページの本稿を、東京大学をはじめとする国史学を学ぶ学生に読んでもらい、忌憚ない批評を仰ぎたいということです。
これまでこのホームページで沢山の古代史関係の本を批評してきましたが、これほど手古摺った本はありませんでした。かかってから終えるまで正味10カ月要した本はこれが初めてです。古田先生の尻叩きも頂きなんとかホームページに掲載することが出来ました。
幸い、古田武彦先生の沢山の著作や沢山の先人の業績を頼りになんとか終えることが出来ました。ブログでもぼやきながらの棟上寅七に、いろいろとご助言頂いた沢山の方々にもお礼申し上げなければなりません。
ネットに上げるに当って、いくら感謝してもしきれない程有難く思っていますことを記して結びとします。 (この項終り)
トップページに戻る
著作者リストに戻る
参考図書
『魏志倭人伝 他三篇』 石原道博編訳 岩波文庫 1951年
『旧唐書倭国日本伝他二篇』 石原道博編訳 岩波文庫 1956年
『古事記』 倉野憲司校注 岩波文庫 1963年
『日本古代国家論 第一部』 石母田正 岩波書店 1973年
『日本国家史1古代』 原秀三郎ほか 東京大学出版会 1975年
『古語拾遺』 西宮一民校注 岩波文庫 1985年
『万葉集(一)』 中西進 講談社文庫 1978年
『続日本紀(上)』 宇治谷孟 講談社学術文庫 1992年
『日本書紀(一)~(五)』 坂本太郎他 岩波文庫 1994年
『俾彌呼』 古田武彦 ミネルヴァ社 2011年
『「邪馬台国」はなかった』コレクション版 古田武彦 ミネルヴァ社 2010年
『失われた九州王朝』コレクション版 古田武彦 ミネルヴァ社 2010年
『盗まれた神話』コレクション版 古田武彦 ミネルヴァ社 2010年
『よみがえる卑弥呼』コレクション版 古田武彦 ミネルヴァ社 2011年
『古代史の十字路』コレクション版 古田武彦 2012年
『邪馬一国の道標』 古田武彦 講談社 1978年
『ここに古代王朝ありき』 古田武彦 朝日新聞社 1979年
『関東に大王あり』 古田武彦 創世記 1979年
『邪馬一国の証明』 古田武彦 角川文庫 1980年
『よみがえる九州王朝』 古田武彦 角川書店 1983年
『風土記にいた卑弥呼 古代は輝いていた』 古田武彦 朝日文庫 1988年
『日本列島の大王たち 古代は輝いていたII 』 古田武彦 朝日文庫 1988年
『法隆寺の中の九州王朝 古代は輝いていたIII 』 古田武彦 朝日文庫 1988年
『まぼろしの祝詞誕生』 古田武彦 新泉社 1988年
『真実の東北王朝』 古田武彦 駸々堂出版 1990年
『神武歌謡は生きかえった』 古田武彦他 新泉社 1992年
『倭人伝を徹底して読む』 古田武彦 朝日文庫 1992年
『人麿の運命』 古田武彦 原書房 1994年
『失われた日本』 古田武彦 原書房 1998年
『古代に真実を求めて 第一集』 古田史学の会 1999年
『君が代を深く考える』 古田武彦 五月書房 2000年
『壬申大乱』 古田武彦 東洋書林 2001年
『年報日本思想史第9号』2009年「近世出土の金石文と日本歴史の骨格」古田武彦
『銅鐸が描く弥生時代』 金関恕 佐原真 他 学生社 2002年
『魏志倭人伝を読む 上・下』 佐伯有清 吉川弘文館 2000年
『邪馬台国論争』 佐伯有清 岩波新書 2006年
『考古学はどう検証したか』 春成秀爾 学生社 2006年
『太宰府は倭国の首都だった』 内倉武久 ミネルヴァ社 2000年
堤克彦 熊本大学社会文化科学研究科研究紀要「江田船山古墳被葬者他」2010年
『日本の歴史1神話から歴史へ』 井上光貞 中公文庫 1973年
『日本の歴史03大王から天皇へ』 熊谷公男 講談社 2001年
『倭の五王の謎』 安本美典 現代新書 1982年
『古代史紀行』 宮脇俊三 講談社 1990年
『邪馬台国は古代大和を征服した』 奥野正雄 JICC 出版 1990年
『古墳とヤマト政権』 白石太一郎 文春新書 1998年
『磐井の乱』 田村圓澄・小田富士雄・山尾幸久共著 大和書房 1998年
『歴史から消された邪馬台国の謎』 豊田有恒 青春出版 2005年
『聖徳太子と日本人』 大山誠一 角川文庫 2005年
『日本の誕生』 吉田孝 岩波新書 2006年
『倭人伝を読みなおす』 森浩一 ちくま書房 2010年
『倭国とは何かII』 九州古代史の会編 不知火書房 2012年
『虚妄の九州王朝』 安本美典 梓書院 1995年
『詳説 日本史B』 石井進ほか 山川出版社 2007年
『石川日本史B①原始~古代』 石川昌康 語学春秋社 2006年
『高等学校学習指導要領解説』地理歴史編 文部科学省 2005年
『昭和天皇独白録』 寺崎英成 文春文庫 1995年
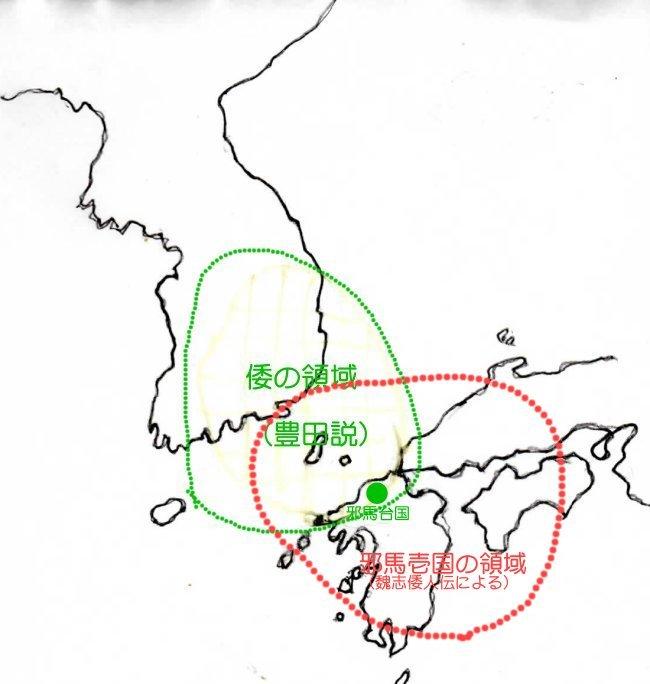
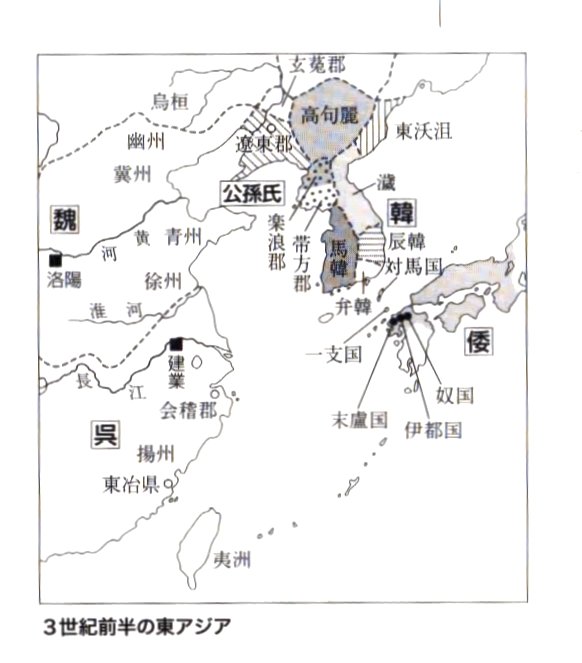

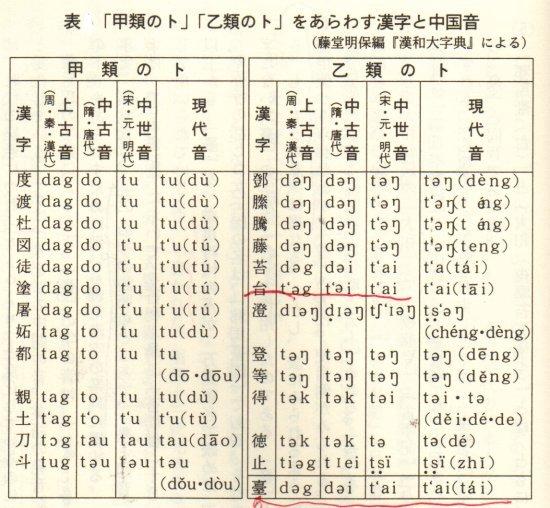


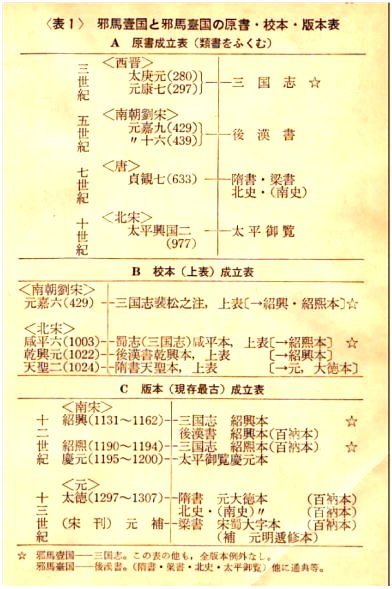
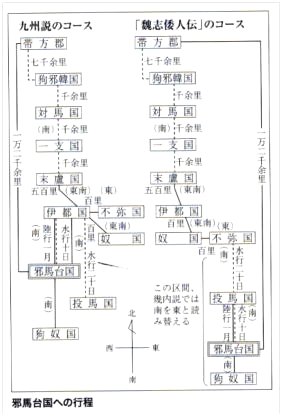
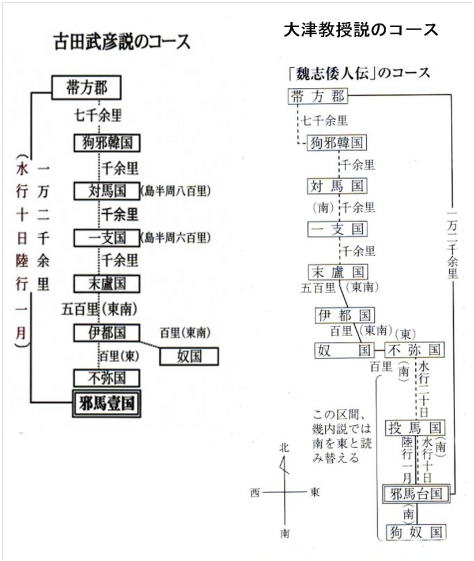
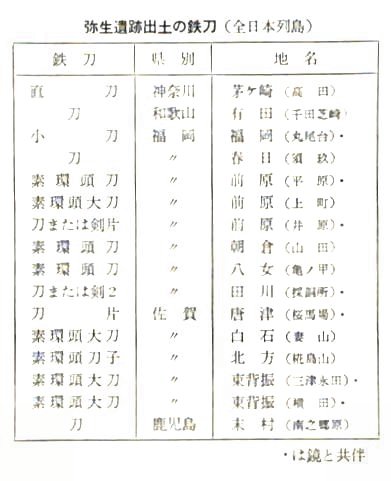 た、近畿地方の古墳からの「三種の神器」セットは、九州地方のに比べると明らかに貧弱だという事実もある。 「三種の神器」の出土事実から、『記・紀』の叙述が真実で、近畿天皇家の万世一系論が復活出来るかというとそうではない。
た、近畿地方の古墳からの「三種の神器」セットは、九州地方のに比べると明らかに貧弱だという事実もある。 「三種の神器」の出土事実から、『記・紀』の叙述が真実で、近畿天皇家の万世一系論が復活出来るかというとそうではない。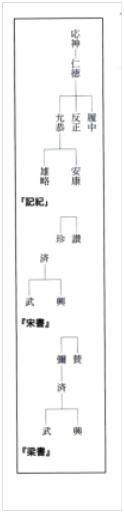
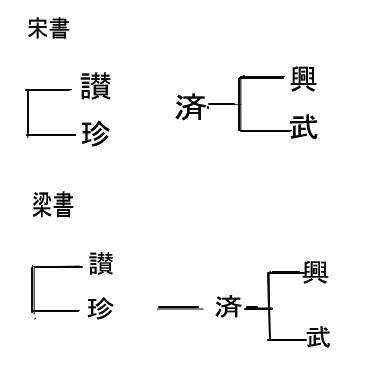
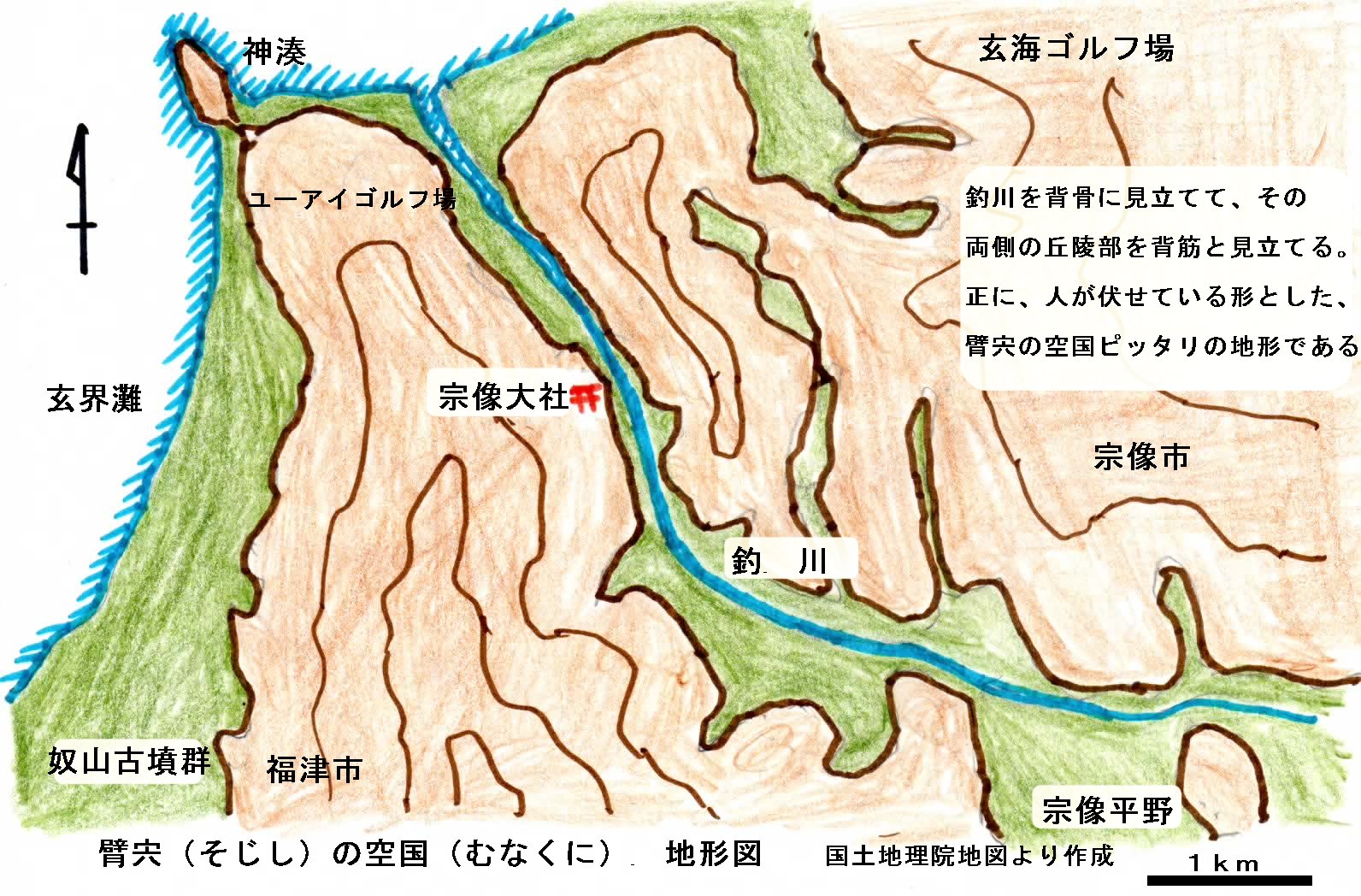 宗像の地形は、筑紫の他の河川河口部平野の形と違っています。現在でも宗像大社の横を流れる釣川という川が、玄界灘に流入する河口付近に、五キロほどにわたって両側に丘陵地がせまっています。「膂宍」とは「背中の肉」という意味ですが、その地形は人が伏せた形をしていて、古代人の表現力に驚かされます。
宗像の地形は、筑紫の他の河川河口部平野の形と違っています。現在でも宗像大社の横を流れる釣川という川が、玄界灘に流入する河口付近に、五キロほどにわたって両側に丘陵地がせまっています。「膂宍」とは「背中の肉」という意味ですが、その地形は人が伏せた形をしていて、古代人の表現力に驚かされます。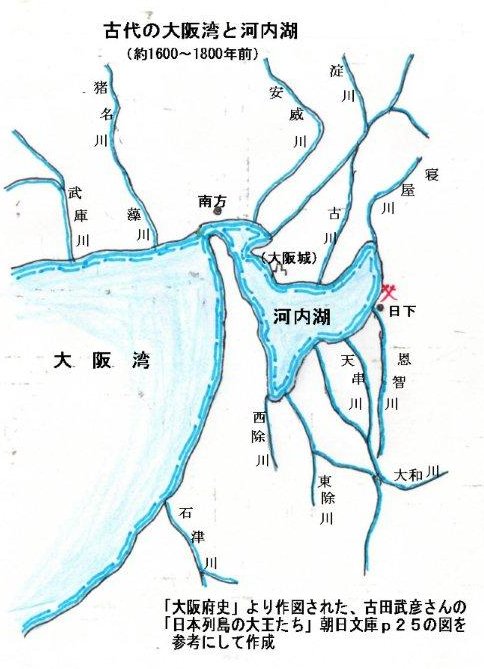
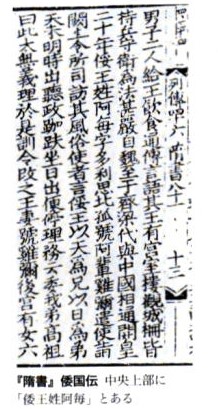 大津教授の『隋書』俀国伝に対する基本的な問題として、「俀国伝」を何ら説明もなく、「倭国伝」と変更されて話を進められることが上げられます。
大津教授の『隋書』俀国伝に対する基本的な問題として、「俀国伝」を何ら説明もなく、「倭国伝」と変更されて話を進められることが上げられます。