このような単純な論理による結論を、なぜ偉い学者先生方は認めようとしないのでしょうか?
「委」はわが国では「わ」と読まれていた、と主張する学者もおられないわけではありません。
【志賀島金印公園に設置されている金印の拡大印章 正面は能古島 筆者写す】

『魏志』倭人伝の「奴」の読みについて 中村通敏
金印の五文字の読み方
まず、「奴」が我国に関係する文章として出てくる、『後漢書』にある「倭奴国は倭国の極南界」の記事と、志賀島で出土した金印の「漢委奴国王」の五文字のなかの「奴」です。
建武中元の記事の原文は次の通りです。
「建武中元二年倭奴国奉貢朝賀使人自称大夫倭国之極南界也光武賜以印綬」
『天皇の歴史 I』講談社 での東大教授大津透氏の読み方は次です。通説の代表と言ってよいでしょう。
”倭の
この読み方ですと次の様な疑問が出てきます。
①「倭奴国」は「倭の奴国」でよいのか。
②「倭国之極南界也」は「倭国の極南界なり」でよいのか。 意味は通るのか?
③「光武賜以印綬」は「なに」を以って印綬をあたえたのか。与えた理由は何か?
①については古来諸説があるようです。志賀島から出土した「漢委奴国王」印の「委奴国」も同様の問題を含んでいます。
金印の「委奴国」の読み方は後にして、まず『後漢書』の記事の「倭奴国」の読み方について検討します。
中国の天子が夷蕃の国に「漢の倭の奴国」というように、三段読みをするような小さな国へ印綬を与えた例があるのでしょうか。つまり、倭国の中の奴国という、間接的な支配権がある小国に直接印綬を与えるものでしょうか?
これは例えて言うと、江戸時代に幕府が陪臣に直接領地の支配権を与えるようなもので、理解しがたいことです。やはり、ここは、漢帝国が自分の庇護下にあることと支配権を認めることを示した印綬渡し、と考える方が合理的解釈と思われます。
通説の「漢の倭の奴国」という三段読みに対する問題提起は、稲葉岩吉 (陸軍大学教授)という方が、一九一一年『漢委奴国王印考』で次の様になされています。
【一、奴国という小国の名が知られたのは魏の時からであり、漢代には未だ知られていなかった。
二、金印は「奴」のごとき小国に与えるものではない。
三、「漢の委の奴」と分けて読むは漢制に即していない。金印を与えるのは宗主国(中心の統率国)に対してであって、その陪従者(被統率者)ではない。漢が、倭の陪従者である「奴」を認めて大国の王となし、金印を与えたとするのは、正に不通の説である】(三品彰英『邪馬台国研究総覧』より)
しかし、古代史関係の学会は、学会のボスの主張に反する意見に対して「無視する」という悪弊がはびこっているようです。古田武彦氏の「邪馬壹国論」も同様に無視する、ということで、丸でそんな議論など存在していないかのような古代史学会であることはご存知の通りです。
論理的にいえるのは、「漢の倭奴国」に印綬は授けられたのであって、「漢の倭の奴国」にではない、ということです。
『後漢書』の「倭奴国」の読みは
そうすると「倭奴国」とは何と読むのでしょうか。『後漢書』が「倭奴国」に印綬を与えた、と書いているのです。その与えた時期は西暦五七年とこれはハッキリしています。この一世紀前後の読みについても諸説あるようです。
問題を整理して、以下の三つを確認しておきます。
① 倭と委は同じ意味なのか。
② それぞれ何と読まれていたのか。
③ 奴は何と読まれていたのか。
漢字の読みの解釈は難しいものです。例えば「奴」について辞書を引いても、漢音では「ド」、呉音では「ヌ」と言う説明があるのが一般的です。その、漢音・呉音が使われていた時期や地域についても諸説があります。しかも「倭」や「委」については、「ゐ」から後代には「わ」になった、という問題があり、その読みを複雑にしています。
倭を「ヤマト」と読み、奴を「ノ」と読んで「ヤマトの国」とこじつけたのは、江戸時代の亀井南瞑です。一般的に、「倭」は「ヰ」「ワ」の両説、「奴」は「ド(ト)」「ヌ(ノ)」「ナ」の三つの読み方。 この双方を組み合わせて、「イド、イヌ、イノ、ワド、ワノ」などの読み方が得られています。なぜか、「イナ」「ワナ」説は日本語〈やまとことば〉的でないのか、あまり見られないようです。
『後漢書』に「倭奴国」として出ていますが、『魏志』倭人伝には「伊都国」という国名が出てきます。それで読みの類似から「倭奴〈ゐど〉=伊都〈いと〉国」説が一般受けされるようです。
この倭奴国は、印綬下賜の半世紀後にも「倭国王帥升が朝貢した」という記事が出てきていますから、この倭奴国が倭国の代表であったという理解の方が、「倭国の中の奴国」という理解よりもはるかに合理的です。
後の中国の正史『旧唐書〈くとうじょ〉』にも「倭国は古〈いにしえ〉の倭奴国也」とあります。「倭国の中の奴国」という小国ということではとても理解できないのです。
また、同じく中国の正史『隋書』には、倭国伝ではなく、俀〈たい〉国伝として記されています。岩波文庫では、この『隋書』の俀国伝を倭国伝と書き換えて紹介しています。俀は倭の誤記として取り扱っていますが、そのように中国の正史の記事を、根拠も示さず、「誤記」として取り扱ってよいものでしょうか。
しかも、隋の煬帝は教科書にも出ていますが、俀国王多利思北孤〈たりしほこ〉から、【日出る所の天子、日没する所の天子に書を致す恙〈つつが〉無きや】という国書をもらい激怒しています。その『隋書』になぜ俀国なる言葉が出て来たのか、を考えてみればわかることです。
多利思北孤は自分の国を大倭国と自称していたと思われるのです。国書に大倭〈だいゐ〉国天子と自署名していたものと思われます。怒った煬帝は、何が大倭〈たいい〉だ、俀〈たい〉国でよい、としたのでしょう。俀は、弱いという意味のある漢字です。つまり、七世紀初めの煬帝の時代まで「倭」は「ヰ(イ)」と読まれていたことの傍証になります。
また「奴」は、皆さんご存知のように、わが国のひらがなの「ぬ」は「奴」のくずし文字です。八世紀以前に成立したといわれる『万葉集』には、「奴」は全て「ぬ」であって「ど」という読みに使われていません。
金印の「奴国」とは?
史書では「倭奴国」なのに、実際に与えられた金印には「委奴国王」と「倭」でなく「委」が使われているのは、「倭」と「委」が「漢代」では同じ読みであったことは間違いないと言えるでしょう。
この同じ読みが「わ」なのか「ゐ」なのかという問題が次に残ります。
古今の辞書を引いても、「委」は「ゐ」「い」の二つの発音だけしか無く、「わ」の読みは存在していないのですから、「奴」の読みがなんであろうと、委奴国を「わ奴国」と読めないという論理になります。つまり、定説の「わのなこく」はありえない、ということになるのです。
このような単純な論理による結論を、なぜ偉い学者先生方は認めようとしないのでしょうか?
「委」はわが国では「わ」と読まれていた、と主張する学者もおられないわけではありません。
【志賀島金印公園に設置されている金印の拡大印章 正面は能古島 筆者写す】

考古学者森浩一先生は、【木簡に「伊委之」と「いわし」の事を書いてある。だから「委」は「わ」と読んでいた】といわれます(『倭人伝を読みなおす』ちくま新書)。
森浩一先生は、一九二八年生まれ。同志社大学卒で同志社大学教授。考古学の泰斗と言われましたが、残念ながら二〇一三年に歿されました。いわゆる邪馬台国九州山門説の方で、北部九州から邪馬台国が東遷した、という説です。考古学者でありながら、古代の遺物の重要な品目「鉄」と「絹」について全く取り上げられないという不思議さがあり、文字文献についても、「臺」の字を「壹」と『魏志』に書かれているのは、「減筆」による、というような非常識とも思える説を提唱されています。
この『倭人伝を読みなおす』という著書については、わたしは棟上寅七のペンネームで、その本の書評を書いてネットに出しています。次の検索語、「槍玉その45」を入力すると読むことが出来ます。
この、森先生が指摘されるその「いわし木簡」は、しかし、八世紀頃のものです。八世紀のわが国では、「倭」を「やまと」、倭国を「やまとのくに/わこく」と読ませていたようです。ですから、「伊倭之」と書くべきところを、略字を使って「伊委之」と木簡に書いた、という可能性の方が高いと思いますし、八世紀のわが国の「委」の発音が「わ」だから、一世紀の中国の「委」の発音も同じ「わ」という証拠にするには弱いと思います。「委」は「ゐ(い)」なのです。
「委」の読みが「ゐ」であって、かつ金印の読みは三段読みにするべき、奴は「な」である説とすれば、その読みは、「かんのゐのなこく」となるのですが、古来どなたもそのような主張はされません。つまり、「委」を「わ=やまと」という前提での三段読みということなのです。
この様な議論を論理的に考えれば、三段読みはありえず、二段読み、つまり「漢の委奴の国王」となります。つまり「委奴国」であり、二百年余の後の『魏志』倭人伝に出てくる「奴国」とは違う国名ということです。
「委」が「わ」と読めないのであれば、「委奴国」は「ゐ(い)どこく」又は「ゐ(い)ぬこく」のいずれかになる、というのが、論理が至る道筋でしょう。
金印の「委奴国」の読みは、「ゐどこく」か「ゐぬこく」となるというこの結論は、金印に刻んである「奴国」は、「委奴国」であり、わの「奴国」として教えこまれていた一般人の常識とは異なるものです、それに、金印を貰った国「倭奴国」と「奴国」とは同じではない、ということになりました。
では、金印を貰った国は何という国なのか、「ゐどこく」なのか「ゐぬこく」なのか、「奴」の読みの検討にうつりましょう。
亀井南冥の著した『金印弁或問』天明四年 には次のように、「委奴=大和」説です。【ヤマトノクニノ云詞ニツイテ、奴ノ字ヲ加ヘテ、倭奴国〈ヤマトノクニ〉ト記シタルナルベシ。奴は華音ニテ、「ノ」ト出ルナリ】
つまり亀井南冥先生は「奴=ノ」と読むべき、「ヤマトノクニ」と説かれたのです。漢委奴国王を「かんのなのこくおう」と読んだのは、儒者竹田貞良です。この人は福岡藩藩校修猷館〈しゅうゆうかん〉の開設者です。
後日談になりますが、亀井南冥は後に罪をとがめられ閉門蟄居の身となり、折角金印の読みで名を挙げた甘棠館〈かんとうかん〉は潰れ、一方、修猷館は現在も、福岡県の最高クラスの高校として残っているのは歴史の皮肉でしょうか?
委奴国を「いどこく」と読んで、三世紀の史書『魏志』倭人伝に出てくる伊都国である、という説を唱えた人に上田秋成(一八世紀の国学者 『雨月物語』の作者)がいます。
現代でも、古代史研究家内倉武久氏(『太宰府は日本の首都だった』ミネルヴァ社刊 ほか著書多数)も伊都国説です。「奴」は漢音で「ト」であり「委奴国」は「伊都国」と、奴=ト説を主張されています。三世紀の倭人伝での「奴」についても「奴=ト」説は取られているようです。
金印に彫られている倭奴国の「委」は「ゐ」であり「い」とは発音が違った、という意見もあります。しかし、中国人が倭人の発音を聞いて書き表した国名でしょうから、「い」と倭人が発音しても、その「い」を「委〈ゐ〉」で書きあらわしている可能性は大です。
「委奴国=伊都国」説について指摘しておかなければならないのは、一世紀の金印に刻まれた「委奴国」が、後年、三世紀の倭人伝に記された「伊都国」と同じ国とすれば、なぜ倭人伝に「委奴国」もしくは「倭奴国」ではなく「伊都国」と書かれるようになったか、『三国志』の著者、陳寿が何らかの注書きをしてしかるべきでしょう。
後年五世紀に、『三国志』に詳しい注を付けた中国の史家、裴松之〈はいしょうし〉という人がいます。彼は。『三国志』本文よりも述べ字数の多い注を付けています。
彼が、後漢時代の倭奴国が伊都国であったとすれば、このような重要なことを見逃したのでしょうか。裴松之は『魏略』という、現代には断片的にしか残っていない書物から多数引用しています。『魏略』にも三世紀の「伊都国」は一世紀の「倭奴国」、もしくは「委奴国」だった、ということは書いていなかった、ということはいえるのではないでしょうか。
金印の「奴」の読みは
亀井南冥が「奴=ノ」と読むべき、と解釈したように、近世の日本語では「奴=ぬ・ど」が一般的ですが、古くは「奴=ぬ=の」であったようです。皆さんもご存知かと思いますが沖縄方言では、沖縄県人以外の日本人のことを「ヤマトヌ(ン)チュ」というように、今でも所有格の「の」は「ぬ・ん」と発音されています。(沖縄方言については、三世紀の倭人伝の「奴」の読み、にてもう少し詳しく述べます。)
「委」が「ゐ」であって、「奴」が「ぬ・の」であれば、「委奴国」は「ゐぬ(いの)国」になります。瑞穂の国の、水が豊かな「井野国」であった可能性はあるのではないかと思います。しかし、地名では、その「ゐぬ」「いぬ」「ゐの」「いの」という地名はかなり広範囲に見出されることと思います。
名前だけでなく、考古学的遺物などなど総合的に「委奴国」は比定されなければならないでしょう。わたしの住まいの近く福岡県久山町に、「猪野〈いの〉」という地名があります。旧かな遣いでは「ゐの」です。その地から、博多湾に注ぐ多々良川の支流「猪野川」という河川が流れ出しています。この近くの「八田」から銅矛鋳型の出土もあり、近くを流れる「タタラ」川という河川名から古代製鉄が行われた可能性も充分考えられます。その「猪野」の地には現在「伊野大神宮」が鎮座しています。充分「委奴国」の資格はあるように思われます。(猪〈ゐ〉=伊〈い〉という変換が無理なく行われている例でもあります。)
歴史が古い地域には、このような「ゐぬ」「ゐの」「いぬ」「いの」などの地域名は沢山残っていることでしょう。しかし、「地名の類似」からの「地名比定」、例えば「大和」と「山門」、「不彌」と「宇美」などには問題があると思います。
いずれにしても、「倭奴国」は中国側が表意的に付けたのか、日本側が名乗った名前に表音的につけた名前なのか、という問題は残ります。日本側が告げた名前を中国側が表音かつ表意的に記録したというのが常識的な解釈と思いますが。
言えることは、一世紀当時の倭人の国を統括していた「倭奴国」が、三世紀には「邪馬壹国」であったこと。そして、三世紀の「奴国」は、女王国の一員としての一国である、と中国の史書に記載されていることで、一世紀の「倭奴国」は決して三世紀の「奴国」ではないことははっきりした、ということでしょう。
三世紀の「奴国」をはっきりさせると、一世紀の倭人国の代表「倭奴国」が三世紀には邪馬壹国にと変わったという、その謎も解けるのではないでしょうか。そのためには、三世紀の我が国の状況を記載している、『三国志・魏書』東夷伝倭人の条(通称「倭人伝」)の記事を検討しなければなりません。
『魏志』倭人伝の「奴国」
金印を貰った一世紀の倭人の国を代表する「委奴国」と、三世紀の倭人伝にある女王国の下にある国々の内のひとつの国の「奴国」とは異なった国ということが、今までの検討ではっきりしました。
倭奴国王が貰った金印の漢の委の奴〈な〉の国王の読みも、その読み方の淵源をたどると、倭人伝の「奴国」の「なこく」読みから遡って援用されたと思われます。
そこで、一世紀の後漢時代の「委奴国」の読みは別として、三世紀の倭人伝に出てくる「奴国」は何と読まれたのか、ということをまずはっきりさせておく必要があります。
三世紀の『魏志』倭人伝に出てくる「奴国」とは何とよばれた国なのでしょうか。まず「奴国」の読みの諸説についてチェックしておきましょう。
「奴国」の「奴」については、「奴=ナ」ではない、「奴=ドもしくはノ・ヌ」という意見は多く、著者も以前、「奴はナにあらず」という小論を、棟上寅七のペンネームで述べたことがあります。(古田史学の会論集十二集)そこでは、その根拠として次のような説明をしています。
【倭人伝には沢山の表音文字が使われている。三十もの国名についても、倭人から聞いた名前と思われるものが漢字で表現されている。
しかし、不思議なことに、通説のように「奴=ナ」とすると、倭人伝には、国名に「ナ」が入る国が沢山あり、しかも、国名に「ノ」が入る国が一つもない、という現象が生じる。
我が国の地名や人名には「ノ」が入るのは、長野、上野、野田、日野、大野など沢山の例がすぐ上げられるように、ごく自然だ。「ナ」も同じように沢山の例が上げられる、という反論が出ることだろうが、倭人伝にあげられている三十もの国の名前に「ナ」が沢山入っていて、「ノ」が全くない、という結果をまねく通説の解釈は異常だ。この「異常さ」を数学的に見たらどうだろうか】、と検証したわけです。
女王国が統轄する三十の国名に「奴」が入っているのは八国です。『魏志』倭人伝では、対馬や壱岐などがそれぞれ「国」として表現されていますから、当時の「国」は今の「県」より小さく「郡」程の大きさのように思われます。
女王国の在処は、西海道の可能性が高いと思われますので、西海道の郡名を平安時代(十世紀)に編纂された辞書、『和名類聚抄〈わみょうるいしゅうしょう〉』からひろい上げ、その郡名を数えたら二五五郡だったのです。
その、二五五個の母集団には「ノ」を含むものが二十一個あります。今その集団から三十個を拾い上げたら「ノ」が一個も入らないという確率を計算したら、四%でした。つまり「奴」が「ヌ/ノ」である確率は九六%です。ここまでを論集十二集に述べたわけです。
又、「奴=ヌ」若しくは転訛〈てんか〉した「ノ」であったとしても、「ヌ」から「ナ」への転訛はありうるのでしょうか。この方面の権威故橋本増吉先生(一八八〇~一九五六年 )の著書を見てもそのあたりは判然としません。
しかし、「倭人伝」に用いられている表音文字には、「ナ」の表音文字が「奴」以外にもあります。「那」や「難」です。そのように「ナ」をあらわす文字があるのに「ナ」の表音文字として「奴」という文字を、それらと別に陳寿が選ぶのでしょうか?
しかし、日本の古代史学会は異常だと思われます。例えば内藤湖南先生でも、「奴」をあるときは「ナ」あるときは「ノ」と読んで平然としています。
同じ本の中でそれも同一の国名群に対して、このように「読み分ける」のはおかしいと思わないのは、裸の王様の家来たちと同じでしょう。
佐伯有清氏が『邪馬台国論争』という本で、内藤湖南先生の倭人伝の国々の地名比定地について次のように紹介しています。内藤先生のいい加減さを示す好例と言えましょうし、佐伯有清氏自体が、そのいい加減さに気付かずに紹介している例でもあります。
佐伯有清氏は、【内藤が卑弥呼を倭姫命に比定したのは、時代的にも、その係累からみても適当であるとし、魏志にある倭の国々を大和地方に比定してみせたからである】(『邪馬台国論争』)、と比定地を紹介しています。
内藤湖南は、倭人伝に記載されている次の九ヶ国にある一〇個の「奴」の字を「ナ」と読んだり「ノ」と読んだりしているのです。
「ナ」 は五カ所 ①奴国(筑前那珂)、②蘇奴国(伊勢佐奈)、③鬼奴国(伊勢桑名)、④烏奴国(備後安那)⑤奴国(再出)
「ノ」も五カ所 ①弥奴国(美濃)、②姐奴国(近江角野)、③華奴蘇奴国(遠江鹿苑)、④狗奴国(肥後城野)
このように、”ナ”でも”ノ”でもよい、地域のサイズも問わない、となれば、どこにでもこれらのワンセットの倭人伝に出てくる国々の名の比定はできるのではないの、と誰しも思うのではないでしょうか。
しかしながら、このような、中学生にでもおかしいと思われる判断をする、古代史界の泰斗に対して、よい大人の佐伯有清氏はじめ誰もが批判の声を上げないというのは、この日本の古代史関係学会は、異常な判断基準を持つ集団と言われても仕方がないのではないでしょうか。
同じ文書(『魏書』)の中に表音語として用いられている一つの漢字が、いくつもの音を著していることなどあり得るものではない、というこれも中学生でもわかる論理性を無視した日本の古代史学会の定説なのです。
ちなみに佐伯有清氏は、(故人二〇〇五年歿)邪馬台国論について多数の著書があります。最後の著作となりましたのが『邪馬台国論争』岩波新書二〇〇五年です。
佐伯氏は、若い時分は“東大の九州説”のような論調でしたが、晩年には京大の近畿説に近寄られたようで、最後の著作では「内藤湖南への回帰」つまり近畿説になったことを述べています。
『邪馬台国論争』の棟上寅七の批評文はパソコンで次の検索語「槍玉その16」を入力することで読むことが出来ます。
奴は「ナ」ではない、の古田武彦説
「奴国」は「なこく」ではない、ということを述べたのは古田武彦氏です。氏は、『魏志』倭人伝の中に用いられている「奴」は、「ド/ト」若しくは「ヌ/ノ」であり、「ナ」ではない、ということについて、その著『よみがえる九州王朝』第二章「邪馬一国から九州王朝」で次のように述べます。
【(三角縁神獣鏡について王仲殊論文が日本の考古学に与えた問題について述べた後)方法上、これに関連する重要なテーマがある。それは「博多湾岸、奴国説」だ。先ほどふれたように、これは先ず本居宣長の唱導にもとづくものだ(新井白石も『古史通惑問〈こしつうわくもん〉』で那珂〈なか〉郡としていた)。
「かの伊都国の次に言へる奴国は、仲哀紀に灘県〈なのあがた〉、宣化紀に那津〈なのつ〉とあるところにて、」(『馭戎慨言〈ぎょじゅうがいげん〉』)という通りである。しかしながら、この宣長の論定方法には大きな欠陥がある。なぜなら倭人伝の表音体系の構造を無視しているからだ。この点、本題に入る前に一言しておこう。
倭人伝には「弥弥〈みみ〉」「弥弥那利〈みみなり〉」というように、「那」が表音表記に使われている。これは明らかに「ナ」の音だと考えられる。従ってもし博多湾岸を“「ナ」国”であるとしたら、ではなぜ「那国」と書かないのか、という問題が生じる。現に宣長も指摘している通り、後世「那の津」と書かれているではないか。これに対し、“「那」は、三世紀には「ナ」と読まなかった”。そのように論者が主張したいのならば、彼等はそれを“立証”せねばならぬ。なぜなら右の「弥弥那利」は「みみなり」と読む点において、異議提出者を見ないのであるから。しかし、わたしはそのような論証を知らない。このように、宣長の性急な判定には“立論上の手抜き”が見られるようである。
この手抜きされた宣長の構築に対して、現代の論者は、いわゆる近代言語学上の「上古音」という概念によって“上塗り”しようとした。“中国の「上古音」では、「奴」は「ナ」であるから、やはり「奴国」を「『ナ』国」と読むのは、正しい”というのである。
しかしながら、もし“倭人伝は「上古音」で読む”という手法なら、隣の「伊都国」も、(「都」の上古音は「タ」であるから)「イタ国」となってしまう。(現に鈴木武樹氏も、それをすでに指摘された)。しかし、あの「恰土郡」や「恰土村」をかつて「イタ郡」や「イタ村」と呼んだ、などという証跡は皆無なのである。一方の博多湾岸は“「ナ」の津”の呼び名がつづいていた。矛盾だ。してみれば、“「奴国」は「ナ国」と読める。その証拠は上古音”といった議論も、「上古音」という学術用語という名の「鬼面」におどされるものの、その実体は意外にも脆弱なのである。やはり宣長の権威を「上古音」の虚名によって“上塗り”してみたにすぎぬ。わたしにはそのように思われる】と、このように述べています。
しかしまだ、「奴」の上古音はどう発音されていたのか、というところまでには古田論証は及んでいません。古田先生は、「奴の上古音はナ」というのは虚言だと思われても、その証拠がなく、そこまでは断言できない、ということでしょう。
そこで、蛮勇を揮って、常識と理性をベースに「奴」の上古音について調べてみました。
奴」の上古音は
調べてみますと、この上古音の論者の論拠は、『学研漢和大字典』に、「奴」の上古音は「ナ」とあるから、ということの様です。藤堂明保編『学研漢和大字典』には、「奴」上古音nag 中古音no(ndo) 近古音nu 現代音nu とあります。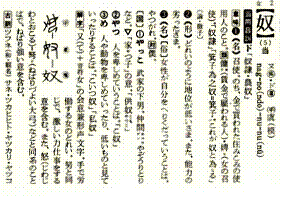
ちなみに音韻学上の、上古とは周~漢代の頃のことで、中古とは南北朝以降のことをいうそうです。『三国志』が書かれた時代は丁度この中間にあり、「ナ」なのか「ノ」なのか決め難い、というところが問題をややこしくしているようです。
この問題について黄當時〈こうとうじ〉仏教大学中国語科教授(一九五三年生まれ。東大大学院博士課程修了。二〇〇一年から佛教大学教授 中国語学専攻)が『悲劇の好字』(不知火書房二〇一三年刊)で『魏志』倭人伝の「奴」の読みについて次のように述べています。
【中国の史官には、極めて高度な漢字の素養があり、提供された音声情報がたとえ「ナ/な」であったとしても、それを正確に伝達できないような「奴」という文字情報に変換することは、ほぼありえないため、倭人の提供したこの音声情報も「ナ/な」でなかったと考えてよい。(中略)ほぼ、と言うのは、『学研新漢和大字典(普及版)』が、上古音としてnagを挙げているからである】
この『学研新漢和大字典』は藤堂明保・加納喜光両氏の編纂によるものです。藤堂氏は、「邪馬臺国」の「臺」の字の読み方を氏の編纂による『学研漢和大字典』では、「上古音 ɗəɡ 近古音 ɖəɨ 中世音 ʈɑɨ とあります。
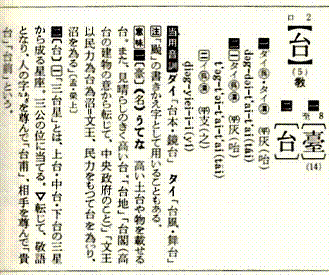
ちょっと見ただけでは分かり難いのですが、上古音に「ɗəɡ」つまり日本語読みだと「タもしくはト」と読めるような発音記号が書かれているのです。
そこで、「臺」を「ト」と読んだ例が本当にあるのか、古田武彦氏が、直接藤堂明保氏に問われたそうです。藤堂明保氏は、日本の歴史学者の皆さんが、「邪馬臺国」は「やまとこく」と読まれるので、というような説明をされたそうです。
このことは、日本の古代語音韻学について、極めて重要な証言だと思います。藤堂氏は残念ながら一九八五年に七〇歳で亡くなり、今となっては古田武彦氏としても確かめる手立てはありません。
この藤堂明保氏とのやり取りは手紙でなされたそうです。プライバシーに関する問題があるかもしれませんが、今となっては重要な資料になると思います。さいわい、この経緯については、『邪馬一国への道標』で古田武彦氏は次のようにかなり詳しく述べられています。
【(倭人伝に記載されている、各国の官名をどう読むか、という問題で)「三世紀の読み」、これがなかなかの難事なのです。わたしは倭人伝を探究しはじめたころ、当然ながらこの問題について読みあさりました。しかし、“これほど著名な言語学者が言っているのだから、これはまちがいないだろう”といった考え方、つまり「肩書主義」とキッパリ手を切っていたわたしにとって、明快な“三世紀の音韻史料に裏づけをもつ、三世紀の確実な読み”の解説には、どうにもお目にかかることができませんでした。それもそのはず、“三世紀の体系的な音韻史料はない”のです。
いや、正確に言えば『声類』という韻書が存在したことは知られていますが、残念ながら現存せず、例によって断片が注記の中に姿を現しているだけなのです。しかし、これらはあまりにも少量で、とても全体の音韻体系をうかがうに足りず、ことに倭人伝内に出現している文字の読みには“直結”しません。それだけではなく、わたしは次のような文章に遭遇しました。
「『魏志』倭人伝で、『ヤマト』を『邪馬臺』と書いてあるのは有名な事実である」
これは藤堂明保さんの名著とされる『中国語音韻論』(一九五七年)の一節です。ここでは逆に「邪馬臺=ヤマト」から“三世紀の臺の音は「ト」であったろう”と推定され、これが好個の“音韻史料”されているのです。
この点、直接、藤堂さんの“三世紀に「臺」を「ト」と読んだという、三世紀の中国側の、確実な音韻史料が存在するか、否か”をお問い合わせしたところ、しばらくして丁重な長文のお手紙をいただきました。その要旨は、“音韻の変遷は、あくまで大勢上の議論です。ですから、特定の時点(たとえばこの三世紀)にどう読んだか、という、その確証となると、資料上容易に確定しがたいと言わざるをえません”とのことでした。そこでその“特定の時点の読み”を“確定”するために、「邪馬臺=ヤマト」という日本史側の「定説」が使われた。こういう次第だったわけです】(同書二五一~二五三頁)
この藤堂明保氏という音韻学の権威と目されている方が、このように、「三世紀の時点の漢字の読みに日本の学者の定説を取り入れる」という編集方針で作られた「漢和辞典」が、三世紀の漢字の読みを縛っているし、学者側はそれを都合よく利用している、という学問の世界と思われない状況にあることを教えてくれます。
古代の漢字の読み方の辞書を編集するのは、非常に困難な作業であろうことは想像できますが、出来上がった、この一連の辞書は古代史文献解釈に問題がある作品と思われます。
ですから、この藤堂明保氏が編集された『学研新漢和辞典』における「奴」の上古音の「ナ」読みも、おそらくは、【日本の歴史学者の皆さんが「ナ」と読まれるので】、ということを根拠にしているのは、ほぼ間違いないことと言えるでしょう。
しかも、古代史特に文献学者は、この『学研漢和大字典』に、「奴」の上古音にnagがあるということを根拠に、「奴」の「ナ」読みの間違いを気付くことがないようです。(たとえ気付いても知らぬふりをしているようです。)
しかし、「奴」の上古音に「ナ」があったとすることに、中国語学者から疑念を持たれていることは確かです。黄當時氏の著書を読むかぎり、中国の史資料にはそのような証拠が見当たらないようです。ただ、東大を卒業され、日本の大学で教鞭をとる黄當時氏にとっては、あからさまに日本の代表的漢和辞典の間違いを指摘するのは、音韻学上の証拠となる資料がない現状では、ためらいがあるように思えます。
ところで「奴=ナ」説をとる学者は、『三国志』に出てくる「奴」を全て「ナ」で通せるのでしょうか。もし、それで通せるものならそれはそれで一つの見識でしょう。残念ながらそのような気骨のある学者、匈奴は「キョウナ」と読むなど主張する学者は皆無で、殆んど「奴」は時には「ナ」、時には「ノ」、と読む亜流内藤湖南の方々です。
しかし、常識的にいって、一つの書物に出てくる漢字「奴」の読みが、「ナ」もしくは「ノ」という混合だ、ということは、注釈が無い限り絶対あり得ないことでしょう。
このこと一つからでも、内藤湖南は基本的に誤りを犯していますし、従って、倭人伝の「奴」の読みを「ナ」で通せない内藤説は間違っていることになります。
つまり、このこと一つをとっても、「奴」の読みは「ナ」ではない、のです。
八世紀に編集された(詠まれた歌の作歌時点は七世紀以前の歌も多い)『万葉集』では、「奴」は全て「ぬ」と読まれています。
国語学者橋本増吉氏によりますと、奈良時代「奴」は「ぬ」で「能」は全て「の」と詠まれた。しかし「怒」は、「ぬ」とも「の」とも読まれた、と仰っています。(『古代国語の音韻に就いて』岩波文庫)少なくとも万葉集に「奴」を「な」と読まれた例はないのです。
以上、上古音における「奴」の読みについて、検討してきました。その間で「奴」だけでなく「臺」の上古音が「ト」であるというのが「定説」となっていることの根拠の無さも明らかになりました。つまり『魏志』倭人伝に書かれている「邪馬壹国」を「邪馬臺(台)国」と読み慣わすのは、倭人伝の女王国を「ヤマト」と読みたいがためのものであったのです。
「奴」は「ド/ト」である可能性はあるか
今まで述べてきように『魏志』での「奴」は「ナ」ではなくとも、「奴」は「ド/ト」と漢音では読む、という問題が残っています。古田武彦氏も踏み込めていないようです。
三世紀末に書かれた『魏志』には、「奴国」以外にも「匈奴」や「奴婢」という語が出てきます。今私達はそれぞれ「きょうど」、「ぬひ」と読んでいます。しかし、『魏志』という一つの書物では注書きが無い限り、「奴」は同じ発音であった筈です。もちろん「奴国」の「奴」も同じ発音です。
「ヌ」であれば、匈奴〈ぬ〉、奴〈ぬ〉婢、奴〈ぬ〉国であり、「ド」であれば、匈奴〈ど〉、奴〈ど〉婢、奴〈ど〉国、という読みになる論理です。
「奴」の読みについて整理しておく必要があります。ネット辞書で調べてみました。
「奴」の読みは、日本語では、呉音では「ヌ」、漢音では「ド」です。中国語(普通語)では、「ヌ」です。中国広東語では「ノゥ」で、韓国語では「ノム」です。
この「奴」は「ド/ト」か「ヌ/ノ」か、という問題解決について、わたしが検討した論理の流れを説明します。
[1] これらの「奴」は同じ書物の中では特に注釈が無い限り、同じ発音をされていた、としてもよいのではないでしょうか。つまり「ド」か「ヌ」か、どちらかということになります。しかし、三世紀の時代に「奴」はひと通りの発音しかなかったのではなく、二つ以上の発音もあった、という可能性を排除することはできないでしょう。
[2]『魏書』における「奴」は全て同じ読みだった、とするのは「書物」の常識からいって間違いないでしょう。とくに、著者の陳寿〈ちんじゅ〉も後年の注釈者、裴松之〈はいしょうし〉も何も「奴」の読みについて注釈をいれていないことからも、そう言えるでしょう。
[3]「奴=ど」とした場合と、「奴=ぬ」とした場合、倭人伝の国々の名の読みはどうなるのでしょうか。倭人国とされている三十ヶ国で、「奴」入りの国は次の八国です。かなり「奴」が入っている国の比率が高いのです。率で二十七%。
「奴=ど」では、奴国(どこく)、彌奴国(みどこく)、姐奴国(しゃどこく)、蘇奴国(そどこく)、華奴蘇奴国(かどそどこく)、鬼奴国(きどこく)、烏奴国(うどこく)、狗奴国(こうどこく)となります。この国の読み方は日本語〈やまとことば〉の感触とは異なる感じがします。しかし、「奴=ぬ」とした場合、奴国(ぬこく)、彌奴国(みぬこく)、姐奴国(しゃぬこく)、蘇奴国(そぬこく)、華奴蘇奴国(かぬそぬこく)、鬼奴国(きぬこく)、烏奴国(うぬこく)、狗奴国(こうぬこく)、となり日本語〈やまとことば〉らしく感じられます。
[4] 改めて『和名類聚抄郷名考證』を調べてみたところによりますと、西日本の二八八郡のなかで、国名に「ド/ト」を含むものは出雲国神門、美作国苫東、苫西・筑前国怡土、筑後国山本・山門、肥後国山本・宇土、讃岐国多度、土佐国土佐の十郡です。率で約三%。
同じく、ノ(ヌ)が含まれる郡名は、丹後国竹野・熊野、但馬国城埼、因幡国巨濃、伯耆国日野、出雲国能養、石見国安濃・鹿足〈カノアシ〉、備前国御野、備後国奴可〈ヌカ〉・沼隈・甲奴〈カフノ〉、安芸国沼田、周防国都濃、阿波国板野、讃岐国三野、伊予国濃満、筑後国竹野・大野・三瀦〈ミヌマ〉、豊後国大野、肥前国彼杵〈ソノギ〉、薩摩国河辺・頴娃〈エノ〉の二十四郡。率にして約八%。
倭人伝の記載の「奴」入りの国の率が二十七%とかなり高く、「奴」を「ド/ト」とした場合は三%で、「ヌ/ノ」とした場合は八%と、「ド/ト」入りの国より二倍以上高い。
このことからも、倭人伝の国名の「奴」は「ド・ト」であるよりも「ノ・ヌ」である可能性が高いことが、理性的に判断できるのではないでしょうか。
[5] 今でも沖縄地方では、日本内地人に対し大和ぬ衆〈やまとんちゅ〉と所有格の「の」を「ぬ」と言うように、古くから「の」は「ぬ」と発音されています。
沖縄方言では多くの古典文法の特徴が保たれています。例えば、終止形と連体形の区別や、所有格「が」(首里方言では死語)、主格「ぬ」(共通語の「の」)、さらにそのほか、主格としての「が」「ぬ」の敬体と常体での使い分けが挙げられています。
沖縄方言には三種類の短母音 ア・イ・ウと五種類の長母音 アー・エー・イー・オー・ウー がある。つまり「ノー」という発音はあっても「ノ」という発音はなく、ヌと発音されている、ということです。(内間直仁(一九八四年)『琉球方言文法の研究』笠間書院による。)
[6] 広辞苑を引きますと、【ぬ(野)はノの母音交代した上代語。特に東国方言で、野(ヌ)。また、「ぬ」は沼。】とあります。
[7]『和名類聚抄郷名考證』によると、備後国の郡名に、「奴可〈ぬか〉郡」・「甲奴〈かふの・こうの〉郡」があり、福岡市早良区の古地名「額田〈ぬかた〉」が現在「野方〈のかた〉」と呼ばれているように、日本語で「ぬ=の」という混用・転訛があった、という傍証になるでしょうし、また、「ヌ」と「ノ」の発音が、古代は同じであった可能性も強いと思われます。
このような思考の流れから、「奴」は「ド・ト」よりも「ヌ・ノ」と読まれていたといえるでしょうし、この方がはるかに日本語的感覚として受け入れることが出来ると思います。
前出の内藤湖南の「ナとノ」の混在説も、氏としては、「ナ」と全てを読みたいのですが「ノ」と読まざるを得ない国名がある、という判断があったものでしょう。
また、「奴」を国名(部族名)に使われているのは何も倭人国だけではありません。例えば東夷伝の高句麗でも涓奴部、絶奴部などの部族名が出ています。これらの読みもワンセットで同じ読みが出来るか、を考えなければならないでしょう。
『魏志』における「奴」の全調査
しかし、先程の「日本語〈やまとことば〉的感覚」で「奴」は「ヌ・ノ」だ、ということでは論証とは言えないでしょう。そのために、倭人伝とか東夷伝だけではなく『魏志』全体で「奴」がどのように使われているのか見る必要があると思い調べてみました。
『魏志』全体に使われている「奴」は全部で、五十六個でした。これらは、匈奴とか奴婢とかいう熟語として使われているのが多く、一覧にしますと次の様です。
出現回数一四回 匈奴
一〇回 奴婢
四回 涓奴部 卑奴母離
三回 奴僕
二回 絶奴部 灌奴部 奴国 狗奴国
一回 奴 雍奴 瑣奴部 順奴部 弁楽奴国 奴佳鞮 彌奴国 姐奴国 蘇奴国 華奴蘇奴国 鬼奴国 烏奴国
計、五五回(五六字)の出現で、うち、東夷伝(第三十巻)は三十八回(三十九字)でした。
倭人伝の読みからは「奴=ヌ」という確率が高いのですが、果たして一般名詞の奴婢・奴僕や匈奴の「奴」が同じ発音なのか、という問題があります。奴婢・奴僕は倭人伝と同じく「ヌ」読みで問題ないと思われますが、問題は雍奴と匈奴です。
雍奴は、『魏書』二六巻田餘伝で「漁陽郡雍奴県の人」、という記事に出てくる地名です。ところが現在では、雍奴県という地名は残っていません。
雍奴の読みを追うのはちょっと困難ですが、もう一つの「匈奴」の読みはどうなのでしょうか。今までの論理の流れによれば、「奴」は「ヌ」ですから、「キョウド」とは読めないことになります。
「匈」は呉音では「ク」です。仏教用語としての「ク」読みはあるかもしれませんが、一般には使われていない読みです。漢音では「キョウ」だから、「匈奴」は漢音読みなら「キョウド」となります。呉音だと「クヌ」ということになります。現代語では「ションヌ」と読まれています。
ところで、「匈」という字の読みには、日本に「キョウ」という読みで伝わる前の読みとして「ハン」乃至「フン」という南方音があったのではないかと思われます。
何故かといいますと、現在「ハンガリー(英語標記Hungary)」という国名を中国語では「匈牙利」と表記しています。これは歴史的な用法で特殊な読みだ、とWeblio辞書の解説にあり、「匈=ハン乃至フン」と読ませているのです。
呉音は、北方から胡族や鮮卑族などに南方に追われた漢族の言葉です。もともとの南方中国語、広東語では「匈」をどう読んでいるか調べてみましたら、「ク」ではなくフン(hung)なのです。
また、韓国語のなかの中国由来の語は、入って来た時期は我が国よりも早いといわれますが、その時期は確定できていません。今回の「匈奴」について、ハングルについて調べてみますと、「フン・ノ(ム)」だそうです。(倭奴はウエノム)
以上のことを考え合わせますと、倭人伝の世界、三世紀には、「匈奴」は「クヌ」もしくは「フンヌ」と読まれていた可能性が高いと思われます。
つまり「匈奴」の「匈」の読みは「ク・ハン・フン」のいずれか確定は出来ませんが、ともかく、「奴」は「ヌ」であったとして問題はない、『魏書』における「奴」は、「ヌ」と読まれていたと結論づけてもよい、ということになります。
三世紀の「奴」の読みの結論
一世紀の金印の時代と、三世紀の倭人伝の時代では、「奴」の中国語の読み方は違ってきたかもしれません。しかし『魏志』全体の使用例を検討した結果は、『魏志』の「奴」は全て「ヌ」であったという結論に至りました。そして、日本の三世紀当時の「ノ」の発音が「ヌ」に近く、魏朝の人に「奴」という字が当てられたものといえましょう。
結論としては、「奴の上古音はナ」という主張は、日本国内の日本古代史関係学会という殻の中だけで通用する議論です。正しくは、三世紀の「奴」の読みは「ヌ」だった、に落ち着きます。
『魏志』倭人伝に二万戸の大国とある「奴国」は、「な」国ではなく、「ぬ」国だったのです。